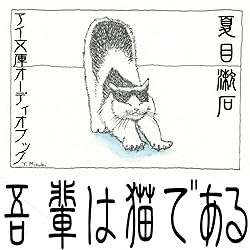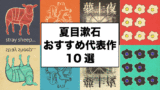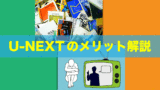夏目漱石の小説『吾輩は猫である』は、38歳の頃に初めて執筆した処女作である。
猫目線で痛烈な文明批評、人間批判がなされる風刺的な物語になっている。
誰もが知る有名なタイトルでありながら、非常に挫折率が高い作品でもある。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察していく。
目次
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表時期 | 1905年(明治38年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 610ページ |
| テーマ | 人間模様の風刺 欧化主義への疑念 |
あらすじ
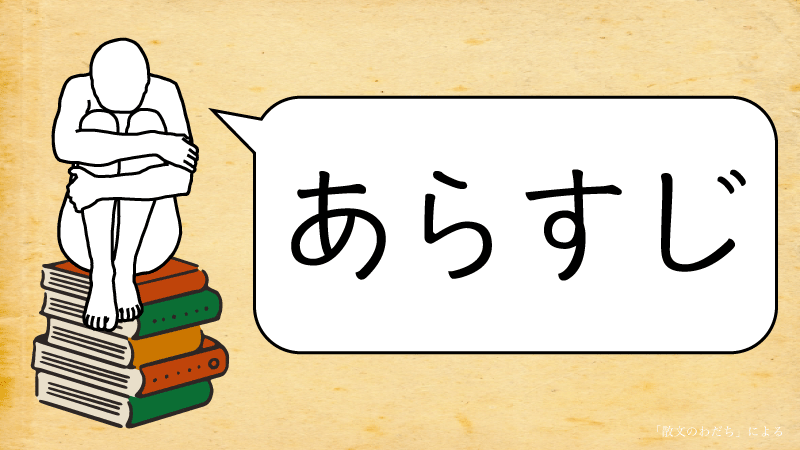
主人公の「吾輩」は名前のない猫である。生まれてすぐ人間に捨てられたが、今は中学の英語教師を務める苦沙弥先生の家に住み着いている。そんな「吾輩」の視点で、人間生活の滑稽さが語られる。
主人の苦沙弥は、多趣味なくせに何も長続きせず、相手と正反対の意見ばかり主張したがる天邪鬼な性格である。そんな主人の家には多くの友人が訪れる。ホラを吹いて他人を担ぎ上げる悪趣味の迷亭。首吊りの力学やどんぐりの研究をする不思議な理学士の寒月。芸術に傾倒し過ぎてズレた感覚を持つ東風。これら個性的な友人たちと、ひたすら恋愛談義や女性論を饒舌に語るのであった。
ある時は、寒月に縁談を迫る金田鼻子という実業家夫人が訪ねてくる。実業家を嫌悪する苦沙弥は迷亭と一緒に、婦人の巨大な鼻を冷やかし、横柄な態度で追い返す。それが原因で、金田家の手回しによって、苦沙弥を罵る者が現れたり、野球ボールが家に投げ込まれたり、嫌がらせを受ける羽目になる。
「吾輩」はこんな人間社会の滑稽な様を嘲笑しつつも、徐々に人間というものに憧れを抱くようになる。来客が帰った後、彼らが飲んでいたビールに興味を持ち、こっそり盗み飲みしていると、次第に酩酊してしまい、水甕に落下して水死するのであった。
Audibleで夏目漱石を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『吾輩は猫である』を含む夏目漱石の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
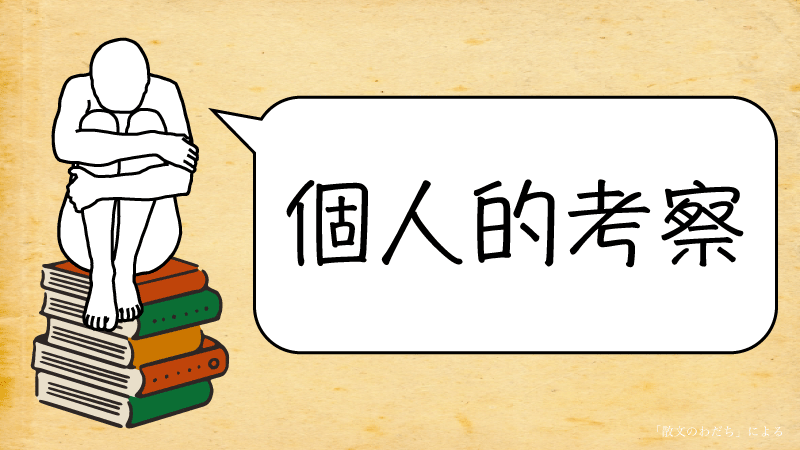
38歳の小説デビュー作
本作『吾輩は猫である』は、夏目漱石が38歳にして初めて発表した小説である。49歳で死去するまでのたった11年間で、数々の名作を生み出したのだから驚きだ。
10代や20代で新人賞デビューすることが多い現代の価値観からすると、やや遅くれた台頭に感じられるが、38歳に至るまで漱石は何をしていたのだろうか?
東京大学英文科を卒業した漱石は、小説の道へは進まず、高等師範学校の英語教師になった。だが精神的な煩悶から2年後には東京を離れ、四国の松山で教師を務めるようになる。そして松山の地で議員の娘と結婚したこともあり、文部省留学生としてイギリスで英語教育研究に従事した。イギリスでは文学論の研究に没頭し、そのせいで神経衰弱に陥るのだが、帰国後も熱心に研究を続けていたようだ。
そんな漱石の同級生に俳人の正岡子規がいた。正岡子規は、漱石の漢詩や漢文の才能を認めており、二人は深く親交を結んでいた。そんな正岡子規の同郷の後輩に高浜虚子がおり、彼は俳句雑誌『ホトトギス』を発行していた。正岡子規を介したよしみによって、漱石も『ホトトギス』に俳体詩を寄稿していたが、虚子の勧めで小説も書くようになる。それが1905年に発表された処女作『吾輩は猫である』だったのだ。
『吾輩は猫である』は11章で構成されているが、当初は第1章きりのつもりだった。だが意外に好評を得たことで連載を継続することになり、夏目漱石は一気に小説家として注目されるようになった。
一人称が猫である魅力
吾輩は猫である。名前はまだ無い。
『吾輩は猫である/夏目漱石』
本作『吾輩は猫である』の最大の特徴は、言うまでもなく、「猫」による一人称視点だろう。「猫」という独特の視点で人間生活を捉えることで、普段人間が疑問を抱かない物事を注意深く観察することができる。
例えば、なぜ人間は四本の足があるのに二本しか使わないのか。なぜ人間はすぐ伸びる髪をいちいち切り整えるのか。
こういった滑稽な疑問に始まり、なぜ人間は服を着るのか。なぜ人間は誰のものでもない土地を所有したがるのか。なぜ人間は世間体ばかり気にするのか。なぜ人間はわざと正反対の主張で相手を困らせようとするのか。こういった、社会的・哲学的なテーマに発展していく。
ある種、最も純粋な視点で人間社会の滑稽さや愚かさを映し出す効果がある。
仮に人間の視点でこの手の疑問を描くと、主人公の自意識が入り込み、例えばサリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』のように(良い意味で)痛々しい作品になりかねない。「全く社会と折り合いを付けられない主人公」というアイデンティティが作品に宿るからだ。
一方で人間社会に属さない「猫」の視点だと、自分とは無関係な問題という「非人情」な立場でいられる。読者の方も、知らず知らず「猫」だからそんな風に思うのも当然だろう、という約束のもとで読み進めているのだ。だからこそ、少々突っ込んだ内容(世間の顰蹙を買いそうな内容)を論じても、ユーモアと捉えることができるのだろう。
また語り手が「猫」という設定を活かし、苦沙弥と対立する実業家の金田家に侵入して、相手側の情勢を見物しに行ったりする。仮に苦沙弥の視点で描いた物語なら、こういった描写は許されない。自由気ままに移動できる「猫」だから叶うのだ。もちろん三人称(神)の視点を使えば、両者の情勢を詳細に描くこともできるが、「猫」である故に障害物に邪魔されたり、人間に追い出されたりと、上手く事が進まない点が、この作品の魅力だと言える。
西洋文明がもたらす生きづらさ
本作『吾輩は猫である』には、物語らしい物語が存在しない。500ページを超える文章の大半が、主人の苦沙弥が友人たちと話す、恋愛談義や女性論や文明批判である。ゆえに挫折してしまう人が多い。
彼らが弁舌する議論は多岐に渡るが、最も印象的なのは、日本と西洋の文明対比だろう。本作以降の作品にも、明治時代の過剰な欧化主義に対する疑念が一貫して描かれているため、夏目漱石の文学を知る意味でも「文明」は重要なテーマである。
西洋の文明は積極的、新取的かも知れないがつまり不満足で一生をくらす人の作った文明さ。日本の文明は自分以外の状態を変化させて満足を求めるのじゃない。
『吾輩は猫である/夏目漱石』
これは独仙という禅坊主崩れの友人が語った言葉である。
知足を心得ず尽く支配侵略する西洋文明が、日本に取り込まれることを批判しているのだ。そういった価値観に侵された民衆は、寝ても覚めても自分のことしか考えられなくなり、その結果他人を陥れたり目を盗んだりして、自分だけ甘い蜜を吸おうと考えるようになるのだ。
このような状態を作中では、文明の発達による「個性中心の世」と記されている。これは一般的な個性という意味よりも、個人主義の果ての醜いエゴイズムを指しているのだろう。個性(エゴ)が高まったせいで、人に犯されまいと過敏になり、その方法として他人を犯してやろう考えるわけだ。傷つけられるのが嫌なら傷つける側に回ればいい、の精神である。こんな風に互いにいがみ合えば、人間社会はますます生きづらくなる。
元来日本では、己を忘れる、という価値観が重宝されていた。それは東洋思想における悟りのようなものだ。だが西洋文明に侵されて以来、己を忘れるどころか、常に己の利ばかりを考えるようになった。主人の苦沙弥は、このような文明がますます進行するなら生きるのが嫌になる、と厭世的に嘆いている。
これらの主張を見ると、あたかも西洋文明が全て害悪のように感じられるが、しかし夏目漱石は日本人の精神に適するか否か、という視点で考えていたことを忘れてはいけない。
実際に夏目漱石は他の作品において、全体主義の風潮の中で自由恋愛や略奪婚が敗北する日本社会の生きづらさを訴えていた。つまり西洋的な個人主義が全て害悪なのではなく、何でもかんでも西洋の価値観を取り入れるのが進歩と考える、過剰な欧化主義に疑問を感じていたのだろう。西洋の優れた分野は取り入れ、しかし日本人の精神に合わない分野は拒否する。そういう判断が重要というわけだ。
もっとも21世紀のグローバリズム社会では、日本人に合う合わないではなく、生き残れるか否かの基準で判断され、すでに我々は寝ても覚めても自分の利しか考えられない病に侵されているのかもしれない。
なぜ猫は死んでしまったのか
語り手である「吾輩」は、最終的に客人が飲み残したビールを飲んで酩酊し、水甕に落下して死んでしまう。なぜ夏目漱石は猫を殺す結末を描いたのだろうか。
そこには物語を通した「吾輩」の心境の変化が関係していると考えられる。
「吾輩」はその一人称の通り、かなり上から目線の存在である。序盤では徹底的に人間を批判し、そのうち人間社会は廃れ、いずれ猫の時代が到来するとまで考えている。また第二章までは、猫社会の交友関係や、吾輩の恋模様も描かれる。だが終盤に向かうにつれて、苦沙弥を取り巻く人間社会の描写のみに限られていく。
物語を通して「吾輩」が、少しずつ人間に興味を持ち出している証拠である。それどころか人間に感情移入するようにもなる。
例えば、寒月の縁談の件で地主の金田夫人と揉め、その後向こうの手回しで様々な嫌がらせを受ける場面では、時たま「吾輩」は苦沙弥の肩を持つような主張を述べたりする。
決定的に吾輩の心境が変化したと分かる文章がある。
吾輩も日本の猫だから多少の愛国心はある、こんな働き手を見る度に撲ってやりたくなる。(中略)こんなごろつき手に比べると主人などは遥かに上等な人間と云わなくてはならん。
『吾輩は猫である/夏目漱石』
これは、嘘で人を釣ったり、虚勢を張って人を脅したり、鎌をかけて人を陥れる、世間の愚かな人間(特に実業家の類)を吾輩が非難した台詞である。なんとここでは、苦沙弥を上等な人間だと称賛しているのだ。
このように人間という生き物を徹底的に見下していた吾輩は、苦沙弥を取り巻く人間社会の様子を観察するうちに、いつしか人間の良い面を発見したり、あるいは人間社会に僅かな憧れを抱くようになる。
その憧れによって吾輩は、人間が楽しげに飲むビールに興味を持ち、自分もあんな風に酔って愉快な気持ちになりたいと思う。結果的にその思いつきが祟って水甕に落下してしまう。
一つ不可解なのは、水甕に落下した吾輩が、途中から抵抗をやめ半ば死を受け入れることだ。
「吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい」
『吾輩は猫である/夏目漱石』
なぜ吾輩はあっさり死を受け入れたのか?
一つは、吾輩の心境が変化したため、これ以上人間を批判する必要がなくなり、それが「語り手の死」へ繋がったのだと考えられる。
あるいは「太平は死ななければ得られぬ」という言葉から、文明の進化に抗うから苦しくなるのであり、いっそ抵抗をやめてしまえば楽になる、という諦念に対する皮肉をが込められているのかもしれない。
そしてもう一つは、人間社会に憧れを持ったせいで、人間社会よろしく不条理な死を迫られたとも考えられる。かつて吾輩が恋をしていた隣家の飼い猫は、人間さながら飼い主に可愛がられていたが、突如病気になって死んでしまう。やたらに人間社会に首を突っ込めば、不条理な死を迫られる、という皮肉が込められていたのかもしれない。
パロディ作品もおすすめ
高い確率で挫折してしまう『吾輩は猫である』は、先にパロディ作品を読んで物語の世界観を把握すれば挫折せずに済むかもしれません。
『漱石先生の事件簿』
こちらはパスティーシュ(文体模写)の名人として知られる柳広司によるパロディ作品です。
ある書生が苦沙弥の家に住み込むという設定で、大方原作と同じ場面展開が描かれます。原作にかなり忠実ということもあり、先にこちらを読んでおけば、抵抗感なく原作を読み進められると思います。
『吾輩も猫である』
こちらは現代作家によるアンソロジーです。
赤川次郎や恩田陸、原田マハらが、独自の世界観によって夏目漱石の「猫目線」の手法に挑んでいます。夏目漱石のファンはもちろん、漱石の原作を知らなくても楽しめるパロディ作品なので、どなたにもおすすめです。
■関連記事
➡︎夏目漱石おすすめ作品10選はこちら
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら