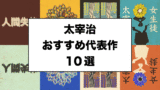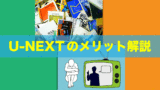太宰治の小説『狂言の神』は、自殺未遂の体験を元に創作された作品です。
『人間失格』でも描かれる入水自殺の7年後の物語です。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
目次
作品概要
| 作者 | 太宰治(38歳没) |
| 発表時期 | 1936年(昭和31年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 24ページ |
| テーマ | 自殺未遂の体験談 些細な幸福 |
| 収録 | 作品集『二十世紀旗手』 |
あらすじ
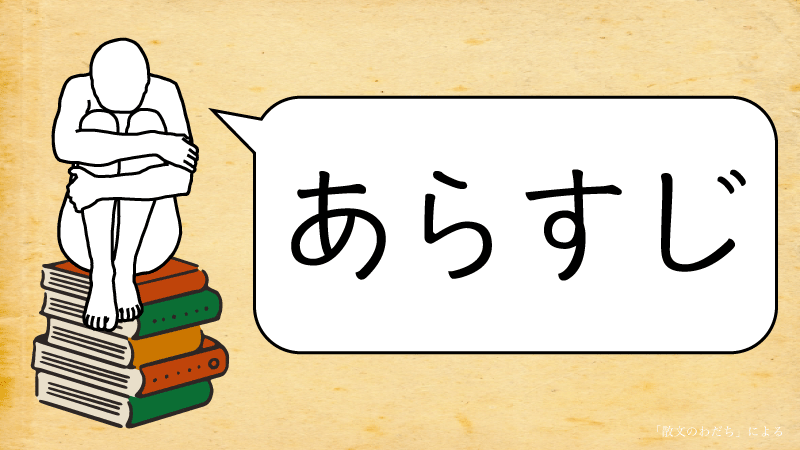
小説家の笠井一は自殺を決意する。理由は就職試験の落第だ。彼は小説家でありながら、人間らしい生活に憧れるあまり、サラリーマンを望んでいたのだ。
死を決意し最後の散財が始まる。慣れ親しんだ飲み屋や、行きずりの女との時間にお金を浪費し、大半を使い果たした段階で、導かれるように江ノ島へ向かった。
江ノ島、それは彼がかつて入水自殺を試みた土地だ。変わりゆく江ノ島の風景に、あれから7年が過ぎたことを実感する。7年越し同じ方法で自殺を考える。だが人通りが多いため一時延期した。
死ぬ前に高価な外国タバコを買った彼は、最後に尊敬する小説家の先生を訪ね、ようやく首吊りを決心する。だが首を括ってもなかなか死ぬことが出来ず、あまりの不快感に縄を振り解いてしまう。
自殺に失敗した笠井は外国タバコに耽る。そしてタバコの楽しみを糧にした庶民的な生活なら、自分にもできるかもしれないと、些細な希望を見出すのであった。
オーディブル30日間無料
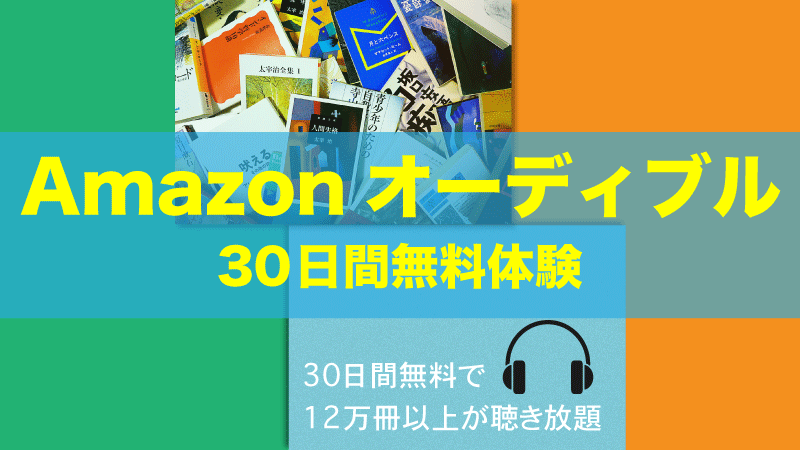
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
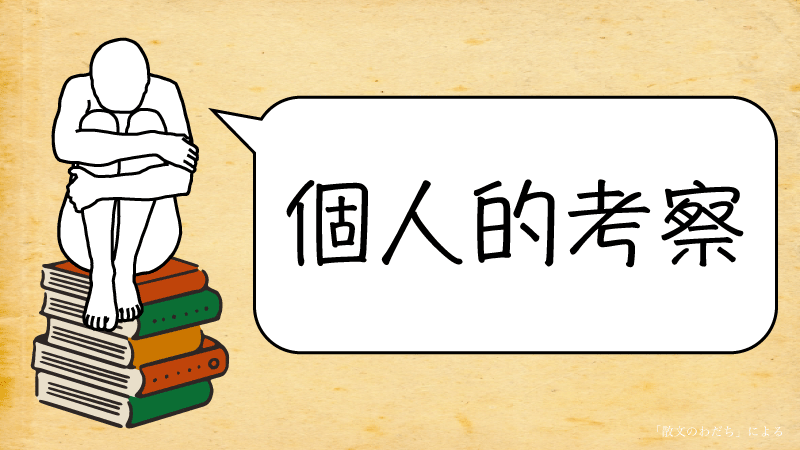
一本の外国タバコが笠井を救った!?
『人間失格』に比べれば、まだ救いのある作品だったのではないでしょうか。
笠井一は死を決意したものの、結局死ぬのを辞めます。それどころか、外国タバコの美味さに幸福を感じ、生活に希望を見出しさえするのです。
「一本の外国煙草がひと一人の命と立派に同じ価格でもって交換されたという物語。私の場合、まさにそれであった。」
『狂言の神/太宰治』
この言葉が、本作の全てを象徴しているのではないでしょうか。つまり、たった一本の外国タバコが彼の命を救ったのです。
人間の命をこの世界に繋ぎ止めているのは、そういう何でもない些細な幸福なのかもしれません。極限まで絶望した人間だからこそ、こんなにも優しくて力強い真実に辿り着けたのでしょう。
また、心温まるクライマックスに、作者の綴る通り、「なあんだ」と微笑みを浮かべた方も多いのではないでしょうか。太宰治の人間生活に対するそこはかない未練が感じられ、思わずほっこりしてしまう短編でした。
笠井は結局死ななかったのか?
ラストを読む限りでは、笠井は生活に希望を見出し、生きることを決心したようにも解釈できます。しかし、物語の序盤で「笠井は新聞社の就職試験に落第し自殺した」とはっきり書かれています。つまり、本作では描かれなかったものの、この物語の後に笠井は確実に自殺したことになります。
しかし、違った目線での考察もできます。
そもそも就職試験に落第して自殺した「笠井一」とは、太宰治本人のことです。自己喪失症の太宰治は、他人の口を借りなければ自分のことを語れないため、「笠井一」という名前を使って自分の物語を書いていたのです。つまり、過去に入水自殺を決行したことも、再び死を決意したのも、太宰治本人の実体験となります。就職試験に落第したのも事実ですが、太宰治はそのことが原因で死んではいません。物語に脚色を加えるために用意された「笠井一」だけの設定だったのです。
よって、笠井は死ななかったという結論も考えられます。もう少し粋に表現するなら、太宰治が続きを描かなかったことで、笠井一は死なずに済んだ、とも言えるでしょう。
それはある意味、この作品を執筆した時期の太宰治が、かろうじて生きることを選んだ証拠なのかもしれません。事実、かの暗黒時代を経て、約10年ほどは作品を執筆し続けるのですから、この当時はまだ生に執着していたことは間違いありません。
少女とナポレオンと女学生の役割
本作には3人の女性が登場します。
1人目は、かつて通っていた浅草の食堂の少女です。笠井は貧乏くさい少女に小遣いを渡したりして可愛がっていました。しかし、看板娘になって以降彼女は、笠井の相手をしなくなります。よって笠井は食堂に通わなくなりました。自分が目をかけていた女性が、周囲にもてはやされるようになった途端、冷たく自分をあしらうようになったからです。
これはつまり、恩知らずな人間の特徴を訴えているのだと思います。これまで何度も太宰治の作品解説で訴えてきましたが、彼は「人の信念」に強いテーマを抱いていました。裏切りに対して過度に敏感なのです。そのため、少女が自分から離れていった様子も、少なからず笠井にとっては、人を信用することに対するつまずきだったのでしょう。事実、店に通わなくなったことに対して、「彼には困難の日々が始まりかけていたのだ」と記されています。
2人目は、横浜で知り合ったナポレオンに似た女性です。彼女の存在は、女性に対する決別の役割を果たしています。ナポレオンと一夜を共にした笠井は、ずっとここで遊んでいたいと感傷的な気持ちになります。しかし、その気持ちを辛抱し、江ノ島へと旅立つのです。その際にナポレオンから5円で買った傘は駅の待合室に捨てます。これも女性に対する決別の現れだと思われます。
そして最後に3人目が、駅で雨宿りをしていた女学生です。こちらはあらすじ中で解説した通りです。ナポレオンの傘を捨てることで果たされた決別は、女学生を見た時に、「傘があれば」と後悔する気持ちによって揺らぎます。まさに「溺れる者のわら一すじ」です。弱った笠井は誰彼構わず縋り付きたくなっていたのでしょう。しかし、彼は黙って駅の向かいの食堂に入ります。決意は揺らいでも、失うことはありませんでした。
深田先生も自殺を考えていた?
笠井が、自殺を決行する直前に尋ねた深田先生の存在も不思議です。以前から会ってみたかったらしいのですが、なぜかよそよそしい描写だけが続いて、すぐに帰ってしまいます。
帰る時に庭の桜の木に縄がかけられているのを目にして、笠井は自殺の方法を首吊りに決めます。ではなぜ、深田先生の家の庭に縄がかけられていたのでしょうか?
一般的には、木が倒れたり折れたりしないように使う、添木を括り付けるための縄だったと想像されます。しかし、文中には「寒くぶらんとぶら下がっている」と綴られています。どこか不自然な印象が感じられますよね。
あるいは、深田先生の特徴として、困惑するほど善良な人だと書かれています。この辺りも、太宰治が描く人間不信に陥った故に道化に成り果てた人の特徴と重なりますよね。
つまり、一見豊な生活を送っている深田先生も、同じように小説家として深い闇に囚われた人間の1人だったのかもしれません。ラストの描写で、笠井が鎌倉の街の光の中で、深田先生の家の光を探していたのも、似た者同士の親和感が描かれていたように思われます。
■関連記事
➡︎太宰治おすすめ代表作10選はこちら
映画『人間失格』がおすすめ
『人間失格 太宰治と3人の女たち』は2019年に劇場公開され話題になった。
太宰が「人間失格」を完成させ、愛人の富栄と心中するまでの、怒涛の人生が描かれる。
監督は蜷川実花で、二階堂ふみ・沢尻エリカの大胆な濡れ場が魅力的である。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら