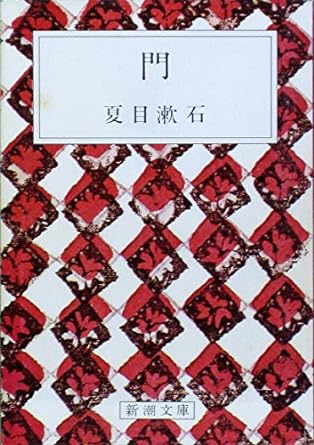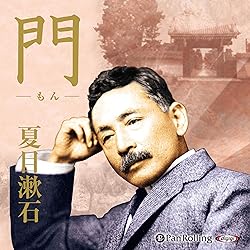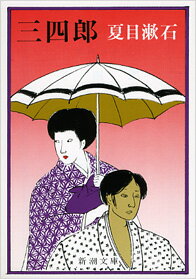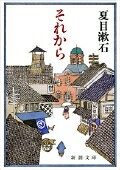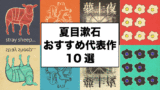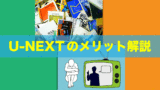夏目漱石の小説『門』は、前期三部作の最終章に位置する作品です。
前作『それから』で、友人を裏切り略奪婚を決心した主人公の、その後が描かれています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
目次
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表 | 1910年(明治43年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 311ページ |
| テーマ | 略奪婚の罪 罪の意識からの救い |
あらすじ
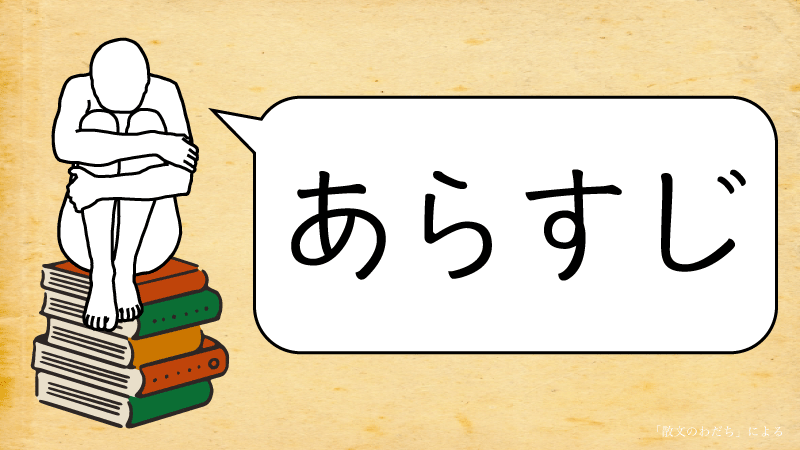
主人公の宗助は妻の御米と仲睦まじく暮らしている。だが彼らには後ろ暗い過去がある。宗助は親友・安井の妻だった御米を略奪し、その償いとして親に勘当され、大学を中途で退学し、世間の目を免れてひっそり暮らしているのだ。
そんな宗助は、父の死後に遺産トラブルに直面する。叔父夫婦と交渉して遺産を弟・小六の学費に充てる必要があったが、宗助は気後からか交渉を先延ばしにし、小六の学費が払えなくなる。それでも宗助は、問題をいつまでも先延ばしにするのであった。
一方で御米は子供ができない問題に悩まされている。それはかつて犯した略奪の罪による因果なのだと、夫婦の背後には常に安井の存在が意識されるのであった。
ある時、大家を訪ねた宗助は、安井の消息を知らされる。大家の弟の事業に安井が加わっていたのだ。安井が東京に来ると聞いた宗助は、不安の思いから神経衰弱に陥り、鎌倉の寺へ出かける。宗教に救いを求めたのだ。しかし彼の行手には「門」が立ちはだかっており、それをくぐることができず、一向に不安は解消されないのであった・・・
Audibleで『門』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『門』を含む夏目漱石の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
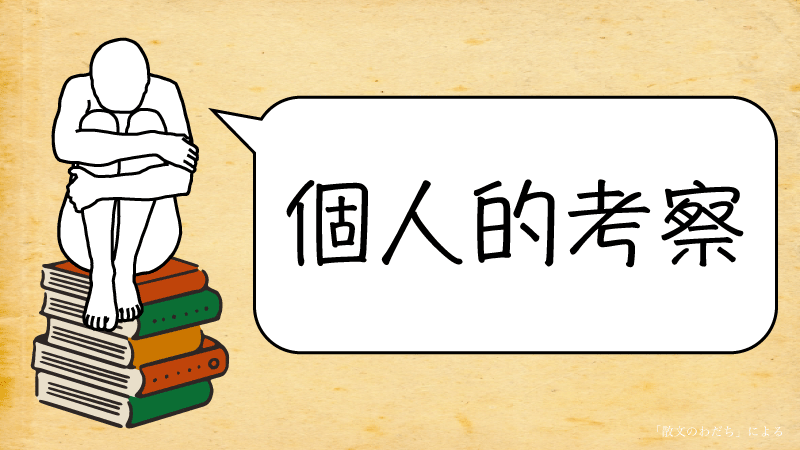
前期三部作の最終章
本作『門』は、『三四郎』『それから』に続く前期三部作の最終章である。
三作品に登場人物上の繋がりはないが、テーマに関しては続編の形式になっている。
一作目『三四郎』は、大学生の三四郎が美禰子に恋をする物語だ。だが最終的に美禰子は家族の決めた婚約者と一緒になってしまう。
二作目『それから』は、まさに『三四郎』の”それから”を描いた物語だ。主人公の代助が友人の妻を略奪するまでの葛藤が描かれている。つまり『三四郎』で叶わなかった恋を、『それから』では略奪という形で実現させたのだ。
そして本作『門』は、『それから』の”それから”を描いた物語と言えよう。
友人の妻を略奪した宗助が、その罪を背負いながら、世間の目を避けひっそり暮らす物語である。全てを投げ出してでも恋を選んだドラマティックな決意の果てには、逃れようのない厳しい現実だけが待ち受けていたのだった。
これら三部作の凄まじい恋愛劇を通して、夏目漱石は何を訴えていたのか。
それは明治時代の価値観に苦しむ人々の葛藤であろう。
自由恋愛が敗北した『三四郎』の結末から分かるように、明治時代には全体主義が根強く残っていた。とりわけ「家」の権威が強く、自由に結婚相手を選べる時代ではなかったのだ。あるいは『それから』や『門』の主人公のように、略奪婚ともなれば、親から勘当され、世間から虐げられる程度の大問題であった。
現在の価値観では想像しずらいが、それだけ「家」の権威や世間体が甚だしく、個人主義的な選択は厳しく裁かれていたのだ。世間に醜態を晒せば社会的死を迫られる、滅茶苦茶に肩身の狭い時代である。
あるいは法律的にも当時は「姦通罪」なるものが存在し、略奪婚など場合によっては刑罰の対象であった。今日でも不倫問題は世間の断罪が凄まじいが、当時は今以上に社会的にも法的に制裁が厳しかったわけだ。
こうした歴史的な背景を踏まえれば、なぜ本作『門』の主人公が、後ろめたい感覚を抱えながらひっそり暮らしていたのか、あるいは宗教に救いを求めたのかが分かるだろう。
略奪婚の末の惨めな生活
『三四郎』『それから』と順に読み進めた人は、おそらく『門』を読んでショックを受けたことだろう。
前作『それから』のラストでは、略奪婚を決心した主人公が仕事を探しに出かける、というやや希望にも感じられる結末が描かれていた。
しかし実際に略奪婚を果たした夫婦の運命は、本作『門』に描かれる通り、救いのない陰鬱とした生活であった。
①人目を憚る住処
略奪婚を果たした宗助は、その報いとして親に勘当され、大学を中途で退学し、かつての知人に会わぬよう地方へ逃げ回っていた。だが縁あって東京での仕事にあり就き、再び上京することになる。
物語は、上京後に宗助と御米が住まう家の情景描写に始まるのだが、そこは歪な立地である。彼らの住処は竹藪を切り拓いた崖の下に建てられているのだ。二人は閑静な住処に満足しているみたいだが、実際は人目を避けて生活していることが伝わる。
あるいは、いつ崩れるとも分からない崖の下に住まう生活は、夫婦が絶えず不安に苛まれている様子を象徴している。
つまり、一見仲睦まじい夫婦は、世間の断罪と、略奪の犠牲となった安井に対する罪悪感に怯えながら暮らしているのだ。
②遺産相続の問題
物語の序盤では、後ろ暗い過去の罪悪は明かされぬまま、先に遺産相続の問題が描かれる。
父親の死後に家を売り払ってできた金を、叔父夫婦が管理していた。親に勘当された宗助は端から相続を受ける積もりはなく、弟の小六の学費に充てるのが順当であった。小六はまだ学生身分なので、親代わりの宗助が叔父夫婦と交渉する必要があった。だが宗助は交渉をずるずる先延ばしにしてしまう。その結果、遺産相続の件が有耶無耶になり、小六の学費が払えないトラブルに発展する。今一度、叔父夫婦に文句の一つでも告げて、金を取り戻すべきであるが、それでも宗助はなかなか行動を起こさない。
一体宗助は何をしているのだ、と読み手は彼の怠慢な性格をもどかしく感じただろう。だが実際は、宗助の怠慢には理由があった。
元々彼は活動的で、友人の多い人間だった。だが略奪婚の末の悲惨な運命に迫られて以来、遠慮がちな性格になってしまったのだ。それは無論友人の坂井に対する罪悪感や、親戚や世間に対する後ろめたさに起因する。
つまり後ろめたさや罪の意識から、世間の荒波を立てないよう努める癖が身につき、遺産相続のような重大な問題が迫っても、優柔不断な態度を取ってしまうのだ。
③子供に恵まれない問題
加えて夫婦には、子供に恵まれない問題も積み重なっていた。
御米は過去に三度出産に失敗している。間接的に自分が子供を殺している罪悪感に苛まれた御米は、易者と呼ばれる占い師の元へ訪れる。すると易者は、「過去の罪が祟って、あなたには一生子供ができない」と宣告する。
易者のこの言葉は、御米の心中を見事にえぐることになる。なぜなら夫婦は、略奪婚の犠牲となった坂井に対する罪悪感を認めており、子供ができないのはその因果と考えずにはいられなかったからだ。
宗助は子供ができないことをさして懸念していない。しかし御米は女性としての尊厳を否定されるような苦悩を抱えることになった。ゆえに二人の心はどこか通じ合わない部分がある。
この夫婦の心の食い違いは作中で重要な意味を成している。
世間に虐げられた分際である夫婦には、お互いだけが唯一の支えであったし、実際に二人は仲睦まじく見えていたが、実は深い部分では通じ合っていなかった。過去の因縁で子供に恵まれない問題に関しては御米一人だけが苦しんでいる。また、友人の坂井が東京にやって来た危機に関しては、宗助は御米に打ち明けず一人で悩んでいる。
陰鬱な生活では、夫婦がお互いを過度に気遣い、また悲観的にならぬよう取り繕っているため、本音をさらけ出せず、そのせいで各々が一人で苦しむ羽目になっていたのだった。
「門」が象徴するものとは?
坂井が東京にやって来て、彼と顔を合わせる危機に迫られた宗助は、精神衰弱に陥る。その末に宗助は、鎌倉の寺で参禅し、信仰に救いを求めようとする。
だが座禅を組んで問題と向き合おうとするが、一向に悟りが開ける気配はなかった。それどころか、彼の前には二度と開かれぬ「門」が存在する、という絶望的な観念に到達してしまう。
彼は門を通る人ではなかった。また門を通らないで済む人でもなかった。要するに、彼は門の下に立ちすくんで、日の暮れるのを待つべき不幸な人であった。
『門/夏目漱石』
「門」とは信仰による悟りの入り口を象徴したものだと考えられる。
ともすれば、「門を通る人ではないが、通らずに済む人でもない」とは、まさに優柔不断な宗助の境遇を言い表している。
世間体に抗って略奪婚を果たした宗助には、逃れられない選択が迫っていた。それは世間の侮蔑を受け入れ、また坂井にどんな復讐をされても耐えるという諦念に近い選択である。だが彼は臆病ゆえにその決心ができず、坂井から逃げ、世間から身を隠していた。その結果彼は絶えず苦悩する羽目になった。だからこそ彼は宗教に救いを求めたのであり、そういう意味で「門」を通る以外に救われる道はなかった。
だが宗助には実生活を捨ててまで悟りの道に進む決心もできなかった。世間に苦しめられても、完全に世間を捨てることはできない。だから彼は「門」を通れる人ではなかったのだ。
いずれの決心もできぬ彼は、ただ門の前に佇む、永久に救われない人間なのだった。
参禅から帰宅すると既に坂井は東京を去っていた。一時的に危機は免れたのだ。だがあくまで”一時的”である。
最後の場面で、御米が春になったことを喜ぶ。しかし宗助は「じきに冬になるよ」と口にする。つまり、夫婦の不安や罪の意識は、季節が繰り返し巡るように、永久に彼らに付き纏うことを示唆しているのだろう。
ちなみに、宗教に救いを求める展開は唐突で、坂井との問題を雑に投げ出した感じが否めない。実際に、この唐突な展開は非難の対象になることが多い。当時の夏目漱石が肉体的に衰弱していたことや、弟子たちが推奨した「門」というタイトルに無理やり関連付けようとしたことが理由だと言われている。
■関連記事
➡︎夏目漱石おすすめ作品10選はこちら
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら