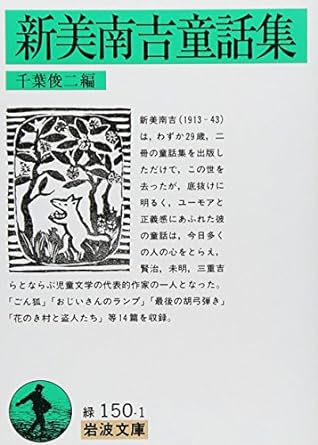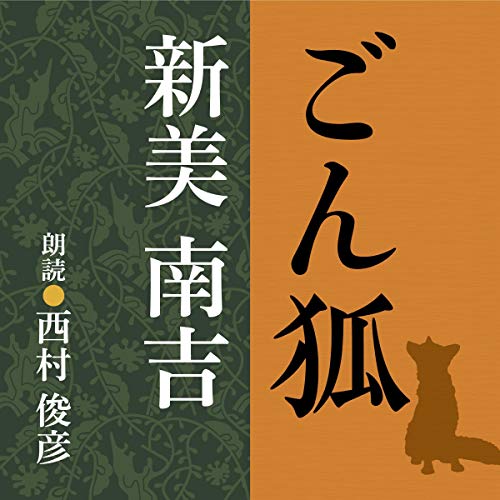新美南吉の童話『ごん狐』は、児童文学の傑作、教科書掲載定番の名著です。
口伝として古くから存在する物語を基に創作し、絵本やアニメにもなり広く親しまれています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、作中に仕組まれたトリックをネタバレ考察しています。
目次
作品概要
| 作者 | 新美南吉(29歳没) |
| 発表時期 | 1932年(昭和7年) |
| ジャンル | 童話 短編小説 |
| ページ数 | 12ページ |
| テーマ | 存在価値 孤独 愛情不足 贖罪 |
あらすじ
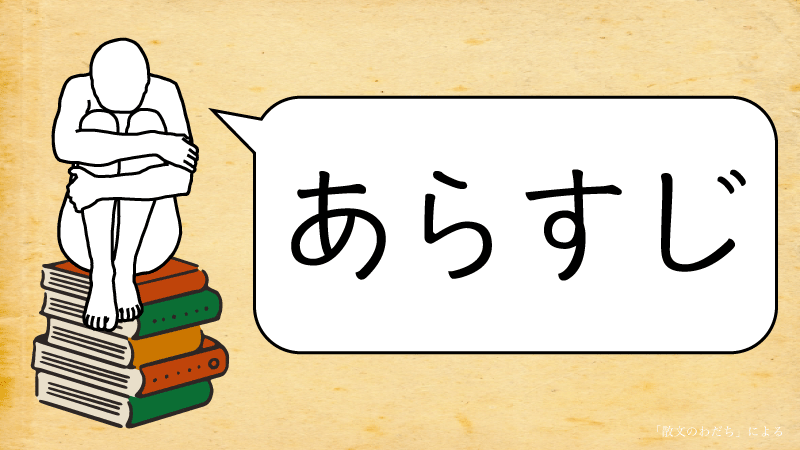
両親がいない小狐の「ごん」は、悪戯をして村人を困らせてばかりいました。
ある日、兵十が川でとったウナギを逃がすという悪戯をします。それから数日後、兵十の母親の葬列を見た「ごん」は、自分が逃がしたウナギが病気の母親のために捕まえたものだった事実を悟り、流石に後悔します。
罪悪感を抱いた「ごん」は、ウナギを逃がした償いのつもりで、兵十の家に栗や松茸を届けるようになります。もちろん兵十は狐の仕業とも知らず、神様の恵みだと考えます。
その日、いつものように「ごん」は栗を届けに兵十の家にやって来ました。しかし偶然に気配を察知した兵十は、また狐が悪戯に来たのだと思い、戸口を出ようとする「ごん」を火縄銃で撃ってしまいます。その直後に初めて、今まで「ごん」が栗や松茸を届けていた事実を悟ります。
「ごん、おまえだったのか。いつも、栗をくれたのは。」と問いかける兵十に対して、「ごん」は目を閉じたまま頷くのでした。
Audibleで『ごん狐』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『ごん狐』を含む新見南吉の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
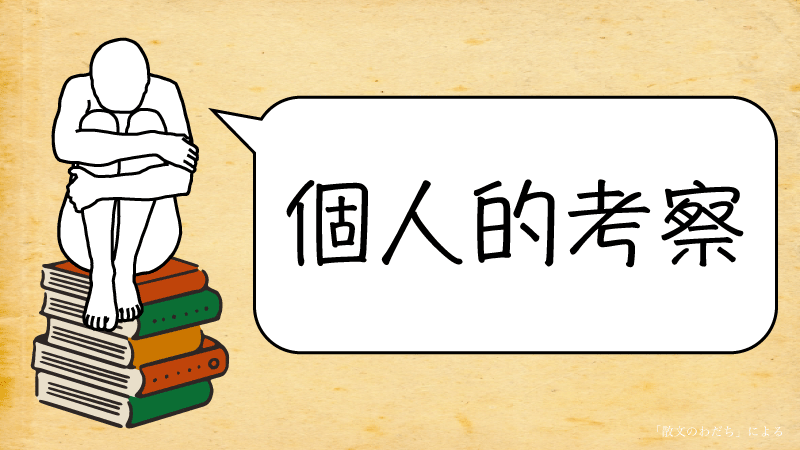
物語が3パターン存在する?
考察の前にお伝えしなければいけないのは、この『ごん狐』という作品は3パターン存在し、多少なりとも変更点があるということです。
古くからの口伝の物語では、「ごん」が兵十の母親の葬列を見たことで悪戯をしなくなる、という物語で完結しているようです。それ以降の「ごん」が撃ち殺されるまでの展開は、新美南吉独自の創作だと言われています。
つまり口伝を抜きにすれば、純粋な意味で新美南吉の作品と呼べるのは草稿の『権狐』になります。それを鈴木三重吉が幼児向けに修正したものが『ごん狐』 です。そして教科書に掲載されている『ごんぎつね』は鈴木三重吉による加筆修正版に限りなく近い作品になっています。
つまり、我々が慣れ親しんだ『ごん狐(ごんぎつね)』は、新美南吉の原作とは多少異なるということです。
ともすれば、新美南吉の原作と鈴木三重吉の修正版にはどんな変更点があるのでしょうか。
具体的には、当時の社会情勢が見える表現を排したり、方言などの地域色を薄めたり、より大衆に理解しやすい文章に変更されています。(「納屋」が「物置」に変更されるなど)
あるいはラストの火縄銃で撃たれた「ごん」が、兵十に「おまえだったのか」と尋ねられる場面に大きな違いがあります。
我々が慣れ親しんだ作品だと、「ごん」は目を閉じたまま頷いて物語は幕を閉じます。しかし、南吉の草稿では「権狐は、ぐつたりなつたままうれしくなりました。」という描写が綴られています。「ごん」はうれしくなって死んでいったのです・・・。
この重要な変更点については後ほど詳しく考察します。
新美南吉の孤独な過去
『ごん狐』を考察するには、作者である新美南吉の人生を知ることが不可欠です。なぜなら「ごん」や「兵十」といった主要人物は作者の写し鏡だと言えるからです。
新美南吉は4歳の頃に母親を亡くし、そのことが生涯の薄幸の出発点だと言われています。程なく父親は再婚し、弟が誕生するのですが、南吉は8歳で祖母の家に一人養子に出されます。
幼少期に十分に愛着形成されなかった南吉には、底知れない孤独や寂しさがあったことが推測されます。それ故に、彼の作品には自身を「不幸者」とする設定が少なくありません。
『ごん狐』の「ごん」は、両親を亡くして一人孤独に過ごしていました。母親と死別し、父親にも捨てられた(養子に出された)作者の惨めな境遇が、そのまま「ごん」のバックグラウンドに反映されていることが判ると思います。
あるいは兵十の母親が死ぬ展開からも、南吉の死別した母親に対する執着が感じられます。もちろん口伝の物語なので、そのすべてを南吉が創作したわけではないのですが、少なからず南吉は自らの境遇から口伝の物語に愛着を感じ、創作にあたって一層自分の屈折した思いを投影させたのではないかと考えられます。
孤独な「ごん」が求めた存在価値
前述の通り新美南吉の原作では、兵十に火縄銃で撃たれた後の「ごん」は、うれしくなって死んでいきました。
果たしてなぜ「ごん」は最後に”うれしい”という感情が芽生えたのでしょうか?
一般的な考察では、「ごん」はウナギを逃がしたことに罪悪感を抱いており、最後に兵十に自分の償いの行為を知ってもらえて、許されたような気持になった、と言われています。
もちろん罪の意識から解放された綻びも含まれていたでしょうが、もっと根源的な部分には自身の存在価値にまつわる問題が含まれているように感じます。
独りぼっちの「ごん」には、母親と死別し父親に養子に出された作者の孤独な境遇が反映されていると前述しました。ともすれば、「ごん」が村で悪戯ばかりしていたのは、愛着形成が十分にされなかった孤独な自分の存在を他人に気づいてほしい、というある種のSOS的な意味があったのではないでしょうか。食べもしないウナギを盗むなど、「ごん」の悪戯には決して目的や思想がなく、ただ自分の存在価値を周囲に認めてもらいたい想いが拗れた結果だと考えられます。
「ごん」は罪償いの目的で兵十の家に栗や松茸を届けていました。ただし兵十が神様の恵みだと思っていることを知り、「ごん」はつまらない気持ちになります。要するに、根本的に自分の行為を認めてもらいたい願望が罪の意識よりも前提に存在するのでしょう。
だからこそ、最後に兵十に自分の行為を気づいてもらった瞬間に、ようやく自分の存在価値を見出すことが出来たのではないでしょうか。ましてやこれまでは悪戯という手段でしか自分に価値を見出すことが出来なかったのですから、最後に善い行いによって他人に認められた「ごん」は、本当の意味で報われて、うれしくなったのでしょう。
悲しい印象が強い本作ですが、原作版を読めば物語の本質的な意図が見えるのでした。
ちなみに鈴木三重吉による修正版では、作品を普及させる目的で、贖罪の要素を強調したと言われています。つまり悪いことをしたら罪償いをしなければいけない、という道徳的な主題に焦点を当てて、大衆に浸透させたのです。それどころか、「ごん」は頷くだけで死んでいくのですから、罪償いをしても微塵も救われません。厳罰のイメージを濃くすれば、教育の題材としては都合がよかったのかもしれませんね。
ただし文学は人間を裁くものではありません。なぜ孤独な「ごん」が悪戯を行ったのか、あるいは栗や松茸を届け続けたのか。それを紐解いていくのが学問の役割でしょう。
これらの理由から、個人的には「うなずきました」よりも、原作の「うれしくなりました」というエンディングを好みます。
皆さんはどちらがお好きですか?
オーディブル30日間無料
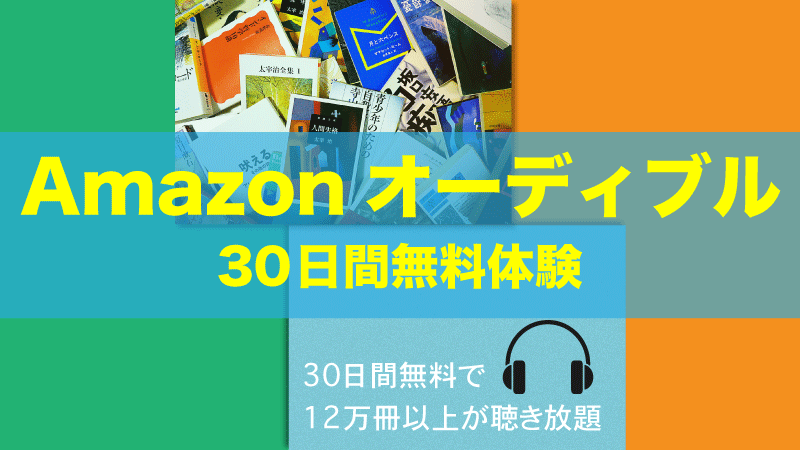
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら