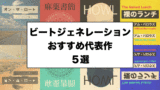ケルアックの『オン・ザ・ロード』は、ビートジェネレーションを代表する長編作品です。
1950年代のアメリカ文学会で異彩を放ったビートジェネレーション。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
目次
作品概要
| 作者 | ジャック・ケルアック |
| 国 | アメリカ |
| 発表 | 1957年 |
| ジャンル | 長編小説 ビートジェネレーション |
| ページ数 | 524ページ |
| テーマ | くたびれの世代の放浪 自由と狂熱 モダンジャズのような生き方 |
| 関連 | 2012年に映画化 フランシス・コッポラ総指揮 |
あらすじ

1947年の7月、作家のサルは、ニューヨークから路上に出た。友人たちがいるサンフランシスコに向かうためだ。そして何より、「西部の太陽の子」ディーン・モリアーティに会うためだった。
ごろつきの父親の元に生まれたディーンは、いわゆる西部の非行少年だったが、生きることに興奮しまくっていた。「いいね!いいね!いいね!」「万事順調!」それが彼の口癖だ。馬鹿で愚者で狂ったディーンは、「ビート(くたびれた)世代」の聖者で、サルもまた彼の生き方に感化されていた。
それからの数年間、サルとディーンは、三度アメリカ大陸を車で横断する。デンヴァー、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューオリンズ。その全てが彼らにとって刺激的で、恍惚で、人生そのものだった。ディーンは三度の結婚をし、その度に片隅の生活に落ち着いたかと思えば、性懲りも無くまた路上に飛び出す。セックス、ドラッグ、アルコール、そしてモダンジャズ。そう、彼らはジャズのような即興性の中に、人生たるものを見出し、生きることがどういうことか、時間がどういうことかを理解し、胸に迫る言語化できない「アレ」に近づくために放浪を続けるのである。
そして彼らの旅は、4度目の放浪、アメリカ縦断にて幕を閉じる。さらなる最終的なものへ近づくために辿り着いたメキシコ。果たしてそこに最終的なものがあったのかは分からない。
サルが最後に見たディーンの姿は、ニューヨークでコンサートに向かう途中の車内からだった。彼はまた路上に出ようとしていた。しかし同席していた人々は、ごろつきのディーンを車に乗せることを拒んだ。仕方なく、ディーンはとぼとぼ歩き出した。ボロ着をまとったディーンが通りを歩いていく姿を、サルは車の窓からずっと見つめいていた。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

ビートジェネレーションとは
1950年代、第二次世界大戦後のアメリカ合衆国の文学界で異彩を放ったグループを、総称して「ビートジェネレーション」と呼びます。代表的な作家として、ケルアック、ギンズバーグ、バロウズなどが挙げられます。
そもそも「ビートジェネレーション」とは、作家ケルアックが生み出した造語です。
騙されふんだくられ、精神的肉体的に消耗している世代。
その一方で、音楽的ジャズ的「ビート」として、躍動感のある興奮した世代、という正反対の意味をも有します。まさに『オン・ザ・ロード』の登場人物、ディーン・モリアーティを表したキャッチコピーと言えるでしょう。
そんなビートニクの思想は、ざっと以下の通りです。
・標準的な価値の拒否
・スピリチュアル世界の探究
・西洋と東洋の宗教融合
・経済的物質主義の拒否
・死・感情・願望・葛藤などの描写
・ドラッグを使用した精神実験
・性の解放と探究
いわゆるアメリカにおけるカウンターカルチャーの走りと言えます。
事実、彼らの文学作品は、のちのヒッピーカルチャーに多大なる影響を与え、あるいは1960年代のロックンロールやフォークシーンにも引き継がれていきます。ボブディランは、『オン・ザ・ロード』を「ぼくの人生を変えた本」と明言しています。
1950年代といえば、冷戦の時代です。米露が軍事力や科学力を誇示し、しのぎを削っていました。弾道ミサイルや核実験、人工衛星の打ち上げ。そういった政治的な背景から考えると、ビートジェネレーションの放浪やドラッグや精神世界の探求は、社会に対する反抗・逃避だったのでしょう。そして1960年代のベトナム戦争によって、その反抗は飽和点に達し、一部の文学グループだけでなく、ユースカルチャー全般にまで波及していくことになったのです。
■関連記事
➡︎ビートニクおすすめ代表作5選はこちら
ケルアックにとってのビートとは
前述した通り、「ビートジェネレーション」の思想は、のちに政治的思想に統合されていくことになりましたが、ケルアック自身は政治的なコンテキストを否定しています。
あの連中は、自分たちの政治的社会的な目的のために、若者の動きをつかまえたいだけさ。おれはそういうのとはまったく関係ない。
文芸誌「パリス・レビュー」
ケルアックが言うには、楽しいことを求めて車で旅をしている連中こそがビートで、それ以上の意味はないとのことです。そして同じビートニクの作家たちに仲間意識などはなく、自分は一匹狼だと言っています。
ここに一つの純粋な答えが存在します。いわゆる反体制、アナキズムの歴史を考えたとき、しばしば左翼主義団体と結びつきますが、彼らは集団、コミュニティを築いています。コミュニティができる以上、そこには必ず人間社会の構図が出来上がり、果ては浅間山荘事件のように、内部による支配が発生してしまうのです。支配から逃れるアナキズムが、内部に支配を生み出す矛盾。
そういった点で、ケルアックの主張する「一匹狼」こそ、誰からの支配も受けずに生きる純粋なアナキズムと言えるのではないでしょうか。
自分の楽しみのためだけに生きて、興奮に任せて路上に出る。何か特定の対象に反抗するのではなく、そんなものの外で自由に楽しむ。それがビートジェネレーションの真意なのです。事実「オン・ザ・ロード」には、一節たりとも政治的思想や、反抗すべき敵が描かれません。
あえて反抗の対象をあげるなら、それは写真に収まるような退屈な人生を送ってる民衆かもしれません。
まったく、悩まずにはいられねえ連中なのよ。(中略)万人が認めるお墨付きの悩みごとを見つけるまで安まらねえ。そして見つけると、今度は、それに似合った表情をしてみせる。つまり、不幸ですよってな顔よ。
『オン・ザ・ロード/ケルアック』
ディーンは、自己憐憫に心酔して人生を無駄にする連中を軽蔑していました。そんな生き方がいかに退屈かを、彼はちゃんと知り、そうでない生き方を体現していたのです。
生きることがどういうことか、時間がどういうことか。本作で描かれるテーマの答えは、自分の楽しみのために自由に生きる、ただそれだけのことなのでしょう。
とは言え、ケルアックはインタビュー等でホラを吹く側面がありましたから、実際に彼が何を考えていたかは分かりません。それぞれの解釈で読めばいい、それも自由、「ビート」だ、という事なのかもしれません。
サルやディーンが求めていたもの
「最終的なものなんか手に入らないよ、カーロ。最終的なものに辿り着くやつなんかいない。みんなそれを手に入れたいと思って、生きてるだけさ」
『オン・ザ・ロード/ケルアック』
最大限に今この瞬間の自由を実感すること、ジャズの即興性のように瞬間瞬間を興奮し続けること。ただそのためだけに生きる、それが本作の大きなテーマでした。
ただし、興奮に狂った放浪の中で、サルやディーンは、何かを求め辿り着けないような感覚をも抱いています。
作中でディーンが、「今度こそアレに近づける」と口にするように、彼らは言語化できない最終的なものを求めてアメリカを横断縦断しているのです。その最終的なものとは、母胎にいるときには存在したが、生まれた瞬間に失ったもの、そして死んだときに再び手に入るもの、なのだそうです。
新しい街に辿り着いた瞬間や、バーでジャズの演奏に狂った瞬間には、彼らはその最終的なものに限りなく近いところまで辿り着いたような感覚になるのですが、それでも完全に手に入れることはできません。だからこそ彼らは狂ったように何度も次の街へ向けて車を加速させなければいけなかったのです。
ひとえにこれは、作者のケルアックがいわゆる「ロストジェネレーション」の時代に生まれ、世界恐慌、世界大戦といった歴史的史実の中で、虚無感や絶望感を抱えていた背景に起因するのだと考えられます。
主人公のサルには父親がいませんし、ディーンの父親は飲んだくれのごろつきです。その理由は明確に記されませんが、おそらく第一次世界大戦ないしはその後の世界恐慌の影響を直に食らった結果だと考えられます。そういった敗北的な世代の親の元に生まれた彼らは、社会がいかに絶望的で不条理か、ということを知らず知らず学んだのでしょう。だからこそ、自分達は何にも縛られず自由に生きたい、という激しい願望に取り憑かれていたのだと思います。
つまり、彼らが求めていた最終的なものとは、完璧な自由と精神の解放でしょう。
しかし引用の通り、そんなものは存在しないのです。この世に生まれた瞬間に完璧な自由や精神の解放は損なわれ、それは死によってしか再び手に入れることができないのです。
そういった背景を踏まえると、彼らのイカれた放浪の旅は、どこか物悲しく、無力に感じられます。それでも社会の支配に抗い、さらなる興奮を求め続ける彼らの姿こそ、この世で最も美しいと思いませんか?
モダンジャズのような生き方
作中には頻繁にモダンジャズのアーティスト名や、ジャズ演奏の場面が描かれます。
それというのも、物語はロックンロールが産声をあげる前の、モダンジャズ全盛期が舞台だからです。
アフリカ系アメリカ人を起源とするジャズは、いわゆる非支配者である黒人が、悲しみや憂鬱を歌った「ブルース」から派生した音楽です。初期のジャズはスウィングを基調とした、ビッグバンド形式のダンサブルな娯楽音楽でした。ところが1940年代になると、バードの名で知られるチャーリー・パーカーを筆頭に、ビバップが誕生します。
ビバップはそれまでのジャズとは異なり、早いテンポかつ即興演奏を多用するのが特徴です。作中で何度も綴られる「バップ」とはこのことです。
そしてこのビバップの即興性こそが、ビートジェネレーションの価値観とピタッとハマったのです。
瞬間瞬間の興奮を求めて、何に縛られることもなく自由に生きる。それはまるで、一音一音が即興的に生み出される自由なモダンジャズのようです。
何が正解か間違いかなどは問題ではない、既存の価値観に囚われず、勝手気ままに、自己のエクスタシーのために、音楽を奏でる。サムとディーンの旅も、その時の興奮のままに行き先を決め、そこで出会った人間と狂ったように暴れ、セックスをし、どこまでもぶっ飛び続ける。まさにモダンジャズのような生き方です。
ちなみにビートジェネレーションの作家たちも、執筆において即興性を重視していました。
とりわけケルアックは異常で、『地下街の人々』を72時間で書き上げ、『オン・ザ・ロード』を3週間で書き上げたと言われています。(実際は何年も構想していたという説の方が有力だが・・・)
あるいは、「ビートジェネレーション」の命名や、ギンズバーグの『吠える』、バロウズの『裸のランチ』などのタイトルも、ケルアックが即興的に命名したと言われています。ただ単に適当な言葉を選ぶのではなく、あらゆる意味を含む秀逸な言葉を即興的に選び抜く点で、彼は本当に天才だったのです。
サルとディーンの別れ
ラストは非常に悲しい別れが待っていました。
コンサート会場に向かう車に乗るサルは、路上から駆け寄るディーンを目撃します。ディーンは再びアメリカを横断しようとしていました。そして駅まで車に乗せて欲しいと頼んできます。ところが同席していた連中は、ごろつきのディーンを拒みます。そのためディーンはとぼとぼ路上を歩き去っていきます。サルはその様子を車の窓から見つめていました。それがディーンを目撃した最後でした。
ここには決定的な二人の断絶が見て取れます。
あらゆる制約を嫌い自由に生きていた二人でしたが、最終的にサルは、ディーンではなく連中の面目を優先します。つまり自由よりも、世俗的な生き方を優先したのです。この場面が最後の対面だったことから、二人は全く別の人生を歩むことになったと考えられます。
かつてのサルは、ディーンを完全に擁護していました。年を重ねるごとに周囲の人間はディーンを軽蔑するようになり、あいつは自分の楽しみのためにしか生きていない、と罵ります。しかしサルは、みんな彼のそういう狂った部分を崇拝し楽しんでいたはずじゃないか、と弁護していました。
ところが、メキシコで赤痢にかかったサルを見捨て、ディーンが勝手に去っていった出来事は、二人の圧倒的な差異を明らかにします。
つまり、ディーンは根っから自分の楽しみのためにしか生きることができず、友人を看病する暇もなかったのです。そんなことは初めから分かりきっていたことですし、サルも恨んでいるわけではなさそうでした。しかし、自分はディーンのようにいつまでも自由に生きていくことはできない、と自覚するきっかけになったことは事実でしょう。
西部の太陽の子、ディーンのように生きられる奴なんて他にはいない。だからこそ最後まで彼と一緒に居れる奴もいないのです。
本当の自由を求める人間はいても、本当の自由を求め続けることができる人間は殆どいない。そんな悲しいエンドロールだったのだと、何度読み返しても胸がギュッと締め付けられます。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら