小説『ロリータ』は禁断の少女性愛を描いた、ロシア人作家ナボコフの代表作である。
中年男性ハンバートが12歳の少女ロリータに性的倒錯を起こす異常な物語は、当時凄まじい論争を巻き起こし、しかし現在では世界文学の最高傑作に位置付けられている。
今日では一般的に使われる「ロリコン」「ゴスロリ」などは、この小説が語源になっている。
1962年には、奇才キューブリックにより映画化され、そちらも不朽の名作として名高い。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を詳しく考察していく。
作品概要
| 作者 | ウラジーミル・ナボコフ |
| 国 | ロシア |
| 発表時期 | 1955年 |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 623ページ |
| テーマ | 少女性愛 |
| 関連 | 1962年に映画化 監督:キューブリック |
あらすじ

ハンバートなる人物が、獄中で書き残した手記という形式で語られる。
■ハンバートの少女性愛
フランス人のハンバートは、少年時代にアナベルという少女に恋をした過去がある。思春期間近の二人は未熟な肉体を激しく求め合ったが、間も無くしてアナベルは病気で死ぬ。彼女の死によって受けたショックが大人になっても忘れられず、絶えずアナベルの幻影を求め続け、一度は結婚したものの上手くいかなかった。
生まれ持った異常性癖か、アナベルのトラウマがそうさせたのか、ハンバートは9歳から14歳の少女に限定して性欲を感じる。
■ロリータとの出会い
アメリカに亡命したハンバートは、未亡人のヘイズ夫人の家に下宿することになる。ヘイズ夫人には12歳になる娘ドロレス(愛称ロリータ)がいて、ハンバートは彼女にアナベルの幻影を見出して一目惚れする。そしてロリータを思いのままにしたいがために、ヘイズ夫人と結婚して彼女の義父になる。あとはヘイズ夫人を殺害すれば、ロリータが完全に自分のものになるという狂気的な願望は、ヘイズ夫人の不慮の事故死で思いがけず叶う。
ヘイズ夫人の死後、ハンバートはロリータを連れてアメリカ中を自動車で旅する。その旅先で2人は肉体関係を結ぶようになる。そしてロリータを学校へ通わせつつも、彼女の行動を逐一チェックして独占しようとする。反抗的なロリータはハンバートの束縛を断固として拒否する。ハンバートは今にロリータが自分の元から逃げ出すのではないかと苦に病むようになる。
■ロリータの失踪
14歳になったロリータは、高熱を出して入院する。そしてハンバートがモーテルに宿泊している間に、叔父と名乗る男がロリータを連れて姿を消した。消息を追ってハンバートはアメリカ中を探しまわるが手がかりは見つからなかった。
3年後、ロリータから手紙が届き、ついに居所を突き止める。17歳になったロリータはディックという青年と結婚し妊娠していた。そのロリータが言うには、かつて彼女を病院から連れ出したのは、クィルティという劇作家の男だった。ハンバートの束縛に嫌気が差したロリータは、クィルティに着いていくことにした。ところがクィルティは極悪人で、ロリータにピンク映画の出演を迫り、それを断ったことで彼女は追い出されたという。その後ディックと出会って結婚した。
■結末
ハンバートはもう一度一緒に暮らさないかとロリータに懇願するが彼女は拒否した。こうしてロリータと永遠のお別れをすると、ハンバートはクルティを見つけ出して殺害する。しばらくしてハンバートは逮捕され、この手記を書き残して獄中で病死する。ロリータも出産時に命を落とす。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

発禁処分となった問題作
著者ナボコフはロシア人作家であり、一般的に『ロリータ』はロシア文学の傑作とされるが、しかし実際はアメリカで執筆され、フランスから出版された複雑な経緯がある。
1899年にナボコフはロシアの貴族として生まれたが、1917年にソ連樹立に繋がるロシア革命(社会主義革命)が勃発すると、イギリスに亡命し、その後ドイツに移住した。ドイツでユダヤ系ロシア人の女性と結婚するのだが、やがてヒトラー政権が台頭するとユダヤ人排斥の空気が高まり、新たなにアメリカへ亡命することになった。
アメリカの大学で非常勤講師として働いていた1950年に、本作『ロリータ』の執筆が開始された。しかし当初は難航し、何度も原稿を焼却しようとしたという。既に50歳のナボコフにとって、ロシア人でありながら馴染みのないアメリカの風俗を作品で扱うのは、あまりに困難だったのだ。
大学が休暇期間に入ると、ナボコフは妻と車でアメリカ中を旅行し、その旅先で執筆が続けられた。『ロリータ』におけるハンバートとロリータの車の旅は、ナボコフのこの旅行体験が反映されている。
そして1953年、ついに『ロリータ』は完成した。だが、アメリカの出版社はこぞって『ロリータ』の出版を拒否した。
キリスト教圏内の倫理観からすれば、少女性愛は最もタブーである。とりわけアメリカでは、子供への性犯罪はその子供の一生涯を破滅させる行為として、「第一級殺人罪」と同等の重罪にあたる。ある出版社は、「もし『ロリータ』を出版したら、わたしもあなたも刑務所行きです」と言って出版を断固拒否したという。
また、西洋人の男がアメリカ人の少女を陵辱する物語は、反米的なものと認識され、それも出版拒否の原因になったみたいだ。
こうして1年以上、『ロリータ』は出版できない状態が続いた。そして次第にヨーロッパでの出版を模索し始めると、ポルノ小説を扱うことで悪名高いフランスの出版社が手をあげた。そして1955年『ロリータ』はポルノ小説という俗悪な形で出版されることになった。
ポルノ小説が世界文学の傑作として文学史に名を刻むなどあり得ない。だが『ロリータ』に関しては、奇しくも英国の作家グレアム・グリーンが絶賛したことで、「これは文学かワイセツか」という論争が巻き起こった。とりわけカトリック団体による抗議活動が凄まじかったと言われている。
良くも悪くもスキャンダルが手伝って、出版を拒否していたアメリカでも話題になり、出版されることになった。結果的に3週間で10万部が売れ、『風と共に去りぬ』以来の大ベストセラーを記録した。
この話題を受けて、日本でも1958年に刊行された。谷崎潤一郎の『痴人の愛』『鍵』と関連をなすエロチックな文学として紹介されることが多かった。
英国などいくつかの国ではポルノ作品として発禁処分を受けたが、現在では最も偉大な古典文学として高く評価されている。
また、1962年には奇才スタンリー・キューブリックによって映画化され話題になった。
検閲や規制の関係上、ロリータ役は原作よりも年齢が上がり、性描写も全く描かれていない。キューブリック自身、「エロティックな面を強調できなかった」と不満を漏らしているが、現在でも映画ファンからカルト的人気がある。
個人的な感想としては、映画『ロリータ』は、原作の主題を描き切れていない感が強いが、それでもキューブリック作品というだけで、充分見る価値があるし、普通に面白い。
エロチックに関しては同監督の『アイズワイドシャット』の方が優れているが、『ロリータ』の方が個人的にはアイコニックで好きだ。もっとも原作者のナボコフは満足していないみたいだが・・・
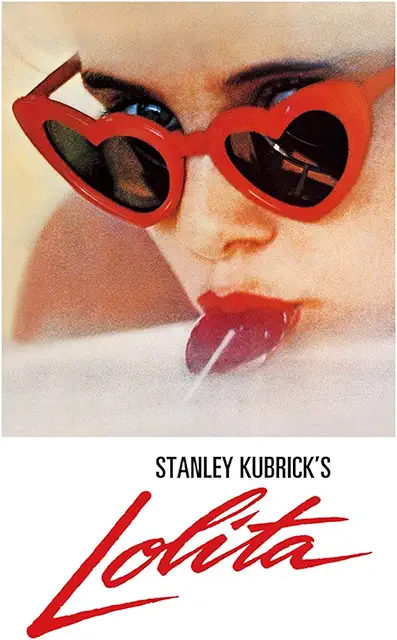
ロリータ(ニンフェット)の定義
ロリコン、ロリータファッション、ゴスロリ。今日では性癖やファッションの分野で一般的に使われるこれらの語源は、ナボコフの『ロリータ』に由来する。ロリータそれ自体に語源はなく、単に少女ドロレスの愛称として用いられるニックネームだ。
少女性愛、少女趣味、それらにまつわるサブカルチャーとして、「少女っぽいもの」を漠然と指す言葉として用いられるが、しかし、ナボコフの『ロリータ』には明確な定義がある。
- 年齢:9歳〜14歳の範囲
- 2倍以上の年齢(30歳以上)の男性を魅了する
- 外見的な美しさは判断基準にならない
- ニンフ(悪魔)の本性を持っている
年齢の定義はともかく、「悪魔的な本性」が最も重要な条件である。
作中ではこの悪魔的な本性を「ニンフェット」と称し、それはギリシャ神話の女神ニンフに由来する。
ニンフは山や森に宿る精霊で、歌と踊りを好む若くて美しい女性の姿をしている。一方で若い旅人を魔力で惑わせる恐ろしい一面も有している。こうした神話伝承から、ニンフは過剰性欲の女性を指す「ニンフォマニア」の語源にもなっている。
いわば、男を破滅させる魔性の女(ファム・ファタル)の素質を持つ少女、という表現がわかりやすいかもしれない。
もっともファム・ファタルは、オスカー・ワイルドの『サロメ』のように、男を破滅させるほど金や性に強欲な女性というイメージだが、ニンフェットの場合は、まだ少女であるゆえに、本人ですら自分の悪魔的な魅力に気づいていないのが特徴である。
この世のものとは思えぬ優雅さ、掴みどころがなく、変幻自在で、魂を粉砕してしまうほどの邪悪な魅力、それこそが、たとえ年齢が同じでもニンフェットとそうでもない者を分かつのである。
『ロリータ/ナボコフ』
実際にロリータのどういった点に、ニンフェットの魅力があるのか。作中では、ロリータのニンフェット的な魅力が、学術的に、ユーモラスに、リズミカルに、言葉遊び的に記され、それが本作最大の魅力なのだが、言ってしまえば、無自覚な少女のあざとさに尽きる。
ロリータは典型的な小生意気な少女で、母親に対して反抗的だが、一方で「キスごっこ」と称してハンバートを誘惑し、それで動揺する彼を見て揶揄う性質がある。もっとも幼いロリータにとって、肉体的な行為は「ベタベタロマンチック」なる言葉で表されるように、必ずしも官能的な認識と結びついているわけではなく、その行為を通して動揺する大人を見て楽しむ、限りなく純粋なイタズラ心のように見える。そしてそれこそが、本人すら認識し得ない悪魔的なニンフェットの素質だ。
しかし、それらはハンバートがヘイズ夫人の家に下宿して次第にわかり始めたことであり、それなのにハンバートは一眼見た瞬間にドロレスが、悪魔的な本性を持つニンフェットだと見極める。作中に記される通り、ニンフェット狂の男は、たとえば少女の集合写真を見るだけで、誰がニンフェットかを見極める感覚能力に優れているのだ。
ハンバートの少女性愛の理由
幼児性愛を先天的な疾患とする場合もあれば、子供時代のトラウマを原因とする場合もある。ハンバートの場合は、後者の子供時代のトラウマが原因になっている。
12歳のハンバートは、同世代の少女アナベルと恋に落ち、思春期間近の2人は互いの肉体を求め合わずにはいられなかった。そのアナベルを病気で失ったトラウマがハンバートの人生に齟齬を生じさせ、大人になっても彼女の幻影を絶えず求めることになった。
アナベルが死んでからずっと後になっても、彼女の思考が私の思考の中をただよい過ぎていくのをよく感じたものだ。
『ロリータ/ナボコフ』
それでも私は、ある魔術的かつ宿命的な形で、ロリータはアナベルから始まったと確信している。
『ロリータ/ナボコフ』
子供時代のトラウマは、その後の人生において回帰願望として現れることがある。ハンバートの場合、子供時代にアナベルと死別した喪失感から、彼女の代わりを求める行為を通じて子供時代への回帰願望が現れ、それが少女性愛の発露になったわけだ。
そしてアナベルの幻影が、ロリータと一致したとき、彼は過去の呪縛から解き放たれたのであり、彼はそれを「転生」と呼んでいる。
少女(アナベル)はそれからずっと私に取り憑いて離れなかった––––その呪文がついに解けたのは、二十四年後になって、アナベルが別の少女に転生したときのことである。
『ロリータ/ナボコフ』
ロリータを一目見た瞬間に、ハンバートはかつて愛撫したアナベルの肉体を想起し、2人には多くの共通点があり、やがて2人の存在(過去と現在)が1つに重なったのである。
ハンバートとロリータの歪んだ関係
少女性愛が非道徳という前提はさておき、これを中年男性と少女の恋愛小説とするなら、それは決して純愛とは言えない歪んだ想いで結びついた恋愛関係である。
当初ロリータが見せた、ハンバートに対して甘える言動(本を読んでもらうために膝の上に座ったり)は、父親を持たぬ娘が、不足した愛情をハンバートに求めていたと考えられる。また母親のヘイズ夫人は厳格なキリスト教徒で、娘に対するしつけが手厳しかったため、ロリータにとってハンバートが優しい父親の代わりの拠り所になっていたのだろう。
そして母親ヘイズ夫人の死後に、ハンバートとロリータは車でアメリカ中を旅し、その旅先で肉体関係を結ぶ。当初ハンバートは睡眠薬でロリータを陵辱しようと考えていたが、結果的にはロリータの方からあっさり行為に及ぶ。そうしたロリータの言動を前章では、動揺する大人を見て楽しむ「ニンフェットの本性」と記したが、これはあくまでハンバートの主観であることを忘れてはいけない。
次章にて詳しく説明するが、この小説はハンバートが獄中で書いた手記という形式が取られ、ゆえにどこまでが真実で、どこからがハンバートの嘘であるか、はっきりしない。そして彼の主観で書かれた文章であるため、実際にロリータが何を感じていたのか、果たして彼女が本当にニンフェットの本性を持っていたかすら、ハンバートの勝手な思い込みである可能性が高いのだ。これは「信頼できない語り手」と呼ばれる叙述トリックである。
唯一ロリータの本音が語られるのは、16歳になり結婚した彼女に再会する終盤の場面である。
あたしの心をめちゃくちゃにしたのはあの人(クィルティ)なの。あなた(ハンバート)はあたしの人生をめちゃくちゃにしただけ。
『ロリータ/ナボコフ』
確かに当初のロリータは、ハンバートに父親代わりの愛情を求めていた。ところが母親が死ぬと、14歳の自分は義父に捨てられたら生きていけないという強迫観念に変わる。そのためロリータは、生きていくためにやむなくハンバートに肉体を与えていた感が強い。
この時点で2人の関係性は対等ではない歪んだものになっている。しかしハンバートはロリータの真意に気づいておらず、ロリータを所有物として独占するために、彼女の行動(友達付き合いや、演劇への参加)などを制限する。それに対してロリータは反抗するものの、最終的にはハンバートの指示に従うことで彼を納得させる。ハンバートに捨てられたら生きていけないから彼の指示に従っていたに過ぎないのだが、ハンバートはそれをロリータの愛情と勘違いしているのだ。
この2人の歪んだ関係性は、非常に親子的であり、恋人的である。親は社会的弱者である子供の生活基盤を握っていることを盾に、利己的に子供を束縛することができる。親は愛の名の下に惜しみなく子供から奪うことができる。こうした歪んだ関係性は恋人に対しても同様で、精神的自立の揺らぎに漬け込んで恋人を利己的に束縛することは、往々にしてあり得るのだ。
こうした異常な束縛によって人生をめちゃくちゃにされたロリータは、ハンバートといるくらいならクィルティを選ぶという決断によって、彼の元を永久に去るにことになる。
少女性愛のテーマが強烈だけに、官能的な描写を期待する読者も多いだろうが、この『ロリータ』という小説は、どんな恋愛小説よりも、どんな親子小説よりも、人間が陥りがちな利己的な愛情の歪みを描き出しているから、単なる変態小説にはとどまらないのではないか。
余談ではあるが、ハンバートからロリータを奪ったクィルティという男は劇作家で、学校の演劇でロリータが演じた『魅せられた狩人たち』の作者である。そのあらすじは、月の女神に扮した農夫の娘が狩人たちを誘惑していくが、詩人の男には逆に娘が魅せられてしまう。これはまさにロリータのその後の展開を暗示するものになっている。
ハンバートの妄想について
新潮文庫版『ロリータ』のあとがきに記される通り、世界文学の傑作と評されて久しい今日でも、絶えず本作が議論の対象とされるのは、結末近くの物語が真実か、それともハンバートの妄想かという問題があるからだ。ハンバートの妄想とする解釈を「修正派」と呼ぶ。
元より語り手のハンバートは、精神的に破綻した性格であり、至る場面で現実か虚構か曖昧な描写が錯綜する。たとえば、ハンバートが自らを、指を鳴らすだけで女性をものにできるほどのハンサムと自画自賛するのも、ほとほと怪しいものである。これは俗に言う「信頼できない語り手」であり、推理小説ではお馴染みの叙述トリックである。
そして「修正派」が結末近くの物語をハンバートの妄想と主張するのには根拠がある。ハンバートが獄中で死んだのは1952年11月16日で、その56日前に獄中で『ロリータ』を書き始めたと記される。ところが56日前にあたる9月22日は、失踪したロリータから3年ぶりに手紙が届いた日にあたり、するとハンバートが逮捕された時期の辻褄が合わなくなる。
こうした矛盾から、ロリータから手紙を受け取って以降の、クィルティを殺害するまでの物語はハンバートの妄想ではないかという主張が生まれたのだ。もっともナボコフは意図して日付の矛盾を採用したのか定かではないので、現在でもこの議論は決着がつかないままである。
確かにクィルティを殺害する場面にて、無茶苦茶に銃をぶっ放しているのに、建物内の人間が全く犯行に気づいていないのは不自然である。また、ハンバートが殺害後にバーカウンターで酒を飲んで、隣の客にクィルティを殺したと告白して冗談ぽく笑い合うのも、どこか現実離れした描写に感じられる。
もしかするとこの物語は、ロリータがハンバートの元を去った時点で終幕しており、その後のロリータと再会する展開などは、彼女を喪失したショックから生み出されたハンバートの狂気的な妄想なのかもしれない。
いずれにしても、ロリータの存在そのものが、ハンバートの妄想であるという結論で本記事の考察を終えたいと思う。元より少年時代にアナベルを失ったショックが生み出した、彼女の幻影がロリータであるならば、ハンバートは絶えず心中のアナベルの幻影をロリータに投影していたのであり、つまりロリータは実在の少女でありながら、ハンバートが生み出した妄想でもあるのだ。
そして人間というのは、多かれ少なかれ、自らの期待や理想を他者に投影するものであり、その利己的な束縛によって他者を妄想の存在に仕立て上げるとき、我々が愛する他者とは、本当にその他者自身であり得るのか、というテーマをこの物語から読み取ることができよう。
この点を踏まえて、再び『ロリータ』を読み返すとき、我々が目にする冒頭の一節は、全く違った響きに変わるのではないだろうか。
ロリータ、我が命の光、我が腰の炎。我が罪、我が魂。ロ・リー・タ。舌先が口蓋を三歩下がって、三歩めにそっと歯を叩く。ロ。リー。タ。
『ロリータ/ナボコフ』
しかし、そこにロリータの姿は見当たらない。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら





