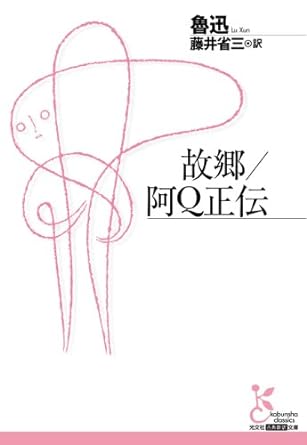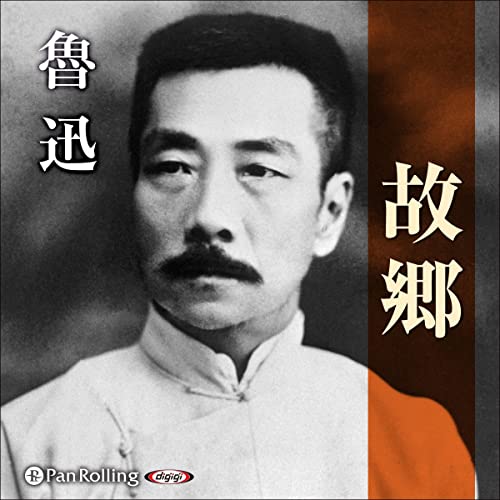短編小説『故郷』は、中国の文豪・魯迅の代表作で、教科書で読み親しまれる名著である。
20年ぶりに故郷に帰省した主人公が、少年時代の旧友と再会するも、悲しい身分の壁を感じる物語が描かれる。
『阿Q正伝』『狂人日記』と並び、当時の封建的な中国社会への風刺が込められている。
本記事では、あらすじを紹介した上で、時代背景から作者が伝えたいことを考察していく。
作品概要
| 作者 | 魯迅(55歳没) |
| 国 | 中国 |
| 発表時期 | 1921年(大正10年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 14ページ |
| テーマ | 封建的な身分制度 辛亥革命後の中国社会 |
あらすじ
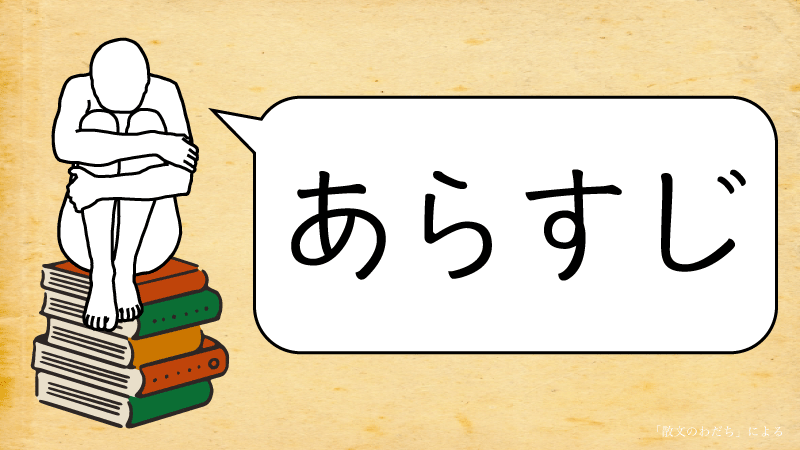
主人公は20年ぶりに故郷に帰ってきます。かつては地主だった生家も没落し、家を引き払う必要があったのです。想い出の中では美しかった故郷はすっかり色あせ、人々の心さえも貧しく荒み果てていました。
主人公は、少年時代に仲良く遊んでいた閏土(ルントー)との再会を楽しみにしていました。生家が雇っていた小作人の息子である閏土は、少年時代の主人公にとって自分の知らない世界を教えてくれる特別な存在だったのです。ところが再会した閏土との間には、少年時代には感じなかった、地主と小作人という悲しい身分の壁が存在しました。
主人公は閏土との別れ際、 甥の宏児(ホンル)が、閏土の息子の水生(シュイション)と再会を約束したことを知ります。自分たちのようにうらぶれた世代とは異なる、新しい世代に期待を託し、明るい未来の存在を願うのでした。
Audibleで『故郷』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『故郷』を含む魯迅の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
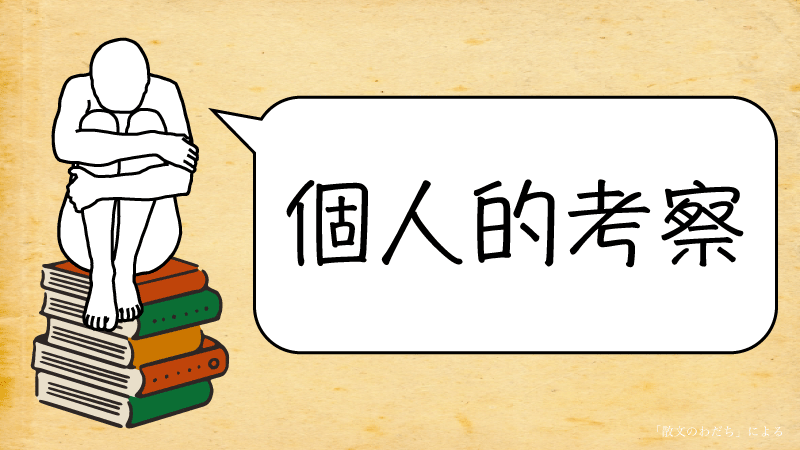
時代背景
本作『故郷』は、1920年に魯迅が生まれ故郷の紹興に帰った時の実体験が題材になっている。
1920年とは、前国家・清が打倒され、新国家・中華民国が誕生した、辛亥革命から約10年が過ぎた頃のことである。
清朝時代の中国は、アヘン戦争以来、弱体化を極め、国内の利権をヨーロッパ諸国に支配されていた。また戦争の賠償金を税金で賄うより他なく、国民は貧困に喘いでいた。
このような状況を経て、外国に支配されない強い国家を作るべく、民族独立を目指して辛亥革命が勃発した。これで何かが変わる、と少なからず魯迅は期待を覚えたものの、しかし実際は何も変わらないどころか、事態はますます悪化するばかりだった。
辛亥革命の指導者だった孫文が臨時的に大総統になったのち、軍閥の袁世凱が実権を握る。この袁世凱が混乱の元凶だ。というのも共和制を掲げて中華民国が誕生したにもかかわらず、袁世凱は再び独裁体制を復活させた。それに反対した孫文は軍事力で制圧され国外に追放される。
よって袁世凱による独裁政治が始まるのだが、彼には国内をまとめ、外国の支配に対抗するだけの権威も支持もなかった。その頃ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発し、各国による支配が弱まると、今度は日本から不平等条約を突きつけられる。これを袁世凱が承認したことで、山東半島、満州、南モンゴルの利権は日本に支配される。国内では不満が爆発し、最終的に袁世凱の独裁体制は崩壊する。しかしその後も各勢力が対立して内乱が続き、国内の混乱が収まることはなかった。
こうした政治のごたごたで最も被害を被っていたのは民衆である。作中では、小作人の閏土の厳しい暮らし向きが描かれる。作った物を売りに行けば何度も税金を取られる、と彼は告白する。というのも、強い国家を作る目的で誕生した中華民国は、依然として外国に支配されていたし、国内で対立した各政党や、軍閥などが、それぞれ勝手に民衆から税金を巻き上げていたのだ。ましてや小作人の閏土は、地主に土地の使用料を払う義務もあり、食うや食わずの生活だったわけだ。
これが20年ぶりに主人公が見た故郷の姿だった。風景はすっかり色あせ、少年時代の親友・閏土は生活苦でかつての面影を失い、美人だった豆腐屋の楊おばさんは意地汚く物乞いする始末だ。
しかし彼らは20年の間に急速に貧しくなったわけではない。彼らは元より貧しかったのであり、その現状を打破するために辛亥革命が起こった。だがいざ中華民国が誕生すると、何も変わらないどころか、国内が主導権争いで混乱し、いっそう不穏に見えた、という方が正しい。
また物語は、主人公の生家が他人の持ち物になり、家族を連れて異郷の地へ移るために故郷を訪れた場面に始まるが、これは何か当時の社会情勢によって主人公が急に没落したわけではない。作中で主人公が「迅ちゃん」と呼ばれる通り、物語は魯迅の実体験が題材になっている。そして魯迅の生家は少年時代に父親が病死したことで既に没落している。「魯迅日記」によると、生家の維持費は、当時北京に住んでいた魯迅が送金していた。そして金銭的な問題から生家を手放し、家族を北京に招き入れた。
確かに故郷を手放すにあたって、それなりの感傷はあっただろう。だがそれ以上に、魯迅には時代を切り拓く文学者としての強い意志があった。北京で新しい生活を希求する魯迅にとって、進歩がないまま古い慣習の中で滅び行く故郷の人たちが、寂寞の念を抱かせたのではないだろうか。
儒教の封建制と身分の隔たり
袁世凱による独裁体制、日本による不平等条約を経て、1919年に中国では、抗日・反帝国主義を掲げる五四運動が勃発する。この運動には女学生も参加し、男女格差や、身分格差など、いわゆる封建的な儒教に対する反抗の意も含まれていた。
そして五四運動の文脈を受けて書かれた『故郷』には、まさしく儒教に対する批判が込められている。それは身分格差による隔たりだ。
閏土は、かつて地主の主人公の家に奉公していた小作人の息子である。少年時代の主人公と閏土の間には、地主と小作人という身分の隔たりは無関係だった。むしろ高い塀に囲まれて過ごす裕福な主人公にとって、野鳥の捕まえ方や、飛び魚や狟(アナグマ)を知っている閏土は、神秘の宝庫とさえ思えた。ところが20年ぶりに再会すれば、閏土はかしこまった態度で主人公を「旦那様」と呼び、そこには明らかな身分の隔たりが生じていた。
これは儒教を支柱とする、当時の封建的な中国社会を反映している。儒教とは過剰に忠義を重んじる宗教のことだ。良く言えば目上を敬う精神、悪く言えば上の者が下の者の権利を軽んじる封建的な精神である。そして当時の中国では、力ある者が忠義の教えを利用して権力を振り回していた。
魯迅は自身の小説で、度々この封建的な儒教の虚偽を批判してきた。そして『故郷』では、より身近な「旧友との身分の隔たり」というテーマでアプローチしている。
『故郷』は中学3年生の国語の教科書に掲載され、授業では「身分差別はいけない」といった陳腐な教訓でしか語られない。中学生に当時の中国の社会情勢や、封建的な儒教の虚偽を説明するには時間が足りないので仕方ない。
しかし魯迅が物語を通して伝えたかったのは、封建的な身分格差を含む、伝統的な悪き慣習から脱却しない限り、列強にカモにされない強い中国はあり得ない、ということに他ならない。
子供たちに託す希望
主人公は、甥の宏児が閏土の息子の水生と無邪気に遊ぶ姿に、かつての自分と閏土を思い出す。そして二人が自分と閏土のように身分の違いで分断されないような、脱封建的な社会を夢想する。
魯迅は処女作『狂人日記』においても、せめて次世代を担う子供たちだけでも、儒教の虚偽から救ってやらねばならない、と常に次世代に希望を託している。
しかし『故郷』の主人公は、次世代に希望を託す想いを明かしてすぐ、それが偶像崇拝に過ぎないことを悟る。主人公が手放した生家から閏土が香炉と燭台を持ち帰ったのを、いわゆる神仏に救いを求める偶像崇拝だと主人公は内心笑っていたが、しかし主人公もまた、次世代に希望を託すという意味では、神仏に救いを求めるのと同じくらい、偶像じみているのだ。
そして主人公は、改めて希望とはいかなるものかを考える。
希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。
『故郷/魯迅』
この言葉には魯迅自身の決意が込められている。唯一人が歩いてもそれは道にならない。その者のあとに大勢が続いて初めて、道になるのだ。そして魯迅は文学を通して大衆に道を示すことで、脱封建的な新しい中国を築き上げようと考えたのだろう。
しかし『故郷』を執筆した4年後の1925年には、魯迅の中に明らかに変化が生じている。「希望」という題の日記を書き、そこにはハンガリーの詩人ペテーフィの詩が引用されている。
希望とはなに?娼婦さ
だれをも魅惑し、すべてを捧げさせ、
おまえが多くの宝物ーおまえの青春ーを失ったとき、
おまえを棄てるのだ
そして、この詩を踏襲するように魯迅は、「絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じだ」と記す。
『故郷』にて希望に対する決意を示した4年後には、希望が虚妄であると思うほどの心境に至っている。そして絶望も虚妄であるとしたら、魯迅は完全に絶望することもできず、ただ空虚な無力感の中に立ち尽くしていたのであろうか。
魯迅は幾度も本当の革命を夢想し、その度に何も変わらないという失意を経験した。翌年の1926年には、抗日運動を行う学生47名が軍隊の発砲で死亡し、それを激しく非難したことで魯迅は名手配にリストアップされる。そして1930年代には反体制文学者として、政府に作品を発禁処分される。
果たして魯迅が示した道に大勢が続く時代は到来したのであろうか。それとも彼の示して希望とは、やはり虚妄に過ぎないのだろうか。
■関連記事
➡︎魯迅おすすめ代表作10選はこちら
オーディブル30日間無料
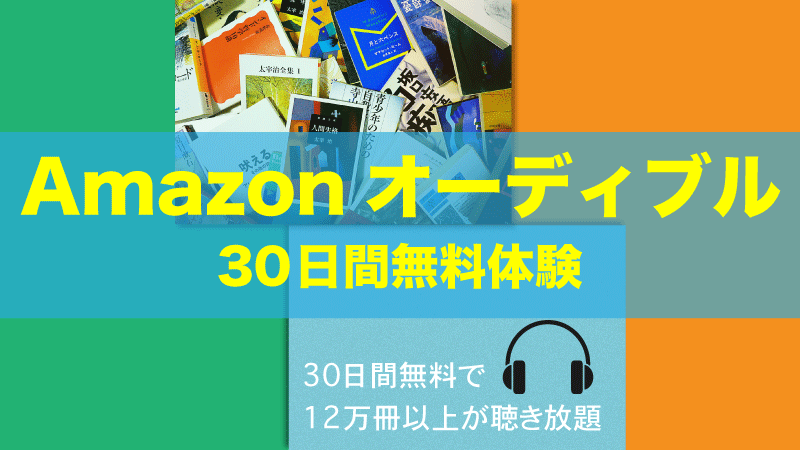
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら