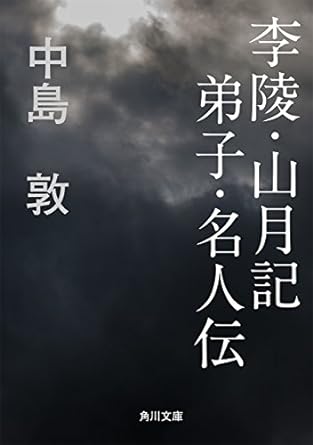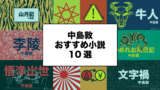中島敦の短編小説『名人伝』は、生前最後に発表された遺作です。
本作は中島敦の作品の中で特別、寓話の要素が強く、尚且つ解釈を読者に委ねる形になっているため、様々な考察がなされています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 中島敦(33歳没) |
| 発表時期 | 1942年(昭和17年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 12ページ |
| テーマ | 儒教的な教訓 偶像化の滑稽さ 芸術的価値の曖昧さ |
あらすじ
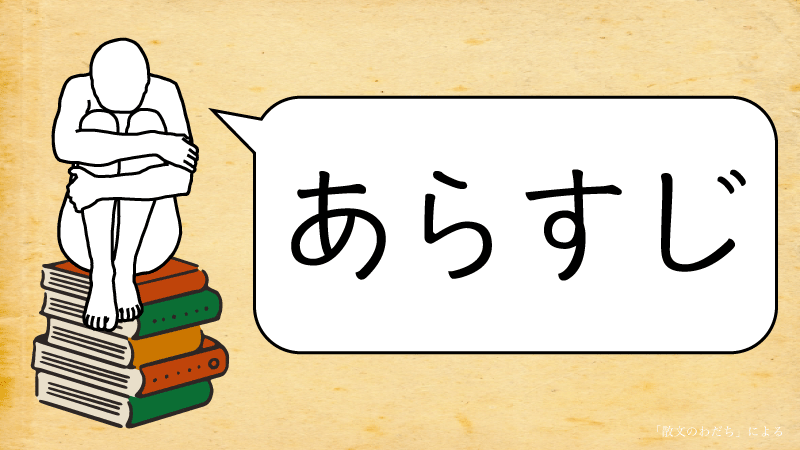
趙の都に住む紀昌(きしょう)は、天下第一の弓の名人を志していました。そのため弓の名手である飛衛(ひえい)に入門し、長年にわたる厳しい修行に専念します。
初めの2年は、瞬きをしない修行として、目前で機織り機を見つめ続けます。その結果、鋭利な錐で眼球を突かれても瞬きをしない能力を得ます。次の3年は、小さいものを視覚で捉える修行として、遠くのシラミを見つめ続けます。その結果、シラミが馬の大きさに見える能力を得ます。これらの修行の成果で、妻のまつ毛を気づかれずに弓で射抜ける繊細な技術を取得します。
修行を達成した紀昌は、師である飛衛を殺すことで天下一になれると考えますが、相討ちに終わります。向上心の止まない紀昌に身の危険を感じた飛衛は、西の霍山に隠居する甘蠅(かんよう)という名人に習うよう諭します。甘蠅は弓を使わずに鳥を射落とすことが出来る名人でした。超人的な技に魅せられた紀昌は、九年間の修行に専念します。
修行から帰ってきた紀昌は、「弓をとらない弓の名人」として有名になります。それどころか紀昌は晩年には弓の名前すら忘れていたのです。世間ではそれが名人の極みとされ、絵筆を持たない画家や、楽器を持たない楽人などが増えたのでした。
Audibleで『名人伝』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『名人伝』を含む中島敦の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
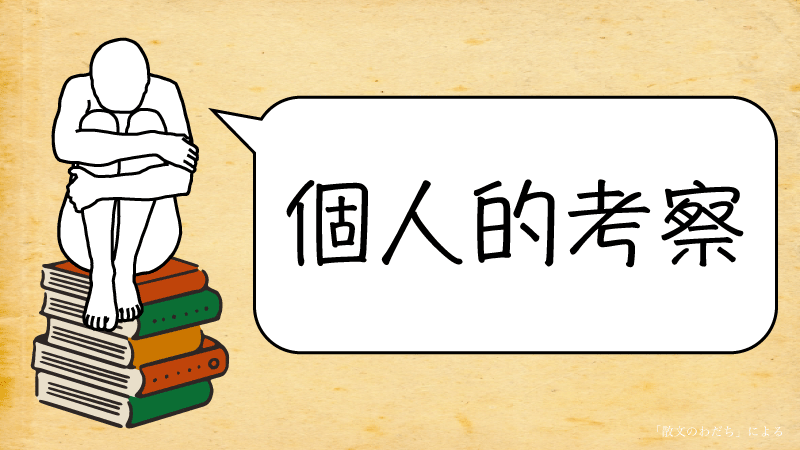
紀昌を「名人」とする説
中島敦の作品を読んだことがある人からすれば、他の著書とは違った作風に驚いたかもしれません。人によって『名人伝』は、『山月記』と対極的な作品と捉えられるようです。
- 『山月記』
プライドが高い故に、何一つ成し遂げないまま自らを破滅へ追い込む - 『名人伝』
弓の名人になるためにいかなる修行も素直に取り組み、天下一の名声を手に入れる
修行の内容は、何年も機織機やシラミを見つめるという、非常に滑稽な内容でした。仮に『山月記』の李朝であったなら、その滑稽さを嘲笑した上で修行を放棄していたことでしょう。
つまり、師に対して非常に素直で謙虚だったために、その志を成し遂げることができた、というある種儒教にも通ずる封建的な教訓が落とし込まれていたのだと思います。
21世紀を生きる我々、とりわけ終身雇用が事実上崩壊した現在に、いかなる場合も師に従順であるという考え方は理解し難いと思います。あくまで本作は中国戦国時代の著書を素材に創作されているため、師に従順であることが美学とされた時代の物語なのです。
甘蠅という超人の元での修行内容は描かれていませんが、素直な性格の紀昌のことですから、弓を使わない修行に真面目に取り組んだことは明確です。
ここで整理しておきたいのが2人の師の対照的な特徴です。
| 飛衛(1人目の師) | 甘蠅(2人目の師) |
| 実践的な修行 | 仙術的な修行 |
| 儒教的思想 | 道教的思想 |
| 弓の名人 | 弓を持たぬ弓の名人 |
甘蠅の元での修行を遂げた紀昌は、弓を使わないことが弓の名人の極み、という難解な結論に至りました。これはある意味、道教的な神仙術を指し、ひいては精神的な修行の一環を意味していたのだと思われます。
つまり、紀昌は弓を極めたその先に、弓をも超越する精神的な修行を成し遂げて、仙人になったという結末だったのではないでしょうか。
紀昌を「名人」としない説
一方で、「名人」を偶像的に捉える滑稽さ、を描いていたという考察もできます。紀昌は弓の名人にはなれなかったという解釈です。
紀昌は弓を極めたいあまり、精神世界の修行に足を踏み入れ、弓を持たないことが弓の名人の極みであるという境地にたどり着きました。少なからず本人にとってはそれが「名人」のあるべき姿だったのかもしれません。
しかし、周囲の人間は紀昌の凄みに圧倒されて、まんまと「弓を持たないことが弓の名人」という偶像的な解釈を助長させていきました。夜になると雲の上で紀昌が古の達人と弓の腕くらべをしているという話も広まっていましたが、中島敦はあくまでそれを「噂」と記していました。つまり、周囲の人間が名人を偶像化したいがために、真実味に欠ける神聖な噂が一人歩きしていたのでしょう。
個人的には、紀昌が名人になったか否かの問題よりも、名人を偶像化する民衆の滑稽さを描いていたのだと感じます。筆を持たない画家や、楽器を持たない楽人が増えた、という結末がそれを象徴しているでしょう。
つまり、何かを極めるということは、どこかの段階で趣旨を取り違えてしまう可能性を含み、民衆はそういった愚劣な事態をも簡単に信じ込んでしまうということだと思います。
芸術的な価値
結末をあえて画家や楽人に置き換えた部分が印象的で、中島敦は物語の中に芸術的価値の問題提起を落とし込んでいたのではないかと考えられます。
例えば、前衛的な芸術の価値を判断するのは非常に困難です。著名人が評価したから、という曖昧な判断でその芸術の価値が大衆に浸透することも珍しくありません。死後に評価されたポスト印象派の画家や、アングラカルチャーの再評価や、抽象絵画に何億円の価値がついたり、正直にいうと訳が判らない世界です。
ただし1つだけ判っているのは、前衛的な芸術の先駆者を真似しただけのニセ芸術家が五万と存在するということです。気を衒っているだけで思想を持たない文化人気取りです。
中島敦は作家ですから、もちろん文章を扱う芸術家です。もしかすると「名人を偶像化する」ようなニセ芸術志向の隣人作家を揶揄していたのかもしれませんし、それを良しとする大衆を非難していたのかもしれません。
個人的な私感が入りすぎているかもしれませんが、「筆を持たない画家」「楽器を持たない楽人」は本当に象徴的でニヤけてしまうのです。
あなたのことだと思いますよ。
私も例外ではなく。
■関連記事
➡︎中島敦おすすめ10選はこちら
オーディブル30日間無料
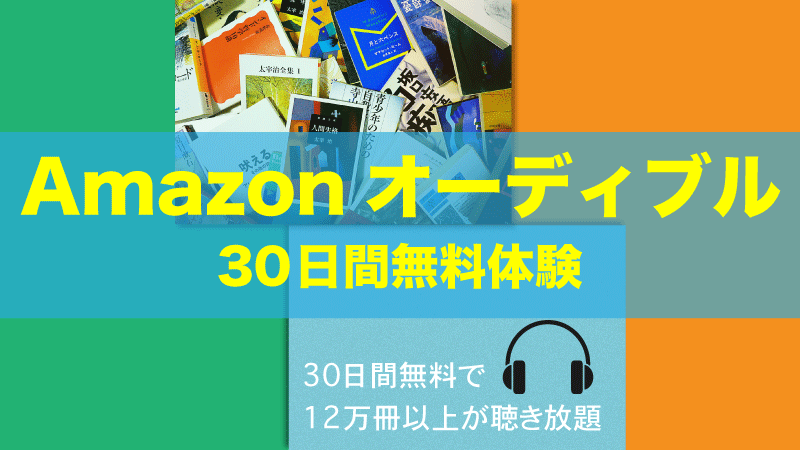
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら