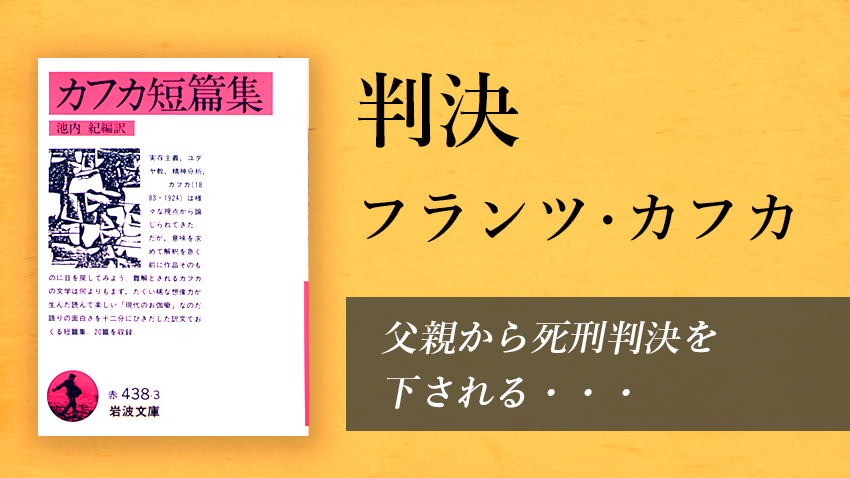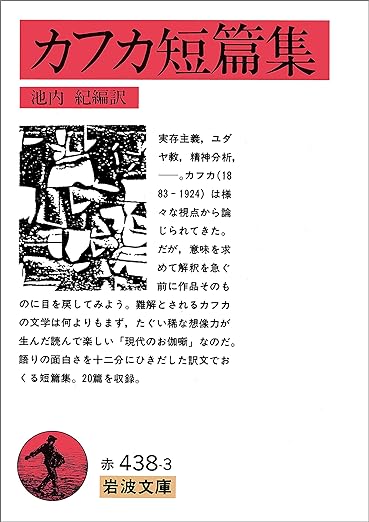フランツ・カフカの小説『判決』は、生前に発表された数少ない短編のひとつです。
のちに婚約者となるフェリーツェ・バウアーとの出会いに触発され、冒頭の献辞には彼女の名前が記されています。
しかしその内容は、婚約者に宛てるにはあまりに不気味で、カフカ文学独特の幻想性と、理解し難い急展開によって幕を閉じます。
カフカはこの物語で何を伝えたかったのか。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の意味を詳しく考察していきます。

カフカ作品はオーディブルで聴き放題なのでおすすめです!
- オーディブルならカフカの作品が聴き放題
| 運営会社 | Amazon |
| 聴き放題作品数 | 12万冊以上 |
| 月額料金 | 月額1.500円 2ヶ月間無料トライアル実施中 |
| 公式サイト | https://amzn.to/4bsOLJv |
作品概要
| 作者 | フランツ・カフカ |
| 国 | ドイツ |
| 発表時期 | 1913年 |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 20ページ |
| テーマ | 父親の権威 芸術と婚約の葛藤 |
あらすじ

主人公ゲオルクは、2年前に母親を亡くして以来、老いた父親と2人で生活し、家業はゲオルクが中心となって切り盛りしている。
ゲオルクはロシアで生活する友人へ手紙を書いている。ゲオルクには婚約者がおり、近く結婚する予定だが、その報告を友人にするか迷っている。友人は商売で一旗揚げるためロシアのペテルブルクに移住したものの上手くいっていない。そんな友人に、順風満帆な自分の近況を伝えれば、相手のプライドを傷つけないかと気にしているのだ。しかしゲオルクはようやく決心して、手紙の最後に婚約の報告を記した。
ゲオルクは完成した手紙を持って父親の部屋へ行き、婚約の報告を手紙に書いたと知らせる。それを聞いた父親は、お前にペテルブルクに友人などいないと言い張る。そんな父親をなだめてベッドに寝かしつけるが、しかし父親は突然激怒し、ゲオルクが婚約者との情事を楽しみ、自分をほったらかしにしていたことをなじる。そして父親はペテルブルクにいるゲオルクの友人に、とっくに手紙で婚約のことを暴露しており、だから友人は何年も帰ってこないのだと言う。
言い争いの末、父親はゲオルクに溺死を命じる。するとゲオルクは家を飛び出し、父母を愛していたと小声でつぶやき、橋の上から身を投げるのだった・・・
Audibleで『判決』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『判決』を含むカフカの作品が聴き放題。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼30日間無料トライアル実施中!
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

カフカ文学の現実と幻想
本作『判決』は、初期の短編にして、カフカの作風を決定づけた作品と言われている。
物語は大きく二段構造に分かれている。前半部分は、春の盛りの日曜日の午前に始まり、ゲオルクは友人に宛てた手紙を書いている。友人はロシアで商売に失敗し苦しい境遇だが、ゲオルク自身は幸福の絶頂にいる。父親が引退してからゲオルクが家業を切り盛りし、商売の売上は何倍にも飛躍し、令嬢との結婚も控えている。まさに、うららかな春の午前のごとく、彼の人生は晴れやかである。
ところが父親の部屋に入った途端に物語は一変する。陽が輝く午前だというのに部屋は窓を閉め切って薄暗い。そして「嘘はやめろ、お前にペテルブルクに友人などいやせんだろ」という父親の衝撃の台詞で物語は一気に不気味な様相を帯び、そのまま急転直下で父親から死刑判決を受ける意想外の結末を迎える。
前半と後半の極端な落差には、「春の盛りの日曜日の午前」と「薄暗い父親の部屋」との対比が機能している。
この突拍子もない物語展開は、「夢の形式」と呼ばれ、その名の通り、急に物語が非現実の世界に迷いこむ手法で、本作『判決』で初めてはっきりと現れた。有名な『変身』では、主人公が巨大な毒虫に変身していると判った途端、物語は現実の境界線を失い、不気味な幻想世界へと侵入していく。あるいは『審判』では、ある朝目覚めると主人公は身に覚えのない有罪宣告を受ける。
何か絶対的な行使力(権力)が主人公の身に降り掛かり、それに抵抗できぬまま敗北する、これがカフカ流「不条理文学」の特徴である。本作『判決』において権力を行使するのは父親である。父親が溺死を命じると、ゲオルクはその判決通り、橋から身を投げる。
しかし判決を受ける以上、ゲオルクは相応の罪を犯しているはずだ。
次章からは、ゲオルクが犯した罪の正体、ペテルブルクの友人の正体、そして婚約者との出会いがなぜカフカにこの小説を書かせたのか、詳しく考察していく。
ゲオルクが犯した罪の正体
カフカ文学を語る上で、父親との関係は切っても切り離せない。代表作『変身』では、巨大な毒虫に変身した主人公に対し、リンゴを投げつけて実行的な疎外をもたらすのは父親である。そして『判決』でもまた然りだ。
これら作品における父親像は、カフカと父親の軋轢がモチーフになっている。カフカの父親は小間物商を営む、いわゆる裕福な都市ユダヤ人だった。商才に長けた実利的な人物で、カフカの文学活動に理解を示さなかった。むしろ父親は家庭内で横暴な態度を振るい、息子を自分の権威に丸め込んでいた。カフカが大人になっても仕事や結婚など、あらゆる面で干渉し、それが軋轢の原因となった。
『判決』では、ゲオルクの婚約について、父親は快く思っておらず、ゲオルクが婚約者と情事を楽しむあまり、自分を放ったらかしにしたことに憤慨している。
実際にカフカは、フェリーツェとの婚約に際して、口煩い父親と険悪な関係になり、その件についてカフカは父親に宛ててこんな手紙を書いている。
父上、あなたは肘掛け椅子に座ったまま世界を支配していらっしゃいました。あなたの意見が絶対正しくて、他の意見はすべて狂って変で、おかしな意見ということになってしまいました。
『父への手紙/フランツ・カフカ』
僕はいつも通り、あなたに何も答えることができません。ひとつには、あなたに抱いている恐れのせいで。そしてまた、恐れている理由というのが、僕がまとまった話にできるよりもずっと多くの、細かなことでできているせいで。
『父への手紙/フランツ・カフカ』
カフカにとって父親は権力の象徴、畏怖の念を抱かせる存在だった。それはある意味、父性そのものである。父性とは、従順な者には情けを与えるが、逆らう者には罰を与える厳格な原理を持つ。息子にとって父親の権威とは、決して超えてはならないものなのだ。しかし『判決』のゲオルクは、それを超えてしまう。そしてそれが彼の罪である。
かつて実行的な支配者であった父親は、母親の死をきっかけに、そのなりをひそめ、今や息子のゲオルクが家業の中心を担っている。そしてゲオルクは、自分が家業を担ってから売上が拡大したという自負によって、父親の権威を退けている。
さらに結婚それ自体が、父親の権威からの独立を意味する。ゲオルクは婚約者と、結婚後に父親の世話をどうするかという話し合いをしておらず、家に放置するのが当然だと考えていた。父親にとっては、ゲオルクが結婚によって独立し、家業をも奪う行為は、息子が父親の権威を超える許し難い罪なのだ。
ゲオルクが父親を抱きかかえ、毛布にくるむ場面で、こんなやり取りが交わされる。
「ちゃんとくるまれているのかな」
『判決/フランツ・カフカ』
「やはりベッドがいいでしょう」
「ちゃんとくるまれているのかな」
「心配ご無用、ちゃんとくるまれていますとも」
「そうはさせん!」
そして父親は急に毛布を蹴り上げて、ベッドの上に立ち上がり、息子に対して自分の権威を主張する。
悪ガキめ、わしをくるみこもうというのだろうが、そうはさせんさ。このとおり老いぼれたが、おまえごときにひけはとらん。まだまだ十分、力がある。
『判決/フランツ・カフカ』
その言葉通り、父親は権力を行使して、ゲオルクに死刑判決を言い渡す。無論ゲオルクの犯した罪は、父親の権威を超えるという、父性原理に対する反逆罪である。しかし老いた父親には判決を下す権力はあっても、直接自分の手で殺す実行力は持っていない。ゲオルクからしてみれば、父親の判決に抵抗するだけの腕力はありそうだが、しかし彼は父親の言いつけ通り橋から身を投げた。
このゲオルクの自主的な死から分かるのは、彼自身が自分の罪を認めているということだ。
父親がベッドの上に立って息子への中傷を捲し立てる場面で、ゲオルクは「前屈みになるがいい、すると転がり落ちる。いちころだ!」と頭の中でつぶやく。これは既に父親が、自分対して何の実行力もないことを見くびっている証拠なのだが、しかし同時にゲオルクは、父親の汚れた下着を見て、世話をなおざりにしきてきたことに胸を痛め、結婚後に父親を引き取る必要性を感じる。
ゲオルクの内部には、父親からの独立を望む思いと、父親の権威を超えることへの罪悪感がせめぎ合っている。妙な例えかも知れないが、毒親を持つ子供にとって、親を棄てる行為は、親に支配されるのと同じくらい辛いという。権力を持つ存在を超える行為は、それが自分に害を与える存在だとしても、罪悪感なくして果たせるものではないのだろう。
だからゲオルクは、「お父さん、お母さん、ぼくはいつもあなた方を愛していました」という台詞を言い残して、自ら命を絶ったのではないだろうか。
ペテルブルクの友人の正体
ゲオルクは、ペテルブルクの友人に宛てた手紙を書いている。しかしその存在は、「ペテルブルクに友人などいやせんだろ」という父親の言葉によって、現実のものなのか曖昧になる。
友人は数年前に、一旗揚げるためロシアのペテルブルクに移住したが、商売がうまくいかず惨めな生活を送っている。それ以外に彼の情報は明かされないが、ゲオルクとは対照的な人生を歩んでいることは確かである。ゲオルクは故郷に居座り、家業を引き継ぎ、しかるべき女性と結婚して、社会的地位を安定させることに満足している。しかし友人は、故郷を捨て、自分で商売に挑戦し、そして現地でも人間関係を持たず、独り住まいを続けている。
この対照的な生き方をするゲオルクと友人は、カフカの内部に存在する二つの人格だと考えることができる。
それは労働者としてのカフカと、小説家としてのカフカである。
実はカフカは、フェリーツェと正式に婚約を交わしたあとも、内心では結婚によって執筆が妨げられるという不安に悩んでいた。小説家カフカにとって結婚は、筆を折る行為に近い挫折を意味した。
このことから分かる通り、ゲオルクは友人に見立てた「小説家としての自分」に対して、婚約の報告をするか否か迷っていたのだ。それはつまり、執筆の妨げになり得る結婚を小説家としての自分が認めるか、というカフカ本人の自己葛藤だったのだろう。
ゲオルクは友人に対して、「すべては失敗だったわけで、もうそろそろ見切りをつける潮どきだ、もどって来い」と告げだてすることに躊躇している。小説家を目指す自分に対して、夢を諦めて安定した生活に身を落ち着けよ、と言い聞かせるのは、最も残酷なことだろう。
ゲオルクが友人の存在を婚約者に明かすと、婚約者は次のように言及する。
「そんなお友達がいらっしゃるんだったら、わたしと婚約などしなければいいのに」
『判決/フランツ・カフカ』
この異常な台詞からも、その友達が単なる友達ではなく、ゲオルクの内部に存在するもうひとつの人格だと推測できる。つまり、「執筆が大切なら、わたしと婚約しなければいいのに」と解釈することができる。
この婚約者の問いに対して、ゲオルクは婚約に後悔はないと答える。そして友人宛ての手紙に婚約の報告を記した。それはカフカ本人が、小説を書きながらも、フェリーツェと一緒になることを決断した、その意志を作品の中で訴えていたのではないか。
だからカフカは、作品の冒頭に、「フェリーツェ・Bのための物語」と付したのだろう。いわばこの作品には、小説家を志す上で結婚に迷っていたカフカが、その決心を固めたことを婚約者に伝えるプロポーズの意図が込められていたのではないか。そう考えると、本作が婚約者との出会いに触発された作品で、冒頭に婚約者の名前が記されている理由が、納得できる。
しかしカフカは、その直後にフェリーツェとの婚約を解消している。そして婚約解消を機に、カフカは初めて勤めを辞めて小説で身を立てる事を考え出す。
結婚の意思を決断したはずの作品が、皮肉にもカフカを小説家の岐路へと導いたわけだ。
その後カフカは『審判』『城』と長編を執筆していくが、多くは未完のまま終わり、それらが公に発表され、世界的な評価を受けるのは死後のことである。まるでペテルブルクの友人のように、カフカは生前何もうまくいかず、尾羽打ち枯らした生活を送ることになったのだ。
そういう意味で本作は、カフカが自分の将来に「判決」を下した、運命的な作品と言える。
■関連記事
➡︎【必見】カフカおすすめ代表作5選
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら