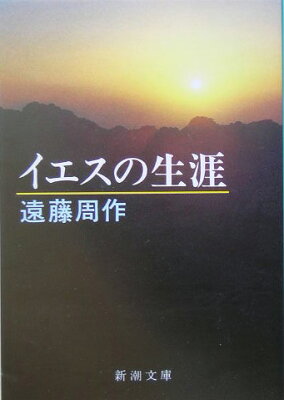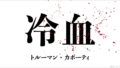遠藤周作の小説『死海のほとり』は、キリスト教の聖地イスラエルを巡礼する物語である。
主人公が巡礼する現代の物語と、イエスが生きた2000年前の物語が交互に描かれ、二つの時代が交錯する構造になっている。
また『沈黙』で見出された、同伴者としての母性的なイエス像が見事に完成された、遠藤文学の重要な位置を占める作品でもある。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を詳しく考察していく。
作品概要
| 作者 | 遠藤周作(73歳没) |
| 発表時期 | 1973年(昭和48年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 349ページ |
| テーマ | 同伴者イエス 母なるイエス 弱者のためのイエス |
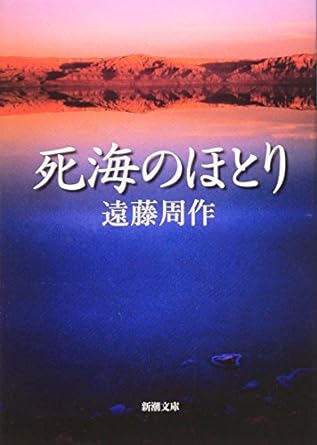
あらすじ

小説家の「私」は、イスラエルを訪れ、大学時代の友人・戸田と再会する。二人はキリスト教の大学の同級生だったが、戦時下の思想弾圧で信仰につまずき、久しく教会へ行っていない。それでもなぜか彼らの人生にはイエスが付きまとい、今さら聖地を巡礼することになった。
「私」は真実のイエスを求めて聖地を歩くうちに、いつしか大学時代の神父で皆から「ねずみ」と呼ばれていたユダヤ系ポーランド人を思い出す。ねずみは貧弱で卑怯で弱虫で、皆から笑いものにされていた。大学職員の女と関係を持ったことで追放され、故郷に帰ってからはナチの収容所で殺された。あの弱虫のねずみが収容所でどんな風に生き殺されたのか、それを知るため、「私」は収容所の生存者を訪ねることにした。
ねずみは収容所でも卑怯な男だった。ナチの看守に媚を売って肉体労働から逃れ、医務室で人体実験に協力していた。疲弊した囚人が医務室の仕事を譲ってほしいと頼んでも、ねずみは拒否した。数日後その囚人が労働不可になりガス室送りになると、ねずみは「自分のせいじゃない」と連呼していた。またある時、空腹で倒れた囚人がパンを半分譲ってほしいと頼むが、ねずみはやはり拒否した。
肉体労働に戻されたねずみは、貧弱でまともに働けず、ガス室送りは目に見えていた。これまでの卑怯な行いから、彼を助ける者はひとりもいなかった。そしてガス室送りが決まった日、ねずみは身をもがいて抵抗し、恐怖のあまり痙攣して尿を漏らす。囚人のひとりが彼を連れて行こうとすると、ようやく彼は泣きながら頷き、そして今までの彼ならあり得ないことだが、最後の食糧のパンをその囚人に与えたのだった。
よろめきながらガス室に向かうねずみの隣には、同じように尿を垂らして歩くある男の姿が一瞬見えた。
これらの話を聞いた「私」は、イエスはねずみのような弱い人間を通して、自分の人生に付きまとっているのではないかと考え、そこに真実のイエスを見出すのだった。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

創作背景
本作『死海のほとり』は、遠藤文学のひとつの到達点であり、『沈黙』で描かれたテーマを引き継いだ作品である。
『沈黙』で描かれたのは、キリシタン迫害の江戸時代に、信仰を守れなかった弱者をも許し包み込む、母性的なイエス像だった。物語のラスト場面で、棄教を迫られた神父が踏絵に足を乗せる瞬間、イエスは神父にこう語りかける。
踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ。
『沈黙/遠藤周作』
この内容は発表当初、カトリック教会から強い反発があり、長崎では禁書に等しい扱いを受けた。というのも、西洋のキリスト教は父性的な特色が強い。父性とは、従順な者には慈悲を与えるが、逆らう者には罰を与える、という厳格な原理だ。たとえキリシタン弾圧の最中とて、信仰を棄てて踏絵に足を乗せる行為は、許し難い罪悪なのだ。信仰を棄てず神に命を捧げる殉教こそ美徳とされる。
これが西洋の父性的なキリスト教の負の側面でもある。迫害に耐え、信仰のために命を捨てることも惜しまなかった強い者だけが神に祝福され、弱さゆえに命を惜しみ、信仰を捨てた者は神に見放される。
しかし遠藤周作は一貫して、弱さゆえに信仰を棄て、そのことで苦しんだ者を、イエスが見棄てるはずがない、という母性的なイエス像を追求し続けた。それは、弱者のためのイエス、同伴者イエス、という言葉で表現される。
そして『沈黙』から6年後に発表された『死海のほとり』では、その母性的なイエス像がひとつの完成形として見事に描き出されている。
物語は二重構成になっている。小説家の「私」が、真実のイエス像を求めイスラエルを巡礼する現代の物語と、2000年前に実際にその場所に生き、処刑されたイエスの伝記が、交互に描かれる。
後者のイエスの伝記に関しては、同年に発表された『イエスの生涯』でより詳しく描かれ、その後『キリストの誕生』という作品に受け継がれた。
そして現代の物語では、長い年月の間に信仰を見失った小説家の「私」が、エルサレムで大学時代の友人・戸田と再会し、真実のイエス像を求めて、死海のほとりを彷徨う旅の様子が描かれる。
真実のイエス像とは、もちろん、弱者のためのイエス、同伴者イエスのことだ。本当のイエスは何ひとつ奇蹟を起こせぬまま、ひたすら弱者に寄り添うことに徹した、弱くて優しい母性的な存在だった。しかし聖書作家や教会は、イエスを神聖化するあまり、人知を超えた奇蹟で彼の生涯を装飾し、荘厳で父性的なイエス像へ作り替えたと遠藤周作はいう。それは友人・戸田の台詞からも見てとれる。
聖書だってエルサレムと同じさ。この町で本当のイエスの足跡が瓦礫の中に埋もれて何処にも見あたらぬように、聖書のなかでも原始基督教団の信仰が創りだした物語や装飾が本当のイエスの生涯をすっかり覆いかくしているのさ。
『死海のほとり/遠藤周作』
父性的な価値観に適した西洋人には、彼らの文化色に装飾された厳格なイエス像が相応しいのかもしれないが、異なる文化圏の日本人には理解できなところも多い。遠藤はそれを、「日本人としてキリスト教徒であることが、ダブダブの西洋の服を着せられたように着苦しく、それを体に合うように調達することが自分の生涯の課題であった」と語っている。
つまり「私」が求めた真実のイエスは、西洋人が生み出した聖書の中のイエスではなく、日本人にも親しみやすいもっと人間らしいイエスのことだ。その実際のイエスが一体どんな人物だったのか、次章にて詳しく解説する。
イエスの生涯
小説家の「私」が戸田と渡り歩くイスラエルの土地を、遥か二千年前に弟子たちを引き連れ歩いたイエスはどんな人物だったのか。
前提として、イエスはユダヤ人で、ユダヤ教徒のひとりだったが、彼が生きた頃のユダヤ人はローマ帝国に支配されていた。そのためユダヤ人たちは、ローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれる救世主(メシア)の登場を待ち望んでいた。
そんな中、イエスは、従来のユダヤ教とは異なる独自の教えを説くようになり、一部のユダヤ人から救世主として崇められ出す。そして、救世主であれば人知を超えた力を持っているだろう、という民衆の勝手な期待から、イエスは病める者を奇蹟で治して回っている、という噂が広まる。実際に聖書には、イエスが盲人の視力を手をかざすだけで治したり、ハンセン病やそのほか多くの大病を治したと記録されている。しかしそれらはイエスを神格化するために、聖書作家が創作した物語だというのが遠藤周作の主張である。
わたしは奇蹟などできぬ。わたしができることは・・・あなたたちと苦しむことだから・・・。
『死海のほとり/遠藤周作』
本当のイエスは奇蹟で病気を治すことはできなかった。病人の苦しみを分つため、ただ寄り添って同じように涙を流しただけだった。だからイエスは皆から棄てられ、裏切られた。
病める民衆にとって必要なのは病気を治す奇蹟であり、イエスの愛など全く無力である。ましてや奇蹟を期待してイエスを迎えたのに、愛を与える以外何もできないのだから、民衆の失望は憎悪に近いものだった。そのためイエスはどこの村でも忌み嫌われるようになる。
またイエスを救世主として崇めていた弟子たちも少しずつ数を減らす。弟子たちがイエスを崇めたのは、自分達をローマから解放してくれる救世主と信じていたからだ。しかしイエスは愛を説くだけで、独立解放の指揮を執ることはなかった。この無力な男に付き従っても無意味だと弟子が悟るのに時間はかからなかった。そしてイエスがローマに目を付けられると、弟子たちは我が身大事さに逃げ出した。
こうして同胞から裏切られたイエスは、ローマとユダヤ教司祭の政治的陰謀に利用され、ゴルゴタの丘で十字架にかけられ処刑された。
何もできない無力な男、優しいだけの男、皆から裏切られた憐れな男。
遠藤周作はイエスの生涯を、嗜虐的とも言えるほど、何もできない惨めで弱い男と描く。何もできないイエスがただひとつ貫いたのは、愛によって他者の苦しみを分つことだった。彼は全ての弱者に寄り添い、自分を裏切った者にさえ最後まで愛を失わなかった。たとえ自分を裏切った者であろうと、自分がその者の人生を横切ったことで生じた愛の痕跡は生涯消えないと知っていたからだ。それが母性的な真実のイエス像である。弱さゆえに自分を見棄てた者をイエスは決して見棄てはしない。
この遠藤周作独自のイエス像に対して、ローマカトリック教会の神父は、「遠藤氏の文学は、キリスト教や聖書をテーマにしたにしても、布教にとって大きなマイナスであり、とくに非キリスト者にとっては、ゆがめられたキリスト教を紹介したにすぎない」と酷評している。
しかし遠藤周作の分身ともいえる『死海のほとり』の「私」は、次のように言及している。
昔から聖書を読んでも日本人のぼくには少しもわかりません。(中略)むしろ辛い病人を治したくても治せなかったイエスのほうが、我々に近く感じられるんです。力あるイエスは、ぼくには手の届かぬ遠い存在のような気がするんです。
『死海のほとり/遠藤周作』
強い光を放つ神だからこそ、人々を魅了し屈服させる力があれど、その光が眩しすぎて、気後れを感じて直視できない者もいる。殊に弱さを抱える者にとっては、厳格な神より、弱者の苦しみを知り、それを許してくれる神の方が、親しみやすい。
そして「私」はまさに、弱さゆえに力あるイエスを直視できず、長い年月の間に信仰を見失った日本人のひとりだった。次章では「私」が信仰を見失うきっかけとなった彼の弱さについて考察していく。
「私」の生涯
「私」がキリスト教の大学に通っていたのは、太平洋戦争の最中だ。当時キリスト教は敵国宗教として、警察に厳しく監視されていた。
学生寮には頻繁に警察が現れ、キリスト教の学生たちに尋問を行った。尋問の内容は、靖国神社と教会のどちらが大切か、いずれ戦場に出たら同じ宗教を信じる敵兵を殺せるか、など回答次第で逮捕される残酷なものだった。
これらの尋問に対し「私」は、家がクリスチャンだから洗礼を受けただけで、自分は深く信仰してるわけではない、戦場に出たらもちろん敵兵を殺せる、と恐怖に慄いて答えた。もし神父が妙な助言をしたら警察に報告しろという命令に対しても従順な態度を示した。我が身大事さに平気で神を裏切る。そんな弱くて卑劣な自分に「私」は屈辱と嫌悪感を覚えた。
これはイエスの弟子のひとりである「ペドロの裏切り」と重ねて描かれている。イエスが逮捕されてからペドロは、おずおずイエスのあとを着けて大司祭の官邸に潜り込む。そして官邸の女中に見つかって慌てたペドロは、「あんな男は知らない」とイエスを裏切ったのだ。
「私」にはもうひとつ屈辱の記憶があった。大学の行事で癩病院へ慰問に行き、ハンセン病患者と野球をすることになった。「私」はランナーとしてベースをかけぬける際、ハンセン病患者にタッチされることに生理的な嫌悪を覚え足がすくんだ。すると患者が、「おいきなさい、触れませんから」と小声で呟いた。二十年経った今でもあの声が頭の奥で鳴っている。
ガリラヤ地区を渡り歩いたイエスは、人々から差別されたハンセン病患者と寝床を共にし、彼らの孤独や苦しみに寄り添った。それが素晴らしい行為だと知っていても、自分にはそれを成し遂げるだけの強さがない。
こうした弱さゆえの裏切りの連続の中で、次第にイエスは手の届かぬ存在として、「私」の信仰を見失わせてしまったのだった。
そして二十年以上の時を経て、何かに導かれるようにイスラエルを訪れた「私」は、真実のイエスを求めるうちに、いつしか、大学時代の神父で皆から「ねずみ」と呼ばれた、弱虫で卑怯な男の生涯を追い求める旅へと変わる。
次章では、「私」が最終的に見出した、「ねずみ」の人生に潜む真実のイエス像とはどんな姿だったのかを考察していく。
「私」が見出した真実のイエスとは
物語のもうひとりの主人公といえる「ねずみ」は、子供のように手足が小さく貧弱で、怪我をした学生の血を見ただけで真っ青になって嘔吐する臆病な性格だった。その上、学生の不始末を陰で暴露する陰湿な性格でもあった。
頼まれてもいない学生の看病に頻繁に赴き、戦時中の配給物資を奪って帰るせこい点も中傷の的になっていた。ペニスが豆のように小さいというので揶揄われてもいた。
そんなねずみは大学の職員と肉体関係を持ったことで追放され、故郷のポーランドに帰ってからはナチの収容所に入れられていた。そこでも狡い立ち回りをしていた。看守に媚を売って楽な仕事を回して貰ったり、飢餓と疲弊に苦しむ囚人の助けを求める声を無視したり。囚人の中には、脱走者の身代わりになって自ら命をなげうつ神父がいたからこそ、ねずみの言動は余計に醜く写った。
しかし、あの収容所では、誰もが他者のことを考える余裕がなかった。飢餓に苦しむものにパンを分け与えれば自分が死ぬ。拷問のような労働を代わってやれば自分が死ぬ。毎日誰かがガス室に連れて行かれる姿を見ていれば、それに悲哀や感傷を抱く心は麻痺する。
ナチの収容所については、のちに『女の一生:二部』という作品でも描かれる。その中で印象的な台詞があるのでここに引用する。
まだここ(収容所)は地獄じゃない。地獄とは・・・愛がまったくなくなってしまった場所だよ。しかしここには愛はまだなくなっていない。
『女の一生:二部/遠藤周作』
確かにねずみは自分が生きるために、他者を見殺しにしてきた。しかしその度に、「自分のせいじゃない、自分のせいじゃない」と弁解しながら、自分の罪に苦しむ姿を見せた。本当に愛がない世界なら、利己的な行為に苦しむ必要もない。しかし、ねずみは苦しんだ。
そしてねずみのガス室送りが決まった。ねずみは身をもがいて抵抗し、恐怖のあまり脚を痙攣させて小便を漏らした。そしてここから、ねずみは驚くべき行動に出る。囚人のひとりがねずみを連れて行こうとすると、彼は泣きながら頷き、その日、最後の食事となるはずだった自分のパンを、その囚人に与えたのだ。
最後の晩餐でイエスが弟子たちにパンを割いて与えたように、ねずみはこれまでの弱くて卑怯な自分の罪を償うように、最後のパンを与えたのだった。
ガス室へよろめき歩くねずみの隣には、彼と同じように尿を垂れながらよろめき歩く男の姿が一瞬浮かび上がった。弱さゆえに罪を繰り返した彼を決して見棄てず、最後まで隣にいてくれる男がいたのだ。それは気高く威厳のある男ではなかった。あまりに見窄らしく、惨めで、崇高さのかけらもない、しかし同じように小便を漏らしてまで共にガス室まで歩いてくれる、そんな永遠の同伴者だった。
その何もできない、ただ寄り添うだけの、愛の男こそ、「私」が求めた真実のイエスだった。
私があなたを棄てようとした時でさえ、あなたは私を生涯、棄てようとされぬ。
『死海のほとり/遠藤周作』
二千年前にゴルゴタの丘で、全ての人間の罪と苦しみを背負って、十字架にかけられたイエスが、三日後に地上に復活した伝説は、遠藤周作が言うところの、もがき苦しむ弱者の隣で同じように苦しんでくれる、永遠の同伴者としての復活に他ならない。
それは厳格なカトリック教会からすれば、歪曲したイエス像なのかもしれない。しかしイエスが特定の人種や民族に限った神ではなく、全ての人間にとっての神であるなら、その土地の精神風土に適した多種多様なイエス像が存在するはずであり、そういう意味で遠藤周作の追究したイエス像は、日本人の精神風土に適した母性的な神なのである。
現代の日本で、特定の宗教を信仰する人間は少ないだろうが、もし遠藤文学で描かれるイエス像に少しでも感動や救いを感じたのなら、既にイエスはあなたの永遠の同伴者であり、あなたが孤独に打ちひしがれ苦しんでいる時に、隣で同じように苦しんでいる、あの何もできない無力な男、しかし最後まで決して自分を見棄てはしない、あの優しい男がいることを忘れてはいけない。
映画『沈黙』がおすすめ
遠藤周作の代表作『沈黙』は、スコセッシ監督がハリウッドで映画化し話題になった。
禁教時代の長崎に潜入した宣教師は、想像を絶するキリシタン弾圧の光景を目撃し、彼らを救うために棄教の選択を迫られる・・・・
ハリウッド俳優に加え、浅野忠信、窪塚洋介ら日本人キャストが共演。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・アダルト動画見放題(5万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら