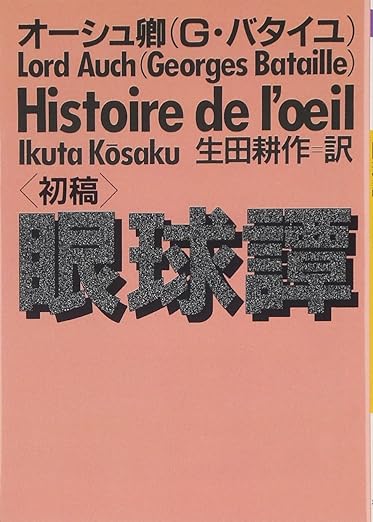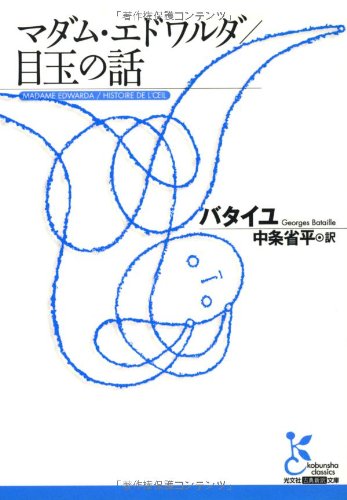バタイユの小説『眼球譚』は、史上最も異端とされる、エロティシズム文学の問題作である。
1928年にロード・オーシュ(排便する神)という匿名で地下出版され、現在ではアングラ文学の頂点のように神格化されている。
その内容は暴力と卑猥な表現に満ちた狂気的なもので、東京大学出版『教養のためのブックガイド』の「読んではいけない15冊」に選出されている。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を詳しく考察していく。
作品概要
| 作者 | ジョルジュ・バタイユ |
| 国 | フランス |
| 発表時期 | 初稿:1928年 新版:1947年 |
| ジャンル | 中編小説 エロティシズム文学 |
| ページ数 | 155ページ |
| テーマ | エロと精神解放 禁止と違反のメカニズム |
■初稿(河出文庫)
■新版(光文社古典新訳文庫)
あらすじ

「私」は16歳の頃に、遠縁の少女シモーヌと出会い、彼女が牛乳の入った皿に尻を浸す姿を見せられたのを機に性的関係をもった。それは互いに尿をひっかけ合う奇妙な官能であった。
ある日、同じ街に住む少女マルセルが、二人の戯れを目撃し、その遊びに巻き込まれる。マルセルは帰りたいと懇願するが、次第にシモーヌの淫らな姿に触発され、衣装ダンスに隠れて自慰を行い失禁する。異変に気づいた「私」が衣装ダンスを開けると、マルセルは発狂する。この出来事は街中に知れ渡り、マルセルは精神病院に入れられた。「私」とシモーヌは、精神病院に侵入してマルセルを連れ出す。しかし彼女は衣装ダンスを見た途端トラウマを再発し、一寸目を離した隙に首をくくって死んでしまう。
シモーヌを愛人にしたがるエドモンド卿の力添えで、「私」とシモーヌはスペインに逃亡する。闘牛の見物に来たシモーヌは、エドモンド卿に頼んで牛の金玉を手に入れ、それを自分の膣に入れる。そして闘牛士が牛に目玉を突かれて死んだ事故の瞬間に、シモーヌは絶頂に達するのだった。
三人は教会に赴く。シモーヌは不意に懺悔をしたいと言い、告解室に入る。そして司祭の前で自慰を行い、司祭のものを口に含む。司祭は「私たちは絞首刑になるだろう」と憤慨する。それに対してエドモンド卿は「男は絞首刑の死に際に射精する」と話す。それを試すごとくシモーヌは司祭に馬乗り、陰部を交えた状態で首を絞めて殺す。
司祭の眼球にハエが止まったのを見て、シモーヌはその眼球を欲しがる。エドモンド卿はハサミで眼球をえぐり取り彼女に与える。シモーヌは眼球を自分の膣の中に入れる。その様は、かつて衣装ダンスで首を括ったマルセルの目玉が、小便の涙を流しながらこちらを覗いているように見えた。
[ad]
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

創作背景
本作『眼球譚』は、当時31歳のバタイユが、匿名で地下出版した処女小説である。
その狂気的な内容は、マルキ・ド・サド(「サディズム」の語源となった作家)以来の、衝撃的なエロティシズム文学とされ、今日ではバタイユは二十世紀最大の思想家にまで祭り上げられている。しかし生前はあくまで地下の人間として殆ど認められることはなかった。
バタイユの文学は、「エロス」と「死」の思想をテーマに、常軌を逸した性描写で埋め尽くされている。排便や流血はもちろん、睾丸や眼球を膣に入れたり。これら常人には理解できないエログロ表現の根源にあるのは、バタイユ本人の凄まじい生い立ちである。
『眼球譚』には、「暗号」と題した作者のあとがきが付され、それによると、物語はあくまで創作だが、しかしバタイユの少年時代の体験が反映された、精神的自伝だという。
バタイユは神父の息子として生まれたが、父親は梅毒を患って全盲かつ半身不随だった。バタイユと母親が排便の世話をし、父親は椅子に座ったまま容器に排尿した。排尿時に父親が白眼を剥く様が、バタイユに<眼球>と<玉子>の連想を起こさせたという。このイメージは『眼球譚』に幾度も登場し、その際に排尿シーンが伴うのも、この体験によるものらしい。
その後、父親は脊髄の痛みに発狂し、医者に対して、「先生!俺の女房といつまで乳繰りあってるんだ」という妄言を叫ぶようになる。これもある種の猥褻体験として、『眼球譚』の創作に大きく関係しているようだ。そして父親が発狂して間も無く、母親も発狂し自殺未遂を繰り返す。それを目の当たりにするバタイユは、何も感じない無感動状態にあったという。
悲惨な少年時代を経たバタイユは、ニーチェに傾倒したことで無神論者になり、国立図書館の公務員の職を務める一方で、雑誌に独自の思想を展開するようになる。だがやがて精神に変調をきたし、精神分析の治療を受け始める。治療の一環で何か文章を書くよう勧められ、バタイユは書くことによって精神抑圧と闘う。そして自己の暗黒面と向き合い、それを克服したときに、『眼球譚』を完成させた。
バタイユが両親の発狂や自殺未遂に無感動だったのは、心の悲鳴を無意識に抑圧していたからだろう。彼自身は何も感じずとも、しかし確実に心は蝕まれ、大人になって精神面に症状として現れた。それを克服するには、これまで抑圧してきた内部の闇を解き放ち、文章によって吐き出す必要がある。その成功体験として『眼球譚』が生まれた。いわばバタイユの内部に眠る闇を赤裸々に吐き出した作品だ。
1928年に初稿が発表されて以来、『眼球譚』は何度も改稿がなされ、最後の大幅に改稿されたものが1947年に発表された。物語の筋に変化はないが、作家として円熟した文章で書き直されている。
現在では河出文庫から初稿が、光文社古典新訳文庫から新版が、それぞれ出版されている。
個人的には生田耕作訳の河出文庫版の方が好みなので、本記事ではそちらを元に、考察を進めていく。
バタイユの「エロティシズム」とは
『眼球譚』の狂気的な物語の意味を理解するには、バタイユが提唱する「エロティシズム」の概念を知る必要がある。
哲学や思想の分野で性欲を扱う場合、「エロティシズム」という言葉が用いられる。官能小説ではなくエロティシズム文学と言えば、何か高尚な印象を与える。これは俗に言う「エロいこと」とは違うのか。単に猥褻なことを、格好つけて勿体ぶってるだけではないのか。
しかしバタイユが提唱する「エロティシズム」の概念は、単に性的で卑猥なものを指すわけではない。
■バタイユの「エロティシズム」とは
・死にまで至る生の称揚
・禁止と違反によって引き起こされるもの
・閉ざされた存在の構造の破壊
これでは何のこっちゃ分からないので、最も核となる二番目の「禁止と違反のメカニズム」を中心に解説していく。
バタイユいわく、人類は労働(生産活動)を始めた時点で様々な禁止を生み出し、それは「死と結びついた禁止」「生殖と結びついた禁止」の二つに分類される。
・死と結びついた禁止
→殺人、死者への冒涜を禁止
・生殖と結びついた禁止
→近親相姦、強姦を禁止
これらは人間が本能的におぞましいと感じる「暴力」を、意識的に遠ざけるために生み出してきたものだ。暴力は共同体における生産活動の利益を損ねる。
しかし人間にとって、禁止されるものは、一方で魅力を感じさせる。むしろ禁止による抑圧は欲望を加速させる。この欲望によって「禁止」を超越した時、人間は「違反」を犯す。そして違反を犯した人間は、日常の世界から、非日常の世界へと移行する。このときに引き起こされる「精神解放」こそが、バタイユの説く「エロティシズム」である。
いわば、日ごろ禁止されるいるものが違反によって解放されると、人間は日常を超越し、自己の存在の奥深くの神秘的な世界に到達できるということだ。これが「閉ざされた存在の構造の破壊」である。
ふだん抑圧されている性衝動が、違反によって解放されたとき途轍もない興奮を感じる。しかしバタイユは性器の興奮だけでなく、殺人や戦争といった違反も、「エロティシズム」の精神解放に含めている。たとえば古代の宗教儀式では、生贄として例外的に殺人を肯定する場合があった。この瞬間における「禁止」の超越は、祝祭や聖の世界への到達を意味する。性行為であれ殺人であれ、人間が違反を犯して暴力的になるとき、そこには日常から解放された精神陶酔があるわけだ。
これらエロティシズムに関するバタイユの概念は、彼の晩年の著書『エロティシズム』で詳しく分析されているので、そちらを参考にしていただきたい。
■『眼球譚』における禁止と違反
そしてここからは『眼球譚』に注目する。この作品は「禁止と違反のメカニズム」を徹底的に繰り返す物語である。
物語は少女シモーヌが「私」の目の前で、牛乳の入った皿に性器を浸す悪ふざけに始まる。しかしそれは単なる悪ふざけではなく、彼らにとって「違反」の始まりだった。やってはいけない行為を犯したときの解放感が彼らに途轍もない興奮を与えたのだ。そして更なる「エロティシズム」を求めて、彼らは小便をひっかけ合うような、異常な性的遊戯に夢中になる。異常であればあるほど、「違反」の解放感は絶大なものになる。
冒頭にわざわざ「私」が孤独な生い立ちだと記されているのは、彼らの「エロティシズム」の追求が、孤独からの解放を目的としているからだろう。前述した通り「禁止と違反のメカニズム」には、日常から非日常の世界へと移行する効果がある。つまり彼らは違反を通して、孤独な日常からの解脱を味わっていたのだ。
彼らの遊戯には、殺人も含まれている。二人が車で若い女性を跳ねてしまい、その女性の首がちぎれたの見たとき、普段の性的遊戯で味わう感情と似たものがあった。これはバタイユが言うところの「死と結びついた禁止」を超越したことによる、エロティシズムである。
むしろ彼らのエロティシズムは、性器的な興奮とは重ならないことが多い。彼らは通常の性行為を長らく実践せず、アブノーマルな行為に夢中になっていた。
そして彼らの「違反」の愉しみは、少女マルセルに集中する。彼らの歪んだ遊戯を嫌がる純粋無垢なマルセルが、突発的に衣装ダンスの中で自慰に夢中になって小便を漏らした出来事は、禁止の一線を越えて違反に突入する、解放的な人間の象徴となったのだ。
その後も闘牛場において、シモーヌが牛の金玉を膣に入れ、闘牛士が牛に目玉を突かれて死んだのと同時に、エクスタシーに達したのも、禁止と違反のメカニズムによるものだ。違反がもたらす精神解放には、性的逸脱と死とが、密接に結びついている。
そして彼らの最後の違反は、神を冒涜する行為だった。神父の前でシモーヌは自慰を行う。そして神父の性器をしゃぶり、神聖な葡萄酒の杯に小便をさせ、聖体パンの器に精液をぶちまけさせる。宗教という最上級の「禁止」を超越したことで、彼らは「エロティシズム」の極みに達したのだ。
エドモンド卿の「男は絞首刑の死に際に射精する」という話は、性と死の結びつきを暗示し、実際にシモーヌは神父と交わった状態で、彼の首を締めて、射精と死を同時に目撃する。
彼らはひたすら「禁止」を超越し、「違反」を犯すことで、精神解放を実践した。現実を生きるということは、自分という人間の孤独を、絶えず実感することである。その悲惨な現実を超越し、「個」という概念のない深い精神世界へ到達する手段として、「エロティシズム」が必要だったのだろう。
「眼球」が象徴するものとは
『眼球譚』というタイトルが示す通り、作中では「眼球」が象徴的に描かれ、「玉子」と「金玉」がその連想で登場する。
眼球とは「見る」ことを司る器官であり、人間の五感の中で最も「意識」に近いものだ。見ることによって物事を把握し、その物事を意識の世界に取り入れるという意味で、眼球は外界との窓のような役割を持つ。
「意識」を象徴する眼球、それを連想させる金玉を、シモーヌは膣に入れる。膣は対照的に、意識ではなく、感覚を象徴する器官だ。そして眼球を膣に入れる行為は、意識を感覚の世界に沈める意図があるのではないか。
つまり肉体から眼球(意識)を切り離し、それを膣に沈めて自慰をすることで、完全に理性を失った感覚の世界だけで快楽を実感できるわけだ。それは意識的な現実から解脱し、非日常の感覚だけの世界に到達する「エロティシズム」の精神解放である。
そして「見る」という意識の主体を肉体から切り離す行為は、自己の消滅を意味する。自己という意識の主体があるから自分と他者を区別できる。逆にいえば、意識の主体があるから、他者との隔たりを感じて孤独になる。しかし主体がなくなれば、自己と他者の区別もなくなる。いわば他者との完全なる一体化である。この感覚の世界における一体化によって、「私」とシモーヌは、孤独な現実からの解放を味わっていたのだろう。
一方で眼球には、「見る」と同時に、「見られる」という役割も持つ。<良心の眼>という慣用句があるように、他者の視線には、道徳や常識といったバイアスで自分を抑圧する働きがある。たとえば世間の目を気にして何かを躊躇するのも、「見られる」ことによる抑圧だ。しかしこの他者の視線は、「私」とシモーヌには不可欠なものだった。
というのも、バタイユが説く禁止と違反のメカニズムは、それが禁止されているという前提がなければ機能しない。仮に「私」とシモーヌの異常な性的遊戯が、世間の目に禁止されていなければ、それを違反する興奮もないわけだ。つまり他者の道徳的な視線によって禁止され、その抑圧を超越して初めて、二人は「エロティシズム」の精神解放に到達できるのだ。
そして二人にとって、道徳的な視線は、少女マルセルに象徴される。純粋無垢なマルセルの、驚きと戸惑いの道徳的な視線の前で、違反を犯すことで、二人は「エロティシズム」の興奮を味わう。マルセルが無垢な視線を向けるほど、それを裏切る興奮があるわけだ。
ある意味、マゾの男性が自分の恥ずかしい行為を、女性から蔑む目で見られ、そのことに背徳的な喜びを見出す感覚と近いものがあるかもしれない。
それは例えばエドモンド卿のように、二人の行為を許容する視線では意味がない。あくまで二人の行為に驚き、恐れ、嫌悪する、無垢なマルセルの視線が必要なのだ。
だからこそ、マルセルの死は、二人に大きな渇きを与えた。マルセルの無垢な視線が失われたことで、それを裏切る「違反」の興奮も失われたのだ。そしてその瞬間に「私」は、シモーヌが全くの他人であることを意識する。「違反」の興奮が失われ、感覚の世界から、意識的な現実に連れ戻されたことで、他者と一体化する魔法が解かれ、孤独な自己を意識せずにいられなかったのだろう。
しかし物語の終盤に、シモーヌが神父の眼球を膣に入れる場面がある。「私」にはそれが、マルセルの眼球が小便の涙を垂らしながら、自分を見つめているように感じられる。これはマルセルの死で失われた他者の視線、「違反」を犯すために不可欠な禁止の視線を、最後に取り戻したことを描いているのではないか。神を冒涜することで取り戻したということは、それは神の視線だったのかもしれない。神の視線の中で違反を犯すことで、彼らは最大のエロティシズムに到達したのだ。
以上が『眼球譚』における、バタイユのエロティシズムの考察である。
60年代に入るとバタイユは日本の若者に神格化されるようになる。中島らもの『今夜すべてのバーで』という作品では、バタイユに心酔する女が、スノッブ的に描かれているが、こういうアングラな芸術を分った気になりたがる若者の気持ちもよくわかる。でも本格的にのめり込んだから、それはそれで危険なので、異端文学との付き合いは、ほどほど、が肝心である。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら