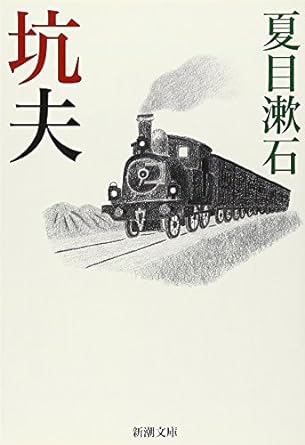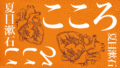夏目漱石の小説『坑夫』は、職業作家として2作目の作品で、朝日新聞に連載された。
漱石文学では珍しい、ある青年の体験を題材にしたルポタージュ小説になっている。
裕福な家で生まれ育った青年が、恋愛関係のもつれから東京を飛び出し、坑夫になる決意をする物語である。
村上春樹がフェイバリットに上げているのは有名だが、漱石文学の中では最も評価が低い。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を考察していく。
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表時期 | 1908年(明治41年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 288ページ |
| テーマ | 恋愛関係のもつれ 全体主義社会からの逃亡 青年の意識の揺らぎ |
あらすじ

裕福な青年は恋愛関係のもつれから、着のみ着のまま東京を飛び出した。行く当てもなく竹林を彷徨っていると、長蔵という男に声をかけられ、儲かる仕事に誘われる。実は長蔵は坑夫のポン引きなのだが、自暴自棄になった青年は、半ば自殺する覚悟で坑夫になることを承諾する。
鉱山町に到着すると、異様な風体の坑夫たちに絡まれ、東京の書生に辛抱できる仕事ではないから帰れと侮辱を受ける。気の優しい飯場頭や坑夫の安さんにすら、坑夫になっても稼げないし、二度と外の世界に出られなくなるから、東京に帰るべきだと忠告される。
鉱山の内部は青年の想像を絶する。深さの分からないスノコという穴があったり、どん底の八番坑まで来ると、腰の辺りまで冷たい泥水が浸かる。青年は命の危機を感じるが、坑夫は平気で作業しているのだった。
地上に戻るための梯子を登る最中、手を離せば転落して死ぬ恐怖で動けなくなる。だが死ぬつもりで東京を飛び出した身分、いっそ手を離そうかと考えるが、こんな暗い場所で誰にも知られず死ぬのは耐えられず、無我夢中で梯子を登り切る。
翌日、病院で気管支炎を診断され、結局坑夫になれなかった。その代わりに飯場の帳簿を付ける仕事を任される。その生活を五ヶ月続けた後、青年は東京に帰った。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的解説

創作背景
本作『坑夫』は、教職を辞めた漱石が本格的に職業作家になって2作目の作品で、朝日新聞に91回にわたって掲載された。
『虞美人草』に次いで発表され、前期三部作の手前に位置する。
漱石文学の中では最も評価が低く、特異な作品に位置付けられている。というのも、漱石文学には珍しく、他者の体験を題材にしたルポタージュ小説なのだ。
或日私の所へ一人の若い男がヒョックリやって来て、自分の身上にこういう材料があるが小説に書いて下さらんか。
『坑夫の作意と自然派伝奇派の交渉/夏目漱石』
青年が体験した鉱山労働を、小説の題材にするよう依頼されたのだ。漱石は当初、「個人の事情は書きたくない」と拒んでいたのだが、ちょうどその頃、朝日新聞の小説連載で、島崎藤村の執筆がはかどらず、急遽、漱石が代打を務めることになった。それで一度は拒否した青年の依頼を、改めて引き受ける気になった。言ってしまえば間に合わせの作品である。
『坑夫』が評価されていない理由は、これといった筋立てがなく、主題が欠落しているからだろう。当時、足尾銅山の坑夫が暴動を起こした事件があり、過酷な鉱山労働はホットな話題だったが、漱石の『坑夫』には社会テーマが全く感じられない。のちに同タイトルがプロレタリア作家・宮島資夫によって発表され、血の滴るショッキングな内容が描かれたのに対し、裕福な家庭で育った漱石にはまるで別世界、リアリティも社会的主張も欠ける。
また本作は漱石の饒舌さが最も表れた作品で、物語の進展が遅すぎる。鉱山に向かう道中だけで100ページ以上あり、その殆どが青年の意識の流れの描写である。実際に足尾銅山に行って現場を見たことがない制限の中で、漱石は何か別の創作手法を編み出す必要があった。それが青年の意識の流れをひたすら書く手法だったのかも知れない。
青年の意識の流れは、過去の恋愛関係のもつれに起因し、その回想を通じて、ひたすら自己内省を繰り返すのだが、果たして青年がどんな問題を起こしたのか、一切明かされないのが異常である。この過去の空白を埋めるには、漱石の他の作品を参照するしかない。特に前作『虞美人草』と深く関わりがあるため、次章にて詳しく解説する。
青年が抱える恋愛のもつれとは
繰り返しになるが、青年は恋愛関係のもつれから東京を飛び出し、ポン引きの誘いで坑夫になる決意をするのだが、肝心の恋愛事情については全く明かされない。作中で言及されるのは、下記の通り漠然とした内容である。
事の起こりを調べてみると、中心には一人の少女がいる。そうしてその少女の傍に又一人の少女がいる。この二人の少女の周囲に親がある。親類がある。世間が万遍なく取り巻いている。ところが第一の少女が自分に対して丸くなったり、四角になったりする。すると何かの因縁で自分も丸くなったり四角になったりしては、第二の少女に対し済まない約束を以て生れて来た人間である。・・・・それを第二の少女が恨めしそうに見ている。親も親類も見ている。世間も見ている。
『坑夫/夏目漱石』
なんとなく三角関係の恋愛模様が見えるが、実はこれは前作『虞美人草』と同じ設定が使いまわされている。
■『虞美人草』あらすじ
主人公の小野は、学生時代の恩師の娘・千夜子を妻に取る口約束を交わしている。恩師と千夜子は困窮しており、彼らを援助する意味でも結婚するのが義理なのだ。ところが小野には他に惹かれる藤尾という女性がいる。
藤尾にも亡き父が決めた婚約者がいるが、本心では小野を好いており、虚栄心が強く小悪魔的な彼女は、婚約者と小野を天秤にかけて二人の反応を楽しんでいる。
小野は藤尾と一緒になりたいが、千夜子との結婚を断るのは義理人情に反する。この板挟みの三角関係を通して、世間や親族のプレッシャー、遺産相続などの問題が介入する。最終的に小野は、藤尾との駆け落ちの約束を破って、千夜子を妻に取る宣言をする。それを聞いた藤尾は精神錯乱を起こし、毒をあおって自殺する・・・・
『虞美人草』は漱石が職業作家になって初めての小説のため、構成に力が入っており、あらすじでは語り切れない複雑な問題が絡み合っている。だが言ってしまえば、世間に翻弄された主人公が、優柔不断ゆえに二人の少女を苦しめる物語である。
こうした恋愛事情が、『坑夫』では過去に経験した出来事、東京を飛び出す原因となった出来事として使い回されている。
そこで自分はこの入り組んだ関係の中から、自分だけふいと煙にしてしまおうと決心した。然し本当に煙にするには自殺するより外に致し方がない。そこで度々自殺を仕掛けてみた。ところが仕掛るたんびにどきんとして已めてしまった。
『坑夫/夏目漱石』
封建的な時代の日本では、世間に顔向できない問題を起こした場合、切腹で肩をつけるのが通念だった。それが明治以降、前時代的な行為になり、かと言って個人主義が浸透しない日本ではひたすら世間の目に苦しめられた。幸か不幸か『虞美人草』の主人公は、最終的に本心より義理人情を優先して恩師の娘を選んだ。だから別に世間に咎められる立場ではない。それなのに同じ設定を引き継いだ『坑夫』の青年は、深い自己内省に落ち込み、自殺さえ考える。自殺する勇気がないから裕福な家を飛び出して、坑夫という社会の底辺に堕ち切り、自然と自滅する瞬間を待ち望んでいる。
いわば『坑夫』は、前作『虞美人草』に対するアンチテーゼ、批評の意味を持つ作品である。
人間程的にならないものはない。約束とか契とか云うものは自分の魂を自覚した人にはとても出来ない話だ。又その約束を盾にとって相手をぎゅうぎゅう押し附けるなんて蛮行は野暮の至りである。
『坑夫/夏目漱石』
無闇に他人の不信とか不義とか変心とかを咎めて、万事万端向うが悪い様に噪ぎ立てるのは、みんな平面国に籍を置いて、活版に印刷した心を睨んで、旗を揚げる人達である。
『坑夫/夏目漱石』
要するに『坑夫』の青年は、世間体や義理人情で他者を束縛し、それに背けば断罪する、全体主義の風潮に批判的だったのだ。彼自身、本心を殺して義理人情を優先した人間だ。個人主義の敗北に落胆した青年は、全体主義社会から逃げ出し、いっそ社会の底辺で自滅することを望んだのだろう。
個人主義の敗北は、漱石が生涯追求した文学テーマである。前期三部作『三四郎』では自由恋愛が見合い結婚に敗北し、続く『それから』では略奪婚を犯した主人公が世間に追放され、最終章『門』では世間に追放された主人公が宗教的な思索に救いを求める。その序章とも言える『坑夫』は、前期三部作を書く上で通過すべき作品だったのかも知れない。
鉱山の内部に見る転落過程
鉱山にやって来た青年は、異様な風体の坑夫たちに絡まれ、東京の書生に辛抱できる仕事ではないと侮辱を受ける。気の優しい飯場頭や坑夫の安さんにすら東京に帰った方がいいと忠告される。
何故こんな所へ来た。来たって仕方がないぜ。儲かる所じゃない。早く帰るが好かろう。帰って新聞配達でもするがいい。おれの様になったが最後もう駄目だ。帰ろうたって、帰れなくなる。だから今のうちに東京へ帰って新聞配達をしろ。書生はとても一月と辛抱は出来ないよ。
『坑夫/夏目漱石』
周囲から忠告されるほど、青年の中で坑夫になる必要性が強くなる。裕福な家で生まれ育った青年にとって、坑夫にならなければ、それは単なる「紳士の逃亡」でしかない。実際に坑夫に転落した安さんいわく、日の当たる社会には鉱山より苦しいところがある。それは全体主義社会の世間体なるものであり、そこから本当の意味で逃亡するには、自殺ないし、坑夫になって社会の底に転落するしかないのだ。
鉱山の中は段階的に深くなり、最も深いどん底が八番坑にあたる。それは青年の転落の過程を表すかのごとく、彼を奥へ引きずり込み、同時に転落に対する抵抗心を起こさせる。
これまで当然のように二足歩行で生きてきた青年は、鉱山で初めて地面を這う経験をする。それは相当な地位にいた青年が、社会の底辺に入場するための儀式と言える。奥へ進むほど道は険しくなり、するとあれだけ強く転落を望んでいた青年は、徐々に転落を恐れ出す。決定的に青年を恐れさせたのは、鉱を落とすための畳二畳分の穴「スノコ」だ。スノコを見た時に、青年は落下する恐怖に尻込みし、安全な場所へと退く。そこには青年の社会に対する捨て切れない執着、完全に堕ち切れない意志の弱さが表れている。
首を横に出して、下を覗いた。よせば善かったが、ついに覗いた。すると急にぐらぐらと頭が廻って、かたく握った手がゆるんできた。これは死ぬかも知れない。死んじゃ大変だ
『坑夫/夏目漱石』
八番坑を目指して梯子を降る際、青年は命を危機を感じ、死にたくないと考える。元より死に場所を求めて東京を飛び出したはずが、いざ死を目の前にすると、生に執着してしまうのだ。
ところが一転、地上に出るために梯子を登る段になると、今度は激しい転落願望に駆られる。
一層の事、手を離しちまおうかしらん。逆さに落ちて頭から先へ砕ける方が、早く片が附いていい。とむらむらと死ぬ気が起こった。
『坑夫/夏目漱石』
だがそれも一時の感情に過ぎない。いざ手を離そうとするとあべこべの感情が働く。どうせ死ぬなら人に褒められる様な華々しい死を遂げたい、こんな暗い場所で死にたくないのだ。
生きてる事実が明瞭な時には、命を捨てる決心がつき、死を目の前にすれば生きたい心持ちになる。青年はこの二つの矛盾した精神状態の衝突の末に、結局は梯子を登って地上に出る決断をするのだった。
生きる選択をした理由
鉱山内部での自殺を断念した青年は、その代わりに日光の華厳の滝に飛び込んで華々しく死ぬつもりだったが、その決心は坑夫の安さんとの出会いによって一変する。
安さんは青年と同じ、高等教育を受けた相当な身分だったが、ある女性との間に罪を犯し、社会にいられない立場になって、仕方なく坑夫に転落した。これは坑夫としては希少なパターンである。鉱山で働く人間は基本的に貧農や末端労働者の生まれである。教育を受けぬまま世間に放り出された結果、坑夫になる以外に選択肢がなかったのだ。彼らにとっては、毎日を生き抜くことだけが問題で、坑夫がいくら辛かろうと、生きてさえいられれば、のたれ死ぬよりましなのだ。
それに比べると安さんは、ある恋愛の罪を犯したばかりに坑夫に転落した。その罪とは法律や神に裁かれる類のものではなく、世間によってのみ裁かれる全体主義社会の罪である。社会が彼を追放したのだ。
安さんが悪いんでなくって、社会が悪いのかも知れない。(中略)安さんは人間から殺されて、仕方なしに此処に生きているんである。
『坑夫/夏目漱石』
青年も似たような境遇だが、彼の場合、最終的には義理人情を優先したため、世間に裁かれる罪人ではない。ただ個人的な自己内省で社会から逃亡したのだ。それに比べて安さんは、世間に裁かれて社会の底に転落してもなお、生きるために働いている。その姿を見て初めて、青年は自殺をやめて生きる決心をするのだった。
(安さんは)生きて働いている。生きてかんかんを敲いている。生きて––––自分を救おうとしている。安さんが生きてる以上は自分も死んではならない。死ぬのは弱い。
『坑夫/夏目漱石』
世間に裁かれ、社会から追放された者は、みな一様に社会に殺されたのである。その結果、自ら命を絶つのは、社会に首吊りの縄をかけられたも同然である。純粋な自殺などあり得ない。だからこそ、生きるという選択だけが、唯一自分を救う手段なのだ。
奇しくも青年は、この直後に気管支炎を診断される。自分で決着をつける前に、病気の方が先に始末をつけに来た。遅かれ早かれ自分は死ぬと分かった青年は、一つの悟りに到達する。
日本一の美人の顔がただの顔である如く、坑夫の顔もただの顔である。そう云う自分も骨と肉で出来たただの人間である。意味も何もない。
『坑夫/夏目漱石』
社会に対する恐怖も憎しみも消滅し、ただ無人の世界が青年の周囲に広がっている。そう悟った青年は、病人でも務まる帳場の仕事を無心にこなし、やがて東京へ、社会の中へ帰っていったのだった。
『坑夫』と村上春樹
村上春樹を通じて、この『坑夫』という作品を知った人も多いだろう。
『海辺のカフカ』にて、少年カフカが夏目漱石全集を読破する場面で、『坑夫』が取り上げられる。
大島さん「一般的に言えば漱石の作品の中ではもっとも評判がよくないもののひとつみたいだけれど……、君にはどこが面白かったんだろう?」
『海辺のカフカ/村上春樹』
カフカ「それは生きるか死ぬかの体験です。そしてそこからなんとか出てきて、また元の地上の生活に戻っていく。でも主人公がそういった体験からなにか教訓を得たとか、そこで生き方が変わったとか、人生について深く考えたとか、社会のありかたについて疑問を持ったとか、そういうことはとくには書かれていない。彼が人間として成長したという手ごたえみたいなのもあまりありません。でもなんていうのかな、そういう『なにを言いたいのかわからない』という部分が不思議に心に残るんだ」
相当な地位の青年が、鉱山という転落の底に足を踏み入れ、再び東京に帰る。二つの世界を行き来する構造が採用されており、それは村上春樹の文学と必ずしも無関係とは言えない。
さらに二人の会話の中で、『坑夫』の魅力が語られる。
「それはある種の不完全さを持った作品は、不完全であるがゆえに人間の心を強く引きつける、ということだ。たとえば君は『坑夫』に引きつけられる、『こころ』や『三四郎』のような完成された作品にない吸引力がそこにあるからだ」
『海辺のカフカ/村上春樹』
確かに『こころ』『三四郎』ほど洗練された作品ではないが、不思議な吸引力がある。それは不完全さというより、異質さが原因ではないかと個人的には考える。漱石にとって坑夫の世界を覗くのは異世界を覗くようなもので、それは他の漱石文学には見られない特異な手法で、ゆえに漱石の作品を読破した時に、妙に『坑夫』だけが浮いて見える。
もしこれから漱石の作品を読むなら、間違っても最初に読んではいけない。おそらく「夏目漱石が読めない」病にかかってしまう。
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら