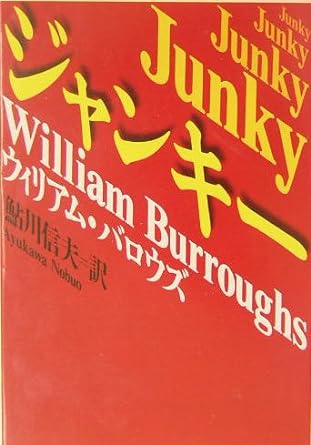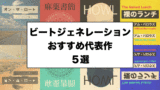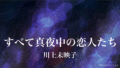ウィリアム・バロウズの小説『ジャンキー』は、自身の麻薬体験を記した処女作です。
麻薬に手を出したきっかけや、ジャンキーの生活や、麻薬にまつわる権力構造が自伝的に描かれます。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | ウィリアム・バロウズ |
| 国 | アメリカ |
| 発表時期 | 1953年 |
| ジャンル | 長編小説 ビートジェネレーション 麻薬体験記 |
| ページ数 | 292ページ |
| テーマ | 麻薬は生き方である |
あらすじ

不自由ない上流家庭で育ったバロウズが、麻薬に手を染めて「ジャンキー」になった記録が綴られる。
大学卒業後、信託財産を頼りに無職で暮らしていたバロウズは、モルヒネを捌く友人の手伝いをきっかけに、自身も麻薬に手を出す。中毒になるには何ヶ月も習慣的に使用する必要がある。そして多くのジャンキーは中毒になるつもりなどなく、ある朝麻薬切れの苦痛に目を覚まし、そこで中毒者になるのだ。
バロウズは麻薬を処方してくれる病院を駆け回り、しかし次第に信託財産では首が回らなくなり、初めて金稼ぎの必要に迫られる。地下鉄で掏摸をしたり、自ら売人として麻薬を捌いたり。そんな風に裏の世界に浸かった彼だから知る、ジャンキーと売人と国家の構造が赤裸々に語られる。
バロウズは幾度となく断薬を試みる。絶望的な禁断症状に耐え、完全に回復した後も、しかし彼は決まって再び麻薬に手を出す。それは彼の精神的な弱さ以上に、彼が麻薬に1つの人生を見出しているからだ。常に新たな麻薬を求めて旅をする人生。物語の最後には、伝説の麻薬「ヤーへ」を求めてバロウズは南米へ旅立つのだった。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

ウィリアム・バロウズについて
バロウズの生涯を語る上で、麻薬は切っても切り離せない。
15年以上麻薬の世界に入り浸り、ラリって妻を射殺した凄まじい経歴を持っている。
そんなバロウズは、ニューヨークでビートジェネレーションの作家、ギンズバーグやケルアックと出会ったことで文学を志すようになる。
■ビートジェネレーションとは
1950年代のアメリカで異彩を放った文学集団。放浪、ドラッグ、セックス、同性愛などをテーマに既存の価値観を拒否した。カウンターカルチャーの先駆けとして、後のヒッピーやロック音楽に多大な影響を与えた。
当初バロウズは執筆に対して消極的だったが、ギンズバーグの勧めで自身の麻薬体験を記し、それが処女作『ジャンキー』となった。ちょうど妻を射殺した直後のことだ。
手紙で『ジャンキー』の原稿を受け取ったギンズバーグは、それを出版社に持ち込んだが、まるで相手にされなかった。というかビートジェネレーションの前衛的な作品は、当時は芸術的価値が認められていなかった。
例えば、ケルアックの『オン・ザ・ロード』は1度もタイプライターを途切れさせずに3週間で書き上げたという伝説的な逸話があるが、同年代の作家カポーティは、そんな風に推敲を試みない創作を、「あれはライティングではなくタイピングだ」と批判した。同様に『ジャンキー』も文学界の反響は皆無で、バロウズは作家として生きていくことを諦めていた。
しかし、その後もギンズバーグらの手助けによって、バロウズは執筆を続け、1959年にはついに問題作『裸のランチ』が発表される。
その内容は、麻薬によって錯綜した超現実を描いたもので、理解不能な上に、猥褻を理由に発禁処分を受ける。それがかえって話題になり、実験小説の雄として注目を集める。伝説的奇人作家の誕生である。
『裸のランチ』は1992年に、奇才クローネンバーグによって映画化され、そちらも映画ファンからカルト的な支持を集めている。
『裸のランチ』の印象が強いバロウズだが、多くの信者たちは『ジャンキー』を最高傑作に挙げる傾向にある。
それは本書で描かれる、ジャンキーの生活や行動原理、麻薬にまつわる権力構造が、後の作品と深く関係しており、バロウズ文学の基礎を型作っているからだ。
またバロウズ特有の理解不能な文章表現が確立される以前なので、かなり平坦で読みやすい内容になっている。『裸のランチ』で挫折した人におすすめしたい1冊である。
次章からは物語を詳しく解説していく。
なぜ麻薬を摂取するのか?
朝ベッドから起き出し、ひげを剃り、朝食をとるために麻薬が必要なんだよ
『ジャンキー/バロウズ』
麻薬を扱った文献は多く存在する。中には麻薬を過度に神格化し、大袈裟な理屈を並べたがる人間もいる。あるいは中毒者の行動原理を、孤独や現実逃避や神秘体験やらと、もっともらしい要因と結び付けがちだ。
一方でバロウズは麻薬を全く神格化しない。
バロウズが麻薬に手を出した理由は、退屈、それのみである。
確かにバロウズは幼少時代から幻覚を見る傾向があり、コミュニティに馴染めない内向的な人間で、成人後も神経症的な不安を患っていた。しかし彼は決して自分の精神面と麻薬を結びつけない。信託財産を頼りに無職で暮らす退屈な日々の中で、何となく麻薬に手を出し、だらだら習慣的に摂取するようになり、ある朝目覚めたら完璧な中毒者になっていたのだ。
麻薬常用者になるのは、それ以外に何も有力な行動目的がないからだ。麻薬は競争相手がいないことによって勝利を収める。私は好奇心から麻薬を使ってみた。そして、麻薬が買えるときはだらだらと注射を打ちつづけ、ついに常用癖に陥ったのだ。
『ジャンキー/バロウズ』
こんな風に麻薬の行動原理を陳腐に記した文献はちょっと珍しい。たとえば後に登場するヒッピーなら、自由や愛や神秘体験といった大袈裟な建前で麻薬を肯定していたが、バロウズは全然違う。退屈だから手を出し、そのままだらだら使っていたら、いつしか麻薬なしで生活できなくなりました、といった具合なのだ。
言い換えれば、ジャンキーが麻薬に手を出す目的や理由は端から存在しない。彼らは中毒になって初めて、目的・行動原理を見出す。「朝ベッドから起き出し、ひげを剃り、朝食をとるために麻薬が必要」になるわけだ。何かの目的のために麻薬を使うのではなく、麻薬それ自体が目的なのだ。
麻薬は刺激ではない。麻薬は生き方なのだ。
『ジャンキー/バロウズ』
目的と行動を転倒させることで、麻薬それ自体が目的になり、麻薬を生き方だと捉える。それはビートらしい哲学感ではないだろうか。
こうしたビートらしい哲学感の一方で、バロウズの滅茶苦茶な持論も繰り広げられる。
たとえば麻薬の身体的な効能についての持論は酷すぎる。バロウズいわく、人間は成長が止まると死に始める。人生に目的を失った途端に脳も肉体も急速に老けていくということだ。この理論からすれば、堕落し切ったジャンキーは早く老けるはずだが、バロウズは真逆の持論を唱えている。ジャンキーには常に目的がある。麻薬を手に入れるという目的だ。ゆえに麻薬を知らなかったかつてよりも、麻薬という目的を得た現在の方が若いし、目的がある限り死に始めないし、むしろ健康であり続ける・・・
まったくもって馬鹿げた理論だ。場合によっては麻薬を推奨していると受け取られかねない。実際に作中では、悪影響となる主張に対してはいちいち、医学的な根拠がないとの注釈が挿入されている。当時出版するにあたって、そうした改ざんが条件だったのだ。
今でこそ麻薬やセックスや、その手の過激なテーマを取り上げても文学的魅力はないが、50年代にこんな強烈な作品を発表したのだから、信じられない。
中毒者・売人・国家の関係性
本作『ジャンキー』の魅力は、実体験として麻薬の効能が記されることだが、さらに歴史的に重要な文献と評されるのは、麻薬をめぐる権力構造が赤裸々に語られているからだ。
ギンズバーグの序文に記される通り、事実としてアメリカ社会では、警察とマフィアが官僚主義的に癒着していた。
マフィアは資金源として麻薬をばら撒き、その収益の一部を警察に賄賂として収めることで、事実上活動が許されていたのだ。
いわゆる警察とマフィアはウィンウィンの関係だったのだ。
一方で売人とジャンキーは明確に強者と弱者の関係にある。麻薬の消費行動は、使えば使うほど効果が薄れ、さらに多くの量を使わないと快楽を得られなくなる。そのため売人はひと度ジャンキーを中毒にすれば、彼らは麻薬を求めずにはいられなくなるので、いくらでも金をちょろまかせるのだ。
バロウズはこうした構造を、資本主義の消費モデルに当てはめて分析している。資本主義社会では、人々は消費の奴隷にされ、中毒的に人々が物を欲する構造を生成することで、資本家たちは人々を搾取しているわけだ。
こうした資本主義の消費モデルは犯罪とも密接に関わっている。ジャンキーたちは麻薬を手に入れるために、いかなる犯罪も厭わない。作中では、地下鉄内で掏摸を行ったり、掏摸に気づいた相手をぶん殴ったり、色々と非倫理的な行為が描かれる。あるいは麻薬の資金繰りのために自ら麻薬を捌くジャンキーもいる。
表層だけを見れば、麻薬欲しさに犯罪を起こすジャンキーが悪である。しかしこうした消費行動や犯罪動機は、いわば国家とマフィアが結託して生み出しているのだ。
国家は表面上は麻薬を取り締まる必要があるので、麻薬の「犯罪化」を強め、ジャンキーを逮捕する。逮捕したジャンキーには、麻薬切れで音を上げるタイミングを見計らい、釈放や麻薬を与えることを条件に売人の密告を強いる。現場の警察にとっても、ジャンキーを脅迫する行為は、憂さ晴らし的に彼らの欲求を満たす要因になっていたのだ。
バロウズが麻薬を入手する際に密告者を注意していたのは、禁断症状に耐えきれず警察に協力する裏切り者が大勢いたからだ。
しかし一度裏切りが知れ渡れば、密告者はジャンキーのコミュニティから締め出され、二度と麻薬を買えなくなる。そうなれば警察にとって使い物にならないため、密告者は牢屋にぶち込まれる。こんな風にジャンキーは、あらゆる権力構造の中で利用されていたのだ。
お金や給料、脅しや非合法利益に対する貪欲さを、マスコミや警察によって「キチガイ」として分類された市民群を犠牲にすることで満たしていたわけだ。
『ジャンキー/バロウズ』
国家やマフィアにとって、これら全ては芝居のようなものだ。国家の許可のもとマフィアは麻薬をばら撒いて資金を得る。末端の売人が逮捕されてもマフィアには何の痛手にもならない。一方で警察は裏で賄賂を蓄え、表ではジャンキーを取り締まる。彼らが口を割ろうが割らまいが、それは表面上の茶番に過ぎない。いわば市民を犠牲にすることで、国家やマフィアは非合法利益を蓄えていたということだ。
本作『ジャンキー』では、こうした腐敗した権力構造や、ジャンキーの消費行動が、社会学的な認識で記されている。そういう意味で歴史的に重要な文献と見なされているのだ。
新たな麻薬を追い求めて
私は麻薬に親しんだことを後悔したことは一度もない。
『ジャンキー/バロウズ』
バロウズの魅力は、いくら権力に翻弄され、牢屋にぶち込まれ、病院に入れられても、必ず次の麻薬を求めて行動を起こすことだ。
作中でバロウズは何度か断薬を決心し、地獄のような禁断症状に耐え、麻薬なしの生活を実現するが、間も無く新たな麻薬に手を出す。
ともすれば、なぜ定期的に麻薬を絶つ必要があるのか。その理由は明確にされていない。
なぜジャンキーは自分から進んで麻薬をやめるのだろうか? この疑問に対する解答はだれにもわからない。麻薬がもたらす損失や恐怖をいくら並べたてたところで、麻薬をやめる心の推進力にはなりはしない。
『ジャンキー/バロウズ』
1つ確かなのは、バロウズにとって麻薬は単なる快楽ではなく、人生そのものということだ。
私は麻薬の方程式を学んだ。麻薬は酒やマリファナのような人生の楽しみを増すための手段ではない。麻薬は刺激ではない。麻薬は生き方なのだ。
『ジャンキー/バロウズ』
麻薬をやめるということは、一つの生き方を放棄することだ
『ジャンキー/バロウズ』
何度も断薬治療を受け、全て失敗に終わり、常に新たな麻薬を求めてアメリカ大陸を彷徨う。そこにはビートジェネレーション特有の求道性がある。麻薬は人生の停滞・堕落に見えて、バロウズは決して一点留まらない。
本書の最後では、バロウズは伝説の麻薬「ヤーへ」を求めて南米へ旅立つ。実際に「ヤーへ」にまつわるフィールドノートは、ギンズバーグとの共著『麻薬書簡』にて記される。本書を補完する内容になっているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。
■関連記事
➡︎ビートニクおすすめ代表作5選はこちら
映画『裸のランチ』おすすめ
バロウズの代表作『裸のランチ』は、奇才クローネンバーグによって映画化され、そちらもカルト的な人気がある。
原作の世界観を踏襲しつつ、そこにバロウズの生涯を反映させた独自の物語になっている。
映像化不可能と言われた原作の悪夢が、ボディホラーの天才クローネンバーグの手によって見事映像化され、その内容は衝撃的である。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら