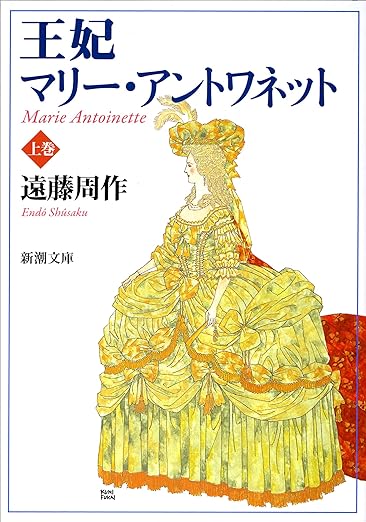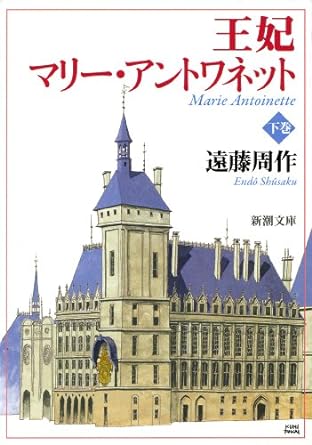遠藤周作の小説『王妃マリー・アントワネット』は、その名の通り、フランス王妃の生涯を描いた作品である。
オーストリアの王女アントワネットが、政治同盟のためルイ十六世に嫁ぎ、やがてフランス革命でギロチンにかけられるまでの壮絶な人生が描かれる。
世界史において悪名高いアントワネットは、なぜ民衆に憎まれ、断頭台に送られたのか。そこには知られざる政治的陰謀と、アントワネットの一命をかけた戦いがあった?
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を詳しく考察していく。
作品概要
| 作者 | 遠藤周作(73歳没) |
| 発表時期 | 1985年(昭和60年) |
| ジャンル | 長編小説 歴史小説 |
| ページ数 | 上巻:496ページ 下巻:464ページ |
| テーマ | アントワネットの生涯 フランス革命 血で血を洗う暴動 |
あらすじ

オーストリアの王女マリー・アントワネットは、十四歳の若さで政治同盟のため、フランスの王子ルイ十六世に嫁いだ。そのあまりの美しさと無邪気な愛らしさに、フランスの民衆は彼女を大歓声で迎え入れた。
しかしルイ十六世は小太りのぼんやりした冴えない男だった。この退屈な男が生涯の夫だと考えるとアントワネットは不安になった。
彼女には他にも気がかりがあった。国王ルイ十五世の愛人デュ・バリー夫人の存在だ。夫人は娼婦上がりにして、妻亡き後の国王に取り入り、偉そうに振る舞っていた。宮殿には夫人を疎ましく思う者もいた。その者たちにアントワネットはそそのかされ、デュ・バリー夫人を徹底的に無視して対抗する。そして国王が崩御し、新国王ルイ十六世が誕生し、アントワネットが王妃になると、デュ・バリー夫人は宮殿から追放された。
新国王の誕生はやがて民衆を落胆させる。当時のフランスは貴族が権力を独占し、民衆は重税に喘いでいた。この苦しい現状を打開してくれると信じていたルイ十六世は政治に消極的で、おまけにアントワネットは洋服から宝石から浪費を続け、民衆の憎悪を掻き立てたのだ。元よりフランスは財政危機に陥っており、財務官はアントワネットに節約を願い出るが、彼女は自分に逆らう財務官を次々に追放する。彼女を「赤字夫人」の異名を付けられ民衆の信用を失いつつあった。
そんな中、詐欺師カリオストロによる、王妃の名義で高価な首飾りを買ってそれを騙し取る「首飾り事件」が起こる。アントワネットは首飾りなど買っていないが、民衆はまんまと彼女が莫大な浪費をしたと信じ、不満が爆発して彼女の排斥を望むようになる。
そしてついに革命派が決起し、民衆は武装してパリで暴動を起こす。国王は穏便なやり方で革命派と手を取ろうとするが、次第に民衆は暴徒と化し、貴族を撲殺して周り、国王とアントワネットの死刑を叫ぶようになる。国王一家はフェルセン伯爵の手助けで、王妃の母国オーストリアに逃亡を試みるが、計画は失敗に終わり、パリに連れ戻され、厳重な監視下に幽閉される。
この逃亡事件で国王と王妃の死刑は運命づけられた。フェルセンは望みを捨てず、王妃だけでも逃亡させようと努力するが、アントワネットは子供を置いて自分だけ逃亡することを拒み、半ば死の運命を受け入れていた。
ルイ十六世の処刑が執行され、続いてアントワネットが断頭台に連行される。その頃の彼女は壮絶な苦難によって老婆のように髪が真っ白になっていた。しかし彼女は最後まで王妃の気品を捨てず、どんな暴力にも屈しない意志を我が子に証明するため、少しの怯えも見せず、優雅な振る舞いによって断頭台にのぼったのだった。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

当時のフランスの社会情勢
世界史において「浪費の女王」という悪名高き異名を持つマリー・アントワネットが、とんでもない浪費で財政を破綻させ、最終的にフランス革命でギロチンにかけられたのは、あまりに有名な歴史的事件である。
しかし史実を辿れば、実際はアントワネットが財政を破綻させたわけではなく、彼女はフランス革命において民衆の憎悪の対象に利用された犠牲者と見る方が正しい。少なからず遠藤周作の『王妃マリー・アントワネット』では、そのような歴史観で描かれている。
仏蘭西の国費が赤字になったことも王妃の過ちではなかった。しかし人々はその生活の苦しさがどうにも改善できぬと知った時、憎悪の対象を探さねばならなかった。その対象がマリー・アントワネットだったのである。
『王妃マリー・アントワネット/遠藤周作』
そもそもアントワネットが王妃になる前から、フランスは財政危機に陥っていた。その原因はアメリカ独立戦争にある。
ルイ十五世の時代、フランスはイギリスと、アメリカの植民地をめぐって争っていた。この戦争に莫大な戦費を投入し、その上でフランスは敗北する。そしてアメリカ各地の実質支配はイギリスが勝ち取るのだが、イギリスは植民地に様々な税金を課し、それに反発した現地人がアメリカ独立戦争を勃発させる。これに対してフランスは、因縁の相手であるイギリスを倒すため、財政が厳しいにもかかわらず植民地側に付いて参戦し、莫大な戦費を投入する。これら一連のプライドをかけた戦争によってフランスの財政は既に破産寸前だったのだ。
そして国が財政危機に陥った時に権力者が考えるのは、国民から税金を徴収することだ。当時のフランスは第一身分の聖職者、第二身分の貴族、第三身分の平民に分かれていた。そして聖職者や貴族の税金は免除し、平民に重税を課していた。これはいつの時代の政治でも行われていることで、政治上の影響力を持った貴族や大企業は税金を優遇される。ましてや当時のフランスは世襲的な王制で、国民選挙が存在しないので、平民の声を聞く必要もなかった。
その上で当時は小麦の凶作に見舞われ、主食のパンの価格が二倍に高騰していた。中流家庭ですらパンを買うだけで生活費の六割を使い、中流以下であればパンを買うのもままならない状態だった。
「パンがないならケーキを食べればいいのに」
これは世間知らずのアントワネットが、食糧不足に苦しむ平民に対して放ったトンチンカンな台詞として有名だが、現在では別の貴族の台詞だったと判明し、それを陰謀的にアントワネットになすりつけたと考えられている。いずれにしても、平民の悲惨な境遇に、貴族がいかに無関心であったかが窺える。
パンもろくに買えず、不公平な重税を課せられた平民の怒りは限界に達していた。貴族を優遇する政治体制を転覆させる革命の機運が高まっていたのだ。
この財政危機を解決すべく議会が開かれた。聖職者、貴族、平民三つの身分の代表者が集結するのだが、聖職者と貴族が結託し、2対1で平民の意見は通らない仕組みになっていた。これに不満を爆発させた平民は、国民議会という独自の集会を開き、きな臭い動きを始める。政府がこれを武力で鎮圧しようとしたことで、火に油を注ぎ、国民議会は市民軍を結成してついに暴動を起こす。そしてバスティーユを襲撃して陥落させたことで、とうとうフランス革命の幕が開いたのだ。
ここまでの流れを見る限り、アントワネットが悪者に仕立て上げられる所以はない。確かに彼女の浪費は甚だしいものだったが、彼女の出費は財政の数パーセントにも満たない。実は彼女が民衆に憎まれたのには、様々な政治的陰謀が関係している。
アントワネット批判の風潮
民衆の憎悪というのは、わかりやすい対象に向けられる。実質的に財政を圧迫する戦費などは民衆の目には見えない。民衆にとっては、自分達の貧しさを顧みず、贅沢な暮らしを送っている貴族や王族こそが最大の敵なのだ。そしてその象徴がマリー・アントワネットだった。
実はアントワネット批判の風潮は、宮殿内の貴族から始まったと言われている。というのも自由奔放な彼女は、朝の顔合わせや、食事風景の公開など、宮殿のしきたりを次々に廃止したことで有名だ。宮殿の貴族にとっては、これらのしきたりにおいて、与えられる役割がステータスだった。たとえば王妃に下着を渡す名誉な役割を与えられれば、それがその貴族の宮殿内での地位を表す。それを奪われるとなると貴族の反感を買うのは当然だ。
おまけにアントワネットは自分のお気に入りの貴族だけを周囲に置いた。彼女の好き嫌いで、宮殿内の地位が大きく変わるということだ。政治の分かる人間なら、上手く人事のバランスを配慮して、不満が出ないようにする。たとえば敵対する派閥の者にあえてそれなりのポストを与えて均衡を保つ、それが政治だ。しかしアントワネットが嫁いだのは14歳、王妃になったのは18歳、そんな子供に政治が分かるわけがないし、わがままに振舞ってもおかしくない。あるいはデュ・バリー夫人の一件のように、出世欲に駆られた側近の権謀術策に利用されることも多々あった。
アントワネットに寵を受けれない貴族は、復讐のため裏でゴシップ雑誌の刊行に協力する。その内容はアントワネットがあらゆる男と乱行を楽しんでいる、という性的スキャンダルの類だった。その悪評が国中に広まると、彼女は一気に民衆の信頼を失う。元よりフランス国民は、王妃の母国オーストリアにネガティブな感情を思っており、その排他的な憎悪も手伝って、アントワネットは「オーストリア女」という外国人差別的な俗称で呼ばれ、フランス人の血を吸う吸血鬼とまで非難された。
そしてアントワネットの信頼を地の底へ落とす事件が発生する。それが「首飾り事件」だ。
ロアン枢機卿という聖職者がいた。彼は宮殿の大臣職を望んでいたが、アントワネットに嫌われているせいで望み薄だった。そんな彼のもとにラ・モット夫人なる人物が接近し、アントワネットが日本円にして192億もする首飾りを欲しがっていて、それの保証人なれば大臣職は確約されると、ホラを吹聴する。それを信じたロアンは、首飾りを代理で購入し、ラ・モット夫人経由でアントワネットに届けられると信じていたが、そんわけもなく、首飾りは解体されて売り飛ばされる。
宝石商は代金の支払いが滞っているので、直接アントワネットに会いに行く。首飾りなど買った覚えがないアントワネットは激怒し、ロアン枢機卿を逮捕する。そしてラ・モット夫人が主犯だと分かり彼女も逮捕する。しかし事実に反して民衆は、本当はアントワネットが首飾りを手に入れるためにロアン枢機卿を利用し、それが表沙汰になったので、尻尾を切るように彼に罪を着せたのではないかと考える。元よりアントワネットの浪費癖は有名で、例のゴシップ関連で信用も失っていたので、そんなふうに民衆に疑われたのだ。
民衆はパンを買えるかどうかの生活をし、その上で重税に喘いでいるのに、彼らの税金でアントワネットが192億の首飾りを買おうとした、という噂は民衆の憎悪を爆発させ、アントワネット批判の風潮を決定的なものにした。そしてこれが革命の直接的な火種となった。
遠藤周作の『王妃マリー・アントワネット』では、この陰謀事件の黒幕として、カリオストロという詐欺師の存在が描かれている。
私は彼女(アントワネット)とその家族がこの国から失脚するのを見てみたいのだな。(中略)私が革命の導火線になる。面白いじゃないかね。
『王妃マリー・アントワネット/遠藤周作』
実際にカリオストロが事件の黒幕だったかは定かではない。遠藤周作の描くカリオストロは個人的な愉しみのために陰謀を企てた。しかし場合によっては、革命派の連中が企てた政治的陰謀だったとしてもおかしくない。いずれにしてもアントワネットは、革命の火種として利用されたのだ。
革命という名の暴動
革命それ自体は悪いこととは言い切れない。民衆たちが立ち上がり、貴族だけが甘い蜜を吸う腐敗した政治体制を転覆させ、人民主体の新たな政治を築き上げる。
しかしいつの時代のどの国の革命も、血で血を洗う暴動は避けられなかった。稀に英国の名誉革命のように、無血革命が実現したが、しかしフランス革命では民衆は暴徒と化し、復讐心や破壊欲を満たすための私刑に熱狂する。
作中ではサド侯爵なる人物が、やがて訪れる革命の正体を的確に見抜いた言葉を口にする。
間も無く、この社会などひっくりかえす革命がやってくる。人々は正義だの平等だの益たいもない言葉を使って国王や王妃や皇太子や皇太子妃を殺すだろう。だが誰一人として本心では社会の正義も平等も信じてはいないのだ。たしかなのはあたらしい支配者とそれに支配される奴隷ができるだけだ。お前のような奴は生まれながらの奴隷。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
この言葉をサド侯爵に浴びせられたのは、もうひとりの主人公とも言える、貧しい平民の女マルグリットだ。売春で稼ぐ彼女は、同じ女としてかけ離れた生活を送るアントワネットに憎しみを抱いて生きてきた。かつて自分をこき使ったパン屋の女将、自分を陵辱した男、そういう憎しみは全てアントワネットに向けられた。そして革命が勃発すると、マルグリットは暴動に参加する。
革命の第一段階のバスティーユ陥落では、相手が攻撃しない限りこちらも攻撃しない、という基本方針が取られていた。革命の目的は、あくまでバスティーユを陥落させ、自分達の権利を国王に認めさせることであり、無駄な血を流す必要はない。しかし陥落に成功し、降参した国王側の軍隊を連れ出すうちに、民衆の間に異様な空気が漂いだす。そして誰かが、「殺せ!」と叫んだ瞬間に、その熱狂は一気に全体に伝染する。マルグリットも一緒になって、「殺せ、殺せ」と叫んでいた。その時の彼女は言いようのない快楽が脳天を貫くのを感じていた。
教養のない民衆は革命が何たるかを理解していない。彼らにとって革命とは、これまで虐げられてきた復讐を果たし、正義の名の下に自分の暴力を正当化する機会に過ぎない。正義や平等といった大義名分を持った時、人間は恐ろしい残虐性を露出させる。
しかし革命の指導者たちは、資本家などの中産階級が中心で、彼ら教養のある人間は、自分達が次の権力を握るために、民衆を利用しているに過ぎない。革命の基本構造とは、上流階級と中産階級が入れ替わることであり、最下層の労働者階級は支配されたままだ。これはサド侯爵の予言した通りである。
たしかなのはあたらしい支配者とそれに支配される奴隷ができるだけだ。お前のような奴は生まれながらの奴隷。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
マルグリットのように、革命に便乗して、ただ暴力の快楽に酔う無教養な人間は、新しい時代が到来しても、永久に奴隷のままなのだ。
マルグリットと共に革命に参加していた中に、アニエスという修道女がいた。彼女は、民衆が飢餓に喘いでいる状況で、聖職者が貴族と手を組む教会の腐敗に疑問を感じ、革命に参加したのだが、民衆による虐殺や私刑が始まると、これは自分が望んでいた革命ではないと感づく。
マルグリット。あなたは間違っているわ。この群衆も間違っているわ。これは革命じゃないわ。革命の名をかりて自分の賤しい本能を満足させているだけだわ。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
実は革命の母体の国民議会は、アニエスのように虐殺や私刑を否定し、王制を残した立憲民主制を望む保守的なフイヤン派と、国王と王妃を処刑して王制を廃止したがる過激なジャコバン派に分裂していた。当初は民衆の大半は保守的な考えだった。しかし国王の家族が、王妃の祖国であるオーストリアに逃亡を図った「ヴァレンヌ逃亡事件」が発生すると、民衆感情は一気に王制廃止に傾く。国王が外国と協力して、革命に燃えるフランスを外側から制圧しようとしている、という噂が広がり、あんな売国奴は殺すべき、と民衆の憎悪が爆発したのだ。
この事件によって過激なジャコバン派が台頭すると恐怖政治が始まる。毎日のように反革命の人間をギロチンにかけていたという。そしてこの時点でルイ十六世とアントワネットの処刑は運命づけられた。
王制を廃止する上で、国王とアントワネットの処刑は必要条件ではなかった。二人から王族という特権階級を剥奪し、一般市民として隠居させる方法で手打ちもできた。しかし革命の大義名分として、みせしめのために彼らを処刑する必要があった。というのもジャコバン派が台頭したからといって、民衆がパンを買えない状況が改善したわけではない。民衆の眼を自分達の失策から逸らせるスケープゴートとして、体制側のシンボルである国王とアントワネットを処刑する必要があったのだ。これが政治である。
マルグリットにとって、アントワネットの処刑は待ち望んでいた瞬間だった。同じ女として対照的な人生を送る王妃が憎くて堪らなかった。その憎しみを晴らす瞬間をしかと目に収めるため、マルグリットはアントワネットの公開処刑を見物する。そしてアントワネットの首が切られた刹那、マルグリットは涙を流す。しかしそれは歓喜の涙とは言い難かった。飢えに苦しみ売春に身を落とした少女時代を回想し、その全てが終わったという空虚な気持ちが彼女を満たしていたのだ。
マルグリットの人生は復讐に支えられていた。アントワネットを恨み、いつか彼女を死刑台に送ってやるという憎悪が、今日まで彼女を突き動かしてきた。しかしその願いが叶った先に、何もないということを彼女は実感したのではないか。革命や暴動の快感に酔っている間は、マルグリットは惨めな生活を忘れられた。しかしその全てが終わった後には、ただ空虚な生活があるだけなのだ。
遠藤周作がこの物語を通して、読者に訴えたかったのは、おそらくマルグリットの涙だ。きっと彼女の涙は、歴史の虚無感でフランスの地を濡らしたことであろう。
ちなみに革命後のフランスは混乱に陥る。ジャコバン派による恐怖政治は、反対勢力に打倒され、指導者のロベスピエールはギロチンにかけられるが、それでもなおフランスの情勢は不安定を極めた。その混乱を収拾させたのが、戦争の天才と言われ、諸外国を次々に侵略して、フランスの権威を復活させた革命児、ナポレオンなのだが、それはもう少し後の出来事である。
アントワネットの死に様
わたくしはもう王妃などでなくてもいい。そして夫や子供たちとだけ、平和に暮らせればいい。神さま。そのような未来をわたくしたち一家にお与えくださいまし。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
フランス革命の時期、アントワネットは30歳を超えており、あの遊び呆けていた自由奔放な少女の面影はもうなかったという。彼女は母親としての毅然とした態度を培っていた。
アントワネットは熱心な教育家として知られている。王族家であれば、宮殿お抱えの教育係がいるはずだが、彼女は自分の手で我が子を教育することを望み、子供たちのそばにいるために宮殿内にアパルトマンを整備した。もともと賭博好きで有名だったが、子供が産まれてからはきっぱり絶っている。
かつて夫を顧みず、仮面舞踏会で遊び呆けていたアントワネットが、子供の存在によって別人のように変化したのだから、母親というのは恐るべし生き物である。
そしてフランス革命が起こると、決断力のない夫に代わって、彼女は積極的に政治に関与しているが、それは王妃の肩書きに縋るためではなく、子供たちの未来を守るためだった。
アントワネットは早い段階で、革命派が王制を廃止するであろう未来を予期していた。そして革命派の手によって子供たちが惨めな人生を負わされることを、彼女は最も恐れていた。夫ルイ十六世は断固として軍事制圧を拒み、革命派の要求を飲む穏健なやり方を望んだ。しかしアントワネットは、一度要求を飲めば、二度も三度も飲まされ、それが王族の崩壊に行き着くことを見抜いていた。だから彼女は明確に戦う意志を示した。
わたくしは自分がこれから夫にかわって戦わねばならぬと思っています。おそらくわたくしは負けるでしょう。負けると知っても戦わねばなりません
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
アントワネットは母国オーストリアの皇帝で、自分の兄にあたるレオポルド二世を通じて、対フランスのためのヨーロッパ連合の結成を呼びかけている。当時のヨーロッパでは王制が主流で、仮にフランスで王制が転覆して共和制が成立すれば、その風潮が自国でも起こりかねないので、各国は反革命の立場をとっていた。アントワネットはそこに助力を求めたのだ。
つまりアントワネットはフランス王妃でありながら、外国と手を組む反逆罪を犯してでも、革命派に立ち向かおうとしたのだ。この一命をかけた大陰謀によって、アントワネットは死刑台に送られることになるのだが、しかし彼女は自らの正義に殉じて死んだのである。そして彼女の正義とは、我が子の未来だった。
死刑台にのぼるアントワネットは、一寸の怯えも見せず、優雅な振る舞いで自らギロチンに首をかけたという。その際に彼女が執行人の足を軽く踏んでしまい、「ごめん遊ばせ、うっかりいたしましたのよ」と王族の振る舞いを最後に見せたことは有名である。
この時のアントワネットの心境を、遠藤周作は次のように描いている。
最後まであなたたちの母は美しく、気品を持って生きています。そして優雅に死を迎えます。なぜならあなたたちの父は仏蘭西国王であり、あなたたちの母は仏蘭西王妃だったからです。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
ごらんなさい。あなたたちの母の死にかたを。どんな暴力もどんな陵辱もわたくしの意志を覆すことはできません。優雅で美しくあろうとするこの王妃の意志を。
『王妃/マリー・アントワネット/遠藤周作』
アントワネットは我が子に宛てた遺書の中に、人生で一番大切なのは、自分の主義を守り、自分の義務を果たすことだと記している。
その言葉通り、彼女は自分の主義を貫いて死んだ。彼女の主義とは、どんな状況におかれても美しさを失わないこと、だった。死に際してもそれをやり遂げることで、彼女は王族としての最後の教育を我が子に施したのだった。
ちなみに少女時代のアントワネットと宮殿で闘った懐かしきデュ・バリー夫人は、ジャコバン派の恐怖政治において同じくギロチンにかけられているが、その際に彼女は泣き叫んで命乞いをしたらしい。そう考えると、アントワネットの死に様は、ちょっと凄すぎる。
民衆からすれば、最後まで王妃のプライドを持ち続けたアントワネットは目障りだったかもしれない。しかしここまで自分の美学を貫いた彼女には、畏怖の念を抱かずにいられない。そして母親という生き物が、我が子のためなら、こうまで強くなれるというのも、驚嘆するばかりである。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップで配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら