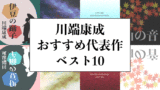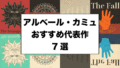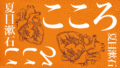川端康成の小説『山の音』は、戦後日本文学の最高峰に位置する名作である。
敗戦後の虚脱し切った日本社会の悲惨な家族の姿が描かれる。
第7回野間文芸賞を受賞し、川端の文壇での評価を決定づけたと言われている。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を考察していく。
作品概要
| 作者 | 川端康成(72歳没) |
| 発表時期 | 1954年(昭和29年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 309ページ |
| テーマ | 戦後の日本の悲しみ 古い道徳の崩壊 |
| 受賞 | 第7回野間文芸賞 |
あらすじ

東京の会社の重役・信吾は、妻の安子、息子夫婦(修一・菊子)の4人で鎌倉に住んでいる。老年の信吾はある夏の夜、地響きに似た「山の音」を聞いて以来、自分の死を強く意識するようになる。
死を意識した信吾は、頻繁に淫夢を見て、若き日に恋焦がれた義姉を懐古する。そして義姉の面影を、息子の嫁・菊子に見出し、舅と嫁の関係を超えた恋心を揺さぶられる。
菊子と修一の夫婦関係は荒んでいる。修一は結婚して2年で未亡人と関係を持ち、その女に子供を孕ませる。信吾が手切金を持って息子の愛人を訪ねると、彼女は独りで子供を産むと言って中絶を拒否する。一方で夫の不貞に苦しむ菊子は、彼との間にできた子供を家族に隠して中絶するのだった。
さらには嫁に行った娘・房子が子供を連れて実家に出戻りする。房子の夫は麻薬の密売に手を出し、自身も中毒になったのだ。のちに夫から離婚届が送られて来て、彼が他所の女と心中を図ったことが明らかになる。
なぜ彼らは尽く堕落し切っているのか。その背後には、敗戦後の日本人の、倫理さえ崩壊した悲しみが潜んでいる・・・
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

戦後日本文学の最高傑作
本作『山の音』は、戦後文学の最高峰に位置づけられ、川端作品の中で最も評価が高い。また日本文学で初めて全米図書賞を受賞するなど海外でも人気がある。
1949年から1954年にかけて、複数の雑誌に各章がバラバラに掲載され、それら計16章が1つの長編にまとめられ単行本化された。それ以前には7章分を別作品『千羽鶴』に併録させて発表している。その際に川端は、どの章で切っても構わない、と言及している。というのも、当初は1回きりの短編を想定していたため、長編としての起承転結が構成されていないのだ。
このように独立した章を複数の雑誌に発表する形式は、異色であるが、『雪国』『千羽鶴』でも採用されている。だがそれは川端の本望ではない。1回きりの短編のつもりが、連載の間に合わせで続きを書き散らし、その結果、意図せぬ形で長編になったのだ。だからこそ構成の練りが不充分で、そんな未熟な作品しか書けぬまま死ぬことを川端は危惧していた。だが皮肉にも本作『山の音』は、川端の作家的評価を決定づける作品となった。
『山の音』が評価された理由は、敗戦後の日本人の傷を繊細に描いたからであろう。川端は敗戦後の数年間を「悲しみの季節」と呼び、次のように言及している。
戦争中、殊に敗戦後、日本人には真の悲劇も不幸も感じる力がないという、私の前からの思いは強くなった。感じる力がないということは、感じられる本体がないということであろう。敗戦後の私は日本古来の悲しみのなかに帰ってゆくばかりである。私は戦後の世相なるもの、風俗なるものを信じない。現実なるものをあるいは信じない。
『哀愁/川端康成』
『山の音』では、修一をはじめ、多くの登場人物が戦争の傷を負い、反道徳的な生活に堕落している。堕落しても何も感じないほど、彼らは虚脱し切っている。
敗戦後の虚脱感は、太宰治の『斜陽』、坂口安吾の『堕落論』『白痴』でも描かれる通り、戦後文学の重要なテーマだった。川端康成の場合は、太宰らと比べて年長であるため、物語も老年の主人公の目線で、堕落した若い世代を描く構造になっている。
加えて、老年の主人公が自らの死期を悟り、若き日の情欲へ回帰するという、死生観が中心テーマになっているのも特徴だ。それは五十歳を迎えた川端が、あまりに周囲の人間の死を経験しすぎたことに影響されている。
片岡君、横光君、また菊池さんらの死去が私の五十歳のこととすれば、五十歳は私の生涯の谷であった。まことに五十歳の私は生きているとこういう時も来るのかと、新たに泉を汲む思いもあって、再生の第一年に踏み出したのかもしれない。
『全集第1巻あとがき/川端康成』
作家仲間の横光利一や菊池寛は、戦時中に右傾化したため「文壇の戦犯」と非難され、文学界から追放され、不遇のうちに病死した。切磋琢磨した仲間が、時代に翻弄され、死んでいく様を身近で見てきたからこそ、川端も自らの死を意識せずにはいられなかったのだろう。
いわば本作は、敗戦後に滅びゆく日本人と、その中で生き残った自分とを描くことで、死生観を深く追求した作品と言える。
以上の背景を踏まえた上で、物語を詳しく考察していく。
戦争の傷を負った若者たち
■修一の場合
結婚して2年で他所に女を作り、その愛人に子供をはらませるほど堕落した修一は、父の信吾にその背徳を咎められ、次のように答える。
「今も新しい戦争が僕らを追っかけて来ているのかもしれないし、僕らのなかの前の戦争が、亡霊のように僕らを追っかけているのかもしれないんです。」
『山の音/川端康成』
戦争が終わって平和な世が訪れてもなお、修一の心には戦争の亡霊が付き纏っている。戦争を経験した彼には、死の恐怖に比べれば、あらゆる背徳も問題ではないという、倫理の崩壊が生じている。その荒廃した心理状態によって、彼の生活は堕落しているのだ。
修一の愛人は、彼の援助を受けずとも、独りで子供を産む決心をした。その問題について、修一は全く情念を抱かない。それは彼が既に落とし子を持つ可能性がある人間だからだ。というのも、戦場には必ず娼婦が存在する。生死の極限状態にある時、人間は本能的に子孫を残そうとするため、戦争と性産業は切り離せない。そして修一も戦場で娼婦を抱き、異国に自分の子供が宿っている可能性を認めているのだ。だから愛人が産んだ私生児が不幸になろうと、戦場で倫理を犯し過ぎた修一には、罪の意識を感じる心が不在だったのだ。
あらゆる倫理が崩壊した戦場から、突然平和な世に連れ戻されても、絶えず彼の心は倫理から浮遊し、その荒んだ心を、放蕩という名の自傷によって埋めていたのだろう。
一方で、夜中に泥酔して帰宅した修一が、妻の菊子に助けを求める場面が描かれる。心の底では妻を求めつつも、素面では妻から逃げ出そうとする。そこには戦争を経験した者にしか判らない、愛を拒絶せねばならない複雑な心理があったのかも知れない。
■房子の夫の場合
同じく修一の姉・房子の夫も、戦後の日本社会で堕落した1人だった。
彼は麻薬の密売に手を染め、自身も麻薬中毒になった。戦中に兵士に供給されたヒロポンが、戦後の市場に大量放出され、多くの日本人が廃人になったのは歴史的事実である。
また戦後の日本では物資が底つき、政府が闇市を半ば黙認するような状態で、誰もが悪いことをしなければ生きていけなかった。そんな風に腐敗した社会の犠牲者として、房子の夫は破滅の道を辿り、房子は子供を連れて実家に出戻りする羽目になったのだ。
最終的に房子の夫は、愛人と心中を図る。彼もまた、妻ではなく、他所の女を選んだ。修一の場合もそうだが、彼らの堕落には、妻を道連れにしてはならないという心理が働いていたのかもしれない。
■未亡人の絹子の場合
戦後には男ばかりが堕落したのではない。多くの女性が戦争未亡人となり、生きる活路を断たれてしまった。
冒頭では、信吾が立ち寄った魚屋で、二人の娼婦が店主に冷遇される場面が描かれる。今とは違い、女性が独りで生計を立てるのが難しかった当時、身寄りのない戦争未亡人は、体を売ってでも生きていかねばならなかった。
修一の愛人・絹子も戦争未亡人の1人である。妻がいると知りながら修一と関係を持ち、彼から酷い仕打ちを受けても、彼女は身を引こうとしなかった。
よその人を返すから、私の戦死した夫を返せ、絹子さんはそんなことを言い出しますの。生きて返してくれさえしたら、夫がどんなに浮気をしたって、女をこしらえたって、私は夫の好きなようにさせてあげる。
『山の音/川端康成』
私たちは夫が戦争に行っても、辛抱していたじゃないの? そして死なれた後の私たちはどうなの? 修一さんは私のところへ来たって、死ぬ気配はないし、怪我もさせないで帰すんじゃないの?
『山の音/川端康成』
戦場を経験した男にとって、死の恐怖に比べればどんな背徳も罪ではないのと同じく、未亡人の絹子にとっては、夫が戦死するのに比べれば夫の浮気など問題ではないのだ。
それは修一の妻・菊子に対する皮肉でもある。夫の浮気に苦しめられ、その憂鬱から子供を中絶した菊子だが、しかし夫は生きて戦争から帰って来た。子供が出来る前に夫が戦死した絹子にとっては、夫の浮気に苦しむ菊子の憂鬱など贅沢な悩みでしかなかったのだ。
そして絹子は、修一との間にできた私生児を産むことで、悲惨な運命(未亡人の人生)に立ち向かおうとする。修一や房子の夫が背徳に塗れて自滅するのに対し、絹子は倫理を犯してでも生に執着する。太宰治の『斜陽』でも同様に、男は自滅の一途を辿るのに対し、女は妊娠を通じて自分の生を肯定しようとする。そこには自らの体内に新たな命を宿し、その命を守るためなら、どんな背徳も厭わない、女性特有の強い生命力が感じられる。
[ad]
信吾と菊子の共依存の関係
信吾はある夏の夜、地鳴りに似た「山の音」を耳にし、それが死期の告知に感じられ恐怖に襲われる。近頃の信吾は老いを自覚し、また同世代の人間との死別を多く経験し、自らの死を意識するようになっているのだ。
「山の音」を聞いて以降、信吾は頻繁に淫夢を見るようになる。死を意識したことで、若き日の情欲へ回帰したい願望、つまり回春願望が夢に表れたのだ。いわば無意識下で死に抵抗しているわけだ。
淫夢に登場する女性は、信吾が若き日に恋焦がれた妻の姉である。義姉は若くで亡くなり、ややあって妻と結婚するに至ったのだが、今日まで信吾の中には義姉の幻影があり続ける。そしてその幻影を息子の嫁・菊子に見出している。
信吾は自分の子供以上に菊子を可愛がり、殊に夫・修一の浮気に苦しむ彼女を誰よりも気にかけている。そこには舅と嫁の関係を超えた不貞な恋心が潜んでいる。
菊子の方も、信吾に好意を寄せている。夫の浮気に苦しむ自分を労ってくれる信吾に慰められているのだ。むしろ信吾がいるから、かろうじて夫婦関係を続けている。実際に彼女は夫婦二人だけで暮らすことを恐れている。そして仮に修一と別れるようなことがあっても、信吾のところにいたいと口にする。
このように、死期を恐れる信吾と、夫の浮気に苦しむ菊子は、互いに慰め合うことで、共依存の関係になっている。それは二人が魂で通じ合えるほどに同じ感覚を所有しているからだ。
二人は、北鎌倉の梅、裏山のからす瓜、鳶の鳴き声など、同じものを見、同じものを聴くことで心を通わせている。自然への関心は、繊細な情緒の表れであり、それらを通して相手の苦悩を察し合っているのだ。
また亡き義姉が紅葉の盆栽を所有していたエピソードを踏まえ、信吾が最後に菊子を紅葉に連れて行こうとする展開も、見事な照応を成している。その一方で菊子の夫・修一は、紅葉に興味がなく、留守番役に名乗出る点で、夫婦が心を通わせていない対比にもなっている。
だが彼らは舅と嫁の関係、不貞な恋が実ることはあり得ない。もっとも戦争で倫理が崩壊した修一らの世代なら不貞も厭わないが、老年の信吾は古い道徳に縛られた世代、菊子と一線を超えることはあり得ない。あり得ないからこそ、日常的な意識の上では仲の良い舅と嫁の関係を育み、夢という潜在意識の中でのみ、性的に愛し合っていたのだろう。
自立を果たした菊子の物語
作中では菊子の苦しみについて具体的に描かれないが、放蕩生活に堕落する夫と向き合えない弱さが原因であることは確かだ。それは必ずしも夫を許すことばかりではなく、夫を捨てる決断さえできない弱さでもある。その弱さは少なからず信吾が助長している。精神面において信吾に依存し縋っているからこそ、菊子は夫と向き合えずにいるのだ。
それに気づいた信吾は、息子の言葉を借りて、菊子が自由であることを伝える。
「よく考えてみると、菊子はわたしからもっと自由になれ、わたしも菊子をもっと自由にしてやれという意味もあるのかもしれないんだ。」
『山の音/川端康成』
信吾の言葉を聞いた菊子は、戸惑いながら「自分は自由でしょうか」と言って涙ぐむ。ちょうどその時、庭の方で鳩が飛び立つ。信吾にはその羽音が「天の音」に聞こえた。
「天の音」を聞いた直後から、菊子の態度は明らかに豹変する。修一の姉が店を持ちたいと話した場面で、修一は「姉さんに水商売ができるのか」と茶化す。それに対して菊子は「女はみんな水商売が出来ます」と反駁して家族を驚かせる。これまで信吾に依存していた菊子が、初めて女性の自立を主張したのだ。それは彼女が自立した女性に変化しつつある証拠だ。
最後の場面では、信吾が庭にぶら下がるからす瓜を発見し、菊子に教えようとするが、信吾の声は洗い物の音で菊子に伝わらない。同じ自然物を見ることで心を通わせていた二人が、最後には同じものを見なくなっているのだ。それは菊子が既に精神的な自立を実現し、鳩のように信吾の元から飛び立ったことを意味する。
このように信吾と菊子の共依存は「山の音」を出発点にし、「空の音」を終着点にする。それは同時に菊子の克服の物語でもある。信吾と違い、菊子は古い価値観に縛られない新しい時代の人間だ。菊子の自立には、敗戦後の虚脱した日本人が新しい時代へと羽ばたく、そんな希望の想いが込められていたのかもしれない。
■関連記事
➡︎川端康成おすすめ代表作10選
映画『伊豆の踊子』おすすめ
川端康成の代表作『伊豆の踊子』は、6回も映画化され、吉永小百合や山口百恵など、名だたるキャストがヒロインを務めてきた。
その中でも吉永小百合が主演を務めた1963年の映画は人気が高い。
撮影現場を訪れた川端康成は、踊子姿の吉永小百合を見て、「なつかしい親しみを感じた」と絶賛している。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら