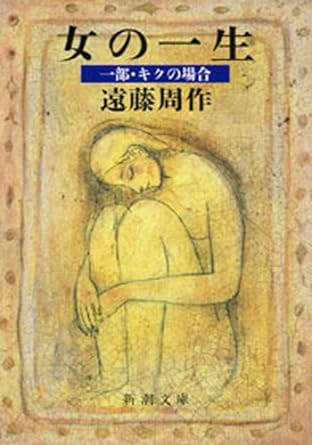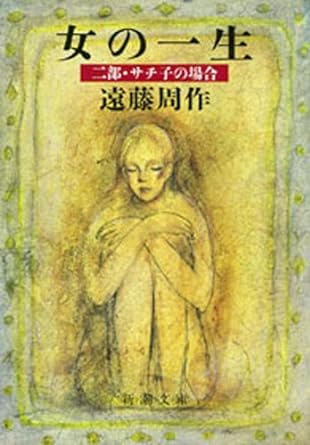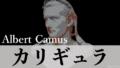遠藤周作の小説『女の一生』は、長崎のキリシタン迫害を描いた、『沈黙』の続編とも言える作品である。
一部「キクの場合」では、幕末から明治初頭にかけての弾圧の歴史が描かれる。
二部「サチ子の場合」では、戦時中に敵国宗教と差別された信徒の葛藤が描かれる。
本記事ではあらすじを紹介した上で、物語を考察していく。
作品概要
| 作者 | 遠藤周作(73歳没) |
| 発表時期 | 1982年(昭和57年) |
| ジャンル | 長編小説(一部・二部) |
| ページ数 | 一部:490ページ 二部:494ページ |
| テーマ | キリシタン弾圧 自己犠牲の愛 |
あらすじ

■一部:キクの場合
幕末の長崎には、三百年の弾圧に耐え、信仰を守り続ける隠れキリシタンが大勢いた。商家に奉公する娘キクは信徒ではないが、彼女が恋慕う清吉はキリシタンだった。
ある時、信徒たちが仏葬を拒否したことで、キリシタンの存在が露わになる。彼らは惨い拷問を受けるが、それでも多くの者は改宗を拒否する。清吉もその1人だった。
拷問に苦しむ清吉を救うため、キクは信徒ではないのに聖母に祈り続ける。そんなキクの心に漬け込んだ役人は、清吉への拷問を軽くする条件で、彼女の処女を奪い、売春で金を稼がせる。愛する者のために肉体を汚すキクに、神は救いを与えるのか・・・?
■二部:サチ子の場合
戦時中の日本では、敵国宗教を信仰するキリシタンは差別されていた。幕末の長崎でキクと一緒に奉公していた従妹ミツは、その後洗礼を受けたので、孫にあたるサチ子はキリシタンだった。
小さい頃からサチ子と同じ教会に通う幼馴染の修平は、慶應大学に進学して文学者を夢見るが、それも束の間、空軍に徴兵される。キリシタンである修平は、人殺しを正当化する戦争の矛盾に苦しむ。そして権力に屈して戦争を黙認する教会が信じられなくなる。
そんな修平の苦しみを、サチ子は自分のことのように苦しみ、彼のために祈り続ける。だが暗い運命の波には逆らえない。修平は特攻隊に選ばれ、同時に長崎の街に原爆の影が歩み寄る・・・
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

創作背景:『沈黙』の続編
本作『女の一生』は、遠藤周作の心の故郷、長崎を舞台にした小説である。
遠藤周作が初めて長崎を旅したのは1965年のことで、その翌年にはキリシタン弾圧を題材にした『沈黙』を執筆した。それから16年の時を経て書かれた『女の一生』は、時系列で言えば『沈黙』の続編にあたる。
『沈黙』は、「島原の乱」直後のキリシタン弾圧を描いた江戸初期の物語だ。そして『女の一生』の第一部は、幕末の「浦上四番崩れ」が題材になっているので、『沈黙』から約200年後の物語にあたる。第二部に関しては、さらに70年が過ぎた戦時中の物語である。
その他にも、江戸時代のキリシタン弾圧を描いた作品は多く存在する。
例えば、『侍』という作品では、禁教時代の直前に海外渡航した侍が、旅の中で洗礼を受けるが、その間に日本で鎖国と禁教が始まり、帰国して悲劇に巻き込まれる物語である。こちらは長崎ではなく東北が舞台だが、テーマは地続きなのでおすすめだ。
■時系列
・『侍』1616年頃
→鎖国の直前
・『沈黙』1638年頃
→島原の乱の直後
・『女の一生:一部』1867年頃
→幕末の浦上四番崩れ
・『女の一生:第二部』1945年頃
→第二次世界大戦
そもそも遠藤周作は、なぜキリシタン弾圧の歴史に執着し、特に長崎にこだわったのか。
『女の一生:第一部』の巻末には、次のように記されている。
(長崎の歴史を知ることで)私の人生に問いかけてくる多くの宿題を嗅ぎとった。それらの宿題のひとつ、ひとつを解くために私は『沈黙』から今日までの小説を書いてきたと言っていい。
『女の一生:筆間雑話』
長崎の歴史から受け取った宿題、それは生涯一貫して追求された、弱者のためのイエス、という独自のイエス像であろう。
西洋の父性的なキリスト教では、善悪の概念が明確で、信仰に背く者は悪とみなされる。しかし遠藤周作の小説で描かれるイエスは、弱さゆえに信仰に背いた者、罪を犯した者を、決して見捨てない。いかなる弱者も救う母性的な存在として描かれるのだ。そこにはキリシタン弾圧の歴史が大きく関係していると思われる。
世界的に見て、キリスト教は他宗教を迫害する立場にあり、日本のようにキリスト教が迫害された歴史を持つ国は珍しい。凄まじい迫害の中で棄教した日本人は多く存在する。西洋的なキリスト教の観点からすれば、信仰を捨てた者は救われない。
しかし日本の弾圧の惨さを知れば、彼らがどんな想いで棄教したかが分かる。そんな苦しい境遇の末に神を捨てねばならなかった弱者を、果たしてイエスは見捨てるだろうか。いや、イエスはそんな人間こそ救うはずである。そういう意味での「弱者のためのイエス」を遠藤周作は追求したのだ。
長崎という街と出会い、キリシタン弾圧の歴史を知ることで、遠藤周作は独自のイエス像を追求できた。その恩返しとして『女の一生』を執筆したと彼は言及している。
以上を踏まえた上で、物語を考察していく。
第一部:自己犠牲の愛
第一部「キクの場合」では、キリシタンではない娘キクが、キリシタンの青年・清吉を愛したことで、悲劇に巻き込まれる。
そんなキクの一生を通して、ここでは「自己犠牲の愛」というテーマに注目する。
長崎の浦上では、過去に三度の弾圧が行われ、キリシタンは絶滅したと思われていた。ところが彼らの間には、「七代耐えれば再び日本に司祭が訪れる」という予言が伝えられており、島原の乱から200年が過ぎても、隠れて信仰を守り続けていた。それが露わになり、幕末から明治初頭にかけて行われた四度目の弾圧が「浦上四番崩れ」である。
この「浦上四番崩れ」で、清吉は津和野に島流しにされ、惨い拷問を受ける。信徒ではないキクからすれば、なぜ清吉がそこまでキリスト教に執着するのか理解できない。それでも清吉が信仰するという理由だけで、キクは教会に訪れて聖母像に祈り続ける。この真っ直ぐな愛情によって、キクは転落の運命を辿る。
浦上の役人・伊藤清左衛門は、キリシタン弾圧を扇動し、自ら拷問を加えていた。そんな伊藤は、美しいキクを手篭めにするため、卑劣な手段で彼女に歩み寄る。身体を許せば清吉への拷問を軽くしてやると誘惑するのだ。その結果キクは処女を伊藤に奪われる。
さらには、津和野の役人に賄賂を払えば、清吉への拷問が軽くなると吹聴され、キクは売春で金を稼ぐようになる。清吉を助けるためなら自己犠牲も厭わなかったのだ。しかしキクが売春で稼いだ金は全て伊藤がネコババしていた。そしてキクは売春がたたって結核になり、最終的に死んでしまう。
ここで問題になるのが、愛する者のために肉体を汚す行為の是非である。
キクの処女は、愛する清吉のために死守すべきものであった。ところが彼女は、愛する清吉を救うために、愛していない伊藤に処女を明け渡し、他にも多くの男に貪られた。キクは愛する者のために死守すべき純潔を、愛するがゆえに汚さねばならない矛盾の中にいたのだ。
さらにキクを苦しめたのは聖母の存在だ。聖母は処女のまま懐胎した、穢れなき純潔の象徴である。清吉がキク以上に愛する聖母は処女であるのに対し、キクは地の底まで肉体を汚してしまった。そんなキクに救いはあるのか。
キリスト教では売春は不道徳にあたる。教父時代には禁欲が重視され、娼婦は差別され教会から排除された。だが注意すべき点は、イエスの教えと教会の方針が、必ずしも一致しないということだ。
イエスは娼婦を差別するどころか、彼女たちを受け入れ、彼女たちを差別する者より、先に神の国に入るだろうと説いた。しかしイエスのこの姿勢をキリスト教会は継承しなかった。イエスそのものは母性的であるのに対し、キリスト教会は父性的な側面が強いのだ。そして遠藤周作は、無論、母性的なイエス像を追求した。
死に際にキクは、聖母像の前で血を吐き、自分の体が汚れ切ったことを懺悔する。この汚れた体では二度と清吉に近づけないと涙を流す。そんなキクに対して聖母はこう答える。
「いいえ。あなたは少しもよごれていません。なぜならあなたが他の男たちに体を与えたとしても・・・それは一人の人のためだったのですもの。その時のあなたの悲しみと、辛さとが・・・すべてを清らかにしたのです。あなたは少しもよごれていません。あなたはわたくしの子と同じように愛のためにこの世を生きたのですもの」
『女の一生:一部・キクの場合/遠藤周作』
そしてキクは力尽き、神の国へと旅立った。
西洋の父性的なキリスト教では、罪や過ちを犯した者に対して厳格である。しかし遠藤周作が描くイエスは、愛するがゆえに身を汚した者、弱さゆえに罪を犯した者に、救いの手を差し伸べる。それはしばしば西洋のキリスト教会から批判された。しかし本来のイエスは、そんな風に弱者を決して見捨てない、母性溢れる存在ではなかっただろうか。
伊藤清左衛門の弱さ
第一部「キクの場合」で、もうひとり重要な人物は、キクを陵辱した伊藤清左衛門である。
最初のプランでは彼がこの小説のなかでこれほど重要な人間となるとは考えてもいなかった。書きすすめるうちに、この陋劣な人間に私は同情し、同情しただけでなく愛情さえ抱くようになった。
『女の一生:筆間雑話』
作者が言うように、伊藤清左衛門は卑劣な人間である。自らの手で信徒に拷問を加え、キクの純潔を穢した張本人だ。だが彼のように、弱さゆえ嗜虐心に憑かれた人間を、遠藤周作は見捨てない。
伊藤清左衛門には、本藤舜太郎という長崎奉行所の同僚がいた。彼らは同じ下級武士の出身であるが、本藤の方は先見の明が優れていた。開国を予見して外国語を学び、明治時代になると通訳者として地位を高めた。一方の伊藤は時代の変化に翻弄された没落武士である。両者の開きに、伊藤は耐え難い嫉妬を抱き、その自暴自棄が、信徒やキクへの嗜虐心を駆り立てた。
確かに伊藤は、信徒の拷問、キクの陵辱に快楽を感じていた。だが同時に、胸をえぐられるような自己嫌悪に襲われる。彼は嗜虐を通して自分を傷つけていたのだ。そういう破滅的な手段でしか、自分の惨めな境遇を晴らせない弱さを抱えていた。
そんな伊藤に対して、プチジャン神父はこんな言葉をかける。
あんたは浦上の切支丹を苦しめて、自分で自分の体に血ば流された。
『女の一生:一部/遠藤周作』
神さまは本藤さまより、あなたさまのほうを愛しておられることはわかっとります。
『女の一生:一部/遠藤周作』
立身出世を成す本藤よりも、時代に翻弄され嗜虐的になる伊藤の方が、神に愛されていると言うのだ。それは弱さゆえに罪を犯し、その罪によって自分を傷つける伊藤の弱さを、神は決して見捨てないという、遠藤文学に一貫するイエスの姿勢である。
時が経ち、政府がキリスト教を容認し、信徒が拷問から解放された後、伊藤は洗礼を受ける。それを予見するかのように、聖母はキクが死ぬ直前にこんな言葉を口にしていた。
あなたの愛があなたにさわった男のよごれを消した筈です。
『女の一生:一部/遠藤周作』
かつてプチジャン神父は、なぜ信徒たちは拷問の苦しみに耐えてまで信仰を守るのか、という問いに対し、彼らの苦しみは決して無駄にならないことがいつか証明される、と答えた。その言葉通り、「浦上四番崩れ」によって日本は世界から圧力をかけられ、それが結果的に近代化の道へ繋がった。信徒たちの苦しみが日本の未来に大きな影響を与えたのだ。
そしてキクが貫いた自己犠牲の愛もまた、罪深い伊藤に影響を与え、彼を信仰へと導いた。
おキクさんはあんたに苦しめられたばってん、あんたば別のところに連れていったとたい。そいだけでもあん人の一生は、無駄じゃなかった・・・・
『女の一生:一部/遠藤周作』
苦しみ抜いた者がいかにして救われるかは神のみぞ知る。しかし苦しみ抜いた者が、キクが、伊藤という卑劣な人間に少しでも影響を与えたのなら、彼女の死は犬死ではなかったのかも知れない。
どうかキクが、神の国で、幸福になっていることを願う。
第二部:権力に屈する教会
第二部「サチ子の場合」では、第二次世界大戦下の長崎を舞台に、キリシタンのサチ子と修平が戦争の悲劇に巻き込まれる。
サチ子は、第一部に登場するキクの従妹ミツの孫にあたる。愛する者のために自己犠牲を厭わないキクの激しい血は、やや遠い血縁のサチ子にも受け継がれている。
物語は、入隊が決まった修平の苦しみを、サチ子が自分のことのように苦しむ、という第一部(キクと清吉)と同じ構造になっている。しかし第二部の場合は、サチ子の自己犠牲よりも、修平の苦しみに重きが置かれている。
■信仰と戦争の矛盾
キリシタンの修平は、幼い頃から人殺しは悪だと教わってきた。ところが戦争は人殺しを正当化する。入隊が決まった修平はこの矛盾に苦しめられる。
修平が最も失望したのは教会の姿勢だ。戦時中の日本では、反戦する者は憲兵に逮捕され殺された。人殺しを悪だと説く教会でさえ、国家の脅威に屈して戦争を黙認していた。
説教を人々にする牧師が人を殺す戦争に目をつぶっているのが、たまらなく不快だった。矛盾していると思った。
『女の一生:二部/遠藤周作』
結局は教会も官僚的で、国家権力には逆らえない。信徒の苦しみより、立場や権威の方が大事なのだ。こうした教会の欺瞞から、修平は神さえ信じられなくなる。
これだけははっきり言います。日本の基督教は怠慢でした。人を殺さねばならぬ目になった私たちがどう納得していいのか、本当の言葉を与えてくれませんでした。いや、教会もまた今の私と同じように、苦しんでいるのでしょう。答えられないのでしょう。
『女の一生:二部/遠藤周作』
教会が言葉を与えてくれぬ以上、修平は自分1人で矛盾を解決せねばならなかった。
多くの者は、死や殺人にもっともらしい理屈を求めて、自分を無理やり欺いていた。
同級生の大橋の場合は、国家ではなく、家族や恋人のために死ぬのだと自分を納得させる。それは最も恐ろしい盲信である。そんな風に自分を欺いても、結局は国家に殺されるのだ。それこそ権力者の思う壺である。
あるいは知人の中条氏は、同じように戦争で殺される者の苦しみと共にあるために、自分も彼らと一緒に戦争に行く、という考えを説く。それはキリスト教的な弱者の連帯を思わせ、修平に些細な慰みを与えるが、しかし戦争による殺人を納得する材料にはならない。
最後まで矛盾を解決できなかった修平は、なんと神風特攻隊に志願する。それは絶望的な運命に対する諦めの結果だが、しかし、もう1つ別の感情があった。
キリスト教徒である修平は、殺人の運命に抗えないなら、その償いとして自分も死なねばならないと考えたのだ。特攻隊は自殺を意味し、キリスト教では大罪にあたる。しかし修平は、殺人を犯す代わりに自分も死ぬという選択をしない限り、暗い運命を割り切れなかったのだ。
結局はこの暗い運命の波から私たちは逃れられなかっただけです。辛い世代でした。本当に・・・辛い世代でした。
『女の一生:二部/遠藤周作』
一部「キクの場合」では、弾圧に耐えるキリシタンの苦しみは、日本の近代化や、伊藤清左衛門の改心によって意味付けされたから、まだ救いがあった。しかし戦争による死は何をも救わない。修平の死は犬死である。原爆の被害は無情である。全ての苦しみは、戦争の前では絶望である。
コルベ神父が伝えたかったこと
第二部「サチ子の場合」では、サチ子と修平の物語と並行して、アウシュビッツ収容所の物語が描かれる。
かつてサチ子や修平が幼かった頃、長崎の浦上に駐在していたコルベ神父は、その後ヒトラー政権に連行され、アウシュビッツ収容所に監禁されていた。
収容所では毎日何千ものユダヤ人やポーランド人がガス室に送られる。女子供は即刻殺され、男は衰弱して働けなくなると殺される。誰かが脱走を企むと二十人が連帯責任で殺される。抗えない死の運命を前に、彼らは仲間の死に心を痛める感情が無くなり、互いに歪み合い、自分だけが生き残れたらそれでいい、というエゴと憎悪と虚無が蔓延する。
そこに神は存在しなかった。
ある囚人は、この収容所は地獄だと訴える。するとコルベ神父はこう答える。
まだここは地獄じゃない。地獄とは・・・愛がまったくなくなってしまった場所だよ。しかしここには愛はまだなくなっていない。
『女の一生:二部/遠藤周作』
愛が欠けた世界なら、愛をつくらねば・・・
『女の一生:二部/遠藤周作』
そしてコルベ神父は、ある囚人の代わりに処刑を志願し、死ぬまで飲食物を与えられない餓死室に閉じ込められ、数日後に息絶える。
コルベ神父の死は英雄主義の自己満足と取られるかも知れない。実際に彼のように、自己犠牲で命を捨てれる者ばかりではない。だが命を捨てれないから弱いということでもない。彼が伝えたかったのは、絶望的な運命そのものが地獄なのではなく、絶望的な運命に際して愛を失った時に世界は地獄になる、ということだ。
確かに、囚人たちが愛を捨てて歪み合う様は、地獄としか言いようがない。だが愛を持ち続けたところで、死の運命を免れるわけではない。コルベ神父が身代わりになった囚人も、恐らくその後ガス室で殺されただろう。そんな絶望的な世界では、愛は綺麗事に変わる。戦争は惜しみなく愛を奪う。
『女の一生:第二部』は、単に愛や自己犠牲の美徳を説いた、ヒューマニズム小説ではないだろう。戦争に巻き込まれた人々が、死や殺人の運命を納得するために、いかに自分を欺かねばならなかったか、その極限の心理状態を描きたかったのだと思う。
そして多くの人々は、何も納得できぬまま、無惨に殺されたのだろう・・・
映画『沈黙』がおすすめ
遠藤周作の代表作『沈黙』は、スコセッシ監督がハリウッドで映画化し話題になった。
禁教時代の長崎に潜入した宣教師は、想像を絶するキリシタン弾圧の光景を目撃し、彼らを救うために棄教の選択を迫られる・・・・
ハリウッド俳優に加え、浅野忠信、窪塚洋介ら日本人キャストが共演。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら