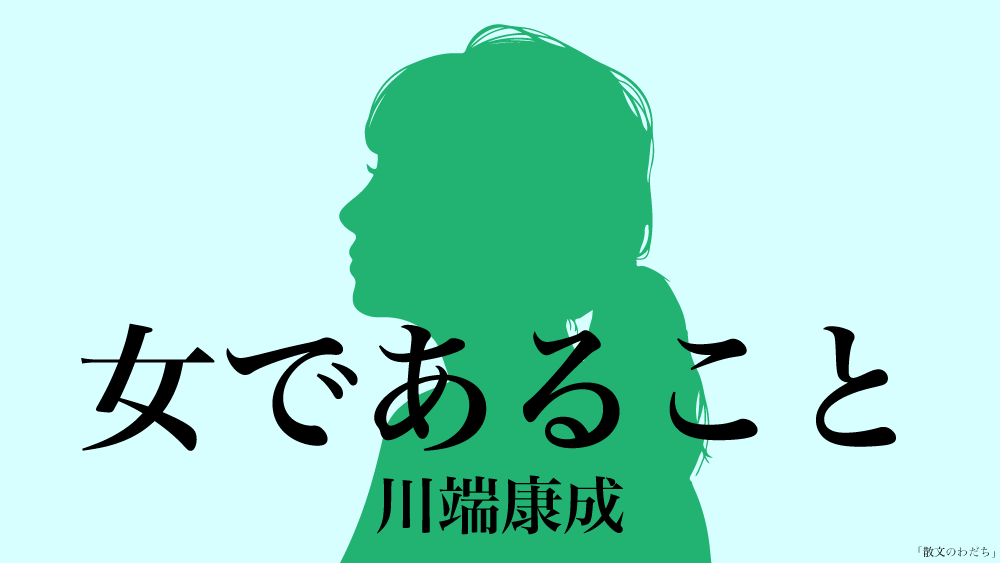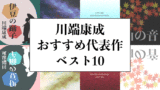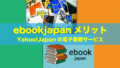川端康成の小説『女であること』は、タイトル通り女の哀しみをとらえた長編小説である。
3人の女性の歪な恋愛行動を通じて、女であることの渇き、恐怖、自己嫌悪、そして決して逃げられない女としての運命が描かれる。
川端文学の中では特異で、他作品に比べて読みやすいので初心者におすすめの1冊だ。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を考察していく。
作品概要
| 作者 | 川端康成(72歳没) |
| 発表時期 | 1956年(昭和31年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 688ページ |
| テーマ | 女の哀しみ 女であることの否定 |
あらすじ

両親への嫌悪感から家出した少女さかえは、東京の知人・佐山夫婦の世話になる。夫婦の家には弁護士の夫が担当する死刑囚の娘・妙子も居候していた。この二人の少女を中心に女としての哀しみが描かれる・・・
父が犯罪者という暗い素性を持つ妙子が病弱で控え目な少女なのに対し、さかえはワガママで気まぐれな少女である。佐山の妻・市子は子供ができないこともあり、二人の娘を大切に世話するのだが、さかえは市子に対する独占欲から妙子を邪険に扱う。
さかえの市子に対する甘え方は、どこか同性愛のような危うさを見せる一方で、夫の佐山に対しても危険な不貞の予感を見せる。さらには幼馴染の光一も誘惑し、彼女の魔性ぶりは周囲の人間を掻き乱していく。しかしさかえ自身も魔性ぶりを自覚し、女であることに嫌悪感を抱いている。
さかえが現れて夫婦の家に居づらくなった妙子は、恋人の有田と同居を始める。死刑囚の父を持つ妙子は、恋愛に強烈な抵抗感を抱いているが、その渇いた情愛の反動からか有田なしでは生きていけなくなる。有田との関係が殆ど体目当てになっても、彼から離れることはできないのだった。
二人が女であることに葛藤する一方で、さかえに掻き乱された佐山夫婦は、かえって回春したかのように奇跡的に妊娠する。それはさかえに大きなショックを与え、ある雨の夜に夫婦の家を去るのだった・・・・
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

創作背景
1956年に朝日新聞に連載された本作『女であること』は、川端文学の中で特異な位置を占める作品と言える。
作品の時系列としては、『山の音』『千羽鶴』『舞姫』『みづうみ』などに続く形で発表された、戦後の川端文学の1つである。
川端の作家としての評価は、『山の音』『千羽鶴』で確固たるものになったが、この一連の傑作を経て発表された『女であること』以降、しばらく執筆が途絶える。そして再び筆を取った『眠れる美女』では、全く新たな前衛的な作風に変化していた。
そういう意味で『女であること』は転換期の作品とも言えるが、しかし創作の節目に重要な役割を与えた作品というわけではない。確かに作品のテーマは、川端文学の特徴でもある女性像が題材になっているが、作中に登場する女たちは、他作品と比べて異色である。
川端が描く女性像には実体がない。例えば『山の音』では、捉え難い女性像を感覚的な手法で描くことで、実体のない幻影のような存在として映し出されている。あるいは『眠れる美女』では、タイトル通り眠り続ける実体のない女性しか登場しない。この虚ろな女性美こそ川端文学の特徴なのだが、『女であること』では体温を持った女たちがいきいきと活動する。言い換えれば、登場人物の実態がとらえやすく、非常に読みやすい初心者におすすめの1冊だ。
同じく女性美を描いた作家として谷崎潤一郎が有名だが、『女であること』のさかえは、『痴人の愛』のナオミを想起させる、天真爛漫で小悪魔的で、周囲を掻き乱す危険な少女である。その小悪魔的な女性像の背後に、女としての哀しみを描くところが、あくまで川端文学だ。
作中に登場する女たちは、それぞれ女であることの葛藤を抱えている。本記事では、さかえ、妙子、市子、三人の女性に注目して、彼女たちの葛藤を考察していく。
女であることを否定するさかえ
大阪の三浦商会の次女さかえは、母の使いに出たその足で東京行きの列車に飛び乗る。ややあって東京の佐山夫婦の家に居候し、そこから彼女の暴走が始まるのだが、そもそも彼女はなぜ実家を飛び出したのか。
さかえの両親は不仲で、父は他所に女を作り、その女との間に子供がいる。世間的に母は夫に捨てられた哀れな女という境遇にある。こんな酷い仕打ちを受ければ、怒りや嫉妬に狂うか、悲しみに暮れるか、そうなってもおかしくないものだが、さかえの母はわざと人前で繕って平和そうに暮らしている。その姿がさかえには堪らなく惨めで、嫌悪感さえ抱いている。それは母に対する嫌悪感というより、女であることに対する嫌悪感だ。
母は人前をつくろって、つまらぬことにも、おもしろそうに振る舞って見せる。それがさかえには、母まで自分を突き放しているかのように思える。さかえは女であることのいやさが、いろいろと感じられはじめて、男装してみたいと望みながら、少女期をすごした。
『女であること/川端康成』
なぜ女ばかり惨めな境遇を強いられるのか。その境遇に堪えて強く振るわねばならない女の哀しみに、さかえは不満を感じ、自分が女であることを否定したがっている。
要するに、母元を飛び出したさかえの家出は、女であることからの逃避行と言える。それは東京駅に到着してから、生理が終わるまで佐山夫婦に会わなかった言動にも表れている。そうした逃避願望が、佐山の妻である市子に対する、同性愛じみた執着へと暴走したのだ。故意に男役を演じることで、自己の女性性を否定していたのだろう。
先に居候していた妙子を邪険に扱ったり、佐山夫にちょっかいを出したり、時おり幼馴染の光一を誘惑するのも、全ては市子の気を引くためである。市子を独占することで、自分が女である呪縛から解放されたがっていたのだろう。
だがさかえの暴走は、女であることを否定すると同時に、女としての小悪魔的な魅力を最大限に発揮してしまう。さかえの思わせぶりな態度に、佐山夫や光一は性的魅力を感じてかき乱される。そしてさかえ本人も自分の無意識的な魔性ぶりを自覚し、自暴自棄になって酒に溺れていく。女である以上、女であることから逃避できない葛藤。あるいは、いくら女であることを否定しても本能的に男を頼ってしまう性に、彼女は苦しんでいたのだろう。
極め付けは市子の妊娠がさかえを絶望させた。子供ができたことで市子を独占できないショックもあっただろうが、結局は男がいなければ女は妊娠できないという、その圧倒的な女の性に直面し、彼女の女であることの否定は、敗北の局面を迎えたのだろう。
最後にさかえは、佐山夫婦に別れを告げ、父に会いにいく。雨の中を旅立つさかえの姿を見た市子は、さかえの暴走は別れた父を求める反動だったのかも知れないと考える。だが実際のところ、さかえが父に会いにいく決断は、自分が母と同じ、男無くして生きていけない、女としての諦めの結果だったように感じられる。
女であることに渇く妙子
さかえと対照的な存在として描かれているのが妙子だ。
妙子は犯罪者の娘である。妻に先立たれた父はある恋愛関係のもつれから、人妻とその夫を刺殺して死刑判決が下された。その上訴を担当するのが佐山夫で、妙子の不幸な境遇を見かねて佐山夫婦が引き取ることになった。
父が犯罪に手を染めるほどの狂気的な激情を持つなら、自分にもその素質が遺伝しているという強迫観念に妙子は囚われている。ゆえに彼女は恋愛を恐れ、同時に恋愛に病的にのめり込んでいく。
さかえが父母への抵抗感から女であることを否定するのに対し、妙子は父の渇望から女であることに飢えている。その飢えが彼女に狂気的な愛情を芽生えさせた。父と一緒に死刑になる妄想に刺すような喜びを感じ、死の中に永遠の愛を見ている。現代的な感覚で言えば、愛する人に殺されたい、という暗い情熱だろうか。
そんな妙子は、学生の有田に父を重ねることで荒んだ愛に堕ちていく。
佐山夫妻の家を出た妙子は、有田と同棲を始めるのだが、有田の両親は快く思わない。有田は両親を説得すると約束するが、いつしか約束は有耶無耶になる。それだけならまだしも、妙子を残して別の下宿先に移り、彼女の肉体を貪る時にだけ訪ねて来るようになる。
それでも妙子は有田を恨まない。例え相手から与えられなくとも、自分が与えるだけで与えられたと同じ喜びを実感し、その一方的で報われない関係の中に、彼女は愛を見出している。
男と別れると、女の方は傷つけられたとか、捨てられたとか、とかく損をしたように思いがちだけれど、人を愛するって、そんなものじゃないのよ。
『女であること/川端康成』
こうした恋愛観においても、さかえと妙子は対照的である。さかえは女の惨めな境遇を心底嫌い、女であることを否定したのに対し、妙子は女であることに固く囚われ、惨めな境遇にこそ自分の居場所を見出している。それは殆ど自傷的な愛と言える。
結局は父との関係が、彼女を惨めな境遇に閉じ込めているのだろう。妙子にとって監獄にいる父は、限られた日に、限られた時間だけ、しかも金網越しに会える存在である。有田との恋愛にも同じ状況を投影することで、そこに擬似的な父性愛の体験を求めているように見える。例え肉体を貪るという不純な動悸だとしても、時おり有田が自分の元へ訪れる行動の中に、彼女は叶うはずのない父との交わりを実現していたのかも知れない。
女であることに回帰する市子
女であることに葛藤する若い娘2人を観察する立場として、佐山の妻・市子の視点は、物語の中核をなしているが、市子自身も女であることに葛藤する1人である。市子の葛藤はさかえのそれに近い、女であることからの逃亡だ。
市子が女であることから逃亡するのには2つの理由がある。1つは本当に愛した相手・清野ではなく、今の夫佐山と一緒になったことだ。
決して佐山との夫婦生活が不幸なわけではないし、むしろ幸福に感じているが、思いがけず清野と再会したことで、市子の中に若き日の情熱が蘇り、これまでずっと佐山に対して借寝の床にいたような不安に襲われる。
借寝の床という言葉通り、佐山との交わりには女としての情熱が欠けている。その最大の原因は、子供ができない体だからだろう。もちろん女性の幸福が出産などという考えは時代錯誤だが、作品の時代背景からすれば、市子が出産できないことに女として負い目を感じていてもおかしくない。何より彼女は子供を欲しがっている。さかえや妙子の世話をするのも行き場のない母性愛の代替に見える。
本望ではない結婚、妊娠できない体。
この二つの理由から、市子は佐山との夫婦生活に安定した幸福を感じるものの、女性として母親としての幸福は享受できずにいる。ましてや清野と再会してからはその鬱積が強くなる。
そんな時に、さかえから同性愛的なアプローチを受け、市子の中に動揺が生じる。同性愛に身を投じて自分の女性性を否定することで、女としての負い目、清野との回春的な情熱から逃避できる甘い誘惑を感じたのだろう。
市子の女であることからの逃避は、夫との交わりを拒否する場面の会話に表れている。
夫「おとむらいの後とか、お通夜のあととかは、妙に女がほしくなるものだな。」
『女であること/川端康成』
市子「わたしは女じゃないわ。侮辱しないでちょうだい。」
しかし市子の台詞には、女であることを否定すると同時に、夫が若い女に感化されて、その吐口として自分が使われることに対する嫉妬、つまりは女でありたい執着も垣間見える。
そして物語の最後には、市子は奇跡的に子供を授かる。最後の流産から10年過ぎた妊娠に、市子は驚きと動揺と不安を感じる。もちろん喜びがないわけではないが、女であることを否定したがった矢先に、結局女に回帰してしまう哀感のようなものも感じられる。
女であることが、幸福か不幸か。それは人間関係としての幸福よりも、もっと複雑で捉え難いものとして、川端康成は描いている。
そして最後には3人ともが女に回帰してしまう哀しさもある。それは肉体的な機能によるところも大きいし、あるいは彼女たちが深層心理で女であることを渇望しているところも大きい。渇きと嫌悪を同時に抱える彼女たちは、孤独と諦念と破滅にぴったり身を寄せながら、美しく哀しく生きているように見える。
女であるということは、じつに奇妙な、不純な、複雑ななにかであって、どんな形容をもってしても、それを現わすことは出来ない。
『女であること/川端康成』
■関連記事
➡︎川端康成おすすめ代表作10選
映画『伊豆の踊子』おすすめ
川端康成の代表作『伊豆の踊子』は、6回も映画化され、吉永小百合や山口百恵など、名だたるキャストがヒロインを務めてきた。
その中でも吉永小百合が主演を務めた1963年の映画は人気が高い。
撮影現場を訪れた川端康成は、踊子姿の吉永小百合を見て、「なつかしい親しみを感じた」と絶賛している。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・アダルト動画見放題(5万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら