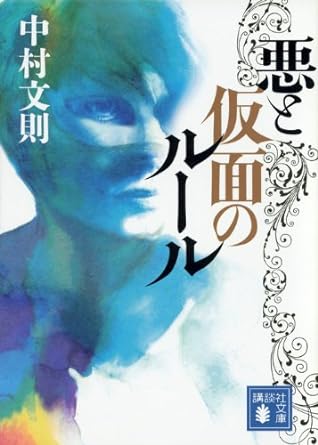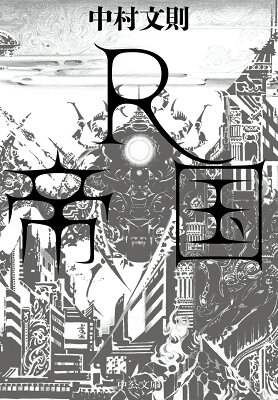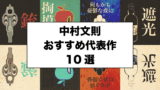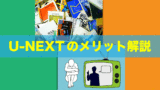中村文則の小説『悪と仮面のルール』は、講談社100周年記念で書き下ろされた、著者9作目の作品である。
ウォール・ストリート・ジャーナル紙、2013年ベストミステリー10に選ばれ、世界中で評価されている。
2018年には玉木宏主演で映画化された。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察していく。
作品概要
| 作者 | 中村文則 |
| 発表時期 | 2010年(平成22年) |
| ジャンル | 長編小説 ミステリー小説 |
| ページ数 | 394ページ |
| テーマ | 悪の因と運命 人を殺してはいけない理由 |
| 受賞 | ウォール・ストリート・ジャーナル ベストミステリー10作 |
| 関連 | 2018年に映画化 |
あらすじ
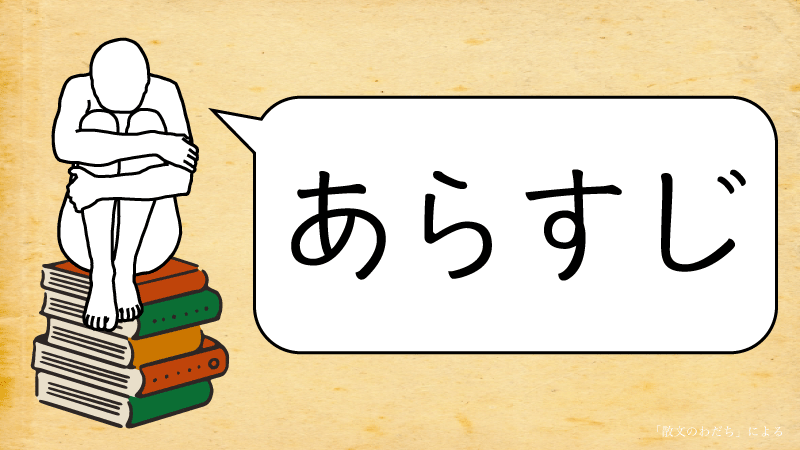
久善家には代々伝わる悪習がある。当主は自分の死が近づくと、世界を不幸にする「邪」の子供を作り出すのだ。
11歳の文宏は、自分が「邪」になるべく生まれた事実を、父・捷三から聞かされる。そして「邪」になるためには、世界を否定したくなる地獄を経験する必要がある。それは久喜家の養子で、文宏が最も大切に想う香織を損なうことだった。
「邪」の風習を断ち切り、愛する香織を守るために、文宏は父・捷三を殺害する。しかし「邪」を断ち切るどころか、まるで父の悪を取り込んだかのように、文宏は日に日に父の人相に酷似する。捷三から性的虐待を受けていた香織は、捷三の面影を持つ文宏に生理的な怯えを抱くようになった。文宏にとってそれは地獄だった。やがて進学と共に二人は疎遠になった。
香織を想うゆえに自分を消滅させ、そして香織の周囲を漂う空気として生きよう。
大人になった文宏は、整形手術で別人の身分を手に入れ、探偵を雇って現在の香織を調べている。すると結婚詐欺師と、テロ組織が香織に接近していることが判明する。背後では久善家の次男・幹彦が手回ししており、彼は亡き父の意志を受け継ぐかのように、香織を損なおうとしていたのだ。
香織を守ること、香織が存在した記憶を守ること。そのために文宏は、久喜家の「邪」の運命に立ち向かい、葛藤し、もがき苦しむ。
オーディブル30日間無料
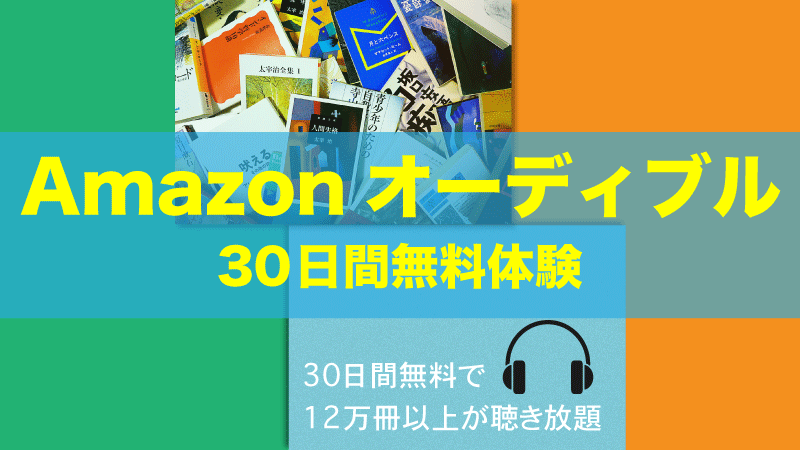
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
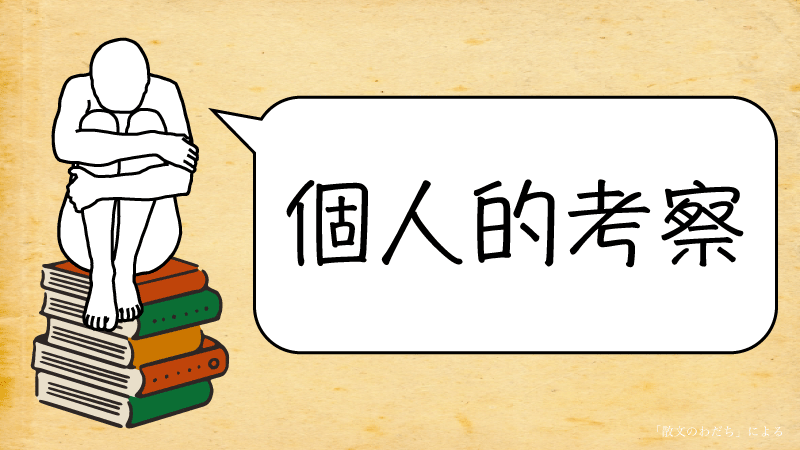
世界で評価されるノワール小説
本作『悪と仮面のルール』は、ノワールとミステリーの要素が組合わさった、著者9作目の小説である。
前作『掏摸』がウォール・ストリート・ジャーナル紙の2012年ベスト10に選出され、世界で注目される作家になった中村文則だが、本作も同紙の2013年ベストミステリー10に選出され話題になった。
本作『悪と仮面のルール』は、過去作品とは一線画し、政治や戦争や、その背後にある利権問題など、より広い世界の物事が描かれている。それは後に1つのジャンルとして『教団X』や『R帝国』に派生していく。そういう意味で本作は、著者の転換期の作品と言える。
作中に記される「幸福とは閉鎖だ」という主張は、もろに『R帝国』の主テーマになっているので、もし本作を気に入った人はぜひ読んでいただきたい。
一方で、初期作『悪意の手記』以降、何度も描かれてきた、なぜ人を殺してはいけないのか、という古典的な文学テーマは健在だ。「このテーマに関しては一旦の区切りをつけた」と著者が述べる通り、本作では集大成とも言える見解が記されている。
他にも『掏摸』で描かれた「悪」「運命」といったテーマも引き継がれている。「悪」の背後には深い愛情が潜んでいるという意味で、物語の本筋は恋愛小説なのだが、それは後に『去年の冬、きみと別れ』や『私の消滅』といったミステリー系の作品へ派生していく。
結局何が言いたいのかというと、本作は転換期の作品であると同時に、総括的な作品ということだ。そのため本作単体では少し理解しづらい部分があるかも知れない。
本記事では、以下3つのポイントに注目して考察する。
・久喜家の「邪」の風習とは
・自分を消滅させた理由
・なぜ人を殺してはいけないのか
・主人公が生に執着した理由
ちなみに本作は、2018年に映画化され、玉木宏、新木優子、吉沢亮など、名だたる俳優がキャストを務め話題になった。
中村文則は、「自分の小説が原作なのに、一観客として惹き込まれ、深い感動に包まれた」と絶賛している。
U-NEXTなら31日間無料トライアルで鑑賞できます。
トライアル期間中に解約すれば料金は一切発生しないので、ぜひ映画『悪と仮面のルール』をチェックしてみてください。
引き継がれる「邪」の系譜
この世界には、時間も空間も越える、そういった幾つもの不可解な因の線が伸びているように思うんだがね。
『悪と仮面のルール/中村文則』
「悪」は時代を超えて因で結ばれている、というのが本作の世界観である。
分かりやすい例として、日中戦争で村を襲撃した兵隊の子孫が、時代を経た現代で、襲撃された村人の子孫を交通事故で殺してしまう、という逸話が語られる。虐げる者の子孫は虐げる者に、虐げられる者の子孫は虐げられる者に。
つまり、人間の無意識下に取り込まれた悪は、因のように連鎖するということだ。
この因で結ばれた悪の連鎖を、風習として故意に実践しているのが久喜家である。
久喜家の「邪」の風習とは
久喜家の先祖の当主は、自分の寿命を意識した頃に、こんな傲慢な考えを抱いた。
自分の人生が終わるのに、この世界は終わらない。彼はそのことが許せなかった。
『悪と仮面のルール』
自分が死ぬのなら世界も終わるべきだ。そこで彼が思いついたのが「邪」の風習だった。
正確には世界を終わらせるのではなく、世界を不幸にする「邪」を生み出す。それは例えば通り魔殺人のような陳腐なものではなく、裏社会を駆け上がって、利権や利益のために戦争を起こし、人間が大量に死ぬのを楽しむ、そんな世界を中枢から揺るがす「邪」だ。久喜家の先祖は、世界が不幸になる余興を見て、死への恐怖を紛らわしてきた。
主人公の文宏は「邪」になるために、父・捷三が年老いてから作った子供だ。
「邪」に育て上げるには、少年時代に理不尽な暴力や飢えを与え、「この世界を否定したくなる地獄」を見せる必要がある。するとその子供は、世界を恨み、全ての幸福を破壊し、不幸をばら撒く「邪」へと成長する。
11歳の頃に文宏は、自分が「邪」になる事実を父に聞かされ、14歳になったら地獄を見せると告げられる。その地獄には、久喜家の養子で、文宏が最も大切に想う、香織が関係していた。具体的な内容は分からないが、おそらく最も大切な存在である香織を損なうことで、文宏に世界を否定したくなる暗い衝動を植え付けようとしていたのだろう。
もちろんこんな風習は小説上のフィクションに過ぎないが、権力者の「悪」は因のように子供に引き継がれ、それは幼少時代からの教育によるところが大きい、ということを寓話的に描いているのかも知れない。
断ち切れない「邪」の運命
文宏は「邪」の系譜を断ち切り、大切な香織を守るために、14歳になる前に父を殺害するが、そこで矛盾が生じる。
「邪」の系譜を断ち切るための殺人によって、彼は「邪」の素質を開花させてしまうのだ。
人間を殺した人間は百パーセントの善を手に入れることはできないが、百パーセントの悪であるのなら手に入れることができる。それがお前の生きる道だ。
『悪と仮面のルール/中村文則』
殺人を犯した以上、文宏は二度と純粋な幸福を味わえなくなった。幸福に遭遇しても、人を殺した事実がついて回る。その苦しみから逃れるためには、100パーセントの悪、つまり「邪」になる以外に道は残されていない。
父を殺さなければ「邪」になってしまう。父を殺せば「邪」の道以外は閉ざされる。文宏はそういう不条理な運命を背負っていたのだ。
お前は『邪』になる。お前は『邪』を避けようとして『邪』となる。それは変更されない。
『悪と仮面のルール/中村文則』
父は死に際に、「お前は殺人によって私の悪を取り込むことになる」と言い残した。その言葉通り、殺人の後味で熱にうなされ、頬がごっそりそげた文宏の顔は、父の顔に酷似していた。
文宏と香織は早熟にも肉体関係を築いていた。ところが、父・捷三から性的虐待を受けていた香織は、捷三の面影を帯びた文宏に生理的な怯えを抱くようになり、二度と心から愛し合えなくなった。それはある意味で、香織を損なうことであり、父の意図しないルートによって、文宏は地獄を経験することになったのだ。
自分を消滅させた理由
大人になった文宏は、なおも香織への執着を止められなかった。しかし『邪』としての彼は、他者を幸福にできない憂鬱な存在に成り果てていた。香織の人生に交われば、彼女を不幸にしてしまう。
自殺未遂の末に文宏が思いついたのは、別の人間になって自分を消滅させることだった。
自分を消滅させ、無となり、人生の傍観者となるためだった。(中略)香織の周囲を漂う空気としての自分を、ぼんやりと想像した。
『悪と仮面のルール/中村文則』
文宏は闇医者の元で整形手術を受け、海外で行方不明になった新谷という男に成り済まし、全くの別人として香織を調査するようになる。
なぜ別人になる必要があったのか。
それは、香織が生理的に嫌悪する「文宏」を捨て、別人として彼女に接近するためではない。事実、文宏(新谷)は探偵を雇い、自らは彼女と対面しない。
文宏が自分を消滅させた本当の理由は、おそらく「邪」としての自分が香織を損なう可能性、を懸念していたからだろう。
お前の無意識は、最大の悪をなしたいと願っている。それは、自分がこの世界の中で最も価値があると思っているものを、完全に破壊することだ。つまり香織だ。
『悪と仮面のルール/中村文則』
お前は全身で焦がれているのだ。その時お前は圧倒的な快楽に震えるだろう。この世界と自分の人生を、徹底的に侮辱した喜びと共に
『悪と仮面のルール/中村文則』
これは父亡き後、父の意思を引き継ぐ次男の幹彦が訴えた台詞だ。
この主張を文宏は否定するが、しかし動揺を隠せていなかった。「邪」の系譜を断ち切れない彼には、香織を損ない、この世界を否定したい欲求が、運命のように無意識下に潜んでいるのだろう。
かつて一度香織と再会した際に、文宏は彼女を襲って自殺することを考えていた。それは未熟な「邪」の蕾ではないか。そういう暗い運命に縛られた自分を殺し、香織を守るために、「文宏」という存在を消滅させる必要があったのかもしれない。
だが表面的な自己消滅は、圧倒的な悪の因の前では無力だった。次男の幹彦が裏で手回しをして香織に接近し、もし文宏が彼女を損なわなければ、幹彦が損なうつもりなのだ。
いくら自分を消滅させようが、久喜家の「邪」はついて回り、香織を損なう運命へ文宏を押し流していく。
ちなみに自己消滅というテーマは、後にミステリー系の作品『私の消滅』で描かれるので、ぜひそちらもチェックしていただきたい。
なぜ人を殺してはいけないのか
ここで一旦、物語の本筋から外れて、「なぜ人を殺してはいけないのか」というテーマに触れようと思う。
人殺しがいけない理由で真っ先に思いつくのは倫理問題である。殺人は倫理に反するから。
けれども倫理は曖昧なもので、戦争のように大義名分さえあれば殺人は肯定される。それは初期作『悪意の手記』でも言及されていた。
次に思いつくのは「罰」の概念である。神に、法律に、世間に裁かれるから、人を殺してはいけない。ともすれば裁く者が存在しなければ、人間は躊躇なく殺人を犯すだろうか?
このように判然としない命題に対して、本作では「生物の本能に逆らうから」という見解が記されている。
あらゆる生物は同種を殺さないよう、有史以前から活動している。それは本能や無意識のレベルで規定されているのかもしれない。というか、生物は本能的に種を繁栄させる欲求(つまり性欲)を持っているため、それに逆らう同種殺しは、いわば想定外なのだろう。
ところが人間には、理性を超えた感情がある。だから種を繁栄させるための性欲が原因で、種の繁栄に逆らう殺人を犯すような異常事態が発生したりする。
殺人を犯せば、生物の本能に逆らうのだから、誤作動を起こす。実際に文宏は、悪夢にうなされたり、幻覚が見えた。
誤作動を起こした人間は普通ではいられない。
人間を殺した人間は、これから、全ての温かなもの、美しきものを、真っ白な感情で受け入れることができなくなる。(中略)命の喜びを感じた時、しかし自分はその命を損なったという事実に苦しむだろう。
『悪と仮面のルール/中村文則』
生物の本能に逆らって人を殺せば、その人間は誤作動を起こし、精神が歪み、二度と幸福を味わえなくなる。
作中では、こういった生物学的な理論で、人を殺してはいけない理由を説明している。
もちろん裁判では、誤作動どころか、ヘラヘラ笑っている殺人犯もいるが、そういう人間は圧倒的に弱く、自分が同種を殺した誤作動に耐えられず、無意識のうちに自分を洗脳して平気だと思い込んでいるだけだ、と作中に記される。
本作でこのテーマを取り上げた理由は、単なる古典的なテーマの深掘りではない。世界には望まずに誤作動を起こす人間が山のようにいる、という問題が背後に描かれているのだ。
戦争には必ず国家の利権が絡んでいるが、実際に戦場で人を殺すのは市民だ。ベトナム戦争やイラク戦争では、多くの帰還兵が精神疾患になった。同種を殺したことによる誤作動である。
そんな風に望まずに誤作動を起こす、気の毒な人間がいるからこそ、「なぜ人を殺してはいけないのか」というテーマを考えることが重要である、と著者はあとがきに記している。
そして本作の主人公・文宏もまた、逃れようのない運命によって、望まずに誤作動を起こした人間のひとりである。そういう人間は、どんな方法で克服を試みるのだろうか。
自殺/生きるという選択肢
「邪」を断ち切る手段、生物的な誤作動を克服する方法、それら全てを叶えるのが自殺だ。
物語にはテロ組織「JL」が大きく関与する。「JL」に属す伊藤は、久喜家の分家で、文宏と同じ「邪」に育てられた1人だ。少年時代に理不尽な暴力と飢えを与えらた結果、未成熟とはいえ一応は「邪」の役割通り、幸福を破壊し、世界を否定するためにテロを決行している。
そんな伊藤は、文宏とは対照的な存在として描かれている。
| 文宏 | 伊藤 |
| 本家 | 分家 |
| 地獄を回避した | 地獄を経験した |
| 殺人を犯した | 殺人は犯してない |
| 「邪」を断ち切りたい | 「邪」として生きる |
| 生きたい | 死んでもいい |
いずれにしても「邪」の運命に縛られる二人だが、決定的に異なるのは、伊藤はまだ人を殺していないということだ。
いずれ殺人を犯すつもりの伊藤に対して、文宏は自らの経験上、生物的な誤作動の話を持ち出して、殺人はやめた方がいいと主張する。すると伊藤は自殺をほのめかす。つまり、生きているから誤作動に苦しむのであって、殺人を犯した後に自殺すれば関係ないと言うのだ。
伊藤の言う通り、自殺は全てのしがらみから解放してくれる。殺人の誤作動に苦しむ文宏が、苦痛から解放されるには、完全な悪(邪)になるか、自殺するか、その二択しかない。そして「邪」を断ち切りたいと願うなら、なおさら自殺以外に術はない。
ところが文宏は死を選ばなかった。彼には苦しみながらも生きる理由があった。それは言うまでもなく、香織の存在だ。
あなたがどこかで存在していると思ったから、死のうとした時もあったけど、踏みとどまることができたって。あなたのような人がいたから、こんな世界でも、少しは肯定できたって。
『悪と仮面のルール/中村文則』
「邪」を断ち切るために殺人を犯した文宏は、永久に誤作動に苦しむことになる。ただし完全な悪に染まれば、そんな苦痛さえも消えて無くなる。幸福を破壊し、世界を否定し、倫理や道徳を離れた場所に到達する生き方だ。そのためには最も大切な人間を損なう必要がある。香織を損なうことで世界から浮遊し、完璧な悪の境地で不幸をばら撒き、やがて自分が消滅する時に尋常ではない興奮と快楽に到達する。それは父の捷三や、兄の幹彦が進んだ人生、そして伊藤が進もうとする人生だ。
文宏にとっては、「そうなること」が幸福なのかも知れない。「邪」の系譜から抜け出せない葛藤も、生物的な誤作動も、悪の境地では一切が無関係なのだから。最も大切な存在である香織を損なえば、もう二度と自分も世界も、肯定する必要がなくなる。それはある意味、自殺と同義である。
それでも文宏は生きることを選んだ。香織を損ないたくない一心から。彼女との幸福な記憶を消滅させたくない。香織が存在することで僅でも肯定できた世界を破壊したくない。
人生という長いベクトルの線の上には、少なからずいくつか温もりがあるはずだ、と文宏は考える。彼にとっては、香織と過ごした過去の幸福な日々がそうだった。完全な悪も自殺も、その「温もり」を消滅させる。文宏はその「温もり」を消したくなかった。だから苦しみながら生きることを選んだのだろう。
物語の最後に文宏は、人生をゆっくり見つめ直すために、海外へ旅立つ。その旅に吉岡恭子が着いてきた。彼女とは何度も肉体を重ね、不思議と彼女に対しては心を開きかけていた。
飛行機の窓から入る陽光が恭子の目に映り、その光が自分を照らしたことをいつまでも覚えておこう、と文宏は考える。それもまた、人生という長いベクトルの上に、ほんのひと時でも存在した温もり、僅でも世界を肯定する理由になったのかもしれない。
■関連記事
➡︎中村文則おすすめ代表作10選はこちら
映画『悪と仮面のルール』
本作『悪と仮面のルール』は2018年には映画化され、主演は玉木宏、その他キャストは新木優子、吉沢亮が務め話題になった。
中村文則は、「自分の小説が原作なのに、一観客として惹き込まれ、深い感動に包まれた」と絶賛している。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら