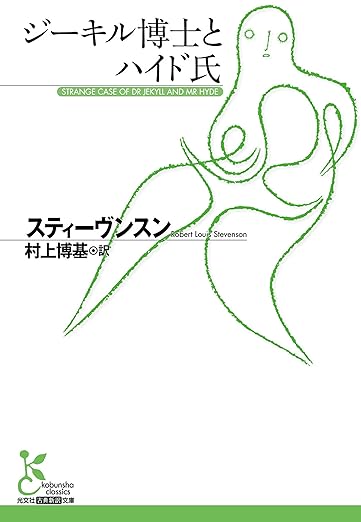スティーブンソンの『ジキル博士とハイド氏』は、代表的な怪奇小説です。
二重人格を題材に、人間の善悪の問題を描いた本作は、キリスト教徒の間でも教訓として取り上げられました。
現在でも、演劇などの多くのエンターテイメント作品でモチーフにされています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | ロバート・スティーブンソン |
| 国 | イギリス |
| 発表 | 1886年 |
| ジャンル | 中編小説 怪奇小説 |
| ページ数 | 130ページ |
| テーマ | 人間の善悪 二重人格 |
あらすじ
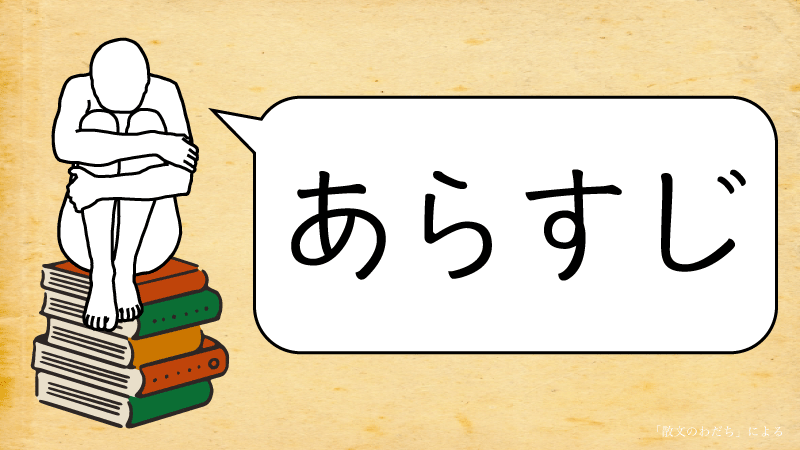
弁護士のアターソンは、散歩中に不気味な建物を見つけます。そして、そこの住人ハイドが転んだ少女を平然と踏みつけた話を耳にします。慰謝料を請求されたハイドが取り出した小切手の署名は、なんとアターソンの友人のジキル博士でした。アターソンは、ハイドがジキルの財産を狙って恐喝しているのではないかと危惧し、ハイドを捜し出す事を決めました。
1年間が過ぎたある夜、ハイドが老紳士をステッキで撲殺する様子が目撃されます。アターソンが再びジキルを訪ねると、ジキルはハイドとの関係を完全に断ったと言います。ところが不思議なことに、ジキルとハイドの筆跡が類似している謎が浮上します。それから数ヶ月後、突然ジキルは訪問者を拒むようになりました。不審に思ったアターソンは、無理やりドアをこじ開けてジキルの部屋へ入ります。するとそこにはハイドの死体があったのでした。
この不可思議な事件の真相は、ジキルの手紙によって解明されます。表向きは善良な紳士であるジキルは、昔から自分の二面性に苦しんでいました。自分の中の欲望旺盛な醜悪な部分を隠しながら、二重人生活を送ってきたのです。そのため、彼は科学実験によって、悪の側面のみを切り離して別人格を出現させる薬品を発明します。つまり、数々の悪事を働いてきたハイドは、ジキルの別人格だったのでした・・・。
Audible無料トライアルで聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『ジキル博士とハイド氏』を含む12万冊以上の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
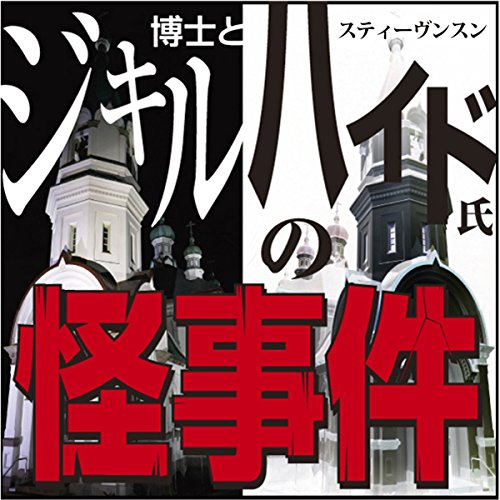
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
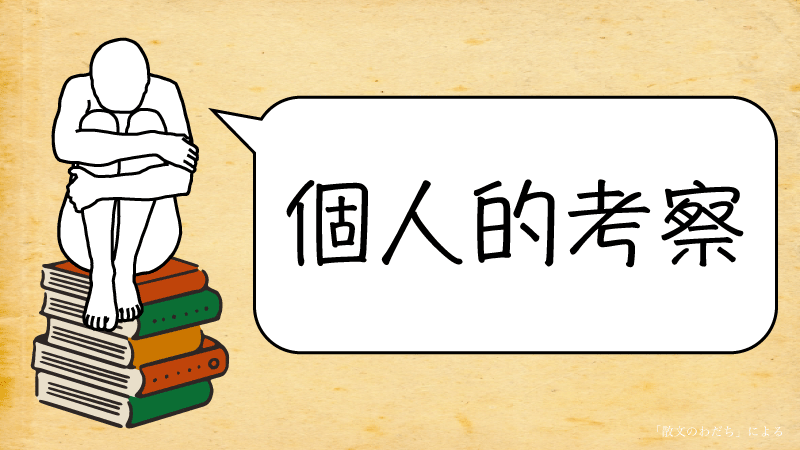
二重人格の題材となった事件
「ジキルとハイド」という言葉を聞けば、二重人格が容易に想起されるほど、我々には親しみのある作品です。
では作者のスティーブンソンはなぜ、このような怪奇的なテーマを文学に取り込んだのか。
その背景には、19世紀ロンドンの荒廃があります。ビクトリア王朝の時代で、産業革命が絶頂期に差し掛かり、ロンドンは人口爆発と公害問題に直面していました。スモッグが充満し、排水で汚染されたテムズ川から暗い霧が立ち込め、当時のロンドンは「霧の街」と呼ばれていました。そんなスラム化が進んだロンドンの治安は最悪レベルでした。「切り裂きジャック」と呼ばれる歴史的事件、あるいは「シャーロックホームズ」の世界観が、霧が立ち込める陰鬱としたロンドンなのは、ちょうどこの時代に当てはまるからです。
そんな中、奇妙な事件が発生します。
エジンバラの市議会議員ウィリアム・ブロディーは、昼間は実業家の顔を持ち、夜間は盗賊として数十件の盗みを働き、スコットランド間接税務局本部の襲撃計画が露見して処刑されました。また同時期、医者のジョン・ハンターは、昼間は医者としての高名な顔を持ち、夜間は墓荒しをして違法に死体の解剖をしていました。
このような、表向きは善良な人間が、裏では想像もよらない悪事を働いている事件を目の当たりにしたスティーブンソンは、一人の人間の中に善悪という別人格が共存する問題に興味を持ち、「ジキルとハイド」という二重人学のテーマを小説に採用したのでした。
ジキルがハイドを生み出した理由
人間とは究極のところ、ひとりひとりが多種多様のたがいに調和しがたい個々独立の住民の集団のごときものに過ぎないものとして把握されるだろう
『ジキル博士とハイド氏/スティーブンソン』
この言葉通り、ジキルは長らく自己の内面の二重性に苦しんでいました。
資産家の家に生まれたジキルは、品行方正、懸命善良な人間であることを求められ、また彼自身もそうあることに誇りを感じていました。その一方で自分の中に享楽性、つまり欲望のまま放蕩したいという思いもありました。
多くの人間はこの欲望にある程度忠実に生きる中、ジキルは羞恥心を抱き、欲望をひた隠して生きてきました。その結果彼は、善良な人間と醜悪な人間という二重の人格の、激しい葛藤に苛まれていたのです。
「解離性同一性障害」とも呼ばれる、内面の二重人格に苦しめられたジキルは、この二つの人格を切り離したいと考えるようになります。彼は研究を重ね、人格を分断させる薬剤を完成させます。
その結果、薬剤を摂取した時には、醜悪な人格であるハイドが肉体を完全に支配するようになったのです。
一つ重要なのは、この薬剤は善悪を分裂させるものではありません。悪のみを切り離すのです。つまり薬剤を摂取しなければ、二重性に苦しむままのジキルで、薬剤を摂取した時にのみ完全な悪になれるのです。つまり、完全な善の人格は存在しないということです。
薬を飲みほした刹那でさえ、わたしはさらに放埒に、さらに凶暴に、悪へ突っ走ろうとする兆しが身内にあるのを意識していた。
『ジキル博士とハイド氏/スティーブンソン』
上記のように、ジキル自身も進んで、ハイドであることに愉悦を感じ、定期的に薬剤で悪の人格を解放して、内面の葛藤を発散するようになったのです。
こういった問題は極端な善悪に限らず、社会との軋轢や、両親の期待や、理想と現実であったり、人間誰しもが抱える自己の二面性に通づる部分があります。社会が要求する人格に抑圧された果てに破滅してしまう、そんな人間社会の問題を暗示した物語とも言えるでしょう。
なぜハイドの人格に侵されたのか
薬剤を使って悪の人格を解放していたジキルは、終いには薬を飲まずとも、ハイドの人格に汚染されるようになります。
その前兆として、ジキルは、一度薬を服用しないことを固く誓ったのですが、耐え切れずに摂取してハイドになろうとします。内面の葛藤を発散する目的だったハイドの人格は、いつしか均衡を崩し優勢になってしまったのです。
多くの聖職者たちは、この物語を、善悪に揺れ動く人間が、悪に屈した結果身を滅ぼすことになった寓話と捉えています。まさしくジキルは薬の服用を繰り返すうちに、善の心を失い、悪の人格に支配され、ハイドこそ本来の姿になってしまったのでしょう。
個人的には、現代におけるドラッグの問題と通じる部分があると思います。精神の解放や強烈な興奮を求めてドラッグを使用した結果、平常時では脳がアドレナリンを分泌できなくなり、依存症に陥ってしまう様です。
わたしは自分を他人とくらべてみた。慈善のために活動している自分と、冷酷に無関心にぶらぶら怠けている他人をくらべてみて、わたしは微笑を禁じ得ないのだった。
『ジキル博士とハイド氏/スティーブンソン』
薬剤でハイドを生み出す前のジキルは、少なからず善良な人間であることにも誇りを感じていました。ところがハイドという悪心の解放を経験して以降、自分が慈善活動をしようが周囲の人間と何も変わらないと感じるようになります。つまり、善良であることに誇りや自尊心を持てなくなったのです。
その結果、彼は悪心でしか自身を満たすことができなくなり、やがて薬物依存症のように、完全にハイドの人格に支配されてしまったのではないでしょうか。
ジキルが自殺を図った理由
間も無く完全にハイドの人格に乗っ取られる間際に、ジキルは薬品によって自殺を図ります。その結果、弁護士のアターソンが部屋に入った時には、ハイドの死体が倒れていました。
作中ではなぜジキルが自殺を図ったのかは明かされていません。
しばしば、ジキルの中に残った最後の善の心が、自らの死をもってハイドの人格を道連れにしようと企んだのではないか、と考察されることがあります。いわば、最終的には悪心よりも善意が優ったという考えです。
しかし個人的には、ジキルの自殺は彼の高慢な虚栄心のためと考えています。
ハイドは殺人で指名手配されていました。仮にその後もハイドが生き続けた場合、正体がジキルであることが明るみになる恐れがあります。無論その頃にはジキルの人格は消滅しているので無関係とも言えるのですが、彼は自分の名声を気にしたのでしょう。ハイドの死体のみこの世に残すことで、ジキルとハイドを完全に無関係な存在に仕立て上げたのだと考えられます。
あるいはジキルは死ぬ前に、自分の失踪後は財産を友人のアターソンに譲渡する遺言を残していました。ともすれば、全ての悪事をハイドに押し付け、ジキル自身は友人に財産を与えたという名声を維持したままこの世を去ることができます。
このように、ジキルは虚栄心によって、死後に自分の名誉が穢されることを防ぐために、自ら命を絶ったのではないかと考えられるのです。
以上の考察はかなり性悪な考えによるものなので、人によっては解釈が分かれると思います。
あなたは最後に優ったのは、善と悪のいずれだと考えますか?
オーディブル30日間無料
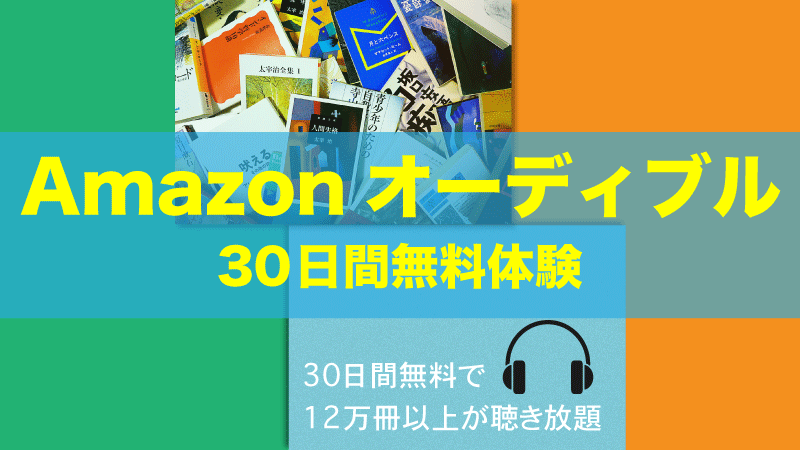
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら