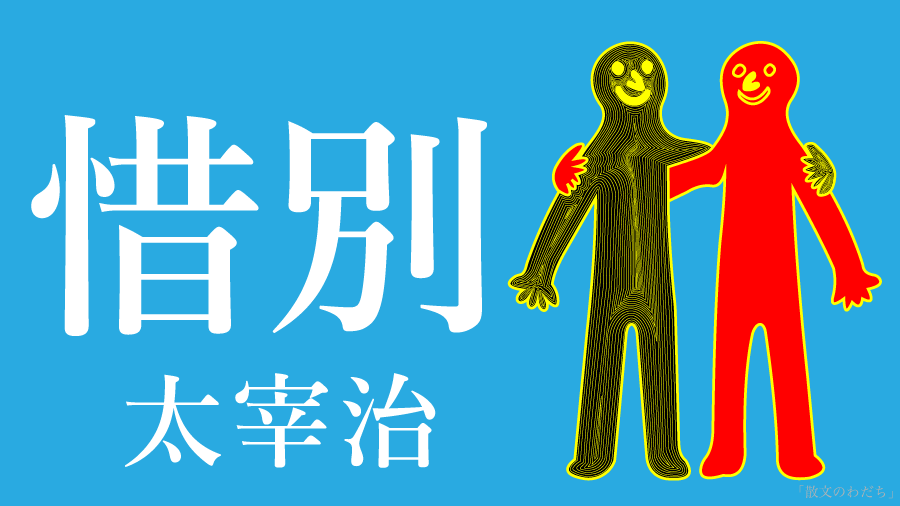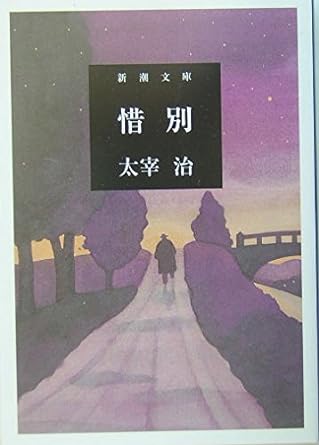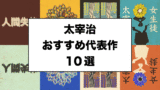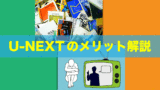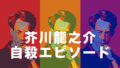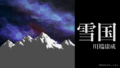太宰治の小説『惜別』は、中国の文豪・魯迅との交流を描いた作品である。
魯迅が日本に留学していた時期に同級生だった主人公の視点で、魯迅が医学から文学に転身し世界的な作家になった経緯が語られる。
また本作は戦時中に国から委託された国策小説という政治的な意図をはらんでいる。
日本人にとって教科書で親しみ深い魯迅とはどんな人物だったのか。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を詳しく考察していく。
目次
作品概要
| 作者 | 太宰治(38歳没) |
| 発表時期 | 1945年(昭和20年) |
| ジャンル | 長編小説 国策小説 |
| ページ数 | 161ページ |
| テーマ | 学生時代の魯迅について 日中の友好 |
あらすじ
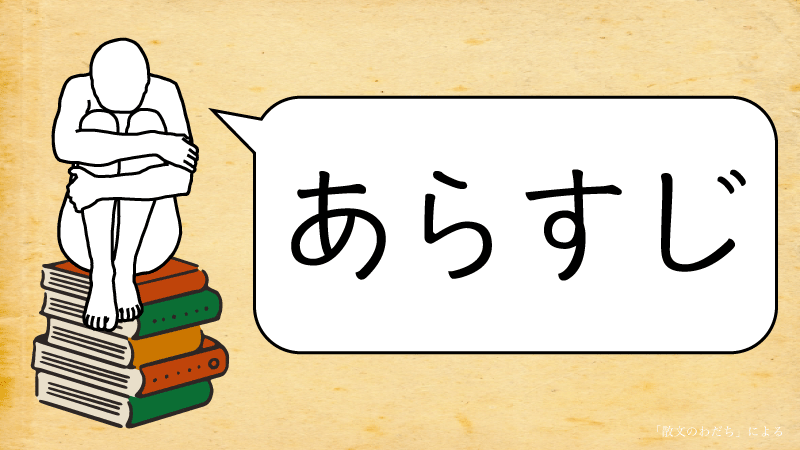
東北に住むある老医師は、学生時代に同級生だった魯迅について記者から取材を受けた。しかし雑誌に掲載された内容は誇張されていたため、老医師は改めて当時の記憶を自分で書き記すことにした。
仙台の医学部に入学した彼は、周さんという中国人留学生と交流を持つ。彼こそのちに中国の文豪・魯迅となる青年だった。
周さんが日本の医学部に留学したきっかけは父の病死だった。当時の中国には、三年霜に打たれたサトウキビや、生涯同棲を遂げたコオロギ、破れた太鼓の皮を飲ませれば病気が治るという迷信が蔓延していた。少年時代の周さんは医師の言いつけを信じたせいで父を失った。この経験から周さんは、祖国の非科学的な医学に疑念を抱き、西洋医学を学ぶために日本へ留学したのだ。
藤野先生は周さんを熱心に教育し、周さんもまた藤野先生を慕っていた。ところが夏休み明けに現れた周さんは医学への情熱を失っていた。夏休みに東京へ行った際に同じ中国の留学生を見てショックを受けたのだ。当時は孫文による革命運動が盛り上がっていた。その考えには周さんも賛同だったが、実際に革命運動に傾倒する学生たちは、単に革命に便乗して踊り騒ぐばかりで、周さんはその現状に落胆したのだ。医学で命を救うより、国民の精神を治療する必要を感じた周さんは、文学の道を志すようになった。
その矢先に「幻燈事件」が発生する。日露戦争でロシアのスパイをした中国人が日本人に処刑される場面において、周りにいる中国人が同胞の処刑を興味深そうに眺めている映像を見せられたのだ。この出来事は、決定的に祖国民の精神を治療する必要性を周さんに感じさせた。そして周さんは文学に励むために祖国へ帰って行ったのだった。
オーディブル30日間無料
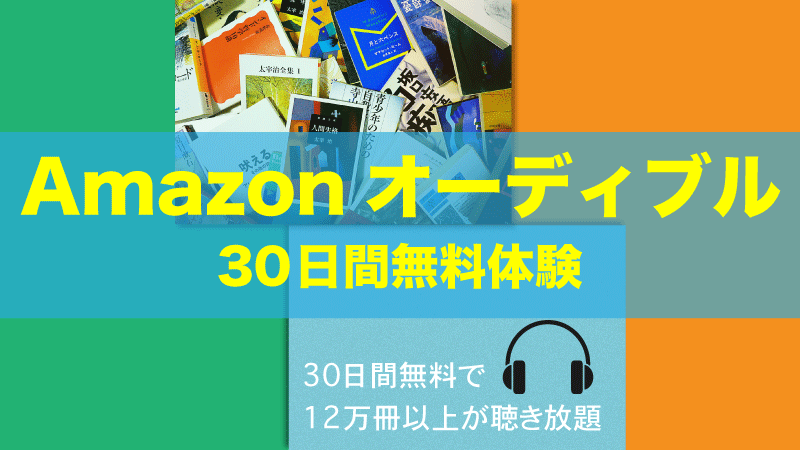
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
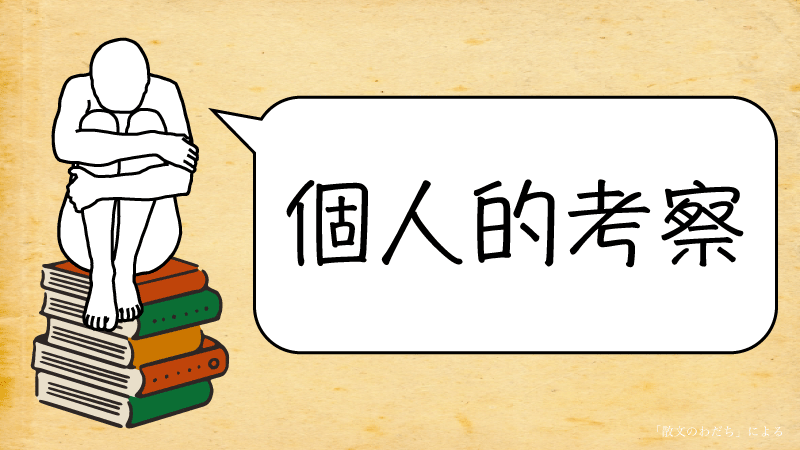
創作背景・国策小説
本作『惜別』は、太平洋戦争末期の1945年1月に執筆された。出版の事情から実際に刊行されたのは終戦間も無くの9月のことである。
出版の事情とは単なる作業上の遅れであり、手配自体は戦中に進められていた。あの悲惨な時期に刊行許可が出たのは、国から委託された国策小説だったからだ。
当時は表現活動が制限されていた。1943年に出版事業令が施行され、出版物が国の統制下に置かれると、多くの文学者が締め出しを食らった。1930年頃から既にプロレタリア文学の弾圧が始まっていたが、太平洋戦争に突入するともはや政治思想にとどまらず、優雅な貴族姉妹の生活を描いた谷崎潤一郎の『細雪』さえ連載を打ち切られた。国民が勝つために我慢する戦時下に贅沢な物語は御法度だったのだ。日本文学の発展が途絶えた不遇な時代である。
このように多くの作家が筆を折られた時期に、太宰は逆に多くの作品を発表した。むしろ太宰の生涯においてこの時期は、特に執筆旺盛な時期だったと言える。実際に彼が残した長編小説の多くは戦時中に執筆された。
■戦時中の太宰の作品
『新ハムレット』
『正義と微笑』
『右大臣実朝』
『津軽』
『雲雀の声』
『新釈諸国噺』
『お伽草子』
『惜別』
太宰は『十五年間』という作品の中で、当時の心境をこう語っている。
私の或る四十枚の小説は発表直後、はじめから終りまで全文削除を命じられた。しかし、私は小説を書く事を、やめなかった。もうこうなったら、最後まで粘って小説を書いて行かなければ、ウソだと思った。それはもう理屈ではなかった。百姓の糞意地である。
『十五年間/太宰治』
太宰は小説を書くために手段を選ばなかった。前述した通り本作『惜別』は、内閣情報局と文学報告会の委託を受けて執筆した、いわゆる国策小説である。そのため作中には一部、太宰の本心とは言い難い過剰な日本賛美が記される。
形式上は戦争協力小説になるので、戦後の評価は批判が多かった。しかし太宰は初版のあとがきで、国から委託がなくともいつか書きたくて構想していた作品だと言及しており、単なる日本賛美の物語にとどまらない。むしろ国策小説の裏をついて独自の政治思想を展開し、「日本人の愛国心は無邪気過ぎる」など、わりと辛辣な文章が記される。
国策小説だからといって毛嫌いするのは早い。確かに国の意図としては、中国植民地化のための偽善的な日中和平を描かせたかった。しかし太宰はそれを利用して、日中が本当の意味で協力する真の和平を描いたのだ。
実際に太宰は次のような発言をしている。
「中国の人を賤しめず、軽妙に煽てる事もせず、独立親和の態度で臨んだ。日支(日中)全面和平に効力を与えたい。」
以上が『惜別』のやや複雑な創作背景である。
次章では中国の作家・魯迅について詳しく説明しようと思う。
中国の作家・魯迅について
中国の近代文学の開祖である魯迅は、前国家・中華民国の時代に活躍した作家である。
『阿Q正伝』『狂人日記』『故郷』などの代表作がある。日本では『故郷』が中学校の全ての国語の教科書に掲載されているので非常に親しみ深い。
魯迅が日本で親しまれる理由は、『惜別』で描かれる通り、日本に留学して医学を学んだ経験があるからだ。そして留学時代に彼が慕った藤野先生との交流は、『藤野先生』というそのままのタイトルで小説化され、日中双方の教科書に掲載されている。
こうした背景から日本では魯迅研究が多くなされていた。その1つの『魯迅伝』を読んだのがきっかけで太宰は『惜別』を書くに至った。
自分と同じように近代知識人の孤独を抱えていること、自分の故郷に近い東北地方に留学していたことなど、太宰にとって親近感を持つ面が多かったのかもしれない。
1年にわたる取材を経て『惜別』を完成させたのだが、その内容は魯迅と同級生だった架空の老人を主人公にした独自の物語である。主人公は実在しないのであくまでフィクションだ。作中で語られる二人の会話や、魯迅が言うはずもない妙な日本賛美は太宰の創作である。
とわいえ当時の時代背景や、魯迅が日本に留学したきっかけ、医学から文学に転身した事件などは、事実に則って描かれているので、伝記としての価値も十分にある。
魯迅が日本に留学したきっかけは、祖国の迷信じみた漢医学へのアンチテーゼだった。あらすじで記した通り当時の中国には、三年霜に打たれたサトウキビ、生涯同棲を遂げたコオロギ、破れた太鼓の皮を飲ませれば病気が治るという非科学的な医学が蔓延していた。
魯迅は『薬』という作品で、人血に浸した饅頭を食えばどんな病気も完治すると信じた両親が肺病の息子をあえなく失う物語を描いた。これはホラーやグロの創作ではなく当時の中国に実在した風習だ。こうした非科学的な風習のせいで魯迅は実際に父親を失った。その経験から魯迅は西洋医学を志すに至ったのだ。
しかし父の死によって貧困になった魯迅には、西洋に留学する余裕がなかった。もっと近場で西洋医学を学ぶには日本が最適だった。日本は明治維新で真っ先に欧化を実現させた国だったのだ。それに当時は日清戦争の直後で、日本は積極的に中国人留学生を受け入れていた。
こうして日本で西洋医学を学び始めた魯迅だったが、1年ほどで文学に転身する。医学で自国民の命を救うよりも、文学で自国民の精神を救う必要性を感じたのだ。その決定的な原因となったのが「幻燈事件」である。
「幻燈事件」については、次章にて当時の時代背景を交えて解説していく。
「幻燈事件」について
魯迅が日本に留学した1904年、中国では辛亥革命の空気が高まっていた。
辛亥革命とは孫文の思想を中心に、前国家・清を打倒し、中華民国を樹立した革命のことだ。
清は君主制の国家で、1人のリーダーが実質支配していた。この独裁体制を打破し、新たに人民主体の共和制を採用したのが中華民国だ。
革命が成功したのは1912年のことだが、魯迅が日本に留学していた時期には既に革命の予兆が表れていた。とりわけ魯迅のように近代化を望む留学生たちの間では革命運動が盛り上がっていた。
けれども魯迅は、夏季休暇中に東京を訪れ、同じ留学仲間を見て愕然とした。確かに彼らは革命運動に盛り上がっていたが、その内容は奇怪なダンスを踊るという滑稽なものだった。彼らの運動は革命を目的とするものではなく、革命に便乗して自分に酔うためのものだった。そんな彼らの姿を見た魯迅は、医学より文学で彼らの精神を治療する必要性を感じた。
代表作『阿Q正伝』では、無知無学な阿Qという男が革命に便乗して、意味もわからず革命を叫びながら村中を駆け回る。その結果彼は本当に革命軍と間違われ、警察に逮捕されて処刑される。流行に便乗するだけの無知無学な人間がいかに悲惨な末路を迎えるかを、当時の留学生の姿と重ねて皮肉的に描いたのだろう。
『阿Q正伝』には続きがある。阿Qの処刑を見物するために集まった群衆は、阿Qが射殺される様子を見て、首斬りの方が見応えがあるのにと不平を漏らすのだ。
これは魯迅が文学を志す要因となった「幻燈事件」が題材になっている。
当時の医学校では講義の中で、幻燈機と呼ばれる今でいう映写機のようなもので、日露戦争のニュースを見せていた。その映像には、ロシアのスパイだった中国人が日本人に公開処刑される様子が映っていた。そして処刑を見物する群衆の中には、好奇心に満ちた表情を浮かべる中国人の姿があった。
同じ中国人が処刑されても何も感じず、むしろ面白そうに見物している。そんな腐り切った自国民の精神に魯迅は失望した。
あのことがあって以来、私は、医学などは肝要でない、と考えるようになった。愚弱な国民は、たとえ体格がよく、どんなに頑強であっても、せいぜいくだらぬ見せしめの材料と、その見物人となるだけだ。病気したり死んだりする人間がたとい多かろうと、そんなことは不幸とまではいえぬのだ。むしろわれわれの最初に果たすべき任務は、かれらの精神を改造することだ。そして、精神の改造に役立つものといえば、当時の私の考えでは、むろん文芸が第一だった。そこで文芸運動をおこす気になった
(竹内好訳『阿Q正伝・狂人日記』岩波文庫)
既に医学より文学に関心が向いていた魯迅の気持ちは、この「幻燈事件」によって確固たるものになったのだ。
しばらくは日本で出版事業に努めていたが、やがて学業半ばで医学部を退学し、自国に帰って本格的に文芸活動を始めた。
その後、魯迅は自国の因習を風刺した小説を多数発表し、長らく反逆者の汚名を着せられていた。しかし彼が自国を風刺したのは、本当に自国を愛していたからだ。現在では中国近代文学の開祖として、自国のみならず世界中で読み継がれている。
太宰が伝えたかった教訓
ここまで魯迅について詳しく記してきたが、最後に『惜別』を通して太宰が伝えたかったメッセージを解説する。
『惜別』は日中和平をテーマにした作品だ。国策小説であるため、中国を植民地化するための偽善のように聞こえるかも知れないが、しかし太宰は本当に平和を望んでいた。
和を以って貴しと為す、というお言葉もあるが、和というのは、ただ仲よく遊ぶという意味のものでは無い。互いに励まし合って勉強する事、之を和と謂う。
『惜別/太宰治』
これは藤野先生が主人公に対して説いた台詞である。主人公は太宰が創造した人物なので、藤野先生の台詞も太宰の創作になる。つまりここに太宰の思想が表れているわけだ。
聖徳太子が掲げた「和を以って貴しと為す」という言葉は、しばしば日本人の精神性を表す言葉として使われる。その意味は、真の平和とは単に仲良くすることではなく、互いに切磋琢磨し助け合うことを指す。
藤野先生は言う。かつて日本は遣唐使を派遣して中国から多くのことを学んだのだから、その恩返しとして今度は日本が中国に学びを与えるべきであり、それこそが真の和平だと。
今や中国は世界2位の経済大国で、1位のアメリカと熾烈な経済戦争を繰り広げている。そして日本は表面的な外交をつとめ、国民に対しては台湾誘致などで危険を煽って軍事費の増額を強行する。中国は中国で反日感情を煽って、日本の外交に難癖をつける。
「和を以って貴しと為す」という精神性はどこへ行ったのか。
無論、互いに切磋琢磨し助け合う社会なんて夢想かも知れない。しかし夢想すら捨てたら、この世界はどうなってしまうのだろう?
今の我々に最も必要なのは魯迅のような和平の架け橋かも知れない。
■関連記事
➡︎魯迅おすすめ代表作5選を紹介
魯迅の作品を読むならこれ!
今回紹介した魯迅の代表作『阿Q正伝』『藤野先生』『薬』『故郷』などは、下記の作品集で全て読むことができます。
kindle unlimitedなら30日無料で読み放題!
・200万冊以上が読み放題
・小説は4万冊以上が読み放題
・月額980円が30日間無料
・今なら2ヶ月間99円のお得プランあり
映画『人間失格』がおすすめ
『人間失格 太宰治と3人の女たち』は2019年に劇場公開され話題になった。
太宰が「人間失格」を完成させ、愛人の富栄と心中するまでの、怒涛の人生が描かれる。
監督は蜷川実花で、二階堂ふみ・沢尻エリカの大胆な濡れ場が魅力的である。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・アダルト動画見放題(5万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら