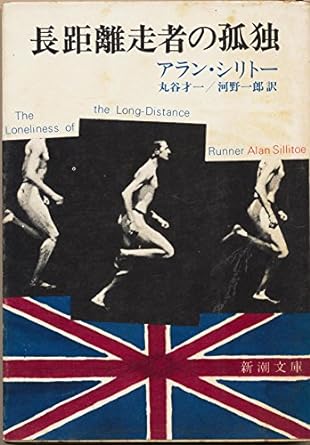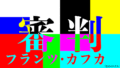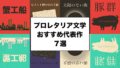アラン・シリトーの小説『長距離走者の孤独』は、戦後の英国文学を代表する作品です。
「怒れる作家」シリトーが、青年期の大人社会への怒りを描いています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
目次
作品概要
| 作者 | アラン・シリトー |
| 国 | イギリス |
| 発表時期 | 1959年 |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 69ページ数 |
| テーマ | 体制の虚偽 オリンピック批判 |
あらすじ
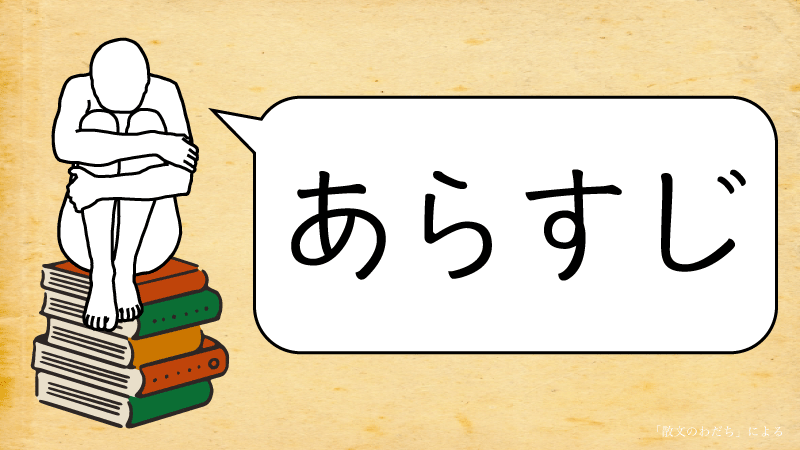
少年院に入れられたスミスは、長距離走者に任命され、大会に向けて訓練している。
そもそもスミスが逮捕された理由は、パン屋の金庫を盗んだことだった。家宅捜査に備えて、札束は雨樋の中に隠していたのだが、不幸にもその日は大雨だった。雨水に押し出された札束は、雨樋から流れ出し、警察にバレてしまう。
長距離走者に任命されたスミスは、少年院の院長の権威にために、大会で優勝することを期待されている。優勝すればそれなりの待遇が用意されている。だがスミスには計画があった。大会ではわざと負けるつもりなのだ。
走りに関して負け知らずのスミスは、皆の歓声の中、ぶっちぎりで1位を駆け抜ける。そして計画通り、ゴール直前でぴたりと立ち止まり、わざと敗北する。
院長の顔に泥を塗ったスミスは、施設退所までの半年間、酷い扱いを受ける。だが彼は、自分のレースには勝ったのだった。
オーディブル30日間無料
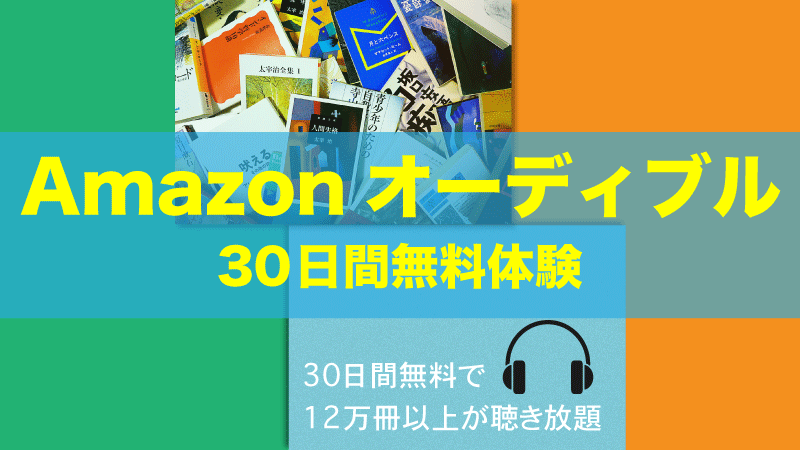
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
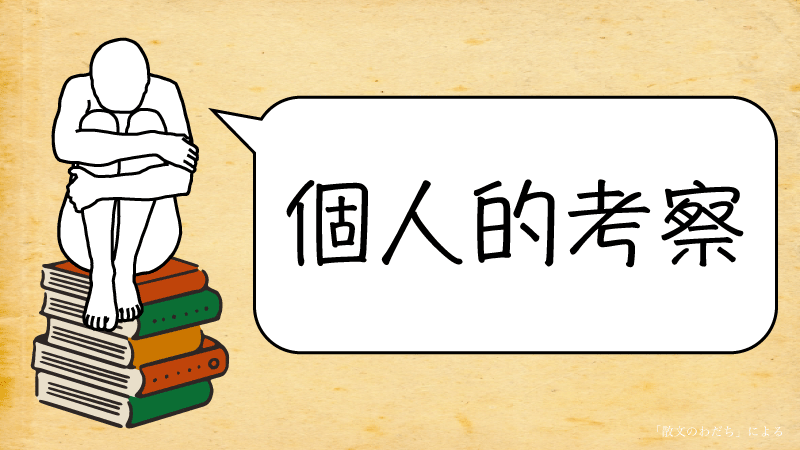
怒れる作家シリトーの人物紹介
アラン・シリトーは、戦後の英国文壇で、新鋭作家として登場した。
「怒れる若者たち」と呼ばれる反体制的な文学一派に数えられる。だが多くの作家はオックスフォード大学出身のインテリであるのに対し、シリトーは14歳で学業を終えると工場で働き出した、根っからの労働者階級である。そのためシリトーだけが権力的な後盾を持たない、特異な作家と言われていた。
14歳で学業を終えると、ノッティンガムの工場地帯で働き出し、第二次世界大戦では英国空軍として戦場に派遣された。そして結核に感染し帰還したシリトーは、療養生活中に読書に目覚め、執筆活動を始める。
デビュー作『土曜の夜と日曜の朝』が好評を得る。さらに翌年に発表された『長距離走者の孤独』も高く評価され、一躍イギリスを代表する作家となった。
労働者階級という出生や、戦争経験者であることから、シリトーの小説は、主に国家に対するプロテストがテーマになっている。
また他の「怒れる若者たち」の作家は、時代と共に主義を失っていくが、シリトーだけは反体制的な怒りを叫び続け、そして今でも世界中の読者に読み継がれている。
以上の背景を踏まえ、物語を考察していく。
スミスが戦う「体制側の虚偽」
パン屋の金庫を盗み、少年院に入れられた主人公スミスは、長距離走者に任命され、大会に向けてトレーニングしている。
そのトレーニングぶりは、一見模範囚のようだが、しかし内心では院長を敵対視している。
スミスが院長を敵対視する理由は、彼が根っからのごろつきで、自分を逮捕した体制側の大人を恨んでいるばかりではない。確かにスミスはごろつきだが、しかし彼は非常に知的で、体制側の虚偽を見抜いている。
▼院長の「誠実」という名の虚偽
院長は非行少年を更生させることを「誠実さ」と呼んでいる。
院長は誠実に非行少年と向き合い、非行少年が誠実に更生することを期待している。その一環として、スミスを長距離走者に任命した。スポーツこそ神聖で、更生に役立つという理論だ。
だがこれらは単なる建前でしかない。
院長がスミスを長距離走者に任命した本当の理由は、競馬的な娯楽と、少年院の権威・名誉のためである。
その証拠に、院長はレースの勝敗に金銭を賭けている。そして他の少年院にレースで勝利することで、自分が受け持つ少年院の優位性、つまり自分の教育こそ優れている、という権威を世間に証明したがっているのだ。
実際に院長はスミスに対し、「きょうはあのカップをわれわれのために取ってきてくれ」と言う。全ては「われわれ」のためなのだ。
こうした体制側の虚偽を見抜くスミスは、決して院長の娯楽や権威のために勝つ気はない。むしろ、わざと試合に負けることで、院長の面目を潰してやろうと考えているのだ。
スミスはなぜ走るのをやめたのか?
前述の通り、スミスはわざと試合に敗北することで、院長の面目を潰そうと企んでいる。仮にも勝利すれば、院長の権威に加担し、利用されたことになる。
言い換えれば、スミスは長距離走とは別に、院長の権威に打ち勝つという、もう1つの戦いに挑んでいたのだ。
だからスミスはゴールの直前で、ぴたりと走るのをやめた。ぶっちぎりの首位を駆け抜け、院長に優勝を確信させたところで、期待を裏切るようにわざと敗北する。それこそ、スミスにとって最大の勝利だったのだ。
このように、スミスは自分の戦いに勝利し、院長は屈辱を味わった。その結果、残り半年の刑期、スミスは院長に酷い仕打ちを受ける。だが自分の戦いに勝利したスミスには、その程度の嫌がらせなど、全く苦にならなかった。
おまけに出所後、院長はスミスを兵隊に送り込もうとしたが、半年間の酷い仕打ちによってスミスは病気になり、出兵を免れた。院長の企みはことごとく失敗に終わり、スミスは二度も自分の戦いに勝利したのだった。
▼スミスの涙の理由
1つ疑問なのは、スミスはゴール直前で立ち止まった時、声をあげて泣き出したことだ。本人は院長の権威に打ち勝った嬉し泣きだと主張しているが、そこには虚勢が感じられる。
スミスは走ることが好きだった。早朝に1人でトレーニングをする時間に最も幸福を感じていた。しかも、自分より早く走れる人間はいないという自負まであった。そんなスミスにとってレースの敗北は、本当にどうでもいい問題だったのだろうか?
本音では、スミスはレースに勝利したかったのだと思う。
もし院長の権威が絡んでいなければ、スミスにとって「大会の優勝」と「自分自身の勝利」が分離することはなかった。だが実際的に院長の権威が絡んでいたため、彼はその権威に打ち勝つために、大会の優勝を手放さなければいけなかったのだ。
ともすれば、ゴール直前で泣き崩れたスミスの涙を、単に嬉し泣きと考えるのは愚かだろう。そして権威によって、選手の純粋な勝利を剥奪する行為の愚かさを考える必要がある。
スポーツとナショナリズム
作者のシリトーは、1972年に「スポーツとナショナリズム」という文章を発表し、オリンピックについて痛烈な批判を主張した。
「ぼくたちはみな、全体主義国家では、スポーツは全体主義体制に個人を訓練し従属させるために利用されていることを知っている。いわゆる民主国家でも、競争的スポーツは同じ目的で同じように利用されるが、そこでは参加者は、第一義的には参加者自身のために競争しているのであって、国家のためではないと思われる。だが彼らはスタジアムや競技場に入場すると、たちまち全体主義体制の人々とまったく同じように、その国の代表になってしまう。」
『Sport and Nationalism/アラン・シリトー』
本来、スポーツとは個人の競走である。それを国家間の権力争いに利用するのは愚かである。だが実際的にオリンピックは、国家の権威を競い合う、ある種の戦争として行われている。事実として、他国との歴史的しがらみが持ち出されたり、疑惑判定があったり、汚職が発覚したり、純粋なスポーツの祭典とは程遠い。
選手は自分の戦い以上に、国家の戦いに服従させられているのだ。
まさに『長距離走者の孤独』で、スミスが強いられた問題である。本来スミスが戦うべきは、自分自身の競技であり、体制側の権威を背負った競技であってはならない。
政府の戦争はおれの戦いじゃない。おれには何の関係もないことなんだ、なぜならおれの気になるのはおれ自身の戦いだけだからだ。
『長距離走者の孤独/シリトー』
このスミスのセリフに、怒れる作家シリトーのメッセージが集約されているように思う。
オーディブル30日間無料
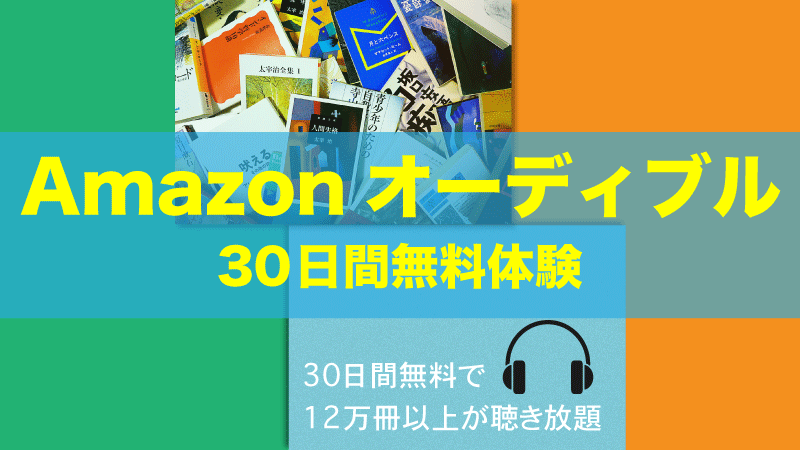
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら