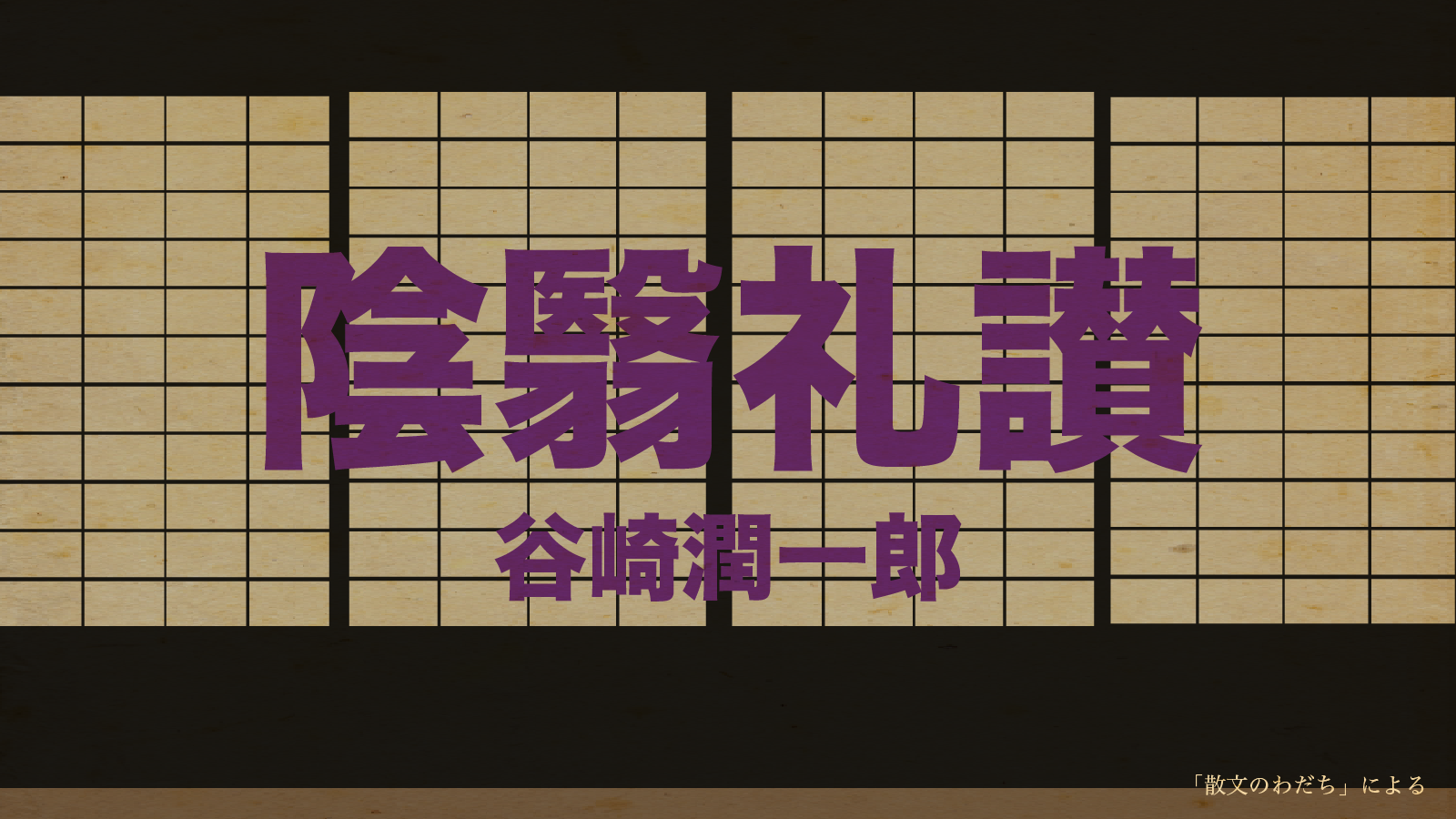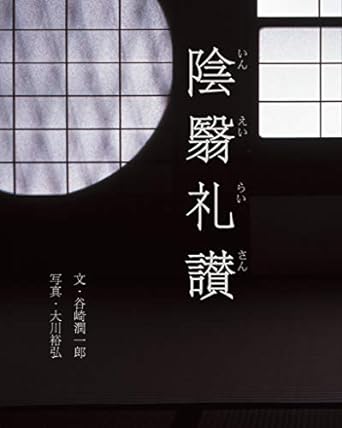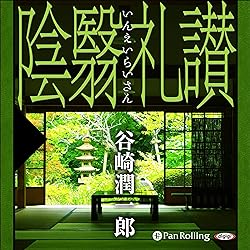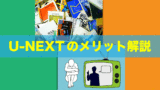谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』は、日本特有の美意識を論じた代表的な随筆です。
近代化によって失われていく、日本人の「陰翳の美」についての批評は、その美的感覚の鋭さから、海外の文化人にも影響を与えたと言われています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 谷崎潤一郎(79歳没) |
| 発表時期 | 1933年(昭和8年) |
| ジャンル | 評論 随筆 |
| ページ数 | 258ページ |
| テーマ | 古典回帰 陰翳の美 文学的価値の再建 |
あらすじ
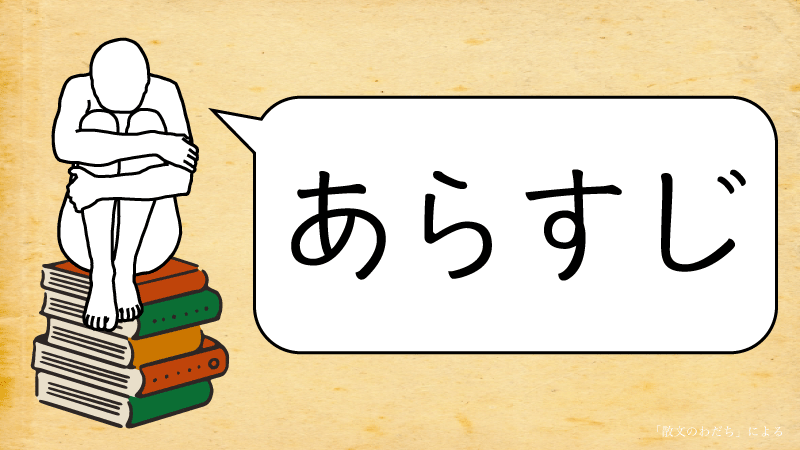
1933年当時の、西洋近代化によって失われていく、日本人の美意識について論じた随筆です。
純日本風の家屋に住むにあたり、近代的な家具設備が、部屋の調和を壊してしまうことに苦慮した、筆者の体験談から始まります。とりわけ、トイレにおける西洋と日本の違いが顕著だと綴られています。日本特有の木造のトイレは、年月で劣化した木目と薄暗い空間が風雅であるのに対し、真っ白なタイルが敷かれた西洋のトイレは、衛生的である故に花鳥風月が失われているというのです。日本人の祖先は、全てのものを詩化し、不潔である場所をも風流に変貌させてきたのでした。
トイレに限らず、西洋では食器でも宝石でもピカピカに研いだものが好まれます。一方で東洋人は、自然に手の油で錆び馴染んだ器に風流を感じます。あるいは西洋人は真っ白な壁紙を好むのに対し、日本人は砂壁のような薄暗い空間を好みます。
これら西洋と日本の違いの端緒は、生活における光との携わり方だと綴られています。西洋のように煉瓦を用いない日本では、屋根を大きくし、庇を深くすることで、横殴りの風を防いできました。その結果、陰の多い暗い部屋での生活を余儀なくされてきたのです。つまり陰の多い環境である故に、日本人は自然と陰翳の中に美を見出してきたのでした。漆器や金蒔絵や仏像や屏風、ひいては能衣装や女性の美すらも、本来、陰翳のある家屋の中で映えるように作られているのです。
また谷崎は、こういった日本人の傾向は、白人と違う、くすんだ陰のある肌に起因しているのではないかと考えています。つまり最終的には、自分の肌と近いものに親しみを覚える故に、日本人は陰に美意識を見出したのではないかということです。
日本人が失いつつある「陰翳の世界」を、文学の領域に少しでも呼び返してみたい、と谷崎は最後に文学論に着地させて筆を置くのでした。
Audibleで『陰翳礼賛』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『陰翳礼賛』を含む谷崎潤一郎の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
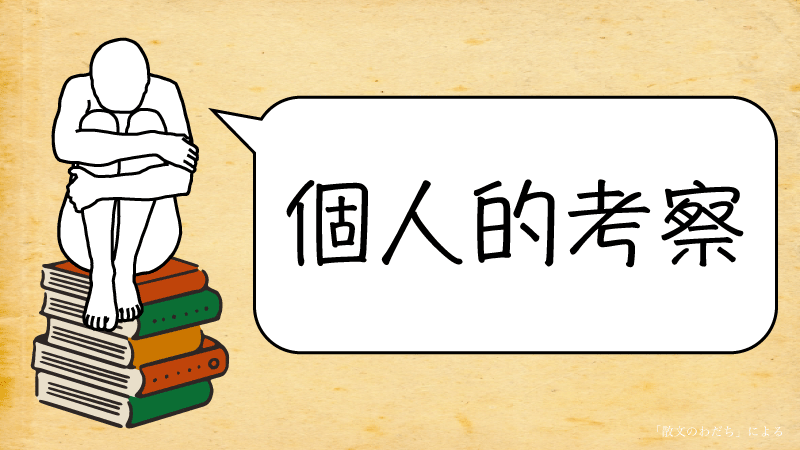
谷崎潤一郎が古典回帰した理由
代表作『痴人の女』を読んだ人ならご存知、谷崎潤一郎と言えば、生活様式に対する美意識が高く、とりわけ西洋趣味を好んだ作家のイメージがあります。
ところが、関東大震災後に関西に移住した谷崎は、古典回帰に目覚めます。震災直後は洋風建築の借家に住んでいましたが、やがて和洋中が混ざった新居を構えます。その家で執筆された『蓼食う虫』には、洋から和に推移していく谷崎の心中が綴られています。
関西に移住した当初は、まるで関西の風土に馴染めなかったようです。エッセイ『阪神見聞録』では、「(関西人は)電車の中で平気で子供に小便をさせる人種である」と批判していますし、電車内で読んでいる新聞を勝手に奪われたことへの憤慨も綴られています。東京人としてのプライドが垣間見え、それ故に関西の風土に順応できていないようです。
一方で谷崎は、昔の東京日本橋の面影を彷彿とさせる関西の街並みを懐かしんでいました。
谷崎が生涯東京に戻らなかったのは、震災後にかつての江戸情緒が失われたためだと言われています。東京と関西の風土を比較する中で、日本から失われていく美意識が顕著になり、それが古典回帰の端緒となったのかもしれません。
あるいは当時の谷崎は、一冊一円の廉価本を毎月出版する「円本」ブームによって、懐を潤していました。これまでは経済的な余裕がなく、西洋趣味という同様のテーマばかりの作品を量産するに留まっていたのが事実です。円本で懐が潤い生活が安定したことで、創作に打ち込む余裕も生まれ、古典回帰という新しいテーマに着手できたのではないかと言われています。
近代化の中で失われる日本人の美意識
明治時代より始まる日本の欧化。西洋事情に通達する文学者たちは、こぞって先進的な思想を取り入れ、日本の近代化に一役買いました。
一方で、過剰に西洋を称賛し、吟味することなく丸々取り入れる風潮に意義を申し立てる文学者もいました。夏目漱石は西洋の個人主義的な思想を謳う一方で、日本人に適した形で取り入れることの重要性を説いていました。
ところが日本は、まるで自国本来の文化を捨て、こぞって欧化の風潮に乗り、その次にはアメリカに追い縋るようになりました。谷崎は作中で、「日本は何でも亜米利加の真似をしたがる国だ」と厳しい批評を綴っています。
最も電燈を贅沢に使っている国はアメリカと日本らしく、お寺にイルミネーションが施され、ベートーヴェンのレコードを大音量で聞かせる月見イベントを、谷崎は近代化の愚行だと指摘しています。お寺、月見、といった日本特有の文化に、西洋の発明品である電燈と、西洋音楽であるベートーヴェンを混ぜ合わせることで、花鳥風月が損なわれていることに憤慨しているのでした。
作中では「日本の美的感覚は陰翳の中に見出されてきた」と繰り返し記されています。ともすれば、上記のような電飾を駆使した月見イベントは本末転倒です。
日本は、独自の美的感覚を手放す代わりに、近代化を手に入れた国だと言えるでしょう。
日本人は古来より、不利になる要素を美的感覚に昇華する性質を持っていると谷崎は考えています。文化や環境の問題から、陰の多い部屋での生活を余儀なくされた故に、陰翳に美学を見出したのはその最もたる例です。
あるいは、西洋人に比べれば醜い肉体である故に、陰を好み、それを隠すような装飾が生み出されたとも記されています。日本人の体型や生活環境に適した装飾が生み出されるのは当然のことです。ところが欧化や欧米化の中で、日本人は自国の得意とする分野を放棄し、他国の主戦場に飛び込んで腕を振るい始めたわけです。
谷崎が評論した時世に留まらず、戦後の高度経済成長期には都市開発が進められ、日本人にとっての原風景は殆ど失われてしまいました。西洋の国々は、自国の魅力や文化的価値を理解し、今でも観光大国として、その国の原風景を留めています。日本のインバウンドは単に経済成長が低迷し、物価が安くなったために爆買い目的に来る人が多く占めていました。
谷崎が評論した問題提起は、決して前世紀に消滅したものではなく、今もなお、日本人が何を愛し、何に美意識を感じていて、経済成長に追い縋るためにそれを本当に手放していいのか、という警笛を鳴らしているように感じます。
我々は今一度、便利という観点だけではなく、美的感覚の観点から、物事の要不要と向き合うべきなのかもしれません。
文芸復興における谷崎の挑戦
本作『陰翳礼讃』が発表された1933年は、文芸復興の年と言われています。
ある文芸雑誌に、川端康成が「時あたかも、文学復興の萌あり」と記しましたが、その「文学」とは、概ね「純文学」のことだと言われています。
純文学の対には大衆文学が存在し、大衆志向の出版物が氾濫する中で、純粋な文学的価値を再建しようという意図があったようです。
とりわけ、谷崎潤一郎は、大衆作家によって文壇が危機に直面しているという言説には同調していませんでした。
大衆作家にパンの道を奪はれて「純文学の危機」などと云ふ音を上げるのは滑稽千高と云ふ外はない。五年や十年不振の期間がつづいたからとて文学が滅びる筈もなく、それで滅びるやうな文学なら滅びるも亦可なりであるが、多分あれは「文壇の危機」の間違ひだったのであろう。
『直木君の歴史小説について/谷崎潤一郎』
大衆文学のせいで文学が消滅することはない、と明言しています。文壇による文芸復興が、どこか啓蒙的になりつつある様子に、谷崎は否定的だったようです。
つまり文芸復興に対して、谷崎は独自のスタンスを貫いていることが分かります。その証拠となるのが『陰翳礼讃』の最後の文章でしょう。
私は、われわれが既に失いつつある陰翳の世界を、せめて文学の領域へでも呼び返してみたい。(中略)一軒ぐらいそう云う家があってもよかろう。まあどう云う工合になるか、試しに電燈を消してみることだ。
『陰翳礼讃/谷崎潤一郎』
谷崎にとっての文芸復興とは、大衆文学よりも広義的な、大衆文化に対するアンチテーゼの要素が含まれています。それは近代化によって普及する大衆の生活様式を指し、日本人の美意識に削ぐわない衛生的な要素に意義を申し立てているようです。
「一軒ぐらいそう云う家があってもよかろう」という文章から分かるように、谷崎はあくまで古典回帰という個人の思想で、文学的価値の再建に携わっています。文壇で盛り上がる文芸復興とは、まるで別の立ち位置なのです。
前述した通り、谷崎は、大衆文学の氾濫が文学を滅ぼすことはありない、それで滅びる文学なら滅びてしまえ、といった主張でした。ともすれば、大衆文学を目の敵にして純文学を啓蒙する文壇よりも、より高尚な位置で、谷崎は芸術的価値を模索していたことが分かります。
ある意味、大衆文学ではなく純文学において、「陰翳の美」が失われ、衛生的になっていく様子を批判的に捉えていたのかもしれません。
谷崎は「純文学の危機」を「文壇の危機」と言い換えて揶揄しています。大衆文学のせいにして廃れていく文壇の滑稽な様を皮肉っているように感じられます。谷崎は小手先の批判などではなく、日本人の美意識問題にまで踏み込むことで、本当の意味でも文芸復興に臨んでいたと言えるかもしれません。
その皮肉と決意によって、本作『陰翳礼讃』が書かれたのではないでしょうか。
■関連記事
➡︎谷崎潤一郎おすすめ10選はこちら
映画『春琴抄』がおすすめ
代表作『春琴抄』は1976年に映画化され、山口百恵と三浦友和のコンビで話題になった。
9歳で失明したお琴と、彼女のわがままに献身的な佐助。そのマゾヒズム的な愛情は、やがて視覚を超越した感覚の世界へ達する・・・・
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら