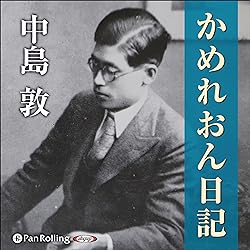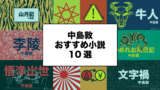中島敦の短編小説『かめれおん日記』は、作者の教員時代の日常が描かれた作品です。
作家としての人生と、教員人生の狭間でジレンマに陥った、中島敦の陰鬱とした心情を読み取ることが出来ます。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 中島敦(33歳没) |
| 発表時期 | 1942年(昭和17年) |
| ジャンル | 短編小説 日記風小説 |
| ページ数 | 112ページ |
| テーマ | 自我と習慣の衝突 存在の懐疑 人生の不安 |
あらすじ
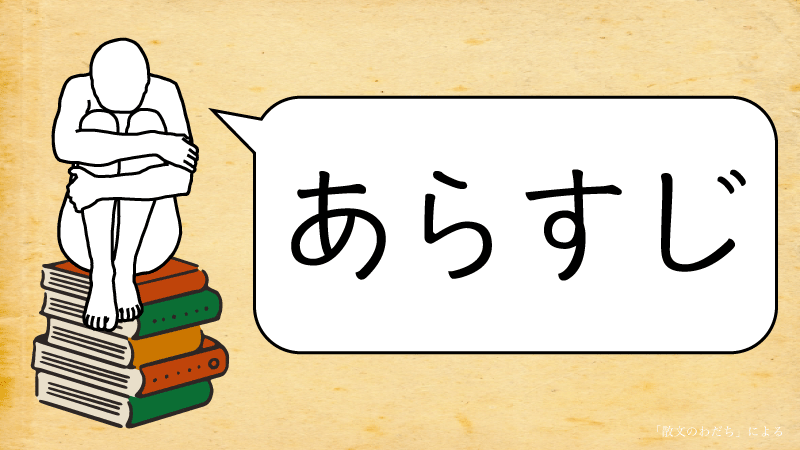
私立女学校で博物の教員を勤める主人公は、職員室に戻る途中に、生徒からカメレオンを貰います。学校で飼育するつもりでしたが、設備が整うまでは主人公が自分のアパートで飼育することになります。
そんな主人公には精神的な蟠りがあります。我欲が強く現実に精力的な同僚を幸福に思う一方で、自分の生き方には疑問を抱いているのです。身を打ち込める仕事を持っていないことが、主人公の憂鬱の最もたる原因でした。習慣や環境に支配されて失われる自我、その絶望的な境遇で、それでも捨てきれないない自意識に辟易しています。
自らの境遇と重なるように、日本の寒さに耐えられないカメレオンは弱っていきます。飼育の難しさを実感した主人公は、カメレオンを動物園に寄贈することにしました。空になった籠に哀愁を感じた主人公は、外国人墓地までやってきます。死者たちの哀しい執着に感傷を抱きながら、主人公は小道を下っていくのでした。
Audibleで中島敦を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『かめれおん日記』を含む中島敦の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽の読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
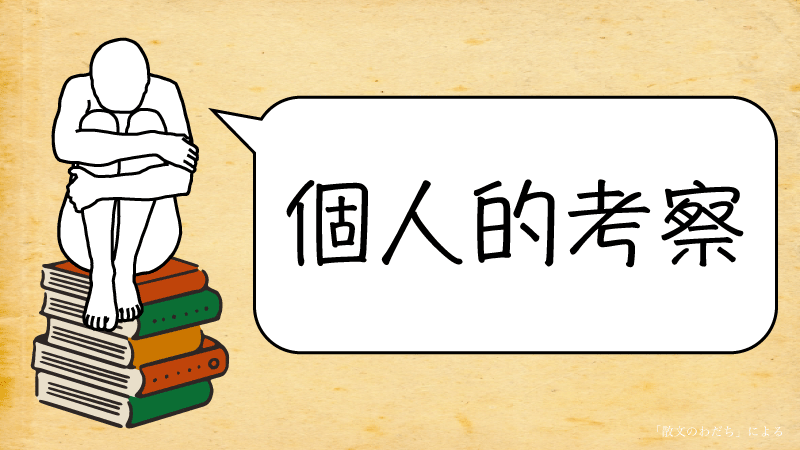
長編小説の挫折と教員生活の苦悩
学生時代から執筆に取り組んでいた中島敦は、東京帝国大学在学中に、『北方行』という長編小説に着手していたと言われています。(諸説あり)ところが、構成や主題や人物設定など、あらゆる面で行き詰まり、執筆を断念してしまいます。
その挫折の経験から、短編小説にシフトチェンジしていくわけですが、中島敦は学生結婚をしているため、家族を養うために定職に就く必要がありました。当時は就職難だったこともあり、なかなか職を見つけられず、最終的には祖父のつてによって、横浜高等女学校の教員に、単身赴任で働き始めます。その教員時代の心情を綴ったのが、本作『かめれおん日記』だったわけです。
その内容はかなり陰鬱としています。存在の懐疑や、人生に対する不安感がひたすら記されているのです。
長編小説の挫折もしかり、短編小説『虎狩』が雑誌のコンクールで選外傑作となり、入賞しなかったことも重なり、小説家として日の目を見ない不安があったでしょう。何より、作中にも綴られる通り、身を打ち込める仕事を持っていないことに対する蟠りが、陰鬱とした心情の最もたる原因でした。
本当は小説家としての人生を歩みたい。されど生計を立てるためには労働が不可欠。その労働さえも、就職難の結果、自分で選んだわけでもない職業でした。何一つ自分の願った通りではない境遇に際して、中島敦は「自分とは何なのか?」「幸福とは何なのか?」といった類の懐疑を持つようになったのでしょう。
この手の、「自我」と「社会」の対立は、永久に個人が抱える問題提起であります。戦前に執筆された中島敦の文学が現在でも全く古臭く感じないのは、我々とて、常に危険にさらされる「我欲」の問題に苦しんでいるからではないでしょうか。
自己の分裂
俺といふものは、俺が考へてゐる程、俺ではない。俺の代りに習慣や環境やが行動してゐるのだ。之に、遺傳とか、人類といふ生物の一般的習性とかいふことを考へると、俺といふ特殊なものはなくなつて了ひさうだ。
『かめれおん日記/中島敦』
エピグラムに『韓非子』の一説、「虫有就者、一身両口、争相噛也、遂相食、因自殺。」が引用されています。
これを咀嚼して現代語訳すると次の通りになります。
「蚘という虫は、ひとつの体にふたつ口を持っており、互いに争い、喰らい合い、最終的には自分の身を亡ぼす」
要するに、自我と社会的な慣習が衝突して、苦しんでいる作者の心情を、この奇妙な虫に比喩していたのだと思います。
それどころか中島敦は、自分の内臓器官を引き合いに出して、それぞれが分裂した個を形成しており、それらが自我と別の意思を持って、互いに衝突する感覚を抱いています。1対1ではなく、複数の衝突なのです。
このように、独立した個が自分の中に存在するために、自分とは一体何者か、自分は本物か、といった自我に対する懐疑が芽生えているわけです。それら分裂した個は、「あやつり手」に支配されており、そのあやつり手の正体は、「習慣や環境」といったものでしょう。
要するに、自分の意思による行動と、習慣や環境の中で無意識に流される行動、それらの対立に疑問を感じているのでしょう。それは前段落で考察した、「執筆に対する渇望」と「望まない教師生活」の狭間に立たされた、中島敦のジレンマの表れだと考えられます。
没我的に仕事に熱中する場合は、このような自己内の分裂や対立は考えずに済むと記されています。ところが主人公(中島敦)のように、望んだ仕事に就いていない人間は、絶えずこの手の葛藤に悩まされるということでしょう。
博識である故に、あらゆる文献や例を用いて、自己の葛藤を分析していますが、結局は、何者にもなれない境遇を嘆き、教師の職に対する嫌気を露呈しているのだと思います。
喘息の薬のために不眠になっている主人公は、寝床の中で多くの思索をしては、そのつまらない考えが、優れたものに発展することを期待していました。その自惚れた精神を眠らせようと努め、その成功によって自分はミイラや化石になったと記されています。小説家として日の目を見ることのない現状に辟易し、いっそ考えることなど放棄して、無意識の習慣に安住してしまう、そう試みても、やはり自我を捨てられない故に苦しんでいたのでしょう。
熱帯地方の生き物であるカメレオンが、日本の寒い気候で段々と弱っていくように、相応しい環境に身を置くことが叶わずに、精神が蝕まれていく中島敦の様子が読み取れます。
寒天質の隔たり
自分は周囲の健康的な人々とは違い、物の感じ方や心の向かい方が違う、と主人公は自負していました。
それはまるで、自分だけが寒天の中に居る感覚だと記されています。現実と自己の間に寒天のような隔たりがあると言うのです。
主人公は、当初はそれを知的装飾と考えて自惚れていました。要するに、自分は頭がいい故に、大衆のように没我的に現実と接触できない、と考えていたのです。ところが勘違いに気づいた主人公は、自分には先天的な能力の欠如があることを認めます。
果たして主人公には何が欠落しているのか。
それは、功利主義だと記されています。自己の幸福を追求する能力が欠如しているのです。これのみを聞くと、あたかも脱利己主義的な、善人のようなニュアンスに感じられますが、実際はそうではありません。臆病の所以、傍観者としてのスタンスから抜け出せないのです。
それから又、ものごと(自分自身をも含めて)の内側に直接はひつて行くことが出來ず、先づ外から、それに對して位置測定を試みる。
『かめれおん日記/中島敦』
物事に身を投げる勇気が不足しているために、外部からあらゆる思索をするだけで、何も実行できない主人公の臆病さが露呈されています。
作中には、無味な概念についてわざと考えることで感覚を鈍くしようと努めた、と記されています。それはある種、必要以上に思案することで、表面上はその物事の正当性を分析しているようですが、実際は行動しなくて済む建前を探しているに過ぎないのでしょう。
つまり、臆病な人間は思弁という寒天質の隔たりを、自分と現実の間に設けて逃避しているのです。
中島敦の文学には、度々「自意識」という主題が登場します。自意識が強いために、世間の目や、失敗した時のことを考えて、実行できない臆病な人間を多くの作品で描いているのです。
『かめれおん日記』に登場する、吉田という教師は、恥じらうことを知らぬ男で、また自分の利益のためであれば必死になる、そんな現実に執着する人間として描かれています。自意識が強く、恥じらいを避けるために、現実との間に寒天質の膜を設ける臆病な主人公とはまるで対照的です。
もはや心を取り換えなければ、現実に直接触れることはできないと主人公は気づいています。それでも心を取り換えようとすれば、本物の自我に抵抗されるようです。要するに、教師生活に安住しようと試みても、作家としての執念をどうしても諦めきれなかったのでしょう。
外国人墓地での感傷
こんな言葉を思出しながら、周圍の墓々を見すと、死者達の哀しい執着が――「願望はあれど希望なき」彼等の吐息が、幾百とも知れぬ墓處の隅々から、白い靄となつて立昇り、さうして立罩めてゐるやうに思はれる。
『かめれおん日記/中島敦』
『かめれおん日記』の結末には、おそらく中島敦が実際に散歩していたであろう、横浜の外国人墓地の描写が描かれます。主人公は死者たちに対して、「願望はあれど希望なき」という言葉を用いて、その悲哀を表現します。
果たしてどんな意味が込められているのでしょうか。
墓地に来た主人公は、去年の今頃も同じ風景を観ていたことに気が付きます。それどころか数日前にも観た気になり、最終的には現在までぶっ続けで同じ風景を見ているような気持になります。自らの生涯の短さを思っては、去年と現在の区別もつかない感覚こそ、死ぬ前の心持に似ているのではないか、と彼は考えています。
まるで荒涼とした生活者である境遇から抜け出せず、区別のつかない日常を次々に消費し、何をも成し遂げないまま死んでいく自らの将来を見定めているような感傷があります。
「願望はあれど希望なき」には、願望を叶えぬまま生涯を終えた死者たちを取り上げ、死ねばいくら願望を持っていても望みは絶たれてしまう、つまり、死んだら終わり、という当たり前の事実を再確認する意味があったのでしょう。
作家と教職のジレンマ留まらず、病弱で短命に終わった中島敦の生涯を思えば、「死者の哀しい執着」という言葉が、一層感傷的に思えてなりません。
中島敦は死ぬ間際まで、「小説を書きたい」と泣き嘆いていた作家なのです。
■関連記事
➡︎中島敦おすすめ小説10選はこちら
オーディブル30日間無料
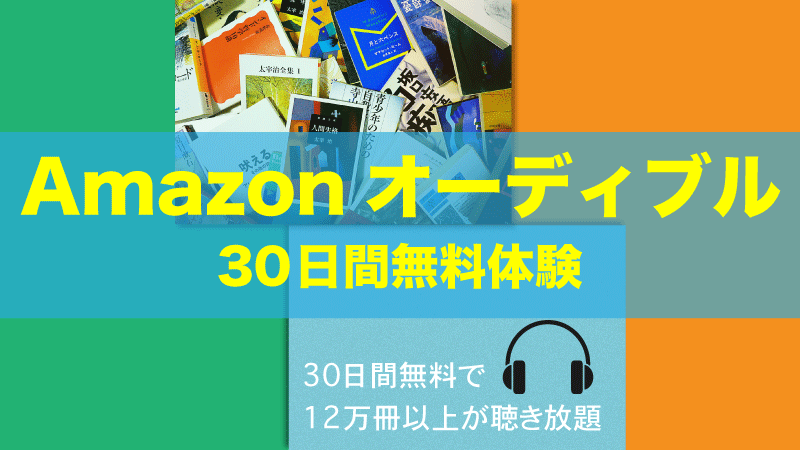
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら