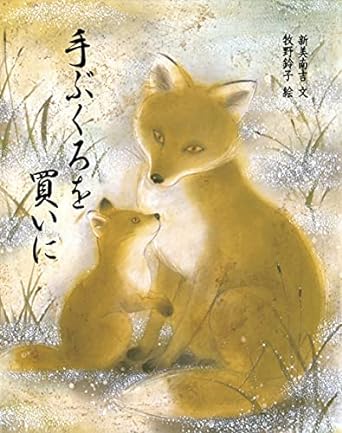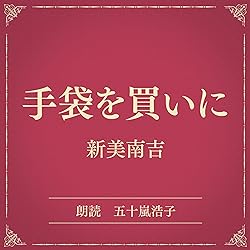新美南吉の童話『手袋を買いに』は、長らく教科書に掲載されていた名著です。
児童文学でありながら、読者の想像を掻き立てる物語は、宮沢賢治同様に大人の心をも揺さぶります。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 新美南吉 |
| 発表時期 | 1943年(昭和18年) |
| ジャンル | 児童文学 童話 |
| ページ数 | 9ページ |
| テーマ | 母性に対する求愛 他者と分かり合う難しさ |
あらすじ
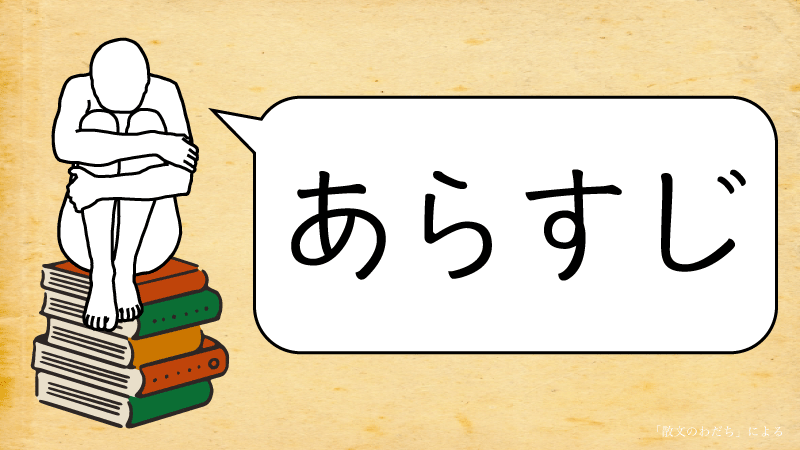
雪の朝、母狐は小狐に手袋を買ってやろうと考えます。ところが、夜になって町に出かける途中で、母狐は怖気付きます。過去に人間から酷い仕打ちを受けた記憶がフラッシュバックしたのです。
そこで母狐は、子狐をひとりで街に行かせることにします。それに際し、小狐の片手を人間の手に変えます。町の帽子屋で、人間の方の手を出して手袋を買い求めるように言い聞かせます。
ところが、帽子屋に到着した小狐は、間違えて狐の方の手を出してしまいます。すると帽子屋は、狐だと気付きましたが、出されたお金が本物だったので手袋を与えました。
帰り道、人間が歌う子守歌を聴いた小狐は、無性に母狐が恋しくなり、急いで森に戻ります。そして、間違った手を出したが無事だったことを母狐に伝えます。小狐は「人間は怖くない」と言います。それを聞いた母狐は「ほんとうに人間はいいものかしら」とつぶやくのでした。
Audible無料トライアルで聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『手袋を買いに』を含む新見南吉の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
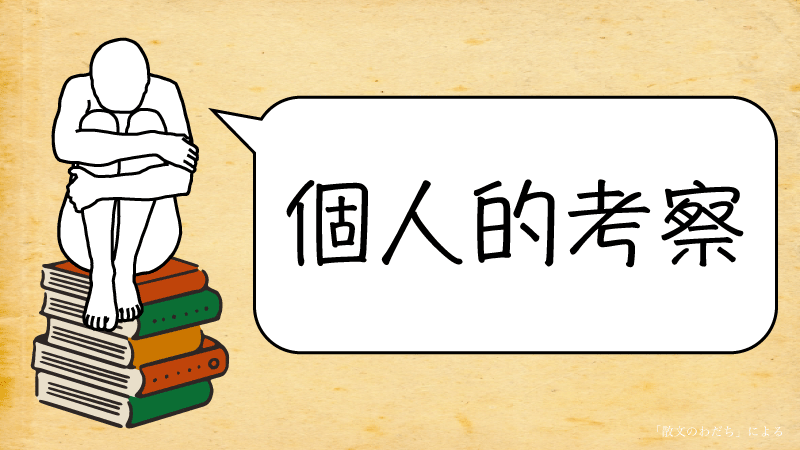
母狐は毒親?(作者の生い立ち紹介)
童話作品は、純文学ではないため、論理性に欠けます。むしろ、読者の想像を掻き立てる不完全さ・隙こそが、童話作品の魅力でしょう。
本作『手袋を買いに』は、隙の多い作品です。とりわけ、母狐の言動が不可解だと議論されがちです。
・なぜ母狐は、小狐を独りで人間の街に行かせたのか
・なぜ母狐は、小狐の片手しか人間の手に変えなかったのか
確かに、そう考えると、母狐は毒親のように見えなくもありません。
しかし、極論を言えば、物語上そうする必要があったからそうした、以外に考える余地はありません。小狐が独りで街に行かなければ物語はつまらないですし、子狐が出す方の手を間違えることに作品の意義があるわけです。
それらを小突くのは、桃太郎はなぜ鬼退治をしたのか、鬼は本当に悪者なのか、という愚問を口走るのと同様です。(芥川龍之介はあえてその愚問に着目し、『桃太郎』を執筆したが・・・)
とは言え、こんなふうにあしらっても退屈なので、作者である新美南吉と母親の関係について掘り下げてみます。
南吉は、幼少の頃に母親を亡くしています。
その後、彼は養子に出され、義母との二人暮らしを強いられます。しかし5ヶ月ほどで寂しさに耐えられず出戻りします。それからは父と再婚相手の継母と異母弟と4人で暮らします。ややこしいのが、南吉の籍のみが母方の「新美」で、他の3人は父方の姓だったみたいで、このことは幼い南吉に衝撃を与えたようです。
こういった複雑な家庭環境で育った南吉の中に、一般的な母親像は欠落しているでしょう。実母を知らない上に、自分だけ母方の姓を名乗る疎外感。彼にとっての母親像とは、本来愛情を注いでくれる存在でありながら、喪失感の象徴であったのかもしれません。
そう考えると、絶対的愛情とは言い難い、母狐の言動は、母性に飢えた南吉が抱く、定まらない母親像の象徴だったのかもしれません。
また、作中では人間の母子の会話を聞いた小狐が、恋しさのあまり急いで帰る場面が描かれます。その小狐の駆け出す速度こそ、欠落した母性を求愛する南吉の想いの強さを表しているように感じます。
他者と分かり合うのは不可能?
新美南吉の作品に共通するテーマは、「他者と分かり合うことの難しさ」でしょう。それはしばしば、動物と人間という異種の対立によって描かれます。
まさに本作『手袋を買いに』は、過去に人間に酷い仕打ちを受けたトラウマで、母狐は人間不信になっています。
あるいは、代表作『ごん狐』では、小狐ごんの懺悔や同情の思いが、上手く人間の兵十に伝わらず、悲劇が起こってしまいます。
とは言え、作者は、他者と分かり合うことは不可能だと断定しているわけではありません。
それが分かる文章を、『嘘』という作品から引用します。
人間といふものは、ふだんどんなに考へ方が違ってゐる、訳のわからないやつでも、最後のぎりぎりのところでは、誰も同じ考へ方なのだ、つまり、人間はその根本のところではみんなよく分りあふのだ、といふことが久助君には分つたのである。
『嘘/新美南吉』
普段は分かり合えない人間も、根本的な部分では共通した認識を持っている。それが新美南吉の考え、ないしは理想だったようです。
確かに『ごん狐』では、小狐ごんと兵十の間に、親を亡くしたという共通点があり、その親和がごんの同情を呼びました。
あるいは、『手袋を買いに』でも、人間の母も、狐の母も、同じように子供に子守唄を歌っている、という内容が記されています。いかなる種族であろうと、母子愛という点では共通していることを訴えているのでしょう。
このように、異なる種族であろうが、分かり合えない他者であろうが、「愛情」という根本的な部分では違わない、と作者は考えていたのだと思います。
あるいは、根本は違わないのに、分かり合えず悲劇を招いてしまう葛藤が、作者にとっての大きなテーマだったのかもしれません。
面白いのが、小狐と帽子屋さんの間にトラブルが生じなかった理由は、その間に金銭取引が交わされていたからです。
帽子屋は、小狐の手を見て、木の葉で買い物をするつもりだと疑い、先に金銭を要求します。そして渡された硬貨が本物であることを知ってから、捕まえたり襲ったりすることなく、手袋を与えました。
金銭や利害は、時にトラブルの元になりますが、逆に分かり合えない他者同士が分かり合うための最善のツールなのかもしれません。
初稿は全く異なる結末だった!?
お母さん狐は、「まあ!」とあきれましたが、「ほんとうに人間はいいものかしら。ほんとうに人間はいいものかしら」とつぶやきました。
『手袋を買いに/新美南吉』
無事に手袋を購入できた小狐が、人間は怖くないと話したところ、母狐が疑心暗鬼に呟いたセリフ。
「ほんとうに人間はいいものかしら」
ところがこれは改稿された文章で、初稿の場合は下記のようになります。
お母さん狐は、「まあ!」とあきれましたが、「ほんとうに人間はいいものかしら。ほんとうに人間はいいものなら、その人間を騙さうとした私は、とんだ悪いことをしたことになるのね。」とつぶやいて神さまのゐられる星の空をすんだ眼で見あげました。
『手袋を買いに(初稿)/新美南吉』
初稿だと、母狐は人間の善良性を認めて、疑っていた自分を恥じるという、いかにも童話らしい結末です。
このことからも分かるように、やはり新美南吉の意識の根本には、他者同士分かり合えるはずだ、という建設的な考えがあったのです。
ではなぜ「ほんとうに人間はいいものかしら」という意味深長な文章に差し替えたのか。
それは決して、180度考えを変換させて、人間を疑いにかかったわけではないと思います。意味深長な文章にすることで、物語に文学的な含みを加え、読者に考える余地を与えたのだと思います。
人間はいいものだ、と断定すれば偽善的な物語になります。人間はいいものではない、と断定すれば作者の主観的な物語になります。「人間はいいものかしら」とすることで、文学的価値が生まれます。なぜなら、人間がいいものか悪いものかを断定することは不可能だからです。
作品から読み取れる個人的な教訓
意味深長な物語であるため、作品からいかなる教訓を読み取るかは読者の自由です。
個人的には、他者認識というものの滑稽さ、を学んだ気がします。
母狐は過去に怖い思いをしたから、人間不信になりました。小狐は無事に手袋を買えたから、人間は怖くないと感じました。つまり、ファーストインプレッションが他者認識にいかに影響を及ぼすかということです。
前述の通り、人間がいいものか悪いものかを断定することは不可能です。突き詰めれば、いい人間もいるし、悪い人間もいる、ということになります。物事は二極化できるほど単純ではないですから、多面的に捉える必要があります。そのため母狐と小狐の主張は両方ともが正解であり、間違いとも言えます。
ただし、母狐と小狐がそれぞれ異なる意見を持ったことは、ある種のきっかけだと思います。なぜなら、母狐は、初めて自分の観念を疑う機会を得たからです。人間は悪いものではないかもしれない、と考える余地が生まれたのです。他者の異なる意見を聞くことは、物事を多面的に捉えるきっかけを与えてくれますし、その人の内面の成長にも繋がります。
そうと知りながらも、意固地になって、他人の意見を封じ、悲惨な状態に陥っている人間がたくさんいます。自分もそういう状況に陥りそうになる瞬間があります。
だからこそ、他者の意見を一旦受け入れて、自問自答することが重要だと感じます。
そういう意味では、「人間はいいものかしら」という母狐の自問自答は、否定的なニュアンスに聞こえますが、実はかなり建設的な思考だと感じます。
ただ一度の印象で極端な他者認識を持ってしまう。それこそが新美南吉の訴える、他者と分かり合えない根本的な原因ではないでしょうか。
オーディブル30日間無料
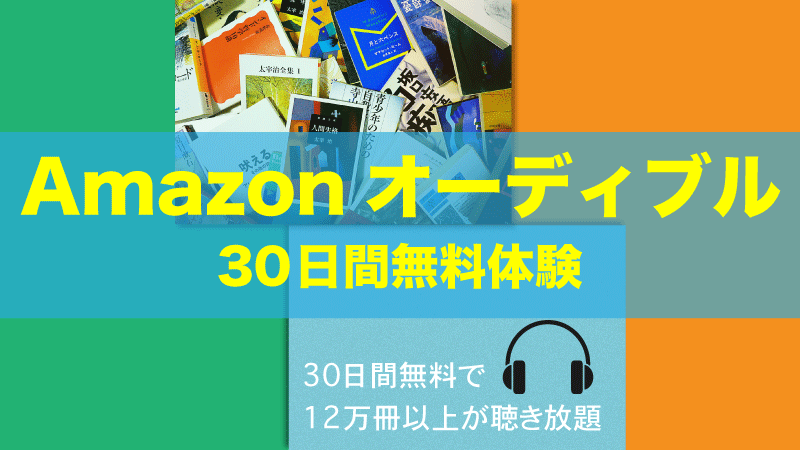
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら