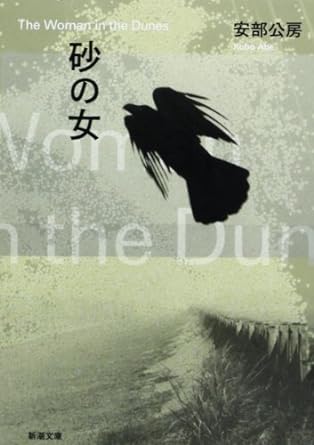阿部公房の小説『砂の女』は、前衛作家として名を知らしめるきっかけになった作品です。
国内のみならず、30か国語以上に翻訳され、近代日本文学の傑作と言われています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 安部公房(68歳没) |
| 発表時期 | 1962年(昭和37年) |
| ジャンル | 長編小説 前衛文学 |
| ページ数 | 288ページ |
| テーマ | 人間の存在意義 抜け出せない日常 自我のしがらみ |
| 受賞 | 読売文学賞 最優秀外国文学賞 |
あらすじ

男は休暇を利用して、新種の昆虫を採集するために砂丘の村にやって来ました。その夜は部落の民家に滞在することになりました。宿泊する家は蟻地獄に似た砂の穴の中にあり、縄梯子でのみ地上と出入りが可能です。家には未亡人の女が1人で住んでおり、砂掻きに追われていました。砂掻きを怠ると、降り積もる砂の重みで家が壊れてしまうようです。
一夜明けると、村人によって縄梯子が取り外されていました。動転した男は這い上がろうとしますが、足が砂に沈み込んで脱出できません。どうやら村人は、砂掻きの人手を欲しており、他所の人間を監禁紛いに連れ込んでいるようでした。脱出できない以上、男は女との同居生活を余儀なくされました。
初め男は砂掻きを放棄して抵抗しましたが、水の配給を絶たれ、やむなく服従することになります。されど様々な手段を試み、一度は地上へ脱出します。しかし逃走中に砂地で溺れ死にそうになり、村人に救出されて再び女の家に連れ戻されます。
絶望と抵抗と女への惑溺を繰り返すうちに、男はあきらめに似た気持で蟻地獄の生活に慣れていきます。女の腹に子も宿ります。妊娠した女は町の病院へ運ばれて行きました。そのときに縄梯子が放置されたままでした。ところが絶交のチャンスであるにもかかわらず、男の心には既に部落への連帯感が芽ばえており、逃げる手立ては翌日にでも考えればいいと居残るのでした。
行方不明から7年後、失踪者の審判が下された男は、死亡が認定されました。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

日常の外にある別の日常
主人公は新種のハンミョウ(昆虫)を求め砂丘の村にやって来ました。一見、人生に目的を持った、趣味で充足した人間かと思いきや、そうではありません。
教師を勤める主人公は、同僚を「灰色の種族」と罵っていました。いわゆる月並みな社会生活に身を据える人間を侮辱していたのです。
とは言え、主人公も彼らと同じ「灰色の種族」に他なりません。されど自分は彼らと違うという高慢な自尊心を持て余していました。
行先も告げずに旅に出たのは、自分は月並みな生活から逸することが出来る豊かな人間であることを、同僚に見せつけたい所以です。あるいは新種のハンミョウを探しているのは、その昆虫に自分の名前が用いられ図鑑に残り続けることを望んだためです。
要するに、平凡な社会生活に辟易し、されど自分は周囲とは違うと驕り高ぶり、その違いを証明する手立てを探していたのです。満たされない承認欲求をぶら下げて、砂丘の村にやって来たのでした。
ところが教師生活の日常と、砂丘での日常は対照的に見えて、実は酷似していました。
- 来る日も来る日も強いられる砂掻き
- その日常を受け入れる住人達
- 逃げないように外された縄梯子
- 歯向かえば断水で制裁
- 脱走すれば捕まえられる
一件、非現実的なサイコホラーの世界の出来事に感じます。しかし、上記の特徴は現実世界の社会生活となんら変わらないのです。
今現在を生きる読者も、こういった社会のしがらみに心当たりがあると思います。とりわけ雇用される立場であればなおさらです。永久に繰り返される平坦な業務。抜け出したいけど抜け出せない。いち抜けしようとすると周囲に引きずり降ろされる。そんな苦悩を知っていると思います。考えてみれば、それは砂丘の村の日常と変わりはしないのです。
脱出に失敗して連れ戻された男は、こんな台詞を口にします。
「納得がいかなかったんだ・・・まあいずれ、人生なんて、納得ずくで行くものじゃないんだろうが・・・しかし、あの生活や、この生活があって、向こうの方が、ちょっぴりましに見えたりする・・・このまま暮らしていって、それで何うなるんだと思うのが、一番たまらないんだ・・・まあ、すこしでも、気をまぎらわせてくれるものの多い方が、なんとなく、いいような気がしてしまうんだ・・・」
『砂の女/安部公房』
日常から抜け出せたと思っても、外には別の日常がある。地上に居れば砂丘の村が羨ましくなり、砂丘の村に居れば地上が羨ましくなる。
結局、男の抵抗は、どこに逃げ込んでも日常のスパイラルからは抜け出せない、という事実を証明したばかりだったのです。
利己的な人間社会のしがらみ
女との生活を送る中で、主人公は砂丘の村の秘密を知ります。
セメントに混ぜる用途として、村は違反的に砂を売って利益をあげていたのです。潮気の多い砂をコンクリートに使えば大事故に繋がりかねません。そのことを主人公が詰った時に、初めて女が凄んだ態度で言いました。
「かまいやしないじゃないですか、そんな、他人のことなんか、どうだって!」
『砂の女/安部公房』
自分が生きていくためには他人に不利益を与えてしまう。されど、その手段を絶てば自分たちの生活が困窮する。かと言って他人(社会)は手を差し伸べてくれるわけでもない。
住人にとっては部落の中だけが日常で、外で何が発生しようと関係ありません。砂掻きをしなければ家が壊れる危機にも勝る、外の世界の危機などは存在しないのです。新聞を取っている村人が殆どいないのはその象徴でしょう。
そもそも村人は主人公を監禁したことに対して罪の意識を感じていません。妙にニコニコしていて、それがかえって不気味なのですが、悪意があるわけではないのです。村の生活を維持するには人手不足で、外部の人間を連れ込むことが必要不可欠でした。あるいは外の世界に見放された村人たちは、違法に砂を売る以外に生計を立てる手段がありません。
その事実を知っているからこそ、引用した女の言い分に主人公はたじろぎ、上手く反論することが出来なかったのでしょう。いずれにも生活があって、こっちを立てればあっちが立たない状況で、いずれかを悪とみなすのは困難です。それを短絡的な大義名分で断罪する群衆を正義と呼べるでしょうか?
我々の生きる現実世界にも、おうおうにしてあり得る問題だと思います。道徳に反する行為を肯定するわけではありませんが、道徳を味方につけた正義が完全無欠な正しさとは言えないように思います。
自我がもたらす弊害
「精神の性病患者」という象徴的な言葉が作中に登場します。
主人公は性病を患ったことがあるらしく、病院では完治したと診断を受けていますが、本人は患っている感覚から抜け出せていません。医師にはノイローゼだと言われています。
その結果、避妊具を付けなければ勃起しなくなり、「精神の性病患者」と妻になじられたことに酷く傷ついているみたいでした。
主人公は、性病は人類の連帯責任と考えていました。ところが妻は自分には責任が無いと主張します。その二人の異なる考えは、鏡を用いた巧みな比喩で表現されています。妻は鏡に映る自分を主役にして、自分の世界に閉じこもる。そして主人公だけが鏡のこちら側に取り残されている、と言うのです。
仮に性病を他人に移したら、という罪悪感が主人公にはあります。されどそれは人類の連帯責任だから仕方ないと考えます。ところが妻のように連帯責任を放棄する連中がいる故に、自分だけが罪の意識を感じてしまうのでしょう。
これは主人公の自我の強さが表れているのだと思います。
あるいは、主人公は「精神的強姦」を嫌っていました。ところが性とは、お互いが精神的強姦を許容することで成り立っているようです。死の危険から遠ざかった人間は、動物本来の発情から解放されました。強姦してでも子孫を残さねば、数秒先には死んでしまうかもしれない、という危機から脱却したのです。その結果、性にはあらゆる制約が伴うようになりました。その制約を理屈っぽく考えすぎると、動物的に欲情できなくなり、主人公のように「精神の性病患者」になってしまうのです。
あまりに自我が強いために、あらゆる制約に理屈っぽくなり、素直に欲情できない主人公の様子が見て取れます。
自分の行為が他者に何をもたらすか。自分の行為を俯瞰的に観察する自分がいる故に、何事にも素直な感情を表せない。これらは自我の強さがもたらす弊害でしょう。
前の段落で、 自分の生存のために他人に不利益を与えてしまう問題について考察しました。
違法な砂の販売。それは確かに他者に不利益を与えるかもしれません。それを過剰に気にする主人公は、鏡のこちら側の、自我が強い存在です。他人の目を気にしない女は、鏡の中の自我から解放された存在です。
結局、自我とは、自分が他者にどう見られているか、を気にする臆病な人間の特性と言えるでしょう。主人公が抜け出したいのは、社会という名の自我なのかもしれません。
過剰な自我によって、日常という蟻地獄から抜け出せない、社会的生物の悲しき境遇を描いているように思います。
希望の変換、生活への順応
あれだけ何度も脱走を試みたにもかかわらず、絶好のチャンスを自ら見送る結末に驚いた人も多いと思います。
失踪から7年が経過し、死亡認定されたことから、砂丘の村に居残る選択をしたことが読み取れます。
この脱走を望んでいた主人公の心情の変化は、一体何を表しているのでしょうか。
作中には次のような文章が記されています。
欠けて困るものなど、何一つありはしない。幻の煉瓦を隙間だらけにつみあげた、幻の塔だ。もっとも、欠けて困るようなものばかりだったら、現実は、うっかり手もふれられない、あぶなっかしいガラス細工になってしまう・・・要するに、日常とは、そんなものなのだ・・・だから誰もが、無意味を承知で、わが家にコンパスの中心をすえるのである。
『砂の女/安部公房』
主人公が砂丘の村に居残った理由は、まさにこの引用に集約されているでしょう。
新聞を強く欲していた主人公は、そのうちに読みたい気持ちが無くなっていきます。新聞は「外の世界の日常」を意味しており、徐々にそれに対して関心が失われていたのです。
女との生活やセックスにも慣れ、砂丘での日常に順応していくのです。欠けて困るものなど無い故に、地上での日常が失われても、砂丘での日常に適応できたのでしょう。
これはある種、前の段落で解説した、本人を苦しめていた「自我(外部から見た自分)」が薄れているとも考えられます。
逃げない選択をした主人公の心情の変化を象徴するのが、溜水装置でした。 溜水装置は当初はカラスを捕らえるための罠でした。捕まえたカラスを伝書鳩代わりにして、僅かでも脱出の望みを託そうとしていたのです。主人公はその罠を「希望」と名付けていました。
ところが、その罠が偶然にも溜水装置の役割を果たしていることに気づき、熱心に研究するようになります。脱出するための「希望」は、居残るための「希望」に転換されたのです。
これは「わが家にコンパスの中心をすえる」ことを意味しているようです。砂丘での女との生活を中心に、その傍らで些細なやりがいを見つける。それは主人公が「灰色の人種」と非難していた月並みな生き方に違いありません。
コンパスの中心を移動させ、「灰色の人種」に抵抗していた主人公。されど最終的には「灰色の人種」としての生き甲斐を見出し、もう日常から脱出しようという気は失せていました。
人間の幸福は、些細なやりがいの中にある、という日常を肯定する結末か。それとも、最終的に人間は灰色の生活を甘んじて受け入れ、その楽に身を据えるものだ、という悲しい結末か。
「罪がなければ、逃げるたのしみもない」と記された冒頭の文章。
砂丘の中の閉塞的な日常に順応し、その結果、自我を失い、罪の意識も失い、逃げる理由も無くなる結末を、的確に言い表しています。
欠けても支障のない社会の部品に成り果てたオートマチックな人間、私にはそのような印象だけが、最後にぽつんと残りました。
永久に繰り返される砂掻き。その傍らで溜水装置に生き甲斐を感じる男。ラジオと手鏡に生き甲斐を感じる女。あなたにとって、その手の幸福は、本当に幸福ですか?
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら