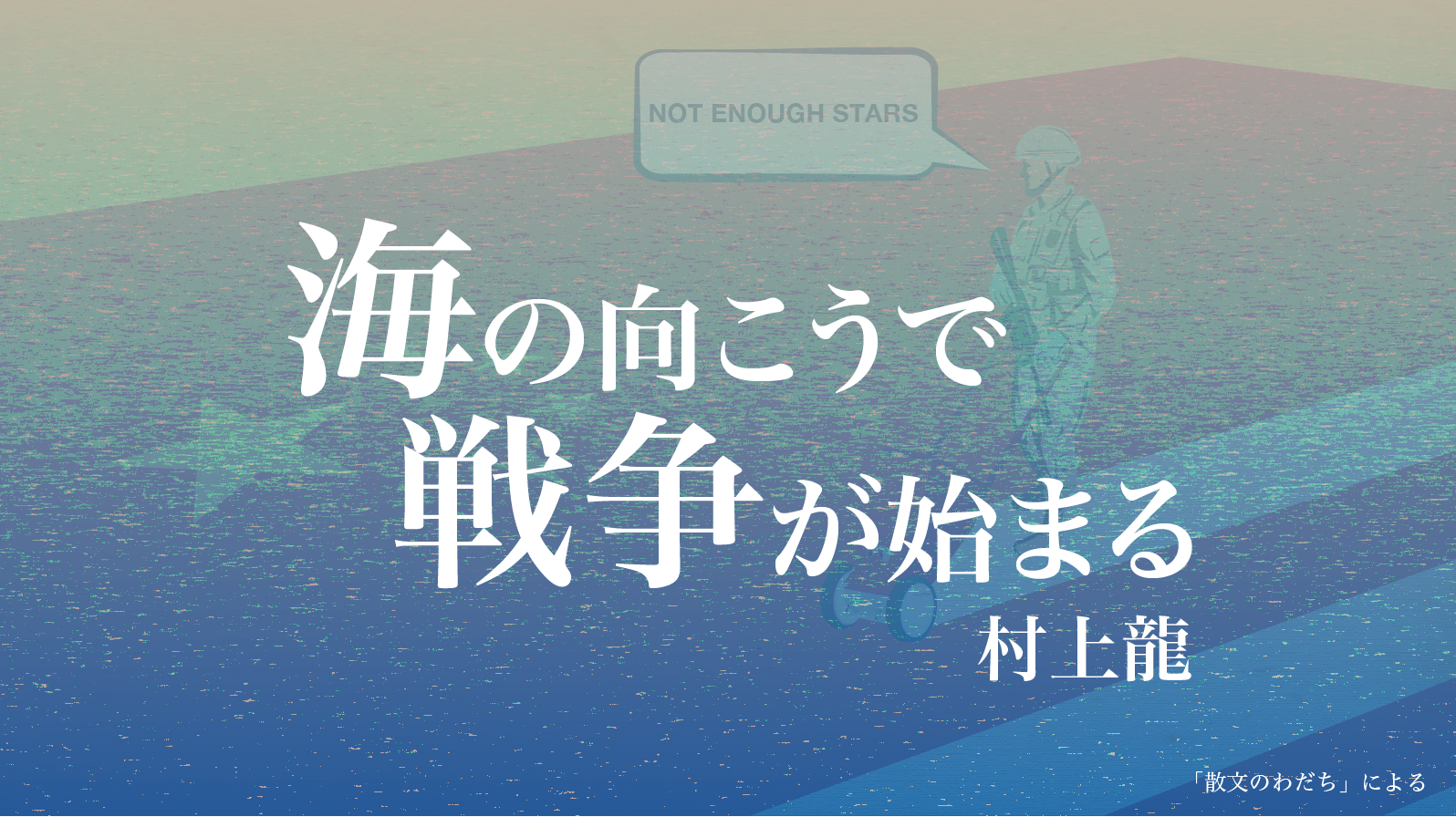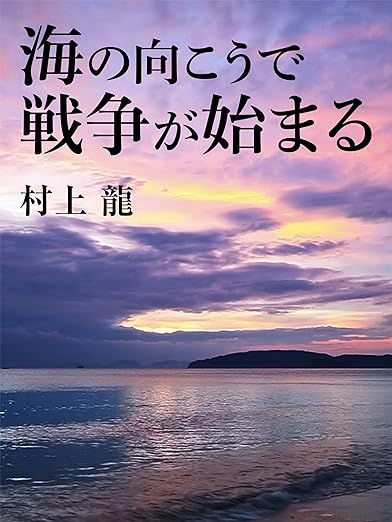『海の向こうで戦争が始まる』は、村上龍の2作目の小説です。
衝撃の芥川賞デビュー作『限りなく透明に近いブルー』より難解な物語になっています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 村上龍 |
| 発表時期 | 1977年(昭和52年) |
| ジャンル | 中編小説 |
| ページ数 | 188ページ |
| テーマ | 見ること 夢想すること 創造と破壊 |
あらすじ

海辺で絵を描く主人公は、フィニーという女性と知り合う。「あなたの目に町が映っている」フィニーのその言葉によって、場面が海の向こうの町に移り変わる。
【scene1】
ゴミ捨て場いる3人の少年は、交尾中のメス犬を角材で殴り殺す。動転したオス犬は少年に襲いかかる。負傷した少年は、オス犬も殺せばよかったと憎悪が芽生えるのだった。
【scene2】
ある家族がサーカスを観に行く。だが祖父が会場の外に行ったきり帰って来なくなる。家族は祖父を探しに行くが、忘れ物に気付き妻だけ会場に戻る。運悪くそこで酔っ払いに絡まれる。汚い真似をされた妻は、こんな酔っ払いは焼き殺してしまいたいと憎悪が溢れるのだった。
【scene3】
病室である男が危篤の母親に付き添っていた。ふと目覚めた母親の頼みで、男は町にメロンを買いに出かける。だが祭りの人混みに苛立ちを覚え、さらに毛虫が服の中に入り、男は悲鳴をあげてのたうち回る。公衆便所に駆け込んで毛虫を取り除いた男は、町の人間共を踏み潰したいと憎悪が溢れる。そして、戦争が始まればいい、と願うのだった。
主人公の瞳に映る町の出来事は現実である。だが自分には関係ない、とフィニーは言う。二人は明日ヨットに乗る約束をする。
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

初めに、物語性の可否について
抽象的で断片的な物語の集合に混乱した人も多いでしょう。
- 海辺の男女から、急に跳躍した複数の物語が綴られる(境目も曖昧)
- 物語の舞台(海の向こうの街)は共通しても、人物同士の直接的な関連性は皆無
- 情景描写が異常に細かく綴られるも、その一方で物語全体としての具体性が欠落している
以上の点から解釈が難解です。読書サイトのレビューには、「よくわからなかった」「駄作」「不快」といった書込みが寄せられています。
『限りなく透明に近いブルー』と『コインロッカーベイビーズ』に挟まれた作品なので埋もれるのは仕方ないにしても、駄作と批判するほど退屈な作品ではないように思います。
確かに本作にはストーリーテラーとしての面白さは欠落しています。海辺の男女、桃を拾う少年、老いた大佐、衛兵、洋服屋。まるで静止画を順番に眺めるような描写です。その写真1枚1枚から意味を紐解いていかねばならない故に、単純に物語を追うだけでは何も残らずに終わってしまいます。
前作の『限りなく透明に近いブルー』においても、これといった物語性はありませんでした。破綻寸前なギリギリの精神葛藤が暴力的に突き抜け、それを起承転結に当てはめて説明するのは不可能です。
そもそも芥川賞の基となる芥川龍之介は、「物語性」を重視した作家ではありませんでした。むしろ、物語性を排除しても小説の芸術性は成り立つ、と主張していたのです。
一方で谷崎潤一郎は、小説の芸術的価値は物語性にあると主張し、二人の相反する考えは論争へと発展していきます。ただし決着がつかないまま芥川龍之介は自殺してしまいます。
結局この歴史的な論争に答えはなく、どちらの主張も正解なのです。物語性があろうがなかろうが、大衆に媚びることなく自分の表現を追求すれば純文学になります。そういう意味では『海の向こうで戦争が始まる』は、その前衛的な表現としての価値を称賛するべき作品に値するでしょう。
前作から続く頭の中の妄想都市
「俺は自分の好きなようにその見る物と考えていたことをゆっくり頭の中で混ぜ合わせて、夢とか読んだ本とか記憶を探して長いことかかって、なんて言うか一つの写真、記念写真みたいな情景を作り上げるんだ。」
『限りなく透明に近いブルー/村上龍』
前作『限りなく透明に近いブルー』で主人公のリュウが口にした台詞です。リュウは頭の中に自分だけの宮殿や妄想都市を作り上げることに愉悦していました。その夢想の先には、宮殿を爆発させたいという破壊衝動がありました。
見たものや考えたことを自由に頭の中に作り上げ、最後にはそれを破壊する。『海の向こうで戦争が始まる』は、前作のリュウの夢想を具現化させた作品だと言えるでしょう。
つまり、主人公の目に映る海の向こうの街とは、頭の中で自由に作り上げた世界だということになります。
事実、物語の舞台がどこの国で、どこの街で、いつの時代か、ということが一切明かされません。それは現実には存在しない、頭の中だけの妄想都市だからでしょう。
「リュウ、あなた変な人よ、可哀想な人だわ、目を閉じても浮かんでくる色んな事を見ようってしてるんじゃないの? あなた何かを見よう見ようってしてるのよ」
『限りなく透明に近いブルー/村上龍』
見ようとする事、夢想する事。それは村上龍の執筆の礎なのかもしれません。「海の向こう」という自分とは隔たりがある世界で起こる出来事を覗いて、それを頭の中で「独自の世界」に組み立てて、作品に消化する。それはもはやSFとも呼べます。
現実世界を題材にした私小説や歴史小説なるジャンルが日本文学の王道とされてきました。一方でSFなるジャンルは文学ではなく、エンタメやサブカルチャーとしての印象が強くありました。言わずとも「文学>サブカルチャー」という絶対的な優劣があったのです。
当時、村上龍の作風は、「サブカルチャーに過ぎない」という批判と、「新世代の表現」という称賛、真っ二つに分かれました。
ただし村上龍のSFは、「あったらいいな」の絵空事を描いた陳腐な世界観ではなく、人間が抱える闇や葛藤に根差しています。その葛藤を表現するのに必ずしも実世界を舞台にしなければいけないという制約の方が陳腐でしょう。地図には存在しない空想の世界を自由に創り上げてもいいのです。そういう意味では、村上龍は純文学の幅を広げた革命児と言えるでしょう。
『限りなく透明に近いブルー』でリュウが提示した妄想都市とは、頭の中で自由に作り上げた世界で文学を表現してもいいのではないか、という意思表明だったのかもしれません。それを『海の向こうで戦争が始まる』で具現化させ、次作の『コインロッカーベイビーズ』で完成形に仕上げたのでしょう。
村上龍の登場によって、長らく日本文学はSF的な世界観で精神的な葛藤を描く作風が主流となりました。
破壊を望むということ
『限りなく透明に近いブルー』のリュウは、頭の中の宮殿を爆破したいという破壊衝動を持っていました。同様に『海の向こうで戦争が始まる』においても、祭りという混沌の中で、各人が破壊や戦争を望んでいました。
- 桃を拾う少年
→牡犬を殺したい - 年老いた大佐
→祭りではなく戦争を望んでいる - 衛兵の妻
→酔った男たちを焼き殺したい - 洋服屋
→広場の人間供を踏み殺したい
「全ては汚らしい嘔吐物だ、(中略)祭りなんかいらない。戦争が始まればいい」
海の向こうで戦争が始まる/村上龍
海の向こうの街で描かれる4つの物語のいずれの登場人物も、現状が破壊されることを強く望んでいました。
年老いた大佐が口にした、戦争の裏には熱狂と興奮と恍惚があり日常が退屈しない、という台詞が象徴する通りです。各人が自分の日常に陰鬱とした問題を抱えており、それを払拭するために破壊や戦争を望んでいたのです。
平和や退屈とは、ある意味では停滞であり、老朽を意味します。「老いた大佐」という存在こそが、まさに社会の老朽化を象徴しているようです。ともすれば戦争とは現状を破壊し、社会を一新する力を持っていることになります。創造し、維持し、破壊する、そのサイクルによって社会は老朽化を防いでいるのです。
ただし、文明の発展は核兵器という「限度」を生み出してしまいました。核兵器という絶対的な抑止により社会は停滞し、その先には何も存在しないことを露呈してしまったのです。限度を生み出したことで、老朽化を防ぐための破壊は失われてしまいました。
退屈を払拭し、社会を一新させるには破壊が必要だと主張する村上龍は、あたかも戦争肯定派のように感じられます。しかし、あくまで彼は核兵器による社会の停滞をメタファー的に露呈することで、個人の興奮や恍惚の必要性を問うていたように感じます。
個人の興奮や恍惚のための破壊。それは芸術に違いありません。頭の中で自由に組み立てたものを破壊する行為。表現活動の鉄則です。つまり、村上龍は小説を執筆することで、自己が属す社会の老朽化を防ぐための戦争に挑んでいるのかもしれません。芸術は常に社会を新しい姿に推し進める役割を担っているのですから。
我々のもうひとつの戦争は、芸術的表現活動に違いなく、それこそが社会を一新させる破壊エネルギーを有しているのだ、と解釈できます。
全てが海の向こうの出来事
子供達の叫び声が聞こえる。ここまで届いてくる。両手を後手に縛られ耳に銃口を突っ込まれる痩せた男が見える。瓦礫に化した舗道を、背中一面にケロイドを作った女の子が歩いているのが見える。首を針金でしめられる老人が見える。僕達はそれをはっきりと見ている。
海の向こうで戦争が始まる/村上龍
「でもあたし達は別にいいのよ」
海の向こうの街で勃発した戦争。そのショッキングな映像に対してフィニーは、「でもあたし達は別にいいのよ」という他人事のような台詞を呟きました。
まるで日本人としてのアイデンティティの写し鏡のようです。
地続きの隣国を持たない日本人にとっては全ての他国が海の向こうに位置します。
1952年生まれの村上龍の心象には、やはり海の向こうで実際に戦争が起きているという空気感が染み付いているのではないでしょうか。その海外譲りの空気感は日本国内でも左翼教養主義による血気盛んなムーブメントに発達しました。ところが、彼らの破壊活動はどこか滑稽でお祭じみた熱狂だったように感じます。
いや、死体は途中で消えてしまうだろう、鋭い歯を持つ貪欲な魚達が啄むだろう(中略)海とはそういうものだ。あの町と僕達の間に海は常にそういう風に横たわっている。
海の向こうで戦争が始まる/村上龍
実際に世界にのさばる危機感は、海を媒介することで、まるで現実味が失われてしまいます。ベトナム戦争はそういった島国としての国民性を露呈した出来事のように思います。
初めての読了後には、「見ようとしない」日本人の怠慢な姿勢を痛烈に批判しているように感じました。ところが再読すると、フィニーの台詞は皮肉ではなく、ある種肯定的なニュアンスなのではないかと感じました。
つまり「あたし達は別にいいのよ」という他人事な精神を正当化しているのではないかということです。
海の向こうで起こる出来事と自分の日常とは永久に分断されたものです。無理やり直視することで沸き起こった狂熱は、日本に届いた頃には滑稽なお祭り騒ぎに成り果てていました。
村上龍の作品『69』では、左翼教養主義的な雰囲気の中で無思想に高校をバリケード封鎖したり、前衛的なフェスティバルを開催する自伝的な物語が綴られていました。あとがきにはこんな一節が綴られていました。
唯一の復しゅうの方法は、彼らよりも楽しく生きることだと思う。楽しく生きるためにはエネルギーがいる。戦いである。わたしはその戦いを今も続けている。
69/村上龍
大学紛争の若者の破壊活動と、それを制する大人達の対立構造をシニカルに観察する村上龍の姿が垣間見えます。社会の混沌に勝つ唯一の方法は自分が楽しく生きる以外にあり得ない、という彼なりの哲学なのでしょう。
世の中で起きている悲劇を「見るということ」は重要でも、それとどう向き合うかを考えたときに、海の向こうと自分の日常を接続させてはいけないのかもしれません。見ることは重要でも、第一に自分の日常を楽しむこと。浜辺の主人公とフィニーは、海の向こうの街から視線を外し、自分の日常に戻ることで、本当の意味での戦いを始めたのかもしれません。
■関連記事
➡︎村上龍おすすめ代表作10選はこちら
映画『ラブ&ポップ』おすすめ
村上龍の代表作『ラブ&ポップ』は、庵野秀明が監督を務め1998年に映画化された。
家庭用デジタルカメラで撮影され、特殊なアングルのカットや、庵野らしい明朝体のテロップが施されている。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら