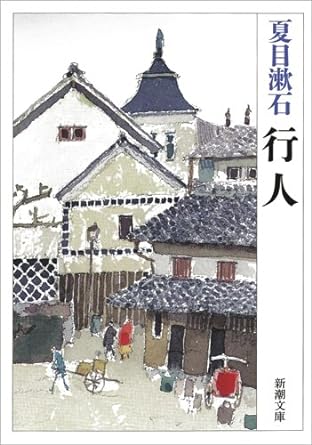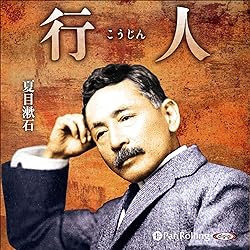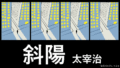夏目漱石の小説『行人』は、後期3部作の2作目にあたる作品です。
『彼岸過迄』に次いで発表され、『こころ』へと繋がります。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表時期 | 1914年(大正3年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 501ページ |
| テーマ | 現代知識人の苦悩 肉と霊 |
あらすじ

女中の縁談を取り持つために大阪にやって来た二郎は、兄に深刻な依頼をされる。
「弟よ、私の妻と一晩よそで泊まってきてくれないか?」
妻が自分を愛していないと勘繰る兄は、妻の貞操を確かめるために、弟にこんな無茶なお願いをしたのだ。
元より兄夫婦の関係は拗れていた。それは淡白な兄嫁の性格を、学者気質な兄が過剰に気にするせいだ。他人の魂は所有できない。その問題に直面した兄は神経症を悪化させることになる。
帰京後に兄はますます消耗し、書斎に籠ってしまう。兄のことを気にかける二郎は、知人に頼んで兄を旅行に連れ出してもらう。
旅行先の知人から、兄の様子を記した手紙が届く。そこには現代知識人が陥りがちな、死ぬか、気が違うか、宗教に入るか、という凄まじい苦悩が記されていた・・
Audibleで『行人』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『行人』を含む夏目漱石の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼30日間無料トライアル実施中!
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

後期三部作とは
夏目漱石の作品群には、前期三部作と後期三部作が存在する。
■前期三部作
『三四郎』『それから』『門』
前期三部作では、明治時代の恋愛観に苦しむ人間の葛藤が描かれている。登場人物や設定は違えど、「自由恋愛の敗北」▶︎「略奪婚」▶︎「略奪後の苦悩」といった感じで、ストーリーに関連性がある。
■後期三部作
『彼岸過迄』『行人』『こころ』
一方で後期三部作には、前期三部作のようなストーリー上の関連性はない。
ではなぜ三部作としてまとめられているのか。
それは「エゴイズム」と「近代知識人の苦悩」という共通のテーマを有しているからだ。
■『彼岸過迄』では、一族の政略や、母親のエゴによって結婚を迫られる青年の、自我の葛藤が描かれている。
■『行人』では、知識人であるゆえに、妻との関係に懐疑心を抱き、精神状態が悪化していく兄の様子が描かれている。
■『こころ』では、人間のエゴに潜む罪悪に苦悩し、明治時代の終焉と共に自死を決意する先生の遺書が綴られている。
このように三作ともが、知識人であるゆえに人間のエゴに苦しむ物語なのだ。それは前期三部作よりも、一層個人の内面の葛藤に焦点を当てた、深いテーマになっている。
実は『彼岸過迄』の執筆前に、漱石は胃潰瘍で危篤状態に陥った。幸い一命は取り留めたが、死の瀬戸際を彷徨った漱石は、より神経を尖らせ、上記のような深いテーマを追求することになったのだ。
以上の背景を踏まえて、物語を考察していく。
兄夫婦の歪な関係性
弟よ、私の妻と一晩よそで泊まってきてくれないか?
『行人/夏目漱石』
妻は自分のことを愛していない。あるいは弟の二郎に好意を持っているのかもしれない。そんな過剰な勘ぐりをした一郎は、彼女の貞操を試すために無茶な依頼を弟に願い出た。
兄は大学の教授を務める、根っからの学者気質で、他者の心についても研究しなければ気が済まない神経質な部分があった。そのため、感情を表に出さない淡白な妻といると、果たして彼女は自分を好いているのか、という不安に襲われたのだ。
結婚すれば、形式的に妻の肉体は所有できる。だが魂までは所有できるとは限らない。それが一郎を神経質にさせた苦悩の種だった。
兄に無茶な依頼をされた二郎は、兄嫁と旅館に一泊する。そして単刀直入に、兄を愛しているのかを彼女に問う。すると彼女は、そんな風に勘違いされるのは自分が淡白な性格のためだ、と弁解した。
なるほど、淡白な性格が生来のものなら、それは仕方がないことだろう。だが問題は、兄と結婚したことで、彼女は淡白な性格にならずにはいられなかった、ということである。
詳しくは次章で考察する。
兄嫁の苦悩(結婚の問題)
兄の無茶な依頼で旅館に宿泊した夜、兄嫁は不意に「自分は簡単に死ぬことができる」と突拍子もないことを口にして二郎を驚かせる。
この緊張感のある場面は、多くの読者を驚かせたことだろう。
それ以降しばらく兄嫁は変わった様子を見せなかったが、しばらくして二郎の下宿先を訪れた際に、またしても意味深長な言葉を口にする。海外渡航を計画する二郎の話を聞いて、「男はどこへでも勝手に飛んでいけるから気楽だ」と言ったのだ。
死への躊躇のなさ、男の気楽さに対する羨望。このことから分かるのは、兄嫁は何かに束縛され、そこから逃避したい願望を持っているということだろう。
これこそが本作の重要なテーマの1つである。そしてこのテーマを理解するには、兄夫婦の問題以前に描かれる、「女中の縁談」と「三沢が話す精神病の女」の話が鍵になっている。
①女中の縁談
女中の縁談は歪だった。結婚する当人の女中は相手の男と顔を合わさないまま、周囲が勝手に事を進行させていくのだ。
おまけに、女中の良き相談相手だった(二郎の妹)お重が、女中の思いを代弁して、結婚相手の情報を詮索するが、二郎は「いい人だ」と適当にあしらって、真剣に取り合おうとしない。両親が納得しているのだから、いい人に決まっている、といった具合だ。
以上の出来事から、当時の女性の立場がいかに窮屈であったかが把握できる。自分の意思とは無関係に、周囲の取り持ちによって強制的に結婚させられていたのだ。
作中では兄と兄嫁がどのような経緯で結婚したのかは語られない。だが女中と同じ運命を辿ったことは容易に想像できる。
兄嫁は、自分は淡白だから夫を愛していないように見られるのだ、と弁解したものの、心から夫を愛しているとは一度も宣言しなかった。実際のところ彼女の真意は不明である。
いずれにしても、結婚した以上、夫を愛さなければいけない、という自己暗示の中で生きていたことは確かだろう。
②三沢が話す精神病の女
これは二郎の友人・三沢が打ち明けた内容だ。
三沢の父親はある娘の仲人を務めた。だがその娘は1年も経たぬうちに夫と別れてしまった。体裁が悪いため娘は実家に戻ることができず、仲人を務めた義理で三沢の父親が預かることになった。
娘は離婚してから精神に異常をきたし、三沢が外出する際には決まって玄関まで送りに来て、「早く帰ってきてくださいね」と、まるで三沢を夫と勘違いしているような文句を口にした。
三沢が言うには、新婚早々娘の夫は殆ど家に帰らず、散々娘のことを雑に扱ったそうだ。だが娘は夫に本音を打ち明けられなかった。だから精神病になってから、当時夫に言えなかった「早く帰ってきてほしい」という本音を三沢に打ち明けていたらしい。
この出来事について、兄の一郎は、女は精神病になって初めて正直になれるのかもしれない、と自論を述べていた。
つまり、当時の女性は結婚したら最後、自分の本音を押し殺して生きていかねばならず、本音を告白できるのは精神病になった時だけだ、というあまりに残酷な事実を訴えていたのだ。
兄嫁だって例外ではないだろう。それを象徴する言葉を、二郎と和歌山に宿泊した夜に兄嫁は口にした。
若し貴方が帰ると仰しゃれば、どんな危険があったって、妾一所に行くわ(中略)貴方が御泊りになれば妾も泊るより外に仕方がないわ。
『行人/夏目漱石』
彼女には自分の意志が全く感じられない。全ては男のなすがままである。彼女自身そんな自分を「魂の抜殻」「腑抜け」と呼んでいる。
このように女性の立場が軽視されていた時代、多くの男性はそれを利用して気楽に過ごしていたことだろう。だが兄・一郎は違った。学者気質の彼は、結婚によって自分が妻を不幸にしている感覚に耐えきれず、精神を消耗していくことになる。
一郎の苦悩については、次章にて考察する。
エゴの問題に苦しむ一郎
死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか。僕の前途にはこの三つのものしかない。
『行人/夏目漱石』
精神療養を兼ねて、知人のHさんと旅行に出た兄・一郎は、これまで家族に見せなかった苦悩の正体を明らかにする。
嫁に行けば、女は夫のために邪になるのだ。そういう僕が既に僕の妻をどのくらい悪くしたか分からない。自分が悪くした妻から、幸福を求めるのは押が強過ぎるじゃないか。
『行人/夏目漱石』
一郎は自分が妻を「腑抜け」にしたことを自覚している。妻は元はちゃんと魂を持っていた。だが自分と結婚したことで魂を失った。その事実が一郎を消耗させていたのだ。
妻の魂の不在に悩む一郎は、彼女が自分に反抗することを望んでいた。それはつまり、彼女の本音を引き出し、彼女の魂の所在を知るためである。だが兄嫁は決して一郎に反抗することなく、本音を押し殺して暮らしていた。それが一層一郎を不安にさせ、自分を責め苛む結果になったのだ。いっそのこと、妻が自分を愛していないとはっきり口にした方が、一郎は楽になれたかもしれない。
結局これは、自分が研究的な人間で、行動的な人間になれない所以だと、一郎は認めている。他者の魂の所在を研究すればするほど、その途方もない乖離を思い知らされ、ますます精神が悪化していくわけだ。
こうした苦悩の末に、一郎は「絶対」という究極的な概念を模索するようになる。それはあらゆる事象を超越し、自己と万物の境界線がなくなる、悟りの境地のようなものだ。いわゆる自我の忘却であり、他者の消滅とも言える。自我や他者が消えれば、魂の乖離という問題に苦しまなくて済むのだ。
だが一郎は自分には宗教に入る覚悟がないことを自覚している。それは『門』という作品でも描かれた、自分は門を潜る人間ではなく、門の前で佇む人間だ、という思想のどん詰まりと同様であろう。宗教は不可、自殺する勇気もない、そうなれば、ただ気が違う瞬間を怯えながら待つしかなかったのだ。
自分のエゴによって他者(妻)を不幸におとしめる、近代知識人の苦悩。それは前期三部作で描かれた社会道徳との葛藤よりも、さらに個人の内部の葛藤として問題が深化している。この個人の罪悪の問題は、次作『こころ』にて、先生の自殺という結果に引き継がれる。
■関連記事
➡︎夏目漱石おすすめ作品10選はこちら
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら