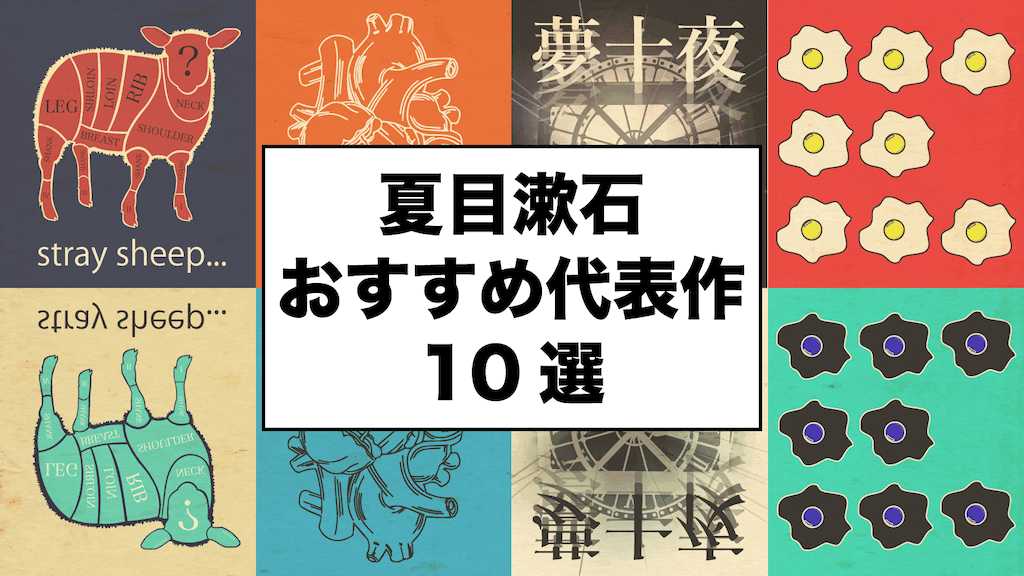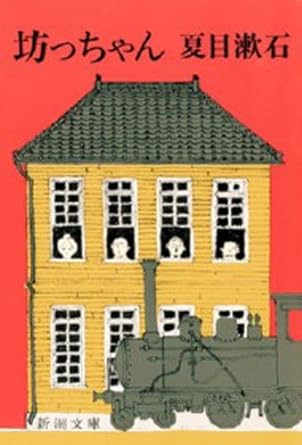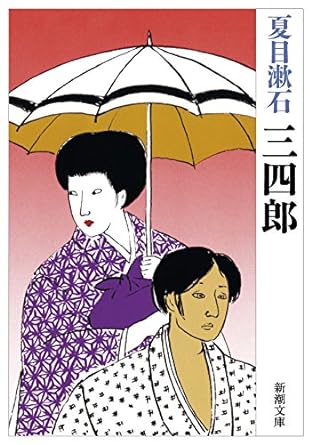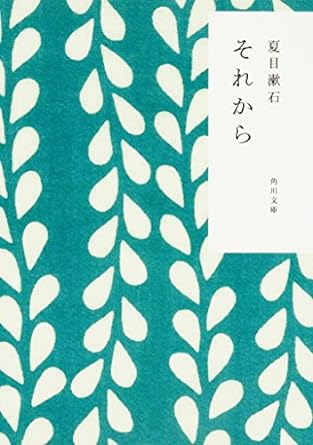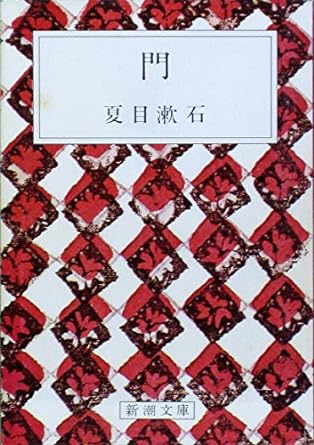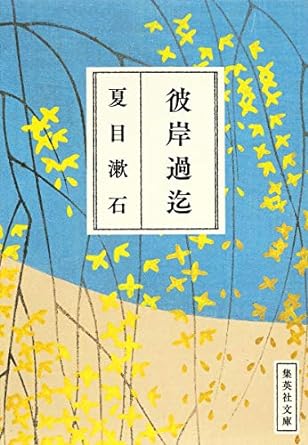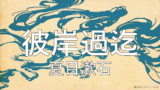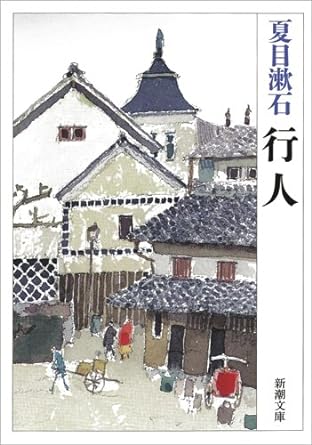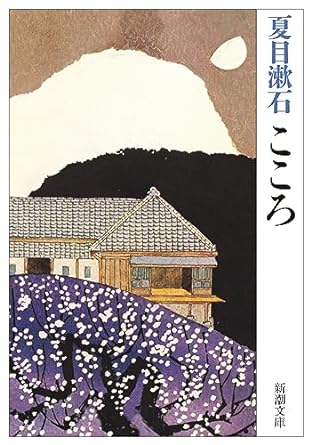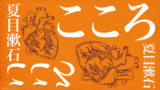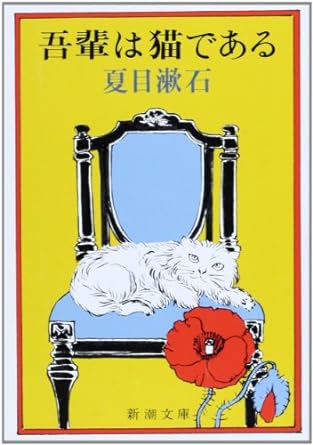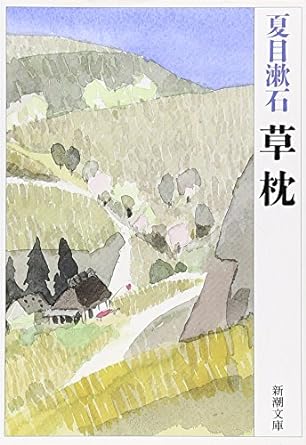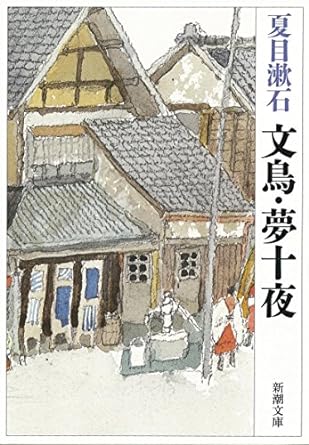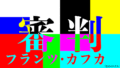明治時代を代表する文豪、夏目漱石。
わずか11年の活動期間で15作もの長編小説を残し、その多くは現在も学校の教科書に掲載されるなど広く親しまれています。
一方で漱石の作品は苦手という声が多く、文学好きでも挫折が多いと言われています。
そこで今回は、夏目漱石のおすすめ代表作10選を読みやすい順に紹介していきます。

夏目漱石を読破した筆者が、挫折せずに済む順番で厳選しています!
①『坊っちゃん』
■入門編におすすめ!義理人情の大衆文学
| 発表時期 | 1906年(明治39年) |
| ジャンル | 中編小説 |
| ページ数 | 240ページ |
■作品紹介
漱石の教員時代を題材にした初期の代表作。他作品より大衆的で読みやすいので、入門編におすすめ!
■あらすじ
「坊っちゃん」が数学教師として赴任したのは、ユニークな教員ばかり揃う学校だった。陰湿な教頭「赤シャツ」は裏で悪さを働き、美術教師「野だいこ」は媚を売って加担している。正義感の強い「坊っちゃん」は、二人の悪事を暴くために、ひと暴れする・・・
普遍的な大衆ドラマ・学園ドラマの設定を駆使した、ひたすら面白い作品。
②『三四郎』
■前期3部作の1作目 東大生の儚い恋物語
| 発表時期 | 1908年(明治41年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 368ページ |
■作品紹介
物語の繋がりを持つ前期3部作の1作目。
明治時代の価値観に苦しむ人々を描いた漱石文学は、この作品によって本格的に始まる。
■あらすじ
熊本から上京して東京大学に進学した三四郎のキャンパスライフが描かれる。
ある日、キャンパス内で出会った絶世の美女「美禰子」に、三四郎は一目惚れする。付かず離れずのもどかしい恋模様の果てに、とうとう勇気を振り絞った三四郎。しかし二人には悲しい運命が待ち受けていた・・・
明治時代の恋愛観と、漱石のお洒落なワードセンスが輝く、ハイカラ文学!
③『それから』
■前期3部作の2作目 『三四郎』のそれから
| 発表時期 | 1909年(明治42年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 352ページ |
■作品紹介
『三四郎』に次ぐ前期3作の2作目。
登場人物や設定は異なるが、タイトル通り『三四郎』の”それから”の展開が描かれる。
■あらすじ
30歳で未婚、しかも無職の主人公には、かつて意中の女性を友人に譲った過去がある。数年越しに再会した女性は、結婚生活に疲弊していた。友人に譲ったのは間違いだったと感じた主人公は、全てを投げ出す覚悟で略奪婚を試みる・・・
『三四郎』の次に絶対に読んでほしい作品!
④『門』
■前期3部作の最終章 略奪婚後の悲劇
| 発表時期 | 1939年(明治43年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 320ページ |
■作品紹介
『三四郎』『それから』に次ぐ前期三部作の最終章。
こちらも登場人物は異なるが、略奪婚後の夫婦の生活、という続編内容が描かれる。
■あらすじ
略奪婚を成し遂げた夫婦は、世間体から人目を避けてひっそり暮らしている。ある日、略奪の犠牲となった友人が東京に訪れる噂を耳にする。その後ろめたさに消耗した主人公は、宗教の道に救いを求めるが・・・
あまりに陰鬱とした結末ですが、ぜひ3部作の最終章まで見届けてください。
⑤『彼岸過迄』
■後期3部作の1作目 自意識に苦しむ青年
| 発表時期 | 1912年(明治45年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 426ページ |
■作品紹介
物語の繋がりはないが、テーマの関連性を持った後期3部作の1作目。
前期3部作から一転して、人間の内面に焦点を当てた、自意識の問題が描かれる。
■あらすじ
主人公・敬太郎の視点で、友人・須永の結婚問題が描かれる。
須永には千代子という従妹がいる。須永の母親は千代子が生まれた時点で息子に嫁がせる口約束をしていた。だが千代子をただの従妹としか思っていない須永は、自分の本心と一族の政略との狭間で苦しむ・・・
複数の短編で1つの長編が構成されており、処女作『吾輩は猫である』と似ている。
⑥『行人』
■後期3部作の2作目 近代知識人の苦悩
| 発表時期 | 1914年(大正3年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 512ページ |
■作品紹介
『彼岸過迄』に次ぐ後期3部作の2作目。
自分のエゴや、他者との関係性に苦しむ近代知識人の苦悩が描かれる。
■あらすじ
「弟よ、私の妻と一晩よそで泊まってきてくれないか?」
兄の一郎は、妻との淡白な関係に悩み、思想の世界で消耗していく。妻の肉体は所有しても、魂は所有できない。その問題に直面した一郎の前には、自殺か、気が違うか、宗教に入るか、という究極の選択が迫っていた。
『門』で描かれた宗教の問題を踏襲しつつ、究極の選択は『こころ』へ引き継がれる。
⑦『こころ』
■後期3部作の最終章 教科書で習う名著
| 発表時期 | 1914年(大正3年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 384ページ |
■作品紹介
『彼岸過迄』『行人』に次ぐ後期3部作の最終章。
教科書で習う名著であり、日本の歴代ベストセラー2位を記録する。
■あらすじ
語り手の「私」が出会った「先生」の、過去の罪悪が遺書で語られる。書生時代、先生は友人Kから好きな人を横取りした。それが原因かは不明だが、Kは自殺してしまう。罪悪感を抱き続ける先生は、明治の終焉、乃木希典の殉死に感化され、自ら命を絶つ・・・
後期3部作の流れ、時代背景を意識すれば、学校教育では理解できなかった先生の自殺の意味が見えてくる?
⑧『吾輩は猫である』
■デビュー作にして最も挫折の多い名作
| 発表時期 | 1905年(明治38年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 624ページ |
■作品紹介
「吾輩は猫である。名前はまだない」という一節で始まるデビュー作。だが最も挫折の多い作品とも言われている。
■あらすじ
猫の視点で、偶然住み着いた家の人間の様子が描かれる。相手と正反対の意見ばかり主張したがる人間、ホラを吹いて他人を担ぎ上げる人間、芸術に傾倒し過ぎてズレた感覚を持つ人間。猫の視点だからこそ見えてくる、人間の滑稽さが非常にユニークである。
物語性のない思想談義が500ページ以上続くので、挫折する人が多い。ある程度他の作品を読んで、漱石の思想を理解した上で臨むことをおすすめする。
⑨『草枕』
■小説の枠を超えた芸術の書
| 発表時期 | 1906年(昭和39年) |
| ジャンル | 中編小説 |
| ページ数 | 256ページ |
■作品紹介
熊本で英語教師をしていた漱石が、温泉地へ訪れた体験が題材になっている。物語性はなく、ひたすら芸術論が語られる特異な作品。
■あらすじ
「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」
この有名な一節通り、人の世に生きづらさを感じた主人公は、山中の温泉地に宿泊し、そこで出会う自然美や女性との交流を通して、自らの芸術論を模索する・・・
『吾輩は猫である』同様、物語性のない作品なので少し難解。
⑩『夢十夜』
■不思議な夢の世界を描く幻想文学
| 発表時期 | 1908年(明治41年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 31ページ |
■作品紹介
漱石には珍しい、幻想的なテイストの短編小説。とりわけ人気の高い作品で、漱石の詩的でロマンチックな作風が最も感じられる。
■あらすじ
「こんな夢を見た」という書き出しで、10個の不思議な物語が描かれる。そこには百年の恋を題材にしたロマンチックな物語や、死生観・西洋批判・芸術論など、様々なテーマがメタファーとして描かれている。
作品集にはその他に不思議な小品が7篇収録されています!
夏目漱石を読むならオーディブルがおすすめ!
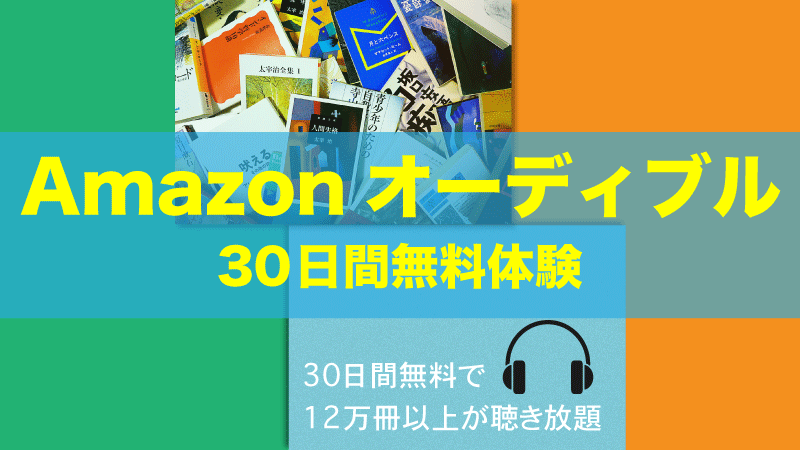
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら