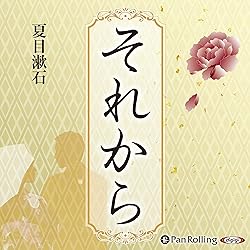夏目漱石の小説『それから』は、前期三部作の二作目にあたる作品です。
『三四郎』に続く、明治時代の全体主義の中で恋愛に苦しむ若者の姿が描かれています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表時期 | 1909年(明治42年) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 302ページ |
| テーマ | 全体主義と個人主義の葛藤 人妻との恋愛 |
| 関連 | 1985年に映画化 主演:松田優作 |
あらすじ

主人公の代助は、父の援助で悠々自適に暮らすぷー太郎である。幾度となく父に縁談を勧められたが、代助はまるで結婚の意思を示さなかった。
一方で親友の平岡は銀行員だったが、部下の横領により辞職を余儀なくされた。そんな平岡には三千代という妻がいる。代助はかつて三千代に好意を抱いていたが、真面目な平岡と結婚させることで三千代の幸福を願った。しかし平岡の辞職により生活は困窮し、挙句平岡は家計を顧みず芸者遊びにうつつを抜かすようになる。平岡に三千代を委ねたのは間違いだったと後悔に苛まれた代助は、平岡の不在時に家を訪ねては三千代を慰めていた。
いよいよ父に政略結婚を迫られた代助は、三千代を自宅に招き寄せ愛の告白をする。しかし、代助は経済的に自立しておらず、三千代を愛するには就職と向き合う必要があった。二人は密会を重ねていたが、ついに後ろめたさから平岡に全てを打ち明け、三千代を譲ってほしいと頭を下げる。最終的に平岡は承諾するが、絶交が条件だった。
平岡はこれらの出来事を、代助の実家に手紙で報告していた。縁談を拒絶し、おまけに人妻に手を出した事実を知った父は、代助は勘当する。唯一の理解者だった兄夫婦からも絶縁を言い渡される。こうして代助は恵まれた生活や家族を捨て、愛する三千代を選んだ。世間と対峙することを決意した代助は、職業を探しに町へ繰り出すのであった。
Audibleで『それから』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『それから』を含む夏目漱石の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

『三四郎』のそれからを描いた続編
「三四郎」には大学生の事を描たが、此小説にはそれから先の事を書いたからそれからである。(中略)此主人公は最後に、妙な運命に陥る。それからさき何うなるかは書いていない。此の意味に於いても亦それからである。
夏目漱石は、本作『それから』について上記のように言及している。
つまり本作は、前作『三四郎』の”それから”を描いた作品なのだ。とは言え、実際的に登場人物やストーリーに関連性はなく、あくまで一貫したテーマにおける続編と言える。
『三四郎』では、大学生の恋愛が描かれた。田舎から上京した三四郎は、美禰子という美しい女性と出会い、特別な感情に駆られる。しかし愚図愚図しているうちに美禰子は見合い結婚をしてしまう。美禰子は何度も三四郎にメッセージを発していた。それは、自由恋愛が許されない明治時代に、新しい価値観を持った女性が、新しい価値感を持ったゆえに、「ストレイシープ(迷える子羊)」になってしまった、という意味を孕んでいた。
そして本作『それから』では、姦通がテーマである。言い換えれば、人妻との恋愛だ。
『三四郎』ではお見合い結婚によって恋が叶わなかったが、『それから』ではまさに”それから”の展開、つまり既に他人と家庭を築いた女性との恋愛が描かれているのだ。
一見、不倫の恋愛と聞くと、大衆文学やテレビドラマのイメージを持つかもしれない。しかし本作が描かれた明治時代には、姦通罪なるものが存在した。不倫が刑罰で裁かれていたのだ。
人妻に手を出した息子と勘当するなど、少し大げさに感じた人もいるかもしれない。しかし、当時は不倫が犯罪だった背景を考えると、物語の深刻さが伝わるのではないだろうか。
以上を踏まえた上で考察を進める。
▼前期三部作の一作目『三四郎』
全体主義に苦しむ代助の恋愛
代助の言動はあまりに優柔不断で、やきもきした読者も多いのではないだろうか。
もとより代助は三千代に好意を抱いていた。三千代の兄からも、嫁に貰ってほしいというメッセージを暗に受け取っていた。それにもかかわらず、代助は友人の平岡に譲ってしまう。だからと言っていつまでも吹っ切れることができず、長らく三千代のことを心の片隅で思い続けていた。そして、いよいよ縁談を迫られたタイミングで、既に人妻である三千代に思いを告げてしまう。代助自身も、もっと早くに伝えるべきだと後悔していた。
全くもって代助の優柔不断が招いた結果なのだが、それでも彼には言い分がある。
そもそも、代助はなぜ三千代を平岡に譲ってしまったのか。
▼第一の理由は、自身の経済力の問題だ。
代助は父の援助で悠々自適に暮らす、いわゆるぷー太郎だった。彼が無職である理由は後に考察するが、とにかく自分の経済力のなさを危惧した結果、銀行に就職した平岡に譲る方が、三千代のためだと考えたのだ。とは言え、代助は裕福な家庭であるため、無職のままでも三千代を十分に養える立場であった。結局は代助の自信のなさや、臆病なプライドによって、三千代と結婚する決心が出来なかったのだろう。
▼第二の理由は、父との軋轢だ。
代助の父はやり手の実業家だった。代助に縁談を迫る本当の理由は事業上の政略である。日露戦争の影響で不景気になり、事業を立て直すために代助を地主の娘と結婚させようと考えていたのだ。これは最終的な父の意向であるため、三千代を平岡に譲った当時に父が何を考えたいたかは分からない。しかし、三千代は北海道で貧しい生活を送る娘だった。三千代と結婚したところで、父の事業には何のメリットもない。こういった「家」の問題を漠然と理解していた代助は、三千代との結婚は端から叶わないものだと半ば諦めていたのではないだろうか。
これらは全て、当時の全体主義的な風潮、つまり世間の目に抑圧された結果だ。
今の価値観からすれば、別に無職だろうが、経済的に不安定だろうが、最終的には当人たちの愛情の問題を重視できる。ところが当時の啓蒙主義的な価値観、つまり個人の本能的な思いよりも、生活上の問題や世間の目を重視しなければいけない雰囲気の中では、なかなか決心できるものではない。
あるいは縁談こそ、全体主義の象徴である。『三四郎』で、自由恋愛の望みがお見合いによって打ち砕かれた通り、「家」の問題を無視して勝手に結婚するなど困難な選択だったのだ。
代助は新式な考えの持ち主だった。つまり当時の日本社会の矛盾を見抜き、個人主義的な思想に目覚めていた。それだけ先見の明を持っていても、やはり周囲の同調圧力には抗えなかったのだろう。
こういった社会のしがらみが、代助を優柔不断にさせていたのである。
代助が憂う日本の現状
人妻とのタブーな恋愛が物語の本筋だが、中途で代助の思想が多く語られるのが本作の特徴であり、夏目漱石の文学的魅力とも言える。
一つは、父の世代との思想衝突が大きなテーマになっている。
もう一つは、過剰な欧化主義に対する疑念が大きなテーマになっている。
父の世代との思想衝突
最終的に父に勘当される代助だが、その結末に至る以前から二人は相容れない部分があった。というか、表面上は父にぺこぺこする代助だが、内心では酷く反抗の意思を抱いていた。
代助の父は、世代的に考えると幕末の人間である。少年時代に刀を持った男に襲われ、逆にその男を斬り殺すという出来事が語られる。そして、他者を殺生した場合、加害者側は切腹しなければいけないという仕来りが取り上げられたりもする。
この回想が意味するのは、父の世代には武士の精神が根強く残っているということだろう。言うなれば、義や仕来りを重視する、封建的な価値観である。
一方で代助は自分の心臓の音を過剰に気にする癖がある。これは彼が生に対して強く固執している証拠であり、父の世代のように度胸を重宝する野蛮な考えとは相容れないことを示している。つまり、義や仕来りよりも、個人を重視する新しい思想を持っているのだ。
とどのつまり、精神論や封建主義を重視する父の世代と、論理的な思考と個人主義を重視する代助の世代との思想衝突である。
例えば仕事の面においても、父は誠実と熱心があれば挫折することはないと主張する。一方で代助は、誠実と熱心だけでは失敗を招くこともあると主張する。この対立は非常に現代にも通づる部分があると思う。精神論を豪語する企業風土に、若手社員が辟易するといった問題は今でも珍しくない。
このように、義や仕来りを重視する父の世代にとっては、代助の生き方は異端である。政略結婚を破断させ、人妻に手を出すような個人主義に生きる代助を認めるわけにはいかず、最終的には勘当という結果に至ったのだろう。
過剰な欧化主義に対する疑念
義や仕来りを重視する封建的な風潮の中で、やりたくもない仕事に就くのは嫌だ、というのが代助が無職である理由の一つである。
そしてもう一つ彼が無職である理由は、過剰な欧化主義も関係している。
「何故働かないって、そりゃ僕が悪いんじゃない。つまり世の中が悪いのだ。もっと、大袈裟に云うと、日本対西洋の関係が駄目だから働かないのだ。」
『それから/夏目漱石』
夏目漱石は度々過剰な欧化主義に対する疑念を主張している。彼は個人主義という点では西洋の前進した思想を尊重していた。しかし、国力がない日本が無理に欧化主義に徹した末の歪みに対しては懸念していた。
作中ではイソップ物語の「蛙と牛の競争」が引用される。体の大きさで牛に対抗するために、無理に空気を吸い込んだ蛙の腹が破裂するという物語だ。西洋に対抗した結果、底抜けになった日本を比喩していた。
無理に西洋に追いつこうとすれば、その圧迫は民衆にのしかかり、こき使われた結果、神経衰弱になってしまうと言うのだ。事実、民衆は今日の生活もままならない状況に陥り、食うために働く、という過酷な境遇を強いられていた。
この「食うために働く」という状況こそが不幸の根源だと代助は主張している。つまり生活と労働を結び付けるのは不幸なのだ。
代助が理想とするのは、労働のための労働だ。生活上の問題は気にかけず、自分のやりたいことを追求して初めて、労働は真の価値を持つわけである。例えば、生活のために銀行員になった平岡は、結果的に貧困に陥り、三千代を不幸にしてしまった。前述の通り、誠実と熱心だけではどうにもならないこともあるのだ。
こういった理知的な思考ゆえに、代助は労働をする気になれなかったのである。
ともすれば、代助には、真の価値とも言える、労働のための労働を見つけられたのか。
答えは否である。言ってしまえば、ただの御託であり、論理は頭の中にあるが、自分が何をしたいのかは分からないままなのだ。ここが代助の欠点であり、しかし読者を共感させる、蟠りや苦悩のポイントなのだと思う。
最終的に代助はどうなったのか
夏目漱石は、最終的に代助がどうなったかは書いていない、と言及している。その通り、妙な情景描写と心象描写を残して物語は唐突に幕を閉じる。
人妻に手を出した結果、父親から勘当され、兄夫婦からも絶縁を言い渡され、一切の援助が尽きてしまった。言い換えれば、代助は全体主義的な風潮に反抗して、三千代と生きていくことを決心したのだ。
三千代と生きるには、あれほど拒絶していた労働をしなければならない。そのため代助は職を求めて電車に乗り込んだ。彼の目には世界は真っ赤に燃えているように見えた。そして自分の頭の中も燃え尽きてしまうまでは、電車に乗り続けようと考えていた。
ここからは独自の見解の域になる。
真っ赤に燃えた世界とは、全体主義に反抗した代助に襲い掛かる試練を意味しているのではないだろうか。そして代助は自分の頭が燃え尽きるまで電車に乗り続けるつもりだった。つまり社会の制裁に破滅するまでは、反抗を続ける決心をしたのだと考えられる。
その先については、ぜひ三部作最終章『門』を読んでいただきたい。
■関連記事
➡︎夏目漱石おすすめ作品10選はこちら
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら