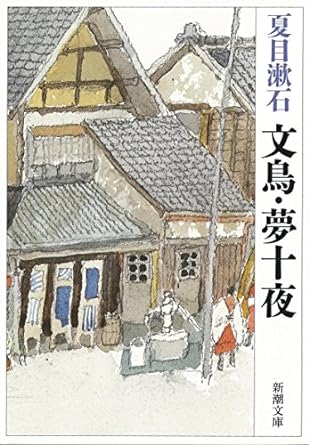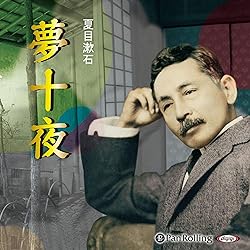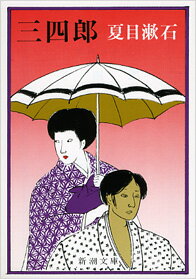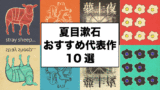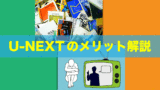夏目漱石の小説『夢十夜』と言えば、東京朝日新聞に連載された短編小説です。
「こんな夢を見た」という有名な書き出しで綴られる10遍の物語で構成されています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 夏目漱石(49歳没) |
| 発表時期 | 1908年(昭和41年) |
| ジャンル | 短編小説 幻想小説 |
| ページ数 | 33ページ |
| テーマ | 死生観 芸術論 明治時代の欧化 |
あらすじ
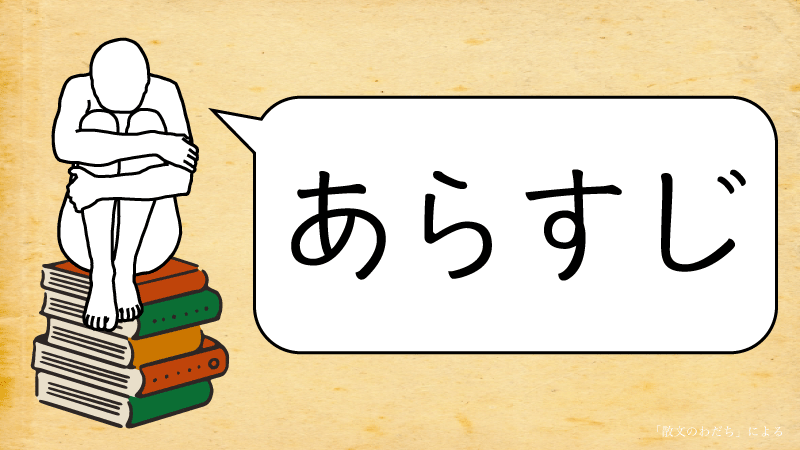
第一夜
死ぬ間際の女に百年待つよう頼まれた主人公は、女の墓の横で待ち続けます。その年月の長さに、女に騙されたのではないかと疑心暗鬼になったりもします。しかし、一輪の百合が咲いたのを見て、いつの間にか百年が過ぎていたことに気付くのでした・・・
第二夜
無を悟れないことを和尚に馬鹿にされた主人公は、悟りを開いて和尚を斬るか、悟りを開けず切腹するかの二択を自らに課し、ついに無には辿り着けないのでした・・・
第三夜
主人公は盲目の子供を背負って歩いているのですが、どこか不気味な彼を捨てて帰ろうと考えています。やがて一本の杉の木の前に辿りつくと、「御前がおれを殺したのは今からちょうど百年前だね」と子供が背中で言うのでした・・・
第四夜
手ぬぐいを蛇に変えると言って、爺さんが笛を吹いています。今になる、蛇になる、と言いながら川の中に入っていき、再び上がってくることはありませんでした・・・
第五夜
戦に敗れ捕虜となった主人公は、恋人に会いたい希望から、明け方まで命を許されます。恋人は馬に乗って必死に駆けつけようとしますが、鶏の鳴く声に時を焦り、淵へ落ちてしまうのでした・・・
第六夜
明治時代なのに、生きた運慶が仁王像を彫っています。運慶は木の中に埋まっている仁王を掘り出しているのだ、と聞いた主人公は、試しに家にある木を彫り始めるが仁王は出てきません。そこで運慶がまだ生きている理由を悟るのでした・・・
第七夜
行き先の分からない船に乗る主人公は、虚無感から海へ飛び込みます。ところが足が船から離れた刹那に、行き先の判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかった、と後悔するのでした・・・
第八夜
主人公が床屋に行くと、鏡の中は別の世界と繋がっていて、女を連れた庄太郎、疲れた芸者、金魚売りなどが歩いていくのが見えます。しかし振り返ると彼らの姿は見当たらないのでした・・・
第九夜
母は幼い子を連れ、戦地へ赴いた夫の無事を祈って百度参りに出かけます。子供を拝殿に残し、お参りを続ける母。無論、既に夫が死んでいることは知りません・・・
第十夜
好色な庄太郎は、水菓子屋で会った美女に絶壁へ連れて行かれ、飛び降りるか豚に舐められるかを選ばされます。命を惜しんだ庄太郎は、何万という豚に襲われるのでした・・・
Audibleで『夢十夜』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『夢十夜』を含む夏目漱石の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
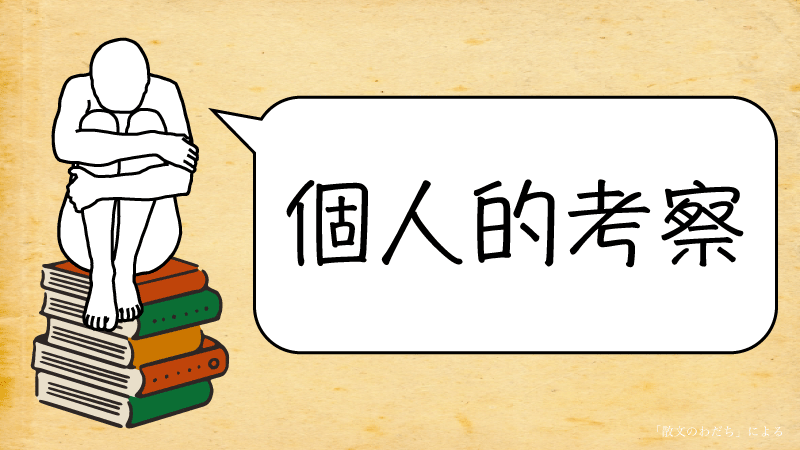
第一夜:なぜ100年過ぎていたのか
「100年待つ」という言葉が、テンプーレート的なロマンチスト像を孕んでいるのは、本作『夢十夜』が後世にもたらした影響でしょう。
死に際の女性に「100年待っていてください」とお願いされた主人公。彼女は100年後に逢いに行くと誓ったのです。その言葉を信じた主人公は、途中疑心暗鬼になりながらも待ち続け、百合の花が咲いたことによって、100年が経過していたことを知ります。
「死んだ女性」と「百合の花」を重ね合わせて描いていることは説明不要でしょう。
- 女性:白い頬、涙が頬を伝う描写
- 百合:白い花びら、露が花びらを伝う描写
まるで対称的な構造になっています。
つまり、百合の花は女性の幻影、もしくは生まれ変わりの役割を果たしています。そのため百合の花が咲いたことが、100年越しの再会をメタファー的に表現していたのでしょう。
また「百合」という漢字は、「百」と「合う」で構成されており、主人公と女性が「100年後」に「再会」することを暗示しています。
今でこそ「人生100年時代」と言われていますが、明治時代の平均寿命は43歳前後でした。つまり100年先とは人間が計り知れない途方もない年月だったのです。
第三夜では、盲目の息子の正体は、100年前に自分が殺した存在(の生まれ変わり)であることが明かされます。ここにも100年というキーワードが登場します。つまり明治時代、もしくは夏目漱石の中には、死者が輪廻転生するまでの年月を100年とする価値観があったのかもしれません。
何故か主人公だけが100年以上生きています。第一夜ではそれが幻想的でロマンチックに描かれます。しかし、第三夜では対照的に、永久に抜け出せない復讐のスパイラル、という着眼点で描かれています。本作『夢十夜』には共通して「死」というテーマが根底にあります。章によって異なる視点で死生観にアプローチしているのが本作の魅力でしょう。
第六夜:運慶が生きている理由
運慶は平安から鎌倉に活躍した仏師で、東大寺の金剛力士像が有名です。ところが物語は明治時代の設定です。とっくに死んでいるはずの運慶が、明治の世で仁王像を彫っているのです。
運慶の常人離れした手捌きを目撃した見物人の1人は、次のような台詞を口にします。
なに、あれは眉や鼻を鑿で作るんじゃない。あの通りの眉や鼻が木の中に埋っているのを、鑿と槌の力で掘り出すまでだ。まるで土の中から石を掘り出すようなものだからけっして間違うはずはない
『夢十夜/夏目漱石』
真っ新な木を削って仁王像を造形しているのではなく、木の中に仁王像が埋まっていて、それを掘り出しているだけだと言うのです。
見物人の言葉を聞いた主人公は、自分も木に埋まった仁王像を掘り出そうとします。しかし、何本の木を彫っても仁王像は見つけられませんでした。その結果、明治の木には仁王像は埋まっていないと悟り、運慶が今日まで生きている理由に気づきます。
この謎めいた物語には、今日の芸術に対する夏目漱石の異議が読み取れます。つまり、明治の木に仁王像が埋まっていないという悟りは、明治文化における芸術性の喪失を意味しているのだと思います。
では、明治から芸術が失われていると夏目漱石が感じた原因は何なのか。
それは見物人の1人が口にした「木の中に仁王像が潜んでいる」という言葉に象徴されているでしょう。
自分で造形するのでなく、存在するものを掘り起こす。それはまるで既存の手法をなぞるだけで、何の新しさも感じさせないニセ芸術を揶揄しているようです。運慶の真似をするのではなく、自分の手法を見つけなければ、真の芸術などは生み出せないということでしょう。
そして、運慶が明治時代でも生きているという不思議。自分だけの手法で新進気鋭の芸術を生み出した者は、いくら時代が移りかわろうが生き続ける、というメッセージが込められていたのではないでしょうか。
なるほど、夏目漱石の文学は100年以上過ぎても生き続けています。
第七夜:大きな船の正体とは
主人公は大きな船に乗っていました。その船の行き先は不明で、毎日太陽が沈んでいくのを追いかけるように西に進み続けています。
船の中には天文学に詳しい者や、ピアノを弾いて唱歌を唄っている者もいます。彼らの様子を見ていると虚無感に襲われ、主人公は死を決意します。ところが、海に身を投げた刹那に一つの悟りを開きます。
自分はどこへ行くんだか判らない船でも、やっぱり乗っている方がよかったと始めて悟りながら、しかもその悟りを利用する事ができずに、無限の後悔と恐怖とを抱いて黒い波の方へ静かに落ちて行った。
『夢十夜/夏目漱石』
この巨大な船とは、いわゆる社会や世間や日常いった類のものだと推測されます。ともすれば主人公は、太陽のサイクルの中を行き先も分からずに進む、そんな人間社会の営みに辟易していたのでしょう。
天文学に詳しい者や、ピアノを弾く者を見て、主人公がつまらない気持ちになったのは、そういった闇雲な人間社会で目的を持つ者に対する嫉妬だと考えられます。ピアノを弾いて唄っている者は、周りのことに頓着せず、船に乗っていることさえ忘れている様子でした。
夢中なる他者を見て、そうなれない自分の見窄らしさに虚無感を覚えていたのでしょう。
あるいは舞台は明治時代、西洋の文化が一気に日本に流入した背景があります。天文学もピアノも、いわゆる西洋の価値観の象徴です。つまり、時代の過渡期に際し、新しい価値観に上手に適合できず、自分の将来に対して不安を感じる当時の日本人の不安が描かれているとも考えられます。
そして、不安や虚無に苛まれ自殺を決行するものの、いざとなれば現世に縋りたくなる人間の脆弱さが感じられます。
第十夜:豚は何を象徴しているのか
庄太郎の道楽は、水菓子屋の店先に腰掛けて、往来の女性を眺めることでした。
ある時、美女が店先に来て買い物をし、庄太郎がその荷物を家まで届けることになります。それから7日間、庄太郎は行方不明になります。なんと庄太郎は、女に絶壁に連れられ、飛び降りるか豚に舐められるか、という不可解な選択を迫られていたのです。命を惜しんだ庄太郎は、7日間豚の大群に迫られます。
この第十夜は、とりわけ多くの解釈が存在します。最も有名なもので言えば、庄太郎が女好きであったことから、好色にハマった男は破滅する、という解釈です。庄太郎の話をする健さんが最後に、「だからあんまり女を見るのは善くないよ」と口にすることからも、確かに納得できます。
ただし作者は夏目漱石です。好色に対する教訓で留まるような主題では、どうも浅はかな解釈な気がします。あえて深読みすれば、次のような解釈も可能ではないでしょうか。
つまり、西洋文化の表層をなぞるだけの日本人の末路を描いているのではないでしょうか。
庄太郎はパナマの帽子を被っていました。当時パナマの帽子は紳士用の正装として流行しました。ハットのような形状の帽子で、無論文明開化によって外国文化が取り入れられたことで正装として扱われるようになりました。つまり、庄太郎はファッションのみ西洋にかぶれている日本人の象徴です。
あるいは正太郎は、女性を見ることを道楽としていました。この「女を見る」行為は単に好色を表現しているだけでなく、物事の表層のみをなぞる当時の日本人の在り方を象徴しているのかもしれません。
表層的な欧化に徹する日本は絶壁に立たされており、飛び降りて破滅するか、豚に舐められるように西洋文化にもまれてしまうか。そういった選択を迫られている当時の日本の状況を、メタファー的に描いているのかもしれません。
『夢十夜』の次に発表された『三四郎』では、「(日本は)滅びるね」という台詞が綴られます。主人公の三四郎が上京する列車の中で、広田先生に聞かされた言葉です。明治時代の表層的な欧化を揶揄する意味があったのでしょう。
以上のことから判るように、夏目漱石は時代の過渡期に際して、自国に合った形で西洋の文化を取り入れようと考えた作家の一人です。ともすれば、庄太郎のパナマの帽子を健さんが貰おうとしている結末は、流行的に欧化したがる日本人を象徴しているのかもしれません。
■関連記事
➡︎夏目漱石おすすめ作品10選はこちら
ドラマ『夏目漱石の妻』おすすめ
2016年にNHKドラマ『夏目漱石の妻』が放送された。
頭脳明晰だが気難しい金之助と、社交的で明朗だがズボラな鏡子、まるで正反対な夫婦の生活がユニークに描かれる。(全四話)
漱石役を長谷川博己が、妻・鏡子役を尾野真千子が担当。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら