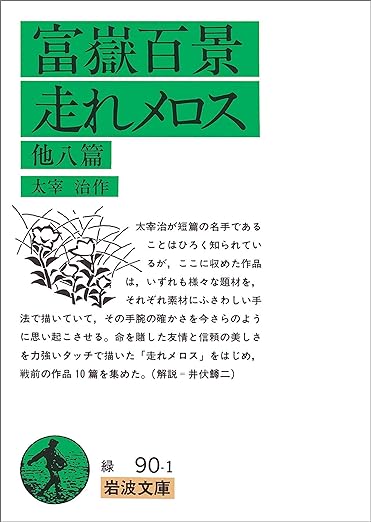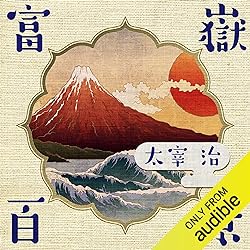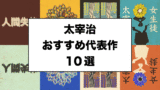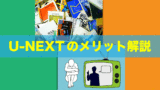太宰治の『富嶽百景』は、御坂峠の旅館に滞在していた作者の 日常を記した作品です。
当時の太宰の精神状態が富士の景観と重ねて描かれる本作は、ファンから人気が高く中期の傑作と言われています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 太宰治(38歳没) |
| 発表時期 | 1939年(昭和14年) |
| ジャンル | 随筆 短編小説 |
| ページ数 | 17ページ |
| テーマ | 太宰の精神の再生 |
あらすじ
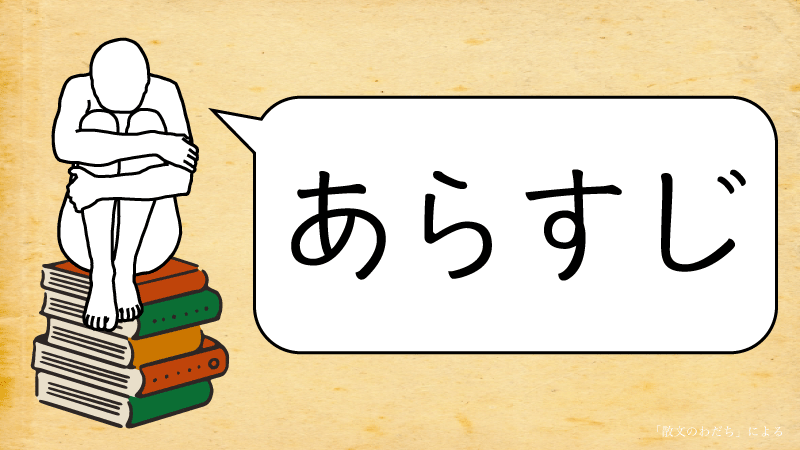
1938年初秋の出来事です。
思いを新たにする覚悟で旅に出た太宰は、師の井伏鱒二が滞在する甲州御坂峠の旅館「天下茶屋」に赴きます。そこは嫌でも向き合わなければならないほど、富士山がよく見える場所でした。まるで銭湯の絵のようにおあつらえ向きな富士山に、太宰はあまり良い印象を抱いていませんでした。
ところが、天下茶屋に滞在した3カ月、井伏との散策や、彼に紹介された縁談相手との出会い、青年たちの訪問、旅館の女将さんや娘さんとの交流を通して、少しずつ富士に対する思いが変化していきます。
甲州を去る直前には、あれだけ嫌悪していた富士に対して「お世話になった」という気持ちさえ芽生えるのでした。
Audibleで『富嶽百景』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『富嶽百景』を含む太宰治の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
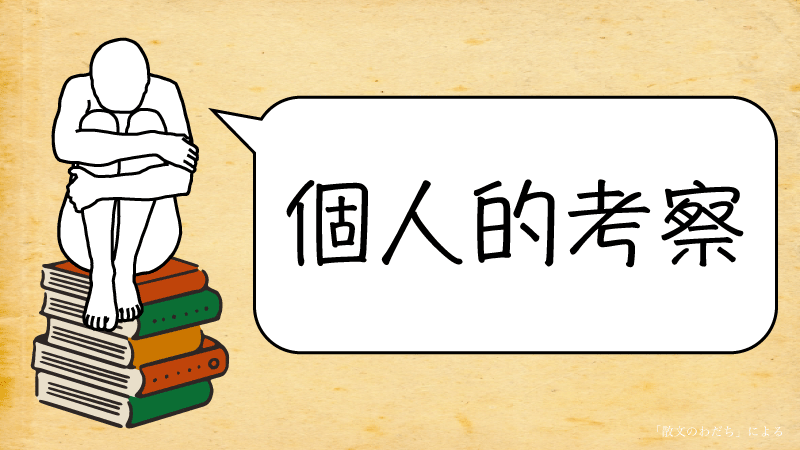
執筆当時の太宰の境遇
本作『富嶽百景』は、作者の精神状態が比較的安定していた中期の傑作と言われています。
物語当時以前の太宰は地の底に落ちていました。鎮痛剤パビナール中毒の治療で精神病院に入院させられます。さらには初妻の不貞行為に打ちのめされ、4度目の自殺未遂を図ります。
その後は周囲の手助けもあり、師である井伏鱒二に新たな結婚相手の世話をしてもらうことになります。縁談が進み、めでたく妻となったのが、太宰が最後まで連れ添った美知子です。(愛人は大勢いたが・・・)
本作『富嶽百景』の中でも、井伏鱒二が滞在する御坂峠の天下茶屋を訪問し、彼の世話によって縁談が進む様子が描かれています。美知子との出会いがここに記されていたのです。そして、美知子との出会いによって、当初ネガティブな印象を抱いていた富士が、やがてポジティブな印象に変化していくという、再生の物語になっているのだと思われます。
物語は甲州を去る場面で幕を閉じますが、その後、杉並区の井伏宅で結婚式を挙行します。この時、太宰は仲人を渋る井伏に対して、「結婚誓約書」という文書を提出しています。これまでの乱れた生活を反省、家庭を守る決意をし、「再び破婚を繰り返した時には私を完全の狂人として棄てて下さい」と記したのです。
また天下茶屋に滞在していた3カ月の甲府時代に、「黄金風景」「女生徒」「葉桜と魔笛」「八十八夜」「畜犬談」などを著し、作品集『愛と美について』と『女生徒』の2冊を出版しています。当初の滞在目的は初の長編作品『火の鳥』の執筆でしたが、結局完成することはなく、今ではファンの間で人気の高い未完の傑作とされています。
美知子との結婚により太宰の精神状態はかなり安定し、『駆け込み訴え』や『走れメロス』など代表作を次々に生み出していきます。
いわば本作『富嶽百景』は、自己破滅的な初期から比較的安定的な中期への転機となった、架け橋のような作品なのです。
物語の位置関係(山梨県)

作中に登場する「富士山」「天下茶屋」「甲府」「吉田」の位置関係は上記になります。
太宰が滞在した旅館「天下茶屋」は現在でも茶屋を経営しています。
2階には「太宰治文学記念館」が設置されており、太宰が逗留した部屋を再現しています。
是非、太宰ファンは訪ねてみてください!
「酸漿に似ていた」とは?
人々との出会い、順調な縁談によって、富士の見え方が変化すると解説しました。
ところで、旅館から去る最後に目にした富士山が「酸漿に似ていた」という比喩で表現されます。果たしてどういう思いが込められているのでしょうか。
酸漿の花言葉は「偽り」です。ともすれば、太宰の精神が再生していった最後に、そのような否定的な比喩を用いるのは相応しくないように感じます。ただし、ここで富士山が一体何を象徴しているかを考えると、その真相が見えてくるかもしれません。
太宰は当初、富士山に対して否定的な考えを持っていました。歌川広重の浮世絵に描かれる富士山は実物とは大きく異なり、皆が富士山に先入観を持っていることを指摘します。世間が持つ俗っぽいイメージが富士山を造形しているのであって、ともすれば、太宰にとっての富士山とは大衆や世間の象徴なのかもしれません。
だからこそ太宰は富士山の存在を認められず、どこか否定的な考えを持っていたのでしょう。その巨大すぎる(世間の)存在に辟易していたのかもしれません。
最終的に精神的な再生を遂げた太宰は富士山を見て、「酸漿に似ている」と表現します。つまり富士(世間)の「偽り」を見抜くのです。
自分を圧迫していた巨大な富士(世間)は、それほど大きな存在ではなかったと気づいたのかもしれません。
あるいは、旅館の女将さんや娘さん、青年や、縁談相手など、人々と関わる中で、世間はそれほど悪い人ばかりではないと、自分の先入観の「偽り」に気づいたとも考えられます。
以上のような解釈をすれば、「酸漿」という比喩も辻褄が合うように思います。
やはり太宰は色男
余談程度に記しますが、本作に描かれる太宰の女性との交流の仕方が、本当にイヤらしいなと感じます。(褒め言葉です)
太宰が宿泊する旅館「天下茶屋」には、15歳の娘さんがいました。太宰が吉田に一泊して帰ってくると、女将さんはニヤニヤしており、娘さんはつんっとした態度でした。彼女たちは太宰が外で女性と遊んでいたと思い込んでいるわけです。娘さんがつんっとした態度である時点で、彼女が太宰に好意を抱いていることが分かります。
とは言え、太宰は縁談相手が決まった身ですし、ましてや15歳の娘さんの意地らしさですから、適当にあしらっておけばいいでしょう。されど太宰は娘さんの機嫌が治るまで、昨夜の潔白を詳細に説明します。女性には分け隔てなく優しく接する太宰の性分が表れています。
あるいは娘さんが1人で店番をしている折に、彼女が泣いていることがありました。原因は分かりませんが、客に怖いことでもされたのかもしれません。それ以来、太宰は彼女が1人で店番をしている時に客が来たら、2階からわざわざ降りてくる、という配慮をします。
気遣いが行き届いていて優しい。そりゃあ多くの女性に惚れられるわ、とほくそ笑んでしまいました。まあ、それが結果的に彼を破滅に追い込むわけですが・・・。
余談でした。
■関連記事
➡︎太宰治おすすめ代表作10選はこちら
映画『人間失格』がおすすめ
『人間失格 太宰治と3人の女たち』は2019年に劇場公開され話題になった。
太宰が「人間失格」を完成させ、愛人の富栄と心中するまでの、怒涛の人生が描かれる。
監督は蜷川実花で、二階堂ふみ・沢尻エリカの大胆な濡れ場が魅力的である。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら