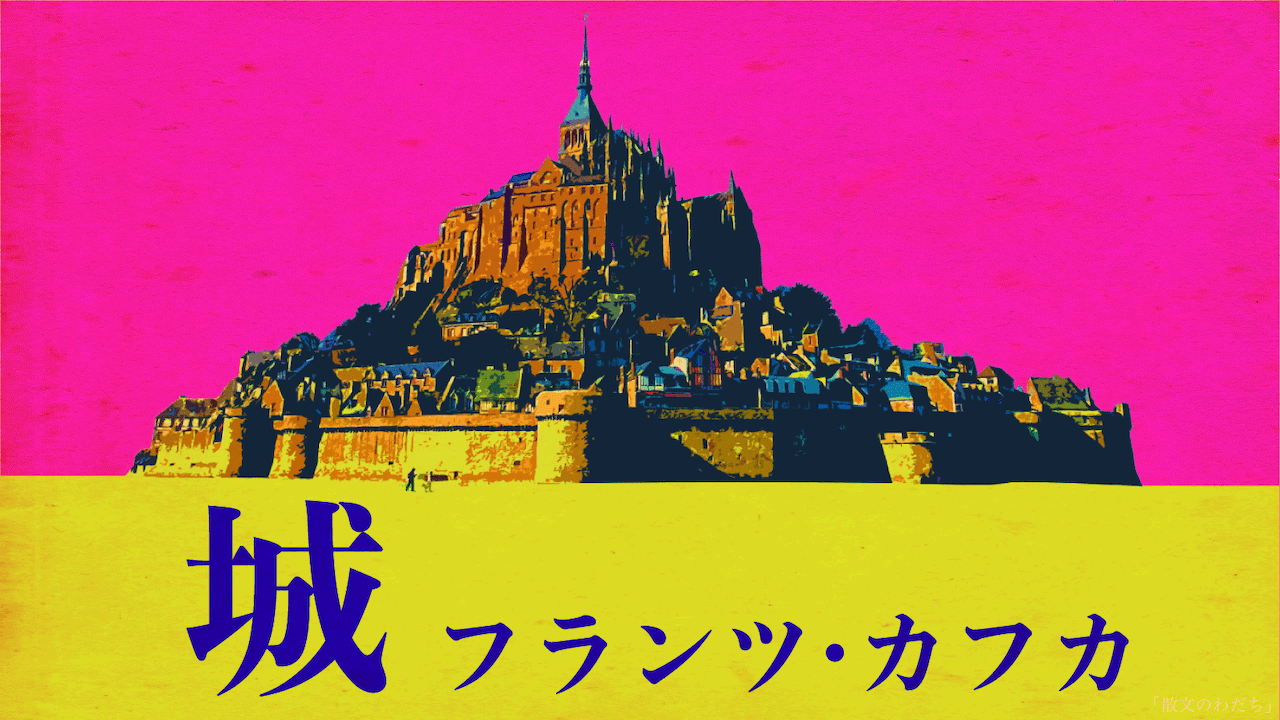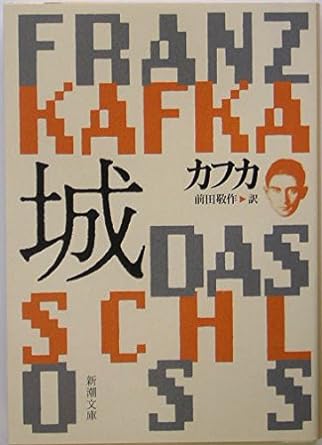カフカの小説『城』は、死後に発表された未完の長編です。
『失踪者』『審判』と併せて、長編三部作と呼ばれています。
城の測量師として雇われたKが、永久に城に入れない不条理が描かれます。
本記事では、あらすじを紹介して上で内容を考察します。
目次
作品概要
| 作者 | フランツ・カフカ(40歳没) |
| 国 | ドイツ |
| 発表時期 | 1922年執筆 1926年(死後に刊行) |
| ジャンル | 長編小説 |
| ページ数 | 630ページ |
| テーマ | 異邦人 現代社会の疎外感 社会的存在の権威 |
あらすじ

Kは夜遅くに雪深い村にやって来た。だが城の許可なしに宿泊できないと告げられる。そこで城に問合せると、Kは城に雇われた測量師だと判明する。
翌日Kは雇用にまつわる手続をするために城を目指す。だが城への道は閉ざされている。許可なしには入場できないのだ。そこで城の執事に電話をかけると、許可は降りないと伝えられる。この不可解な状況において、Kは測量師でありながら仕事を与えられず、村人からも忌避される。
それからKの奔走が始まるが、全ては徒労に過ぎなかった。1つ確かなのは、城は絶対的な権威で村を支配しているということだ。城の役人と愛人関係にあるフリーダは価値のある存在と見なされ、役人に逆らったアマーリアは村八分に遭っている。
そんな権威と秩序に丸め込まれた村で、Kはいつまで経っても城に辿り着けず、翻弄され続けるのであった・・・・
Audibleで『城』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『城』を含むカフカの作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼30日間無料トライアル実施中!
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

未完の長編小説
カフカの作品は、生前に数冊しか発表されていない。本作『城』を含む長編三部作は、いずれも未完の原稿を死後に再編したものだ。
つまり生前は殆ど評価されず、死後に再評価された作家と言える。
そんなカフカは、労働に忙殺されながら、合間を縫って執筆活動を行なっていた。実際に代表作『変身』は多忙のため思い通りに完成できなかったと言及している。
さらに追い討ちをかけるように結核を患い、長期療養と職場復帰を繰り返すようになる。そんな状態で本作『城』の執筆を開始するが、やがて病状の悪化で勤務不可能になり、『城』の執筆も途中で放棄される。以降は実家とサナトリウムで療養生活を送り、1924年に40歳という若さでこの世を去った。
未完のまま放棄された『城』の原稿は、大判のノート6冊に及ぶ量だった。遺言では死後に全ての原稿を焼却するよう伝えていたが、友人ブロートはその意図に反し、未完の原稿を再構成して出版に向けて動き出した。そしてカフカが生前に「城の物語」と表現していたことから、『城』というタイトルが付けられた。
このような経緯で発表されたのだが、物語が未完であることに変わりはない。城に辿り着けぬまま疲弊したKが、酒屋の女将と会話をして、とぼとぼ店を出ていく場面で唐突に終了する。
果たして、Kの運命はその後どうなる想定だったのか?
実はカフカは生前に友人のブロートに、次のような結末を伝えていた。
Kは城との戦いに疲れ果てて病気を患う。村に住む権利は与えられないが、情状酌量として村で働くことを許される。しかしKは病気によって息絶えてしまう。
結局Kに対して城の門は開かれぬまま、ついには病気で死んでしまう想定だったようだ。
とはいえ不可解な点は山積みのままだ。一体Kは何者で、城は何を象徴し、そしてなぜKは城に辿り着けないのか。
次章からは物語を詳しく考察していく。
Kの正体/異邦人カフカ
物語は曖昧性を極めている。最も曖昧なのはKが何者かということだ。
Kの存在の曖昧性
Kは村の住人ではなく、測量師で雇われるために外部から訪れた異邦人である。だが城はKが測量師であることを黙認するものの、実際的な承認は下さない。そのためKは測量師でありながら一向に仕事を与えられない。従って村人たちはKの存在を認めようとしない。
そこでKは自分の存在価値を証明するために城の訪問を試みるが、道は閉ざされている。城に辿り着くことも、長官のクラムに会うことも叶わない。
この物語の構成は、長編三部作の1つ『審判』と非常によく似ている。『審判』の主人公はある日突然見覚えのない罪状を突きつけられ、誤解を解こうと奔走するが、決して裁判所の門が開くことはなく、いつまで経っても無罪を証明できない。
いずれも目的のために特定の対象へ接近しようと奮闘するが、どうしても辿り着けない、という構造が取られているのだ。
これら二作品に共通する不可解な状況は、社会の権力構造の中で、個人の権利が剥奪される不条理な運命を想起させる。城は確かに存在し、向こうの気まぐれ次第で一方的に命令は下されるが、こちらから近づいて権利を主張する術は閉ざされているのだ。
K自ら城に接近できない以上、測量師という存在価値を立証できず、村人の一員になることも許されず、永久に何にも属せない異邦人のままということだ。つまりKが何者かを定義する要素が存在しないのだ。
このような存在の曖昧性、異邦人の感覚は、作者自身が抱えていた問題だと考えられる。
カフカが抱く異邦人の感覚
なぜカフカは異邦人の感覚を抱いていたのか。その背景には彼の出生が関係している。
カフカはユダヤ人だが、正統なユダヤ教徒ではなく、西洋化されたいわゆる「西方ユダヤ人」だった。そのためユダヤ教徒でもキリスト教徒でもない、という曖昧な境遇にあった。
また父がチェコ語を母国語とするのに対し、母はドイツ語を母国語とし、カフカ本人はチェコに住みながらドイツ語を母国語とする複雑な境遇にあった。さらに当時のチェコ・プラハは、オーストリア=ハンガリー帝国領で、その複雑な支配下において、チェコ人・ドイツ人・オーストリア人、そのいずれでもないという曖昧な民族意識で育った。
そして決定的にカフカを異邦人たらしめたのは父だった。封建的な父の権威に丸め込まれて育ったカフカは、絶えず家庭に居場所がないという感覚を抱いていたのだ。
要するに、宗教・民族・家族という、人間のアイデンティティを司る集団から阻害されたカフカは、何にも属せず、自分が何者であるか定まらない状態だったのだろう。
こうした存在の曖昧性が、村にも城にも属せない異邦人Kに投影されているのだろう。そして測量師という職業を通して、自分の存在価値を確立しようと奮闘していたわけである。
そして、Kが存在価値を証明するために、職業に固執したのが、本作最大のテーマである。
職業だけが存在意義になった社会
職務とは別な日常生活とは、一体なんであろうか。(中略)ときには職務と生活が入れ代わっているのではないかという気がするほど交錯していた。
『城/カフカ』
これは城に支配された村人の生活を端的に言い表した文章である。そしてKも例に漏れず、測量師という職業に固執することで、自分の存在価値を証明しようと必死になっていた。
要するに、「職業」だけが唯一の存在意義になった現代社会への皮肉を訴えているのだろう。それはカフカ文学に共通するテーマでもある。
例えば、代表作『変身』の主人公は、過酷な労働に辟易し、いっそ放棄したいという惰気を抱いたことで、目覚めると巨大な毒虫に変身していた。つまり職業だけが唯一の存在意義になった社会で、職業を放棄した者は、社会的な存在価値を剥奪され阻害されてしまうのだ。
同様に本作『城』においても、測量師という存在価値を立証できないKは、村人から敬遠され軽蔑される。いわば社会的な存在意義を失った毒虫の状態にあるのだ。
そして職業が人々の存在意義を司る以上、そこには社会的な権力構造が存在する。つまり村人の存在意義は、城という権威に完全に委ねられているのだ。
何人も権威に逆らうことは許されない。実際に権威に逆らったアマーリアという女性は、社会的な存在価値を剥奪され、村八分を受ける羽目になった。しかも城が直接手を下したわけではなく、城に逆らったという行為そのものが、村人たちに敬遠の念を芽生えさせ、アマーリアを阻害させたのだ。
つまり城はその直接的な実行力以上に、市民の盲信によって力を保持する、あまりに秩序立った権力構造になっているのだ。
そして一度でも社会的な存在価値を失えば、二度と名誉回復する余地は与えられない。なぜなら城から村人に力を行使することはあっても、村人から城に接近することは不可能だからだ。
Kや村人が城に接近できない理由は、城の役人もまた実態を持たない曖昧な存在だからだ。
「城」の長官であるクラムを目にした村人は殆どいない。実際に目にした者はいるが、彼らはクラムの容貌を覚えていない。なぜなら村人にとって城の役人は、「城」「役人」「長官」という実態のない肩書きによってのみ存在しているからだ。村人は実態のない権威によって支配され、実態がない以上その存在に接近する術は閉ざされているのだ。
要するに、現代社会において、権威に逆らったり職業を失うことは社会的な死を意味し、その権力構造は実態のない力で市民を服従しているということだ。
自己の確立をめぐる闘い
前述した通り、「城」の権威に逆らう者は、社会的な存在価値を剥奪される。その例がアマーリアの家族の悲運である。
アマーリアの家族は何不自由ない靴屋職人だった。ところがある時、アマーリアが役人に逆らったことで、彼女の家族は社会的な死を迫られる。その役人はアマーリアを見染め、下劣な手紙を寄越して彼女を「城」に呼びつける。恐らく情欲に任せた卑劣な命令だったのだろう。だがアマーリアは手紙を破いて使用人の顔に投げつけて命令に反く。それが原因で彼女の家族は村八分を受ける羽目になった。
このアマーリアの反抗を、姉のオルガは「英雄的な行為」と言及している。普通の人間なら悲惨な運命を恐れて、役人の命令に従うのに、アマーリアは個人的な意志を優先したのだ。
この出来事から読み取れるのは、人間は「個人的な存在価値」「社会的な存在価値」という相反する二つの権利を有するということだ。
殆どの人間は悲運を恐れて、社会的な存在価値を優先する。ところがアマーリアは、役人の下劣な手紙に対して、個人的な感情を優先した。その結果、社会的な存在価値を剥奪された。
個人的な意思を優先する行為。それは自己を確立する行為であると同時に、権威に逆らい、社会的な存在価値を剥奪される行為でもある。
要するに本作『城』は、個人と社会いずれの存在価値を優先すべきか、という命題に対して、多くの人間は権威に屈服して個人を放棄する、という答えを提示しているのだろう。
そして社会的な存在価値を失った者に、二度と城の門は開かない。Kは城に辿り着けない。
■関連記事
➡︎【必見】カフカおすすめ代表作5選
映画『変身』がおすすめ
カフカの代表作『変身』は、2012年に映画化され話題になった。
目覚めたら巨大な毒虫に変身していた男の悲劇と孤独が、衝撃的な映像で描かれる。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら