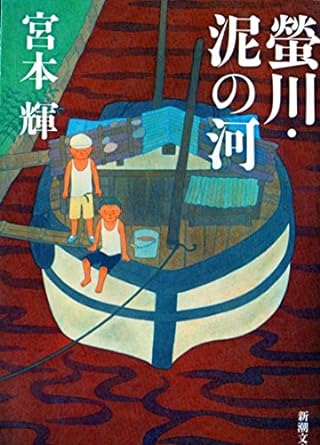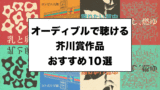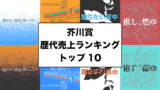宮本輝の小説『螢川』は、芥川賞を受賞した作品です。
『泥の河』『道頓堀川』と合わせて「川三部作」と称されています。
長らく芥川賞の選考委員を務めていた宮本輝。審査する当の本人が受賞した作品にはどのような主題が描かれているのでしょうか。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 宮本輝 |
| 発表時期 | 1977年(昭和52年) |
| ジャンル | 中編小説 |
| ページ数 | 92ページ |
| テーマ | 生死の対比 陰鬱とした思春期像 父子の対立 |
| 受賞 | 芥川賞 |
| 関連 | 1987年に映画化 |
あらすじ

中学二年生の竜夫の父は、戦後はやり手の実業家でしたが、いつしか事業が停滞して家族は窮するようになりました。そんな矢先に父は脳溢血で倒れてしまいます。竜夫は父に思春期特有の生々しい恐ろしさを感じており、あまり見舞いには行きませんでした。
そんな竜夫には関根という親友がいます。関根は同級生の英子が好きで、彼女と同じ高校に進学するために猛勉強しています。ところが彼の父は息子に家業を継がせるために進学を反対しています。そのことで関根は父と喧嘩しているようでした。
実は竜夫も英子のことが好きなのですが隠していました。しかし、ある日関根に問い質されて、自分も英子が好きであることを白状します。すると関根は大事にしていた英子の写真を竜男にあげ、一人で川釣りに行きました。そして、関根は川で死体となって発見されます。
「4月に大雪が降った年には、川上に蛍の大群が現れ、その様子を見た男女は固く結ばれる」という伝承がこの土地に残っています。
親友が死に、父親も死んだその年、4月に大雪が降ります。竜夫は村の銀蔵爺さんと母親と英子を誘って、一か八か蛍を見に川辺へと向かいます。散々歩いても兆しはなく、殆ど諦めた頃に、蛍の大群が物凄い光彩を払って舞い上がります。竜夫には蛍の大群の光が英子の体の奥深くから生まれているように見えました。母親が川縁にいる竜夫と英子を覗き込むと、そこには蛍が織りなす人間の形の光があったのでした。
Audibleで『螢川』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『螢川』を含む宮本輝の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルで聴く芥川賞おすすめ10選
個人的考察

父と竜夫の張り詰めた関係性
北陸の荒涼とした風土の中で、登場人物のあまりに繊細な心情が描かれていました。物事を受け入れるには敏感すぎる思春期の竜夫は、最も受け入れがたい近しい人間の死を立て続けに経験します。
竜夫が父の死に真剣に向き合おうとしなかったのは、無惨な父親から逃れたいという心情の表れでしょう。
かつて父親は北陸で有数の成功者として名を轟かせていました。ところが事業は行き詰まり、借金だけを増やして没落してしまいます。脳溢血で倒れたのは長年の飲酒が影響しているようで、事業に失敗した父がヤケになっていたことが推測できます。そういった精神的にも年齢的にも衰弱していく父に対して、竜夫が嫌悪感を抱いていたのは確かです。
竜夫は確かに父を避けていた。老いて憔悴した父が嫌いだったのである。
『螢川/宮本輝』
体の半分が動かなくなり、殆ど言葉も利けなくなった父を見て、竜夫は得体の知れない恐怖に似た感情を抱きます。病室で衰弱しきった父は子供のように泣きながら竜夫のベルトを掴みましたが、竜夫はまるで逃げ出すように父のを手を振り解いて帰ってしまいます。
父の危篤を知り病院へ向かう道中、竜夫は若き日の父の写真を思い浮かべていました。父と友人が初めて女性と遊んだ日に撮った18歳の頃の写真です。そこには衰弱した現在の父とは対照的な、精力が盛んな年頃の面影がありました。竜夫はそこに誇り高い父の幻影を見出していたのではないでしょうか。
子供にとって父親とは威厳があり、弱みを見せない、人間としての強さの象徴だと思います。そんな父が衰弱し、涙さえ流す様子に思春期の少年が真正面から向き合えるわけがなく、若き日の父の幻影によって、現実の父親からの逃避を試みていたのだと思われます。
生と死の対比が美しい
親友の死と父の死を立て続けに経験した竜夫は、蛍に対する執着を強く持っていました。いわゆる生に対する執着を象徴しているのではないでしょうか。
四月に大雪が降る年には、大量の蛍が一斉に交尾をするので、幻想的な光の風景が見れます。それは新たな命が誕生するという意味での「生」のメタファーだったのでしょう。
- 妊娠した妻がつわりに襲われた時に彼女の体が青光りしているのを竜夫の父は見た
- 蛍の大群の光が英子の体の中から生み出されているように竜夫は感じた
いずれも、人間の生命力を蛍の幻想的な光と重ね合わせて表現していることが判ります。
父や親友が儚い死の象徴として描かれる一方で、英子こそが生の象徴であり、性の対象であり、新たに生命を生み出す存在だということになります。
父の友人は、父が事業で失敗したことに対して「運の恐ろしさ」を引き合いに出しました。事業の失敗も脳溢血も、あるいは関根が親に家業を継ぐように強いられていたのも、ある種の抗うことができない悪運です。そしてその運命は最終的に彼らを死へと導きました。
その一方で、竜夫の父は前妻を捨て、生命を宿した千代を妻に選んだという過去があります。抗うことのできない死の運命とは対照的に、生命の系譜を自分の意志で選んだのです。その選択は幻想的な光となって闇夜を照らし、竜夫という新たな生命を地上に宿しました。そうして竜夫もまた、英子という新たな光を自分の意志で選んだのでしょう。
抗うことの出来ない死の運命と対比させて、生命を生み出すことの美しさを表現した作品だったのではないでしょうか。四月まで続く長い冬の陰惨たる風景を、生命の交配が新緑の季節へと押し進める、その凄まじいエネルギーに圧巻させられます。
思春期の葛藤を乗り越える成長過程
思春期の少年少女に焦点を当てたことで、生と死の対比がよりリアルに表現されているように思われます。
冒頭では、中学生になった竜夫が自慰行為を覚え、英子の白い肌や香りに熱情的なフェロモンを感じている描写が何度も記されます。衰弱する父への嫌悪感とは対照的に、思春期の性の興奮が描かれているのです。
思春期の竜夫は小さい頃は親しかった英子のことを避けていました。性の興奮が生命力の根源であると同時に、別の側面では罪悪感になり得る繊細な年頃です。生きることへの執着と罪の意識が密接に絡み合っているのです。一歩間違えれば破滅してもおかしくない、張り詰めた精神状態を思春期の少年は抱えているのです。その不安定な精神状態を乗り越えた先に、闇夜を照らす生命の輝きが待っているのでしょう。
つまり「蛍の大群を見た男女は固く結ばれる」という伝承は、竜夫が思春期の葛藤を乗り越え、英子によって愛を知り、生命の輝きを放つまでの成長過程を象徴していたのでしょう。
一方で親友の関根は突然死んでしまいました。具体的な原因は語られませんでしたが、父とのいざこざや、英子への恋心など、彼の精神を不安定にする要素はいくつもありました。ひとつはっきりしているのは、関根が英子の写真を竜夫にあげる行為は、生に対する執着の放棄を意味していたということです。
一歩間違えれば破滅してもおかしくない思春期に、愛する人への欲情を諦めた者は、死を選ぶ以外に術がないのかもしれません。
宮本輝の実体験に基づく
『螢川』は私小説ではありませんが、宮本輝が幼少時代に経験した家族の不運不幸が基調となっています。
少年期の宮本輝は父親の事業のために大阪を離れて富山で暮らしていました。しかし富山での事業は失敗に終り、父は多額の負債を残したまま息を引き取ってしまいます。父の死後は、母がビジネスホテルの賄い婦の仕事を始めたようです。そういった自身の不運な10年間を1年間に凝縮して『螢川』を創作したようです。
決して私小説ではないのですが、作者の実体験や原風景を基調にしているからこそ、北陸の暗くて寒い風土(それも他所か移り住んだ者だからこそ感じる鬱屈とした心情)をリアルに描くことができたのでしょう。
改稿前の作品
実は『螢川』は、デビュー作の『泥の河』よりも先に執筆された作品なのですが、完成形に持っていくのに苦労したようで、初稿から著しく改稿されています。
例えば初稿では入院した父と竜夫の関係はよりシビアで、竜夫が父を殺してしまいます。
僕は父を殺した。(中略)ふと目覚めた僕の瞳に飛び込んできたもの――それは醜悪な、遺恨に満ちた、いぎたなく命乞いをしているような、父の泣き顔だった。父は泣いていた。声もたてず涙を流さず、それでもすべての顔筋をひきつらせて、父は泣いていた。(中略)たまらなかった。何もかもを壊したいと思った。僕は吸い寄せられるように父に近づき、ゴム管を抜いて鼻と口を両手でふさいだ。長いあいだ、そうしていた。(中略)数秒間の絶息が、父の最後の力を奪い去ったのだろう。五分後に父は息をひきとった。
『螢川(改稿前)/宮本輝』
いぎたなく命乞いする父の姿に醜悪を見出した竜夫は、破壊的な衝動に駆られます。
衰弱した父に対する見るに耐えない感情とは別に、竜夫は父に対して憎悪を抱いているように感じられます。
改稿後の『螢川』では、サーカスを観にいった帰りの食堂で、父が母を殴る描写が綴られますが、それについてあまり深く掘り下げられることはありませんでした。しかし改稿前では、父の死後には、母が苦しみから解放されるような描かれ方が為されています。父の浮気と暴力、そして大阪の地を離れたことなど、母にとっては父の言動が不幸の元凶だったのでしょう。それを側から見ていた竜夫もまた、父が許せない存在だったのかもしれません。
ラストでは、竜夫は蛍の光を自分自身に見立てます。そして生まれたもの全てが死んでいくことの嘆きと、自らの罪を通して死と対峙する心情によって幕を閉じます。英子の内側から生まれる生命の幻想的な光という結末は改稿後に付け加えられた内容で、本来は死に対する主題を強調して描いている作品だったのです。
生と死は対極にあるわけではなく、生の中に死があり、死の中に生がある。蛍の光は積雪を溶かす生命力とも、儚く消える生命の残骸とも解釈できる故に、宮本輝はどちらの構想を採用するかであぐねていたのかもしれません。
■関連記事
➡︎芥川賞売り上げランキングはこちら
映画『泥の河』がおすすめ
宮本輝の処女作『泥の河』は1981年に映画化され高い評価を得た。
第55回キネマ旬報ベストテンで日本映画1位、日本映画監督賞、助演女優賞を受賞。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
➡︎電子書籍や映画館チケットが買える!
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら