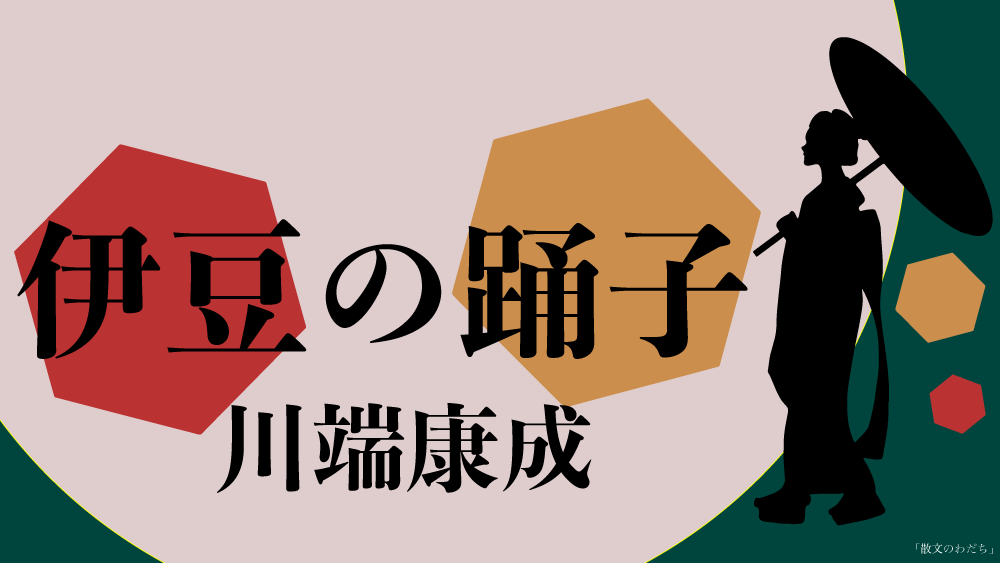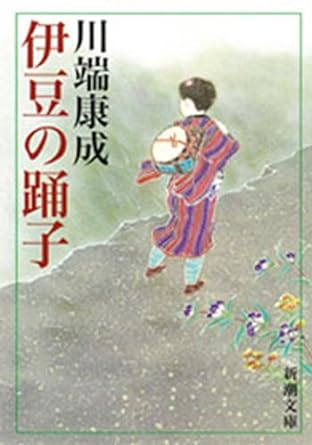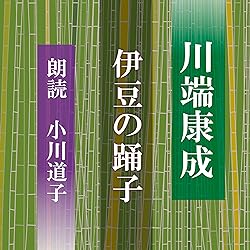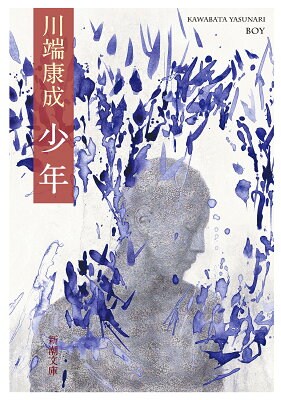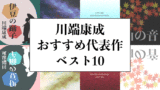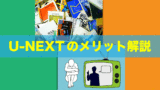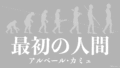川端康成の小説『伊豆の踊子』は、伊豆を旅した19歳の実体験を題材にした作品である。
孤独を抱えた青年が、踊子の少女に淡い恋心を抱く旅情の物語。
これまで6回も映画化され、吉永小百合、山口百恵など、名だたる女優がヒロインを務めた。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察していく。
作品概要
| 作者 | 川端康成(72歳没) |
| 発表時期 | 1926年(大正15年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 33ページ |
| テーマ | 身分の違う恋 孤児根性の憂鬱 青年期の自意識の克服 |
| 関連 | 1963年映画化(吉永小百合) 1974年映画化(山口百恵) |
簡単なあらすじ
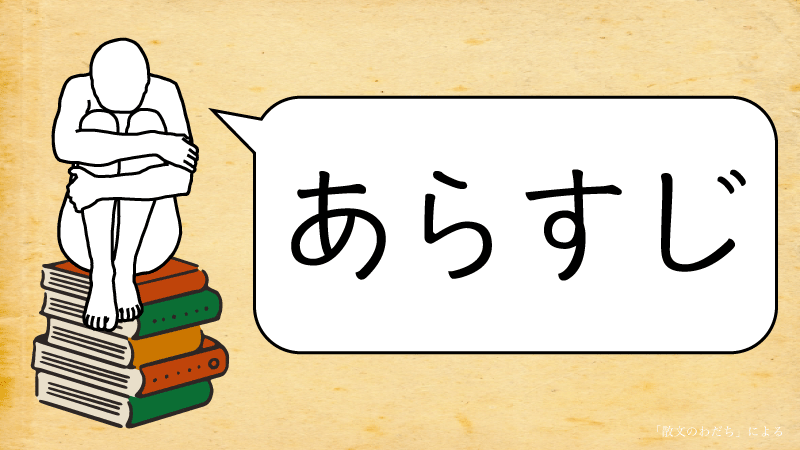
青年は伊豆を旅する道中に、旅芸人の家族と出会い、踊子の少女に惹かれる。そして天城峠から下田まで旅を共にする。
その夜、宴席から太鼓の音が聞こえ、踊子が客に汚される疑念で苦しくなる。しかし翌朝の温泉で、踊子の無邪気な裸体を見て、彼女がまだ14歳の子供だと知り安心する。
旅芸人は差別される身分だ。そんな素性を気にせず、彼らを通じて生身の人間の温かさを知った青年は、旅の目的である「孤児根性」の憂鬱から抜け出せる気がした。
下田に着くと、約束通り踊子を活動(映画)に連れて行こうとする。しかし母親が反対したため、青年は独りで出かける。明日に東京へ帰る青年は、夜の町で遠くから聞こえる踊子の太鼓の音に、わけもなく涙を流す。
旅立ちの朝、踊子は昨夜の化粧のまま、港まで見送りに来ていた。彼女は俯いて何も話さない。やがて船が港を遠ざかると、踊子が白いものを振っているのが見えた。青年は涙を流し、その涙には甘い快さがあった。
Audibleで『伊豆の踊子』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『伊豆の踊子』を含む川端康成の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼30日間無料トライアル実施中!
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
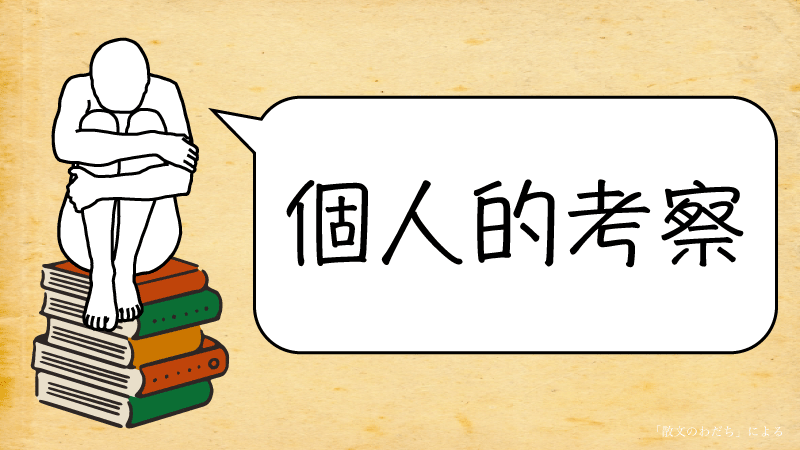
創作背景
「伊豆の踊子」はすべて書いた通りであった。事実そのままで虚構はない。あるとすれば省略だけである
『一草一花/川端康成』
川端康成が伊豆を旅したのは、一高(現東大)時代の19歳の頃である。学生寮の誰にも告げずに出発した8日間の旅だった。道中での踊子との交流は、本人が言及するように、物語で描かれた通りである。
旅の動機については次のように語っている。
私の幼年時代が残した精神の病患ばかりが気になって、自分を憐れむ念と自分を厭う念とに堪へられなかった。それで伊豆へ行った。
『一草一花/川端康成』
「幼年時代が残した精神の病患」とは、幼くして身内を失ったことに起因する。1歳で父親、2歳で母親、7歳で祖母、10歳で姉、15歳で祖父を亡くし、孤児になったのだ。作中では「孤児根性」という言葉が使われ、その憂鬱に耐えきれずに旅に出たと記されている。
そして旅の中で踊子とその家族に出会い、彼らと交流することで、自身の憂鬱から解放されるような、そんな特別な体験をし、その末に悲しく甘い別れを味わったのだ。
伊豆の旅から4年後に、川端は再び湯ヶ島に滞在し、随筆『湯ヶ島での思ひ出』を書いた。そこには高校時代の知られざる同性愛体験や、踊子との思い出が記されていた。その踊子の部分を独立させ、小説へ発展させたのが、本作『伊豆の踊子』というわけだ。
一方の同性愛体験は、のちに『少年』という小説に発展した。
1927年に『伊豆の踊子』の単行本が刊行されるまで、川端は毎年のように湯ヶ島を訪れた。転地療養で湯ヶ島に訪れた梶井基次郎に旅館を紹介したのがきっかけで、『伊豆の踊子』の校正は彼が担当した。
以上の経緯で誕生した『伊豆の踊子』は、初期の代表作であると同時に、川端作品の中で最も人気が高い。計6回も映画化され、吉永小百合や山口百恵など、名だたるキャストがヒロインを務めた。
吉永小百合がヒロインを務めた映画は、歴史に残る名作と言っても過言ではない。若き日の吉永小百合が本当に美しいので、ぜひチェックしていただきたい。
U-NEXTなら31日間無料トライアルで鑑賞できます。
トライアル期間中に解約すれば料金は一切発生しないので、ぜひ映画『伊豆の踊子』をチェックしてみてください。
身分の違いによる共鳴
■旅芸人は差別されていた
旅芸人とは、その名の通り、旅をしながら芸を披露して金を稼ぐ職業である。現在の芸人や芸能人の源流にあたるが、今のように華やか存在でなく、近代に至るまで差別対象だった。
モノや財を生み出す農民や商人や職人は、社会にとって不可欠な存在だ。一方で大道芸などの娯楽は、極端に言えば無くても困らない。そういう理由で、身分制度が厳格だった江戸時代には、彼らは卑しい職業とされ、「河原乞食」とまで蔑まれていた。
作中では、天城峠の茶屋の婆さんが、旅芸人のことを侮辱する。宿の女将さんも、「あんな者にご飯を出すのは勿体無い」と毒づく。また道中で通りかかった村の入り口には、「物乞い旅芸人村に入るべからず」という立札があった。彼らがいかに差別されていたかが判るだろう。
さらに旅芸人は、もちろん芸を披露するのが主であるが、売春も行なっていた。むしろ世間からは、その目的で認識されていたようだ。作中には、踊子が男性客に汚される疑念に青年が胸を痛める場面がある。それは彼らが暗黙の了解で売春をしていたという通念のためだ。しかし踊子の場合はまだ14歳の少女であったため、春を売る年齢ではないということで、青年は安心したのだ。
■青年が旅芸人に惹かれた理由
主人公の青年は、東大の前身である一高の学生だ。旅芸人との身分の違いは明らかである。
川端自身、両親が早死にしたため経歴はややこしいが、彼が育った母方の実家は地主だった。そもそも当時は恵まれた家柄の人間でないと、大学には進学できないだろう。
だが川端の場合は15歳までに、全ての肉親と死別し、彼は孤児になった。親戚たちは優しく世話をしてくれたみたいだが、わがままを言えるような温かい繋がりは失われた。そのため、常に他人の顔色を窺い、心を閉ざす内向的な性格になったようだ。
こうした孤独感や疎外感を、彼は「孤児根性」と呼んだ。その憂鬱から逃れるために伊豆へ旅に出たのだ。そこで出会ったのが旅芸人の家族だった。前述した通り、彼らは社会から差別される存在だ。しかし「孤児根性」を抱える川端にとっては、素性は違えど、同じく疎外感を抱える彼らに、親和を感じたのかもしれない。
好奇心もなく、軽蔑も含まない、彼等が旅芸人という種類の人間であることを忘れてしまったような、私の尋常な好意は、彼等の胸にも沁み込んで行くらしかった。
『伊豆の踊り子』
疎外感という名の親和は、旅を通して一層深まり、身分を超えた生身の人間としての繋がりへと発展する。血縁を失った孤児の川端は、その失われた温もりを彼らの中に見出していたのかもしれない。
また川端は次のように言及している。
いい人だと、踊子が言って、兄嫁が肯った、一言が、私の心にぽたりと清々しく落ちかかった。(中略)平俗な意味での、いい人という言葉が、私には明りであった。湯ヶ野から下田まで、自分でもいい人として道づれになれたと思う、そうなれたことがうれしかった。
『湯ヶ島での思ひ出/川端康成』
川端は孤児の境遇を憐れむと同時に、そのせいで歪んだ性格を嫌っていた。そんな卑屈な自意識に囚われた彼は、踊子が「いい人」だと言ってくれたことで、自分を素直に肯定することができたのだろう。彼らに認められることで、川端はひと時でも、孤児という自意識から解放されたのかもしれない。
青年が踊子に抱いた想い
踊子と旅の道連れになる以前から、青年は彼女の美しさに惹かれていた。しかし青年はそれを恋心ではなく、「旅情」という曖昧な言葉で表現している。
茶屋の婆さんが、「彼らはどこにでも泊まる」と売春をほのめかした場面では、青年はそれなら踊子を自分の部屋に泊めようか、という色欲の感情を抱く。そういう意味で、この時点では純粋な恋心ではなく、単に肉体的な美に惹かれていたのだろう。
しかし踊子が処女だと気づいた時点で、青年の想いは明らかに変化する。踊子が男性客に汚される疑念、しかし彼女が春を売るには幼すぎる事実に、一喜一憂するのだ。踊子に対して、肉体的な美を越えて、より内面的な美として好意を抱き始めている証拠だ。
踊子のハニカミや羞らい、天真爛漫な幼さ、花のような笑顔、袴の裾を払ってくれたり下駄を直してくれる献身的な真心に、青年の想いは確実に強くなっていく。しかし青年は決して恋という甘い感情を認めない。
東京へ帰る前日、踊子を活動に連れていく約束は、母親の反対で叶わなかった。仕方なく独りで出かけた青年は、夜道で涙を流す。青年はそれを「わけもなく涙がぽたぽた落ちた」と説明する。この涙に理由はないと自分に言い聞かせることで、踊子への恋心を無理に否定しているように見える。
こうした心の矛盾は、青年の自意識の強さによるものだろう。旅芸人との身分を越えた交流によって、彼は憂鬱からの解放を実現した。そういう意味で、生身の人間としての親和に身分など関係ない。しかし恋となれば別だ。東大に通うエリート青年と、卑しい踊子とが、一緒になる運命は端から存在しない。言い換えれば、恋をしたとて、失恋に終わることは判り切っているのだ。だから青年は、自らの甘い恋心を否定し、叶わぬ恋の運命に引きずられるのを避けていたのだと考えられる。
別れの朝、旅芸人は昨夜の宴会が遅くまで続いたので、男以外は見送りに来なかった。ところが船着場に到着すると、踊子が昨夜の化粧のまま待っていた。その瞬間に青年の胸中は感情的になるが、それを露わにしない。お互い殆ど言葉を交わさぬまま、船に乗り込んでしまう。二人の別れは至って冷静なものだった。しかし遠ざかる船に向かって、踊子が白いものを振る姿を目撃した時に、とうとう青年は感情を抑えられなくなり、船室に入って涙を流す。青年はその涙を「わけのない涙」と誤魔化さない。別れの悲しみをはっきり自覚している。その時に初めて、青年は踊子に対する恋心を認めたのではないだろうか。
身分の違いを自覚しているからこそ、青年は恋心を自意識の檻に閉じ込めていた。しかし最後には、そんな自意識も消し飛んで、素直な恋心が溢れ出たのだろう。どちみちそれは失恋を意味するのだが、同時に過剰な自意識を克服できたため、彼は悲しみの涙に快い甘さを感じていたのだと考えられる。
身分の違いによる儚い恋だけなら、俗っぽいテーマに過ぎない。しかし青年期の複雑な心理を描くことに成功している点で、本作は唯一無二である。
■関連記事
➡︎川端康成おすすめ代表作10選
映画『伊豆の踊子』おすすめ
川端康成の代表作『伊豆の踊子』は、6回も映画化され、吉永小百合や山口百恵など、名だたるキャストがヒロインを務めてきた。
その中でも吉永小百合が主演を務めた1963年の映画は人気が高い。
撮影現場を訪れた川端康成は、踊子姿の吉永小百合を見て、「なつかしい親しみを感じた」と絶賛している。
➡︎U-NEXT無料トライアルで鑑賞できます!
・見放題作品数No.1(26万本以上)
・毎月1200ポイント付与
・月額2,189円が31日間無料
■関連記事
➡︎U-NEXTのメリット解説はこちら