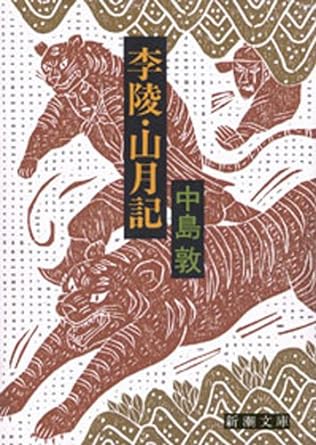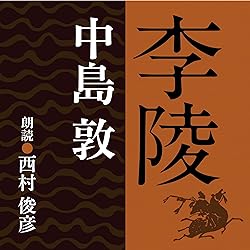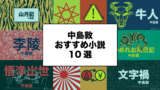中島敦の小説『李陵』は、前漢の将軍の人生を描いた遺作です。
農民から成り上がった一族の子孫の、悲しい運命が描かれています。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
さらにおすすめ代表作も紹介しています!
作品概要
| 作者 | 中島敦(33歳没) |
| 発表時期 | 1943年(昭和18年) |
| ジャンル | 短編小説 |
| ページ数 | 52ページ |
| テーマ | 思弁による破滅 創作に執着する人生美学 |
あらすじ
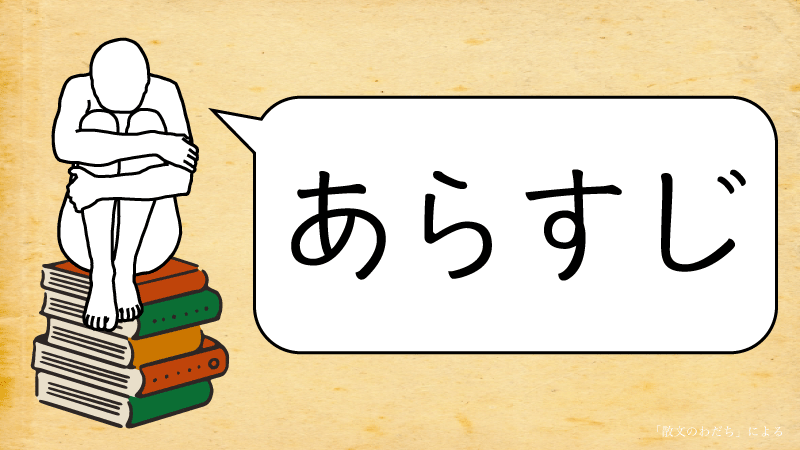
前漢の武帝の時代の物語です。
3万を超える敵の遊牧民族に対して、李陵は5千の兵で立ち向かいます。一時は優位に立ったものの、仲間の裏切りによって、李陵は敵に捕獲されてしまいます。それからは敵国での生活が始まります。
漢の国では李陵が自国を裏切り、近頃は敵の戦略に加担しているという噂が広がります。怒り狂った武帝は李陵の家族を皆殺しにします。ただし司馬遷という歴史書を執筆する男だけは李陵のことを擁護します。その結果、司馬遷は宮刑(男性器を切り取られる刑)に処せられます。恥辱に苛まれた司馬遷は自殺を考えたものの、歴史書編製という使命にのみ執着し、何年間も黙々と創作を続けます。
一方で李陵は、時期を見計らって脱走を企んでいましたが、敵の将軍と親しい間柄になり、ついには脱走のタイミングを失います。それどころか家族を皆殺しにされた報を受け、自国を捨てることを決意します。
同じく敵に捕獲された蘇武という男は、自国を捨てないために、敵国で貧しい生活を強いられていました。自分とは対照的な蘇武を見た李陵は、敵国で生きる運命を決心したとは言え、やはり心苦しくなります。
暫くして武帝が亡くなり、19年ぶりに帰国の機会が訪れますが、李陵は今更帰っても恥だと断り、蘇武のみが帰国を果たします。
その後、敵国で生涯を送った李陵については、殆ど記録が残されていません。
Audibleで『李陵』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『李陵』を含む中島敦の作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察
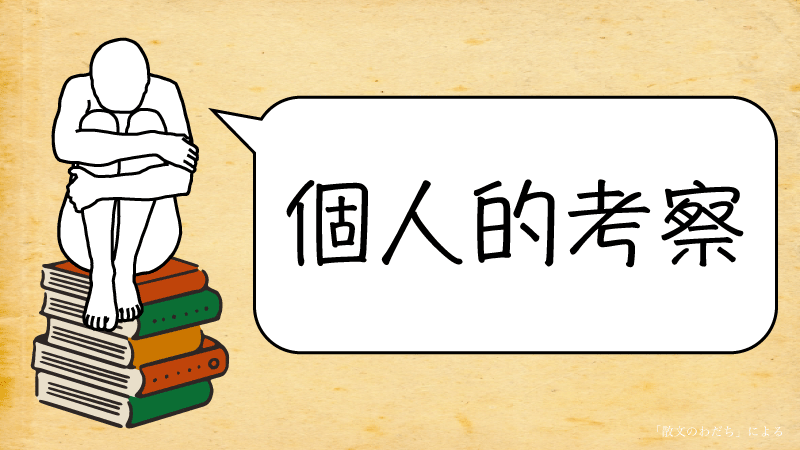
李陵と蘇武の異なる運命
本作は無論、主人公である李陵の人生に重点を置いて描かれているのですが、作品全体を通すと、李陵、司馬遷、蘇武という3人の異なる人物の生き方や運命が比較されています。
最も顕著に比較されているのは、旧友であり、同じ敵国に囚われた立場でもある、李陵と蘇武の運命でしょう。
李陵と蘇武の運命を大きく隔てたのは、二人の性格が対極的だったからだと思います。
李陵は「思考の人」でした。兵を指揮する将軍としては勿論、捕獲されてからも、敵の首をとって帰国しようと、思考を巡らせていました。しかし、当然そんな危険な作戦はリスクが大きく、失敗すれば「自分は自国を裏切っていなかった」という事実が誰にも知られないまま事切れることになります。自分が売国奴ではないという事実を知ってもらえないまま自国への忠誠心を保つのは難しく、結果的に作戦を実行することはありませんでした。要するに、思慮深い人間である分、「他人にどう思われるか」ということに敏感だったのです。
一方で蘇武は「行動の人」でした。敵に囚われた際には自害を決行し、一命を取り留めてからも敵に協賛することはなく、いくら貧しい境遇を強いられても自国への忠誠心を忘れませんでした。李陵とは違い、自分の静かな忠誠心が周囲に知られなくても、その信念を保つことができる性格だったのです。
その結果、「思考の人」である李陵は帰国を断念し、「行動の人」である蘇武は帰国を果たしました。あれやこれやと考えるだけで行動に移せない思弁家の人間は報われない、という教訓が二人の運命の比較によって訴えられていたように思います。
李陵に著しく人徳が欠落していたというわけではありません。本来は自国に献身的でしたし、将軍としての才も人一倍優れていました。ところが思弁家故に、いつの間にか自分の行動を自分で制限することになり、最後は誰にも知られず敵国で生涯を終えることになりました。
司馬遷の強い意志
司馬遷の運命は蘇武に近く、つまり李陵とは対極的だったと言えるでしょう。彼もまた、思弁よりも行動に生きた人間でした。
ただし司馬遷の場合は蘇武とは違い、自らの行動が時に悲劇をもたらすという教訓も含んでいました。
李陵が敵に囚われた事実について、否定的な憶測が飛び交う中、司馬遷だけは自分の主張を曲げることなく李陵を擁護しました。それが災いをもたらし、結果的に男性器を切り取られるという最も屈辱的な悲劇に陥ります。
一時は自殺をも試みた司馬遷でしたが、彼はやはり行動の人、父親から譲り受けた使命である史書の編製によってその命を燃やします。あれこれ考える間も無く、彼は殆ど俗世を捨てて自分の目的を完遂したのです。
信念を貫けば、周囲に屈辱を与えられ、時に自殺したい精神状態にまで陥る可能性があるが、それでもなお目的を持った人間は、あらゆる恥辱に堪え、最後まで命を燃やすことが出来る、という人生哲学が司馬遷から読み取れます。
作中では司馬遷は史書を完成させた後に、一種の虚無感に襲われ、原因も綴られないまま亡くなっていました。実際の歴史上においても司馬遷の死期は判っていないとのことです。もしかすると、使命を終えた脱力感によって自ら命を絶った可能性も考えられます。ある種、芸術家のような命の燃やし方ですね。
中島敦の短命な人生から考える
本作を考察する上で、短命な中島敦の人生を振り返る必要があるでしょう。
中島敦は、教職を勤めながら、精力的に執筆活動を行っていました。ところが持病の喘息が酷く、当時日本が占領していたパラオで転地療養することになります。療養中も小説の執筆に注力し、友人に原稿を託して、日本で出版してもらうよう懇願していました。その頃に創作されたデビュー作こそ、有名な『山月記』です。
パラオから帰国した中島敦は、間も無く持病が悪化し、33歳の若さで亡くなってしまいます。
死ぬ間際まで「書きたい、書きたい」と、作家業に執着していたようです。
彼が最期に残した言葉は、涙ながらに訴えた「俺の頭の中のものを、みんな吐き出してしまいたい」でした。有り余る創作欲は短命のために絶たれてしまったのです。
執筆に対して強い信念を持っていた中島敦は、蘇武や司馬遷のように自らの信念を貫く人物に自分の姿を落とし込んでいたのではないでしょうか。とりわけ、司馬遷のようにいくら惨めな境遇でも創作に命を燃やす姿は、中島敦の写し鏡だと感じます。
一方で、李陵の思弁的な側面も、作者にとっての蟠りのひとつだったのではないでしょうか。つまり、自分の信念を誰にも知られないままで保つのは難しいと考える李陵の弱さです。
(蘇武は)誰にもみとられずに独り死んでいくに違いないその最後の日に、自ら顧みて最後まで運命を笑殺しえたことに満足して死んでいこうというのだ。誰一人己が事蹟を知ってくれなくともさしつかえないというのである。李陵は、かつて先代単于の首を狙いながら、その目的を果たすとも、自分がそれをもって匈土の地を脱走しえなければ、せっかくの行為が空しく、漢にまで聞こえないであろうことを恐れて、ついに決行の機を見出しえなかった。
周囲に自分の功績が伝わらないことを恐れて、李陵は行動を起こせなかったのです。その自分の弱さを蘇武と比較して苦しんでいました。
もちろん中島敦は最後まで執筆に生きた人ですが、その期間はあまりに短く、本来認められるはずの評価を十分に受けずに死んだように見受けられます。長く生きたなら、もっと多くの傑作が生まれ、周囲からの称賛も期待できたことでしょう。そういった点での不満足感が、ある種、李陵の臆病な部分に反映されているのではないかと感じます。あるいは、李陵の後年の記録が殆ど残されていないように、死後に自分の存在が人々に忘れられることを懸念していたのかもしれません。
中島敦の迸る創作意欲の隙間に垣間見える、短命を予期した弱さみたいなものを想像すると、いつも胸が苦しくなりますね・・・。
■関連記事
➡︎中島敦おすすめ10選はこちら
オーディブル30日間無料
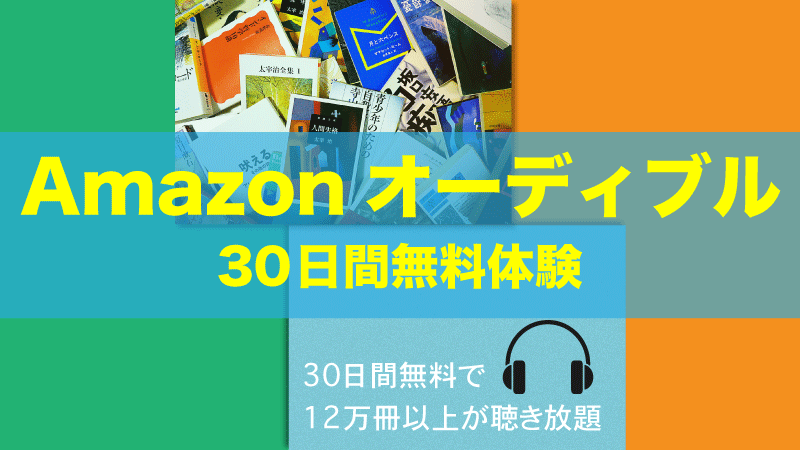
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら