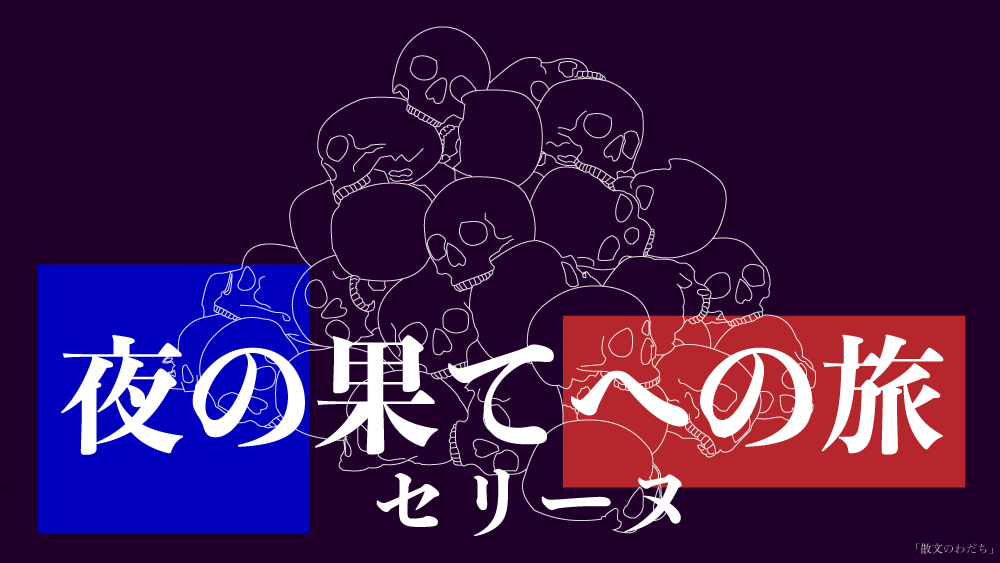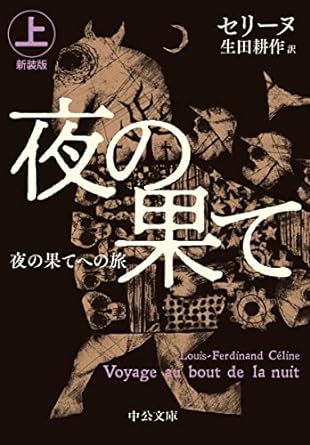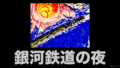セリーヌの『夜の果てへの旅』は、第1次世界大戦を経験した作者の半自伝的小説である。
アナーキスト的放浪者の主人公を通して、戦争や植民地支配や資本主義への、呪詛、怒り、罵詈雑言が吐き散らかされる。
あまりに過激で絶望的な内容ゆえ、東京大学出版『教養のためのブックガイド』の「読んではいけない15冊」に選出されている。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語を考察していく。
作品概要
| 作者 | セリーヌ |
| 国 | フランス |
| 発表時期 | 1932年 |
| ジャンル | 長編小説(上下巻) 半自伝的小説 実存主義文学 |
| テーマ | 反戦 植民地支配の欺瞞 絶望的な世界からの逃亡 |
あらすじ

パリの医学生バルダミュは、第1次世界大戦で兵隊に志願するが、悲惨な戦場を体験し、戦争がいかに滑稽で無意味かを悟る。負傷して帰還兵となった彼は、精神的な後遺症と反戦思想を植え付けられ、恋人には売国奴のように非難される。
愛国心で猛り狂う地獄のパリから逃げ出し、植民地のアフリカへ向かう。そこでも植民地支配の欺瞞を目撃した彼は、おまけに不当な賠償責任を押し付けられそうになり、逃げるようにアメリカへ旅立つ。そしてデトロイトの工場に勤め、心優しい恋人と出会うが、しかし資本主義を象徴するアメリカの空気に馴染めず、彼は再びパリに帰るのだった。
大学を卒業したバルダミュは、パリの貧困街で医者を開業するが、そこには貧困に喘ぐ絶望的な人間ばかりが集まっていた。さらにはかつての戦友ロバンソンが、ある家族に依頼されて老婆を爆殺しようと企み、その失敗で大怪我を負って視力を失う。このロバンソンは疫病神のようにバルダミュの人生に付きまとう。パリの大きな精神病院に転職してからも彼との腐れ縁は続き、やがてそれは最悪の悲劇を招くことになる・・・
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら
個人的考察

呪われた作家セリーヌ
「呪われた作家」「国賊作家」の異名を持つ、20世紀を代表するフランスの小説家セリーヌ。
『夜の果てへの旅』で彗星のごとく登場し、前例にない文体・内容で旋風を巻き起こし、瞬く間にベストセラー作家となった。
が、それも長続きはしない。
第二次世界大戦期に、反ユダヤ主義に傾倒したことで、戦後は国家反逆罪に問われ、亡命や投獄の末、貧困のうちに生涯を終えた。彼の存在は長らくタブー視され、今でも1部の作品は出版が差し止められている。まさに呪われた人生を送った奇妙な作家である。
こんな末路を誰も想像しなかった当時、無名のセリーヌは文壇の革命児として注目された。
ある時、出版社に差出人不明の原稿が届き、その内容に感銘を受けた編集者は、郵便局の消印からセリーヌを見つけ出し、本作『夜の果てへの旅』の出版に漕ぎ着けた。事前に編集者から原稿を見せられた作家のヘンリー・ミラーは、これぞ自分が書きたかった小説だと絶賛し、明らかに感化された『北回帰線』を執筆した。さらに若き日のサルトルも影響を受け、本作『夜の果てへの旅』は、実存主義文学の誕生に貢献したと言われている。
セリーヌが文学界に衝撃を与えた理由は、その破格の文体にある。アナーキスト的放浪者の主人公を通して、俗語的な口語が大胆露骨にぶちまけられる。もはや文章力の優劣や、表現の美しさなどは無関係、下品で卑猥な言葉がひたすら吐き出される。そんな異端な文章は前例がなく、彼の登場前後で、小説の文体は大きく変化したと言われるほどだ。
おまけに物語は反社会的思想で充満し、戦争や植民地支配や資本主義を徹底的に批判する。だからといって左翼主義とも言い難く、革命を望むどころか、この世界は生きるに値しない、という絶望的な怒りで満ちている。
場合によっては読者に危険な思想を与えかねない。実際に、東京大学出版『教養のためのブックガイド』では、「読んではいけない15冊」に選出されている。
そんな危険な作品『夜の果てへの旅』は、セリーヌの半自伝的小説である。
パリの貧困街で少年期を過ごしたセリーヌは、第1次世界大戦で志願兵として戦場に赴き、その悲惨な体験から反戦思想を植え付けられた。負傷兵として帰還した彼は、国際連盟の局員として各国を渡り歩いた後、パリの貧困街で医者を開業し、その傍で執筆活動に取り組んだ。
こうした遍歴のうち、第1次世界大戦を体験してから、各国を放浪し、医者を開業するまでの出来事が小説で描かれている。
ちなみに2作目の『なしくずしの死』は、それ以前の少年時代の出来事が描かれている。前作よりさらに実験的な文体なので注意していただきたい。
そして第二次世界大戦期に、反ユダヤ主義の評論や政治パンフレットを多く執筆したため、国家反逆罪に問われる。当時は世界中がナチスに対して感情的だったため、反ユダヤ主義者は死刑になってもおかしくなかった。セリーヌは亡命先のポーランドで投獄されたが、運良く特赦で帰国することができた。帰国後は戦犯作家として文学界から完全に無視され、再び日の目を見ることはなく、貧困のうちに生涯を終えたのだった。
しかし今日では世界文学の要人として再評価されている。作家のブコウスキーは、セリーヌの小説だけを読めばいい、と言及するほどだ。
こんな波瀾万丈な人生を送ったセリーヌの『夜の果てへの旅』は、一体どんな作品なのか、詳しく考察していく。
反戦思想について
セリーヌは第1次世界大戦で負傷し帰還兵となった経歴がある。頭部と右上腕に重傷を負い、さらに不眠、頭痛、耳鳴りなど、生涯精神的に苦しめられた。
この恐怖体験が反戦思想を芽生えさせる要因になったことは間違いないが、しかし主人公のバルダミュは戦場に着いてすぐ、早くも戦争がいかに滑稽で不可解かを悟る。なぜ自分の命を投げ出してまで、個人的に恨みのないドイツ兵と殺し合わねばならないのか、その理由が皆目わからないのだ。
こんなぐあいに、お互い顔も知らずに、撃ち合っているのは。こいつはこっぴどくどやされずにやっていいことの一部なのだ。それどころかまじめな連中から公認され、たぶん推奨されているのだろう・・・
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
バルダミュが抱いた疑念、それは、戦争を扇動する国家と、前線で戦う兵士の目的とが、あまりに乖離しすぎていることだ。
国家には利権という大義名分があれど、兵士には相手に恨みなどない。そんな無意味な戦いで命を落とすなら犬死である。ところが兵士たちは、国家の大義名分を自分のものと見紛い、狂ったように銃をぶっ放して、次の瞬間には死体になっている。この異常事態を目撃したバルダミュは、盲目的な愛国心から目覚め、逃亡を図るのだった。
幸か不幸か負傷で帰還したバルダミュは、しかし新たな悪夢に苦しめられる。
1つは精神的な負傷だ。戦場から遠ざかってもなお、絶えず死の恐怖が彼に付きまとう。レストランで食事をしても、賑やかな縁日に出かけても、射殺される恐怖に襲われるのだ。戦争体験によるPTSDである。
こうした悲惨な体験によって、彼は戦争の醜さを一挙に見抜き、強い反戦思想を抱くが、しかし本心は隠し通さねばならなかった。
祖国が危機に瀕しているときに、戦争を否定するなんて、気違いか、腰抜けくらいよ
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
多くの市民は国家と一体化し、戦争を賛美している。戦死は名誉なのだ。仮にも戦争に反対するなら、戦死した英雄を侮辱したも同然で、そんな人間は売国奴か気違いと見なされる。実際にバルダミュは精神病院にぶち込まれ、恋人から「ドブネズミ」呼ばわりされる。
しかし本当に戦争を恐れることは<気違い>なのだろうか?
バルダミュは考える、気違いかそうでないかを決めるのは大多数なのだと。大多数が賛成する戦争に反対する者は精神病院にぶち込まれ、愛国心という名の大量投薬がなされ、そうして善良な市民に回復すれば、再び戦場に送り出されて、今度こそ犬死させられる。貧しい市民は戦争によって殺されるか、さもなくば売国奴として同胞に殺される運命なのだ。
それでもバルダミュは戦争を否定する。英雄は死んで、気違いが生き残るなら、自分は気違いで構わないと考える。彼には名誉や勲章に価値があると思えない。戦争で犬死した英雄を、のちに人々が思い出すだろうか? 国家に英雄に仕立て上げられた人間は、いずれ誰の記憶からも忘れ去られ、つまり無意味に死んだも同然なのだ。そんな名誉ある無意味な死より、命にこそ価値がるのだとバルダミュは断言する。例え世界中の人間が否定しようと、彼にとっての正しさは、生きることなのだ。
そうしてバルダミュは、ナショナリズムで猛り狂うパリから逃亡し、アフリカへ旅立つ。
「夜の果てへの旅」とは、絶望的な社会から逃亡する彼の、一連の放浪を指す。一見「夜の果て」は幻想的なイメージを想起させるが、しかし実際は永久に明けない暗闇を意味する。この世はすべて暗闇、どこへ行っても希望はないのだと、彼は思い知ることになる・・・
植民地支配の欺瞞について
バルダミュは新規まき直しを図ってアフリカに旅立つが、そこにも希望はなかった。当時フランスに植民地支配されていたアフリカは腐敗し切っていたのだ。
彼が訪れた植民地には総督が君臨し、貧困に喘ぐ黒人を傭兵に仕立て上げ、絶対服従の支配体制を維持していた。加えて、植民地に派遣された官吏や軍人も、安い給料によって酷使されている。いわば総督のみが潤う完全搾取の体制が構築されているのだ。そこには暴力と横領が蔓延っている。
さらに黒人と軍人の間にも搾取の関係が出来上がっている。軍人は強引に輸入煙草を黒人に売りつける。すると黒人は薄給を使い果たし、おまけに前借りをしてでも煙草を買い求める。借金をすれば黒人はますます絶対服従から抜け出せないのだから、卑劣な商売だ。しかし軍人も自分が生きるためには、弱者から搾取する以外に術がなかった。
バルダミュはこの腐敗した植民地で、アルシイドという軍人と出会い、強烈な失望感を抱く。アルシイドは、孤児になった兄の娘を養うために、煙草の密売で黒人から搾取している。その娘は小児麻痺にかかっており、できれば植民地を去って会いに行きたい。だが少しでも席を開ければ、他の者に密売の役を横取りされるので帰れない。そういう理由でアルシイドは、過酷なアフリカ滞在の年数を伸ばして、娘を養う金を必死に貯蓄しているのだ。
戦場では貧しい市民が前線に駆り出されて犬死させられていた。それに絶望してアフリカに来たのに、ここでも貧しい者は搾取され、地獄の労働に喘いでいた。そして国家だけが潤う。
一体どこに希望があるというのか?
ここで少し、植民地支配の歴史を解説する。
第一次世界大戦期、フランスとイギリスは、マス取りゲームのごとく、アフリカを次々に占領していった。そのためアフリカの国境線はマス目状になっているのは有名な話だ。現在では独立した国家として機能しているが、しかしマス取りゲームの弊害は続いている。
フランスとイギリスは好き勝手にアフリカに国境線を引いた。ゆえに1つの国家に複数の民族が無理やり押し込まれている。そしてアフリカは民族意識が強いため、勝手に線引きされた国家に属している意識を持たない。だから国民は国家のために生産性を高めようと考えない。さらに大統領は自分の民族を優遇した政策ばかり実施するため、民族同士の衝突が絶えず、常に国家は不安定な状態にある。
これら全ては、先進国による植民地支配が引き起こした結果なのだ。
かつて植民地支配は肯定されていた。日本もアジアの発展を建前に進めていた。その実態は自国の利権を優先した卑劣な行為であり、搾取の関係が存在し、その弊害は将来的に続くことを絶対に忘れはいけない。
こうした植民地支配の欺瞞を目撃したバルダミュは、おまけに貿易会社の不当な賠償責任を押し付けられそうになり、急いでアフリカからアメリカに逃亡する。
永久に明けることのない<夜の果てへの旅>がまた再開されたのだ。
ロバンソンが与えた絶望
僕は自分の悪癖を、あの至るところから逃げ出したい欲望を愛していたのだ。自分でもわからぬなにものをか求めて
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
アメリカにやって来たバルダミュは、一時は近代的な生活と、心優しい恋人との出会いに満足するが、次第に資本主義の空気に耐えられなくなり、本国フランスに舞い戻る。そして大学を卒業して、パリの貧困街で医者を開業する。
バルダミュが医者になった(下巻)では、主にロバンソンとの交流が描かれる。ロバンソンはかつて戦場で出会った、同じように戦場からの逃亡を企んだ仲間だ。
ロバンソンは不思議な存在で、バルダミュが「そこにいる」と思う先々で必ず登場する。同じ軌跡を辿るかのように、アフリカでもアメリカでも再会するのだ。「至る所から逃げ出したい欲望」を抱えたバルダミュの分身のような存在で、同時にどこにも適応できないアナーキスト的放浪者に付きまとう疫病神のような存在でもある。事実、ロバンソンは実在の人物か、バルダミュの妄想か、怪しい部分がある。
そんなロバンソンとの出会いによって始まった<夜の果てへの旅>は、ロバンソンの死で幕を閉じる。
バルダミュが医者を営む一方で、ロバンソンは極貧に喘ぎ、報酬欲しさに老婆の殺害依頼を引き受けるが、爆弾の扱いを誤り視力を失う。そして神父の手助けによってパリから離れた街で仕事にありつき、そこで許嫁と出会う。一時は平穏な生活に落ち着いていたが、視力が回復した途端、許嫁の元を飛び出してパリに戻ってくる。嫉妬と憎悪に狂った許嫁は、ロバンソンを探しにパリにやって来て、最終的に彼は銃で撃ち殺される。
前述した通り、バルダミュにとってロバンソンは分身のような存在だった。それどころか、バルダミュが医者に落ち着いてからも、ロバンソンは絶えず逃亡の旅を続けていた。バルダミュが途中で放棄した<夜の果てへの旅>を代わりに実行する、ある種、希望を託した存在だったのだろう。だが結局ロバンソンは、永久に明けることのない<夜の果て>で死んでしまった。それは同時にバルダミュの敗北でもあった。
自分の生活に二度と直面せぬために、姿をくらます努力を試みたが、無駄だった、いたるところでたやすくそいつに出くわすのだ。自分に戻るのだ。僕の放浪、そういつはもうおしまいだった。世界はもう一度閉ざされてしまったのだ! 果てまで来ちまったのだ、僕たちは!
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
戦争から逃げ出し、植民地から逃げ出し、資本主義から逃げ出し、恋愛から逃げ出した。そんな風にいくら世界から逃亡しようと、<夜の果て>から脱却することは不可能だと、ロバンソンの死が証明してしまったのだろう。
とはいえロバンソンはなぜ、許嫁との激しい情愛から逃げ出す必要があったのか?
実はここには、戦争という狂乱に巻き込まれた兵士の末路が、メタファー的に描かれている。
不慮の事故で視力を失ったロバンソンは、許嫁のマドロンに夢中になる。ところが視力が戻った途端、彼女の元から逃げ出し、最終的には彼女に撃ち殺されてしまう。これは盲目的に愛国心に取り憑かれた市民が、正しい判断を取り戻して戦争から逃げ出すが、いくら戦場から遠く離れても、最終的には戦争の恐怖に殺されてしまう、というメタファーだと考えられる。
さらに重要なのが、ロバンソンの死は縁日の射的場が引き金になっていることだ。
かつて戦争から帰還したバルダミュは、射的場を見ただけで精神錯乱を起こすPTSDの状態にあった。ところが二度目に射的場を訪れた際には、バルダミュは精神錯乱を発動しないが、その代わりにロバンソンが撃ち殺されてしまう。
見方によってはバルダミュのPTSD克服、つまりロバンソンという戦争の病を象徴する存在が死んだことで、長く患った狂乱が取払われた、という克服の物語と考えることもできる。
だがそんな安っぽい希望を信じれるほど物語は生温くない。<夜の果てへの旅>とは、絶望的な社会からの逃亡であると同時に、戦争の後遺症から逃れる試みでもあった。そしてロバンソンの死は、どれだけ逃亡しようと、最後は戦争の恐怖に殺される事実を訴えていたのではないだろうか。
事実、バルダミュはこんな言葉を口にする。
旅とは、結局このとるにたらぬしろもの、いくじなしのための小さな眩暈の追求だ
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
希望を求めた<夜の果てへの旅>の最果てで、バルダミュは気づいたのだろう。
どこまで行っても、この世界には絶望しかないのだと。
もう何も言うことはない。
『夜の果てへの旅/セリーヌ』
■関連記事
➡︎不条理・実存主義文学おすすめ7選
オーディブル30日間無料

Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら