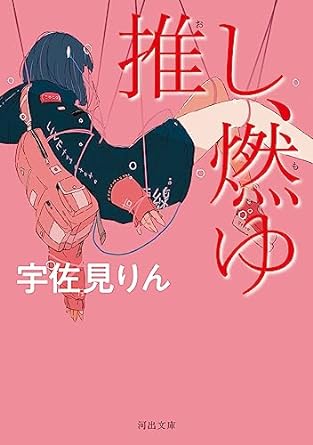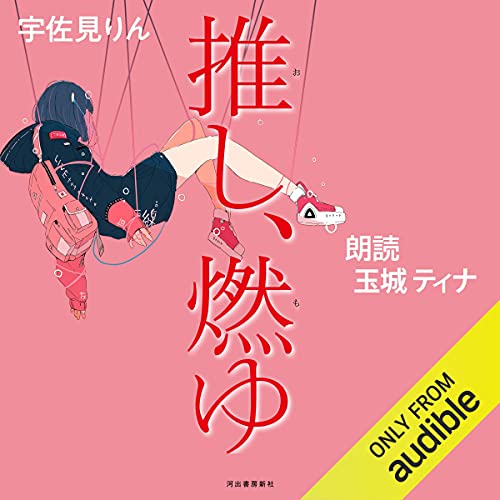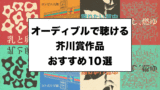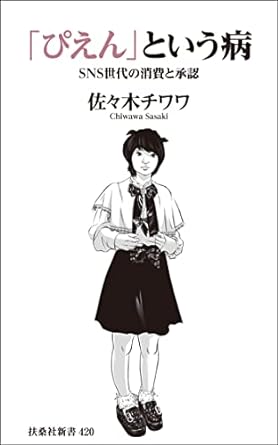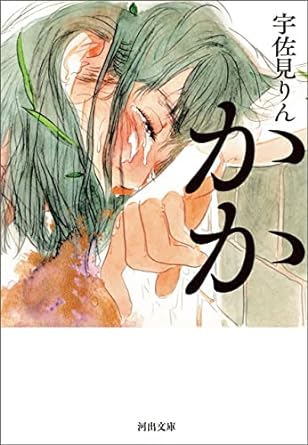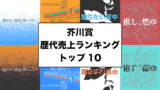宇佐見りんの小説『推し、燃ゆ』は、2020年下半期の芥川賞受賞作です。
「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい」という、衝撃の冒頭で始まる現代の若者文化を描いた物語です。
本記事では、あらすじを紹介した上で、物語の内容を考察しています。
作品概要
| 作者 | 宇佐見りん |
| 発表時期 | 2020年(令和2年) |
| 受賞 | 第164回芥川賞 |
| ジャンル | 中編小説 |
| ページ数 | 160ページ |
| テーマ | アイドル推し論 推し文化 幸福の多様化 |
あらすじ
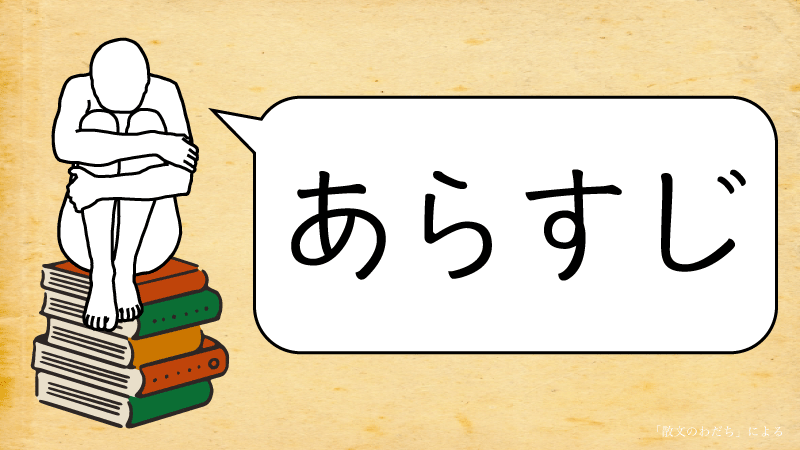
「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。」
アイドルグループ「まざま座」のメンバー真幸が、ファンを殴りネットで大炎上します。謝罪会見で淡々と話す真幸の言葉を、一字一句を逃さないよう、主人公のあかりはノートにメモします。推しである真幸の発言をしたためたノートは20冊を超えています。さらには殆ど毎日推しについてのブログ記事を投稿するほど熱狂的なファンです。されど、真幸と物理的に繋がりたい願望なく、人と作品を解釈し精神的に同化することが、彼女の推しの流儀なのでした。
推しのことであれば努力を厭わないあかりですが、学校では劣等生、家族からは見放され、バイトでも無能扱い、常連客からは、推し活動を馬鹿にされる始末です。
炎上後のファン投票で真幸が最下位に転落します。呼応するようにあかりも留年で高校を中退することになります。危機感を抱いた両親に、一人暮らしをするように命じられ、家を追い出されてしまいます。そんな矢先に「まざま座」の解散、さらに真幸の芸能界引退が報道されます。記者会見の真幸は指輪をつけており、結婚を匂わせたことで大炎上します。真幸の住居が特定され、ネットに拡散される始末です。
現実を受け止められないあかりは、ラストライブ終焉後、自分の背骨を奪われる感覚に冷や汗と涙が止まりませんでした。気がつくとあかりは、ネットに拡散された住所にやって来ていました。すると、ショートボブの女性が洗濯物を干す姿が目に入ります。引退した推しをこれからも近くで見続ける結婚相手が想起され、自分がこれまで大量に集めたグッズや情報は、たった一枚の洗濯物にすら敵わないのだと知ります。
家に戻ったあかりは衝動的に目の前の綿棒ケースを床に叩きつけます。這いつくばりながら散らばった綿棒を拾い、これが自分に相応しい姿勢だと悟ります。二足歩行が向いていない自分は、当分この姿勢で生きていこうと考えるのでした。
Audibleで『推し、燃ゆ』を聴く
Amazonの聴く読書オーディブルなら、『推し、燃ゆ』を含む芥川賞作品が聴き放題!
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
▼初回30日間無料トライアル実施中
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルで聴く芥川賞おすすめ10選
個人的考察
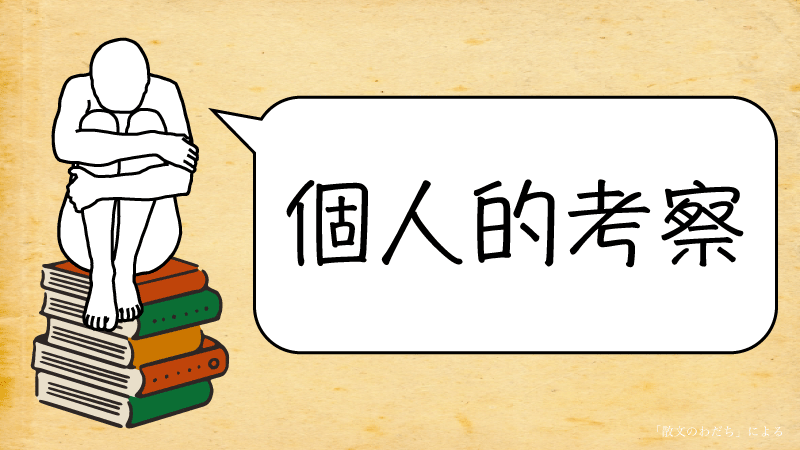
推し文化とは
若者が日常的に口にする「推し」という言葉の普及には、国民的アイドルAKB48が大きく関係しています。総選挙制度を設けたことにより、同封される投票券を目的にCDを大量に購入し、応援するメンバーに投票するという文化が誕生しました。この消費文化の中で、自分がどれだけ「推し」に費やしたかをある種の美徳とする価値観が芽生えたのです。
歌舞伎町のルポライター佐々木チワワ氏は、著書『「ぴえん」という病』の中で、こういった推し文化を「誇示的消費」と呼んでいます。
推しにいくら費やせるかで、自分の価値(誇り)が決定づけられるのです。同著では、ホストに貢ぐ女性を中心に論じられていますが、その中で「推しのホストに貢げない自分に生きている価値はない」という強烈なフレーズが登場します。
つまり、AKBの総選挙を発端に浸透した推し文化は、推す側のアイデンティティを大きく司る側面を持つということです。
『推し、燃ゆ』のあかりも、アイドルグループ「まざま座」の真幸を「推し」ていました。彼女の場合は周囲にマウンティングして誇示するわけではなく、自己完結的な偶像崇拝として真幸を推していました。とは言え、彼女は推し活動を「生活の背骨」と表現していました。それだけ真幸を推す行為が自分のアイデンティティと直結していたのです。
真幸がファン投票で最下位に転落すれば、あかりの精神は病み、言い合わせたように堕落しました。投票のためにもっとCDを買えばよかったと後悔する始末です。彼女の中で、自分の推し不足と真幸の転落は因果関係にあり、だからこそ、真幸がアイドルとして輝けば輝くほど、あかりの自己肯定感も高まるのです。
解散ライブ終演後のトイレで、あかりは悪寒を感じて、冷や汗と涙が止まりませんでした。その時の様子を「自分の背骨を奪われる感覚」と表現しています。
推しを応援することが自分のアイデンティティと直結しており、推しのために努力した分だけ自分の価値(肯定感)が上がる。だからこそ、推しの存在が消滅すれば、あかりのアイデンティティは崩れます。まるで背骨を奪われるように、自己の存在が危ぶまれたのでしょう。
芥川賞は、その文学的芸術性に加えて、リアルタイムな社会を切り取った作品が受賞する傾向にあります。第164回芥川賞を受賞した本作は、なるほど、確かに2020年の日本社会、とりわけ若者が抱く存在価値のしがらみを秀逸に描いており、納得の受賞です。
ちなみに「推し文化」について使用した下記参考文献も非常に面白いのでおすすめです。
物質を求めない推し方
あかりの心情を推測するのに重要なのが、文中で幾度となく対比される「推し方の違い」でしょう。
地下アイドルを推す友人の成美は、「推しと接触すること」が最終的な目的でした。チェキ撮影に1万円を払って肉体を接触させたり、ひいては裏で交際することを望んでいたのです。ところがあかりの場合は対照的で、推しとの直接的な接触は求めず、アイドルとしての推しを解釈することに注力していました。
いわゆる、物質的に推しを求めるのではなく、偶像としての存在を遠く離れた場所から解釈するという、精神的な接触を求めていたのです。相互的な意思疎通ではなく、一方的な解釈によって自己を満たしていたのでしょう。
アルバイト先の常連に、「現実の男を見ないと行き遅れる」と忠告される場面では、あかりは次のような心情を語っていました。
あたしは推しの存在を愛でること自体が幸せなわけで、それはそれで成立するんだからとやかく言わないでほしい。お互いがお互いを思う関係性を推しと結びたいわけじゃない。(中略)一定のへだたりのある場所で誰かの存在を感じ続けられることが、安らぎを与えてくれるということがあるように思う。
『推し、燃ゆ/宇佐見りん』
現実での人間関係とは異なり、相互理解を取っ払った一方的な関係だからこそ、あかりは100パーセントの熱意を推しに注げたのかもしれません。
文中では元々ファンだった人たちが、炎上した途端アンチに豹変する様子が描かれていました。それは少なからず、物質的な欲求、つまり相互理解を求めていたからこそ、「裏切られた」という感情が芽生えたわけです。いくら炎上しようとも最後までファンであり続けるあかりは、物質的には隔たりがあるからこそ、超越した深い部分で推しと繋がっていられたのでしょう。
このように、淡白な人間関係は仮想現実へとシフトし、閉塞的な社会の中に個人の幸福を見出すという、昨今の我々の安らぎのカタチが描かれているように思います。
「推しが人になった」の意味
推しが芸能界を引退すると表明した途端、あかりの中には、推しが人になる、という感情が芽生えました。極論を言うと、彼女にとっては推しの死を意味していたのだと思います。
先ほどの考察通り、あかりは推しに対して物質的な関係を求めていませんでした。例えば、成美のように裏で推しと繋がり、相互的な関係を築けば、推しが芸能界を辞めようが人間としての存在はあり続けます。ところが、あかりは偶像としての推しを崇拝していたがために、彼が芸能界を辞めて普通の人間になれば、推しの存在は消失し、二度と解釈できなくなってしまうのです。
特定された推しの住居の前にやって来て、洗濯物を見た時のあかりの心情がまさにその事実を物語っていました。今まで自分が生活の全てを注ぎ込んだ推し活の結晶であるグッズや語録やブログが、洗濯物が内包する推しの現在の生活には敵わなかったのです。
つまり、相互的な関係を築き上げた人間だけがこの先の推しの解釈を許されて、遠くから偶像崇拝していた自分は今後の推しを解釈できないということです。この先自分が知る由のない、人間になった推しの人生が、洗濯物という生活感のあるアイテムによって表現されていたのでしょう。
デビュー作がおすすめ
宇佐見りんさんは、前作『かか』にて作家デビューしました。文藝賞、三島由紀夫賞の二冠を獲得し、名だたる作家からもかなり称賛されていました。
一部のファンからはこちらで芥川賞を受賞しても良かったのではないか、という意見があるほどです。
独特の文体と痛くて切ないテーマ、是非読んでみてください。
■関連記事
➡︎芥川賞売り上げランキングはこちら
オーディブル30日間無料
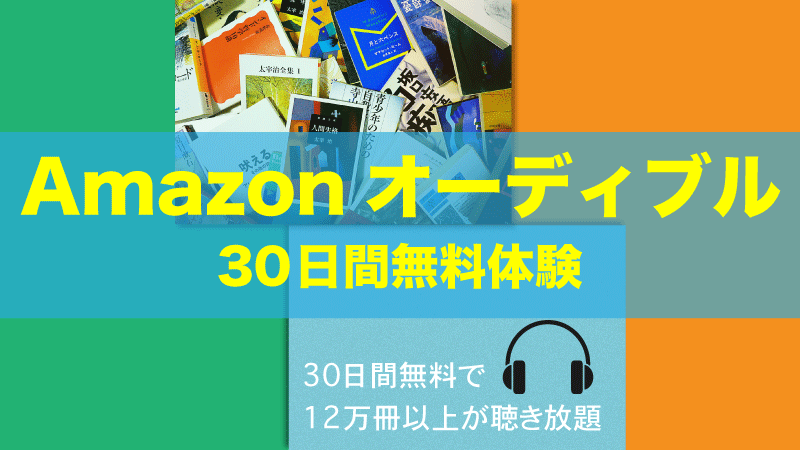
Amazonの聴く読書オーディブルなら、12万冊以上の作品が聴き放題。
近代文学の名作から、話題の芥川賞作品まで豊富なラインナップが配信されています。
通勤中や作業中に気軽に読書ができるのでおすすめです。
・12万冊以上が聴き放題
・小説やビジネス書などジャンル豊富
・プロの声優や俳優の朗読
・月額1,500円が30日間無料
■関連記事
➡︎オーディブルのメリット解説はこちら